Down
無用録
1-
51- 101-
150- 191-
229- 255-
293- 311-
333- 361-
383-
trivia's
trivia
Up Down
#150
イロハ順だった「現役海軍士官名簿」は1929年版から50音順になるが、ア行の最後がヲになっている.
現在、ヲはワ行の最後に置かれているので、これは奇妙な感じのするものである.
2015年5月15日
Up
Down
#150
イロハ順だった「現役海軍士官名簿」は1929年版から50音順になるが、ア行の最後がヲになっている.
現在、ヲはワ行の最後に置かれているので、これは奇妙な感じのするものである.
2015年5月15日
Up Down
#151
50音図というと、近代のもののような気がするが、実際には平安時代からある.
これは、仏教を通じて伝わったサンスクリットの研究から派生したものらしいが、現在のものとは配列が随分と異なる.
それが現在のような配列になったのは室町時代以降のようだが、アイウエヲとア行の末尾がヲになっている点が異なる.
また、ワ行の最後がオになっているが、これはヲとオの発音が一緒だったからである.
2015年5月21日
Up
Down
#151
50音図というと、近代のもののような気がするが、実際には平安時代からある.
これは、仏教を通じて伝わったサンスクリットの研究から派生したものらしいが、現在のものとは配列が随分と異なる.
それが現在のような配列になったのは室町時代以降のようだが、アイウエヲとア行の末尾がヲになっている点が異なる.
また、ワ行の最後がオになっているが、これはヲとオの発音が一緒だったからである.
2015年5月21日
Up Down
#152
ヲをワープロ・ソフトで出すにはWoと打てばよい.
本来、ヲはウォに近い発音だったからである(より正確に言うと唇をウの形にしてオと発声する音).
ただ、現在ではオと同じ発音になっているので、この使い分けは便宜上のものである.
これは江戸時代でも一緒であったが、オもWoと発音されていた点が違う.
現在の50音図と配列が異なるのは、このためである.
2015年5月23日
Up
Down
#152
ヲをワープロ・ソフトで出すにはWoと打てばよい.
本来、ヲはウォに近い発音だったからである(より正確に言うと唇をウの形にしてオと発声する音).
ただ、現在ではオと同じ発音になっているので、この使い分けは便宜上のものである.
これは江戸時代でも一緒であったが、オもWoと発音されていた点が違う.
現在の50音図と配列が異なるのは、このためである.
2015年5月23日
Up Down
#153
このオがア行に、ヲがワ行に位置すべきであることを見出したのは本居宣長である.
彼は万葉仮名に使われる漢字の音を調べていくうちに、古代においては、ヲはWoであり、オはOと発音されていたということに気付いたのである.
そして、この発見は明治政府に引き継がれ、国定教科書に載せられた50音図では、ア行にオを、ワ行にヲをおくようになっている.
したがって、「現役海軍士官名簿」のア行の最後がヲになっているのは、宣長以前に、つまり、江戸時代以前に戻ったとしか言いようがない.
2016年5月25日
Up
Down
#153
このオがア行に、ヲがワ行に位置すべきであることを見出したのは本居宣長である.
彼は万葉仮名に使われる漢字の音を調べていくうちに、古代においては、ヲはWoであり、オはOと発音されていたということに気付いたのである.
そして、この発見は明治政府に引き継がれ、国定教科書に載せられた50音図では、ア行にオを、ワ行にヲをおくようになっている.
したがって、「現役海軍士官名簿」のア行の最後がヲになっているのは、宣長以前に、つまり、江戸時代以前に戻ったとしか言いようがない.
2016年5月25日
Up Down
#154
「現役海軍士官名簿」の索引には、他にもおかしな点がある.
以前、香宗我部がカのところにあるのは、「かうそかべ」という歴史的仮名遣いに由来するものだと書いた.
ならば、猪原という苗字はイのところにあってはおかしい.
猪の歴史的仮名遣いは「ゐのしし」であって、「いのしし」ではないからある.
当然、猪原という苗字も「ゐはら」もしくは「ゐのはら」である.
ところが、この本の索引にはヰ(ゐ)の項すらないのである.
2016年5月27日
Up
Down
#154
「現役海軍士官名簿」の索引には、他にもおかしな点がある.
以前、香宗我部がカのところにあるのは、「かうそかべ」という歴史的仮名遣いに由来するものだと書いた.
ならば、猪原という苗字はイのところにあってはおかしい.
猪の歴史的仮名遣いは「ゐのしし」であって、「いのしし」ではないからある.
当然、猪原という苗字も「ゐはら」もしくは「ゐのはら」である.
ところが、この本の索引にはヰ(ゐ)の項すらないのである.
2016年5月27日
Up Down
#155
それどころか、「現役海軍士官名簿」の索引には、オの項もない.
小川であれば、「をがは」であり、大川は「おほかは」であるので、両者は別々に立項すべきである.
ところが、小川も、大川も、ともにヲの項に並んでいるのである.
そして、ヱ(ゑ)の項もないので、たとえば、遠藤(ゑんどう)はエの項に収められているのである.
2016年5月30日
Up
Down
#155
それどころか、「現役海軍士官名簿」の索引には、オの項もない.
小川であれば、「をがは」であり、大川は「おほかは」であるので、両者は別々に立項すべきである.
ところが、小川も、大川も、ともにヲの項に並んでいるのである.
そして、ヱ(ゑ)の項もないので、たとえば、遠藤(ゑんどう)はエの項に収められているのである.
2016年5月30日
Up Down
#156
実は、「現役海軍士官名簿」がイロハ順であった時から、オやヰの項はない.
したがって、大川だとか猪原というような苗字の人は、本来の表記とは異なるが、イとヲの項に収められているのである.
無学だったからというのは考えにくい.
この名簿は発行元の表記がないが、海軍省の発行である.
そして、当時、海軍士官には日本中から俊英が集められた.
当然、この名簿も俊英の仕事である.
ア行の最後がヲではないなどということは百も承知のはずなのである.
2016年6月1日
Up
Down
#156
実は、「現役海軍士官名簿」がイロハ順であった時から、オやヰの項はない.
したがって、大川だとか猪原というような苗字の人は、本来の表記とは異なるが、イとヲの項に収められているのである.
無学だったからというのは考えにくい.
この名簿は発行元の表記がないが、海軍省の発行である.
そして、当時、海軍士官には日本中から俊英が集められた.
当然、この名簿も俊英の仕事である.
ア行の最後がヲではないなどということは百も承知のはずなのである.
2016年6月1日
Up Down
#157
「をがは」であろうと「おほかわ」であろうと、頭の文字の読み方は、ともにオである.
しかし、小川だからヲの項を、大川だからオの所を見に行くというのは、現代仮名遣いになれた我々には難しい.
そして、これは、明治生まれの人にも簡単ではなかったのではなかろうかと思う.
というのは、夏目漱石や樋口一葉の原稿を見ていると、仮名遣いを間違っている例が散見されるからである.
もちろん、出版段階では正しくなっているが、それは、編集者が校正しているからである.
しかし、漱石は東京帝国大学の教授であり、当時の最高の頭脳の一人であると思われる.
そのような人ですら仮名遣いを間違うのである.
一般人が仮名遣いを間違っても、そう変なことではなかったのかもしれないと思う.
2016年6月4日
Up
Down
#157
「をがは」であろうと「おほかわ」であろうと、頭の文字の読み方は、ともにオである.
しかし、小川だからヲの項を、大川だからオの所を見に行くというのは、現代仮名遣いになれた我々には難しい.
そして、これは、明治生まれの人にも簡単ではなかったのではなかろうかと思う.
というのは、夏目漱石や樋口一葉の原稿を見ていると、仮名遣いを間違っている例が散見されるからである.
もちろん、出版段階では正しくなっているが、それは、編集者が校正しているからである.
しかし、漱石は東京帝国大学の教授であり、当時の最高の頭脳の一人であると思われる.
そのような人ですら仮名遣いを間違うのである.
一般人が仮名遣いを間違っても、そう変なことではなかったのかもしれないと思う.
2016年6月4日
Up Down
#158
旧日本海軍では上の者に対して敬称をつけない.
司令官閣下でも分隊長殿でもなく、司令官であり、分隊長である.
一兵卒が司令官に話しかけるということはまずないだろうが、その場合でも、司令官である.
ところが、陸軍の場合は逆である.
一階級でも上位にのものに、閣下だとか、殿とかつけないと大変なことになる.
したがって、海軍式のやり方というのは、非常に不思議なやり方に思える.
2016年6月4日
Up
Down
#158
旧日本海軍では上の者に対して敬称をつけない.
司令官閣下でも分隊長殿でもなく、司令官であり、分隊長である.
一兵卒が司令官に話しかけるということはまずないだろうが、その場合でも、司令官である.
ところが、陸軍の場合は逆である.
一階級でも上位にのものに、閣下だとか、殿とかつけないと大変なことになる.
したがって、海軍式のやり方というのは、非常に不思議なやり方に思える.
2016年6月4日
Up Down
#159
しかし、社長様とか、社長閣下とは言わない(韓国ではつける).
社長という言葉には、すでに敬意が表れているからである.
これに様だとか、閣下などという言葉をつけると、慇懃無礼に感じる.
したがって、陸軍式のやり方は、やりすぎであると海軍は考えたのであろうが、より端的にいえば、無駄だと考えたのであろう.
2016年6月15日
Up
Down
#159
しかし、社長様とか、社長閣下とは言わない(韓国ではつける).
社長という言葉には、すでに敬意が表れているからである.
これに様だとか、閣下などという言葉をつけると、慇懃無礼に感じる.
したがって、陸軍式のやり方は、やりすぎであると海軍は考えたのであろうが、より端的にいえば、無駄だと考えたのであろう.
2016年6月15日
Up Down
#160
海軍はスマートということを大切にした.
したがって、無駄というものを排除しようとした.
官職に敬称をつけなかったのはその流れの延長線上にあると思う.
そして、「現役海軍士官名簿」の索引においても、オ、ヰ、ヱの項を作らなかったのは、同様であると思う.
発音が一緒であるのなら、一ヶ所にまとめておくほうがスマートだからである.
小川が「をがわ」だからヲの項、大川は「おほかわ」だからオの項を見よというのは、無駄な手間だというのである.
これが、オ、ヰ、ヱの項がない理由であろうが、ならば、アイウエヲというのはどうしてだろうか.
2016年6月16日
Up
Down
#160
海軍はスマートということを大切にした.
したがって、無駄というものを排除しようとした.
官職に敬称をつけなかったのはその流れの延長線上にあると思う.
そして、「現役海軍士官名簿」の索引においても、オ、ヰ、ヱの項を作らなかったのは、同様であると思う.
発音が一緒であるのなら、一ヶ所にまとめておくほうがスマートだからである.
小川が「をがわ」だからヲの項、大川は「おほかわ」だからオの項を見よというのは、無駄な手間だというのである.
これが、オ、ヰ、ヱの項がない理由であろうが、ならば、アイウエヲというのはどうしてだろうか.
2016年6月16日
Up Down
#161
「現役海軍士官名簿」は、もともとイロハ順であったことはすでに書いた.
そして、オとヲは、オではなく、ヲの所に入っている.
これは、イロハ順では、オよりも、ヲのほうが先に来るからではないかと思っている.
単純に、先に来るほうにまとめたということだろう.
そして、ヰ、ヱよりもイ、エのほうが先に出てくるので、当然、イ、エのほうにまとめられた.
その時、問題になったのが、ヲにまとめられていた歴史的仮名遣いではヲとオで始まる苗字の部分である.
2016年6月20日
Up
Down
#161
「現役海軍士官名簿」は、もともとイロハ順であったことはすでに書いた.
そして、オとヲは、オではなく、ヲの所に入っている.
これは、イロハ順では、オよりも、ヲのほうが先に来るからではないかと思っている.
単純に、先に来るほうにまとめたということだろう.
そして、ヰ、ヱよりもイ、エのほうが先に出てくるので、当然、イ、エのほうにまとめられた.
その時、問題になったのが、ヲにまとめられていた歴史的仮名遣いではヲとオで始まる苗字の部分である.
2016年6月20日
Up Down
#162
もしかすると、アイウエヲという一般的でない配置は、イロハ順を引きずっているのではないかと思う.
イロハ順では、オ、ヰ、ヱより先にヲ、イ、エのほうが先に登場する.
このため、オとヲを結合して立項した場合、ヲの項に入れたほうがよいと考えたのではないかと思う.
また、同様の性格を持つイ、エがア行にあるのなら一緒にしようということも考えられる.
ただ、今までヲの項にまとめられていたのが、急にオのところに入ったのでは混乱を招く.
これがアイウエヲという配列の理由ではないかと思っている.
結局、あまりスマートでない解答になってしまうのだが、アイウエヲの理由を考えると、これぐらいしか思いつかない.
読者諸賢の御意見を伺いたいと思っている.
2016年6月22日
Up
Down
#162
もしかすると、アイウエヲという一般的でない配置は、イロハ順を引きずっているのではないかと思う.
イロハ順では、オ、ヰ、ヱより先にヲ、イ、エのほうが先に登場する.
このため、オとヲを結合して立項した場合、ヲの項に入れたほうがよいと考えたのではないかと思う.
また、同様の性格を持つイ、エがア行にあるのなら一緒にしようということも考えられる.
ただ、今までヲの項にまとめられていたのが、急にオのところに入ったのでは混乱を招く.
これがアイウエヲという配列の理由ではないかと思っている.
結局、あまりスマートでない解答になってしまうのだが、アイウエヲの理由を考えると、これぐらいしか思いつかない.
読者諸賢の御意見を伺いたいと思っている.
2016年6月22日
Up Down
#163
タヌキをシンガポールの動物園に贈呈したら、パンダ並みに歓迎式典を開いてもらったという話がある.
実は、タヌキは、日本の他には、朝鮮半島と中国、ロシアの東部にしかいない.
もっとも、戦前、毛皮を採る目的でソ連に導入されたタヌキが野生化しており、国境を越えてフィンランドやドイツ辺りまで進出している.
したがって、Wikipediaでタヌキを引いて、ロシア語版やドイツ語版を開いてみると、現地名が出てくるが、
イタリア語版やスペイン語版等では、学名が見出しに使われている.
また、フランス語では、見出しこそ現地名であるが、その下に学名が使われている.
そして、多くの版で文中にTanukiという言葉が使われている.
タヌキは、実は珍しい動物なのである.
2016年6月23日
Up
Down
#163
タヌキをシンガポールの動物園に贈呈したら、パンダ並みに歓迎式典を開いてもらったという話がある.
実は、タヌキは、日本の他には、朝鮮半島と中国、ロシアの東部にしかいない.
もっとも、戦前、毛皮を採る目的でソ連に導入されたタヌキが野生化しており、国境を越えてフィンランドやドイツ辺りまで進出している.
したがって、Wikipediaでタヌキを引いて、ロシア語版やドイツ語版を開いてみると、現地名が出てくるが、
イタリア語版やスペイン語版等では、学名が見出しに使われている.
また、フランス語では、見出しこそ現地名であるが、その下に学名が使われている.
そして、多くの版で文中にTanukiという言葉が使われている.
タヌキは、実は珍しい動物なのである.
2016年6月23日
Up Down
#164
しかし、タヌキは、日本では珍しい動物ではない.
市街地にもいるらしく、時折、不幸にも交通事故に遭ったらしいのが転がっている.
鎌倉で、タヌキに餌をやっている人も知っている.
にもかかわらず、シンガポールではパンダ並みの歓迎を受けたし、写真を見ると実に立派な獣舎の中で飼われている.
それどころか、石川の動物園が世界3大珍獣の1つとされるコビトカバを贈呈してもらった際に、代わりにリクエストされたのがタヌキだったというのだから驚く.
2016年6月26日
Up
Down
#164
しかし、タヌキは、日本では珍しい動物ではない.
市街地にもいるらしく、時折、不幸にも交通事故に遭ったらしいのが転がっている.
鎌倉で、タヌキに餌をやっている人も知っている.
にもかかわらず、シンガポールではパンダ並みの歓迎を受けたし、写真を見ると実に立派な獣舎の中で飼われている.
それどころか、石川の動物園が世界3大珍獣の1つとされるコビトカバを贈呈してもらった際に、代わりにリクエストされたのがタヌキだったというのだから驚く.
2016年6月26日
Up Down
#165
シンガポールでそこまで厚遇される理由を考えていって、これはアニメのせいではないかと思った.
御多分に漏れず、シンガポールでも日本のアニメは大人気である.
そして、日本のアニメだから、タヌキが登場するのかも知れないと人に話していたら、実際にそういう作品があると教えてもらった.
調べると、1994年に公開された「平成狸合戦ぽんぽこ」という映画らしい.
Wikipediaを見ると、各国語版がリンクされているので、いろいろな国で上映されたのだろうと思う.
うち、英語版はPom Pokoという名で公開されている.
多分、シンガポールでも、その名で公開されたはずである.
ところが、主役のタヌキが何かわからない.
分からないとなると見たくなる.
まして、そういうアニメを喜ぶのは子供たちであり、動物園の顧客層と重なるのである.
そういう欲求があったから、動物園でもコビトカバと交換してもとなったのではないかと思う.
もっとも、タヌキでコビトカバを釣るという諺はまだない.
2016年6月29日
Up
Down
#165
シンガポールでそこまで厚遇される理由を考えていって、これはアニメのせいではないかと思った.
御多分に漏れず、シンガポールでも日本のアニメは大人気である.
そして、日本のアニメだから、タヌキが登場するのかも知れないと人に話していたら、実際にそういう作品があると教えてもらった.
調べると、1994年に公開された「平成狸合戦ぽんぽこ」という映画らしい.
Wikipediaを見ると、各国語版がリンクされているので、いろいろな国で上映されたのだろうと思う.
うち、英語版はPom Pokoという名で公開されている.
多分、シンガポールでも、その名で公開されたはずである.
ところが、主役のタヌキが何かわからない.
分からないとなると見たくなる.
まして、そういうアニメを喜ぶのは子供たちであり、動物園の顧客層と重なるのである.
そういう欲求があったから、動物園でもコビトカバと交換してもとなったのではないかと思う.
もっとも、タヌキでコビトカバを釣るという諺はまだない.
2016年6月29日
Up Down
#166
ブラジル人と話していて、日本ではキツネやタヌキが人を化かすと言ったら、キツネは通じたのだが、タヌキが通じなかった.
だいたい、なぜ、動物が人に化けたりするのかと言う.
たしかにヨーロッパでは、多くの神話に変身譚はあるが、その多くは神や人間が動物に化けるのであって、その逆はないように思う.
また、「聖書」には、どちらの変身譚もなさそうである.
このあたり、動物に心があるとしないキリスト教の教義と反するからかもしれないが、敬虔なカソリック信者の多い南アメリカでは、あまり語られないことなのだろう.
それに、この「平成狸合戦ぽんぽこ」は、メキシコでは公開されたようだが、調べた限りでは、南アメリカ各国ではそうではない.
タヌキを知らないのも当然なのである.
したがって、南アメリカの動物園に、タヌキと交換でというのは難しいだろう.
2016年7月2日
Up
Down
#166
ブラジル人と話していて、日本ではキツネやタヌキが人を化かすと言ったら、キツネは通じたのだが、タヌキが通じなかった.
だいたい、なぜ、動物が人に化けたりするのかと言う.
たしかにヨーロッパでは、多くの神話に変身譚はあるが、その多くは神や人間が動物に化けるのであって、その逆はないように思う.
また、「聖書」には、どちらの変身譚もなさそうである.
このあたり、動物に心があるとしないキリスト教の教義と反するからかもしれないが、敬虔なカソリック信者の多い南アメリカでは、あまり語られないことなのだろう.
それに、この「平成狸合戦ぽんぽこ」は、メキシコでは公開されたようだが、調べた限りでは、南アメリカ各国ではそうではない.
タヌキを知らないのも当然なのである.
したがって、南アメリカの動物園に、タヌキと交換でというのは難しいだろう.
2016年7月2日
Up Down
#167
なぜ、キツネやタヌキが人を化かすかというと、中国の影響である.
狐狸精という言葉があり、中国では、狐狸は人をたぶらかすものとされていたからである.
ただし、現代中国語で、狐狸はキツネとタヌキを指すわけではない.
狐狸は、その2文字でキツネを指す語だからである.
そして、どうやら、それは昔かららしい.
また、狐はキツネだが、狸はタヌキを意味しない.
現代中国語では、タヌキを意味する漢字は貉だからである.
ただし、日本では、貉はムジナと読む.
2016年7月4日
Up
Down
#167
なぜ、キツネやタヌキが人を化かすかというと、中国の影響である.
狐狸精という言葉があり、中国では、狐狸は人をたぶらかすものとされていたからである.
ただし、現代中国語で、狐狸はキツネとタヌキを指すわけではない.
狐狸は、その2文字でキツネを指す語だからである.
そして、どうやら、それは昔かららしい.
また、狐はキツネだが、狸はタヌキを意味しない.
現代中国語では、タヌキを意味する漢字は貉だからである.
ただし、日本では、貉はムジナと読む.
2016年7月4日
Up Down
#168
芥川龍之介に「貉(むじな)」という小品がある.
その冒頭に「書紀によると、日本では、推古天皇の三十五年春二月、陸奥で始めて、貉が人に化けた」とある.
これは、文中にもあるように、「日本書紀」の「(推古)卅五年春二月、陸奧国有狢、化人以歌之」という記述に基づくものである.
狢が人に化けて歌を歌ったというのである.
そして、これが動物が人に化けた本邦での最初の例であるらしい.
推古天皇の時代は、中国文化全盛の時代であるので、この狢も大陸から伝わってきたものかもしれない.
しかし、ムジナとは何であろうか.
2016年7月9日
Up
Down
#168
芥川龍之介に「貉(むじな)」という小品がある.
その冒頭に「書紀によると、日本では、推古天皇の三十五年春二月、陸奥で始めて、貉が人に化けた」とある.
これは、文中にもあるように、「日本書紀」の「(推古)卅五年春二月、陸奧国有狢、化人以歌之」という記述に基づくものである.
狢が人に化けて歌を歌ったというのである.
そして、これが動物が人に化けた本邦での最初の例であるらしい.
推古天皇の時代は、中国文化全盛の時代であるので、この狢も大陸から伝わってきたものかもしれない.
しかし、ムジナとは何であろうか.
2016年7月9日
Up Down
#169
「広辞苑」によると、ムジナはアナグマのことである.
1970年代には年間7000頭のアナグマが狩猟されたとあるので、そう珍しい生き物ではなかったらしい.
それが80年代には、年間2000頭となっているので、それなりに数を減らしているようである.
そして、アナグマは、その名の通り、穴の中に住んでいる.
したがって、人目に触れることが少ないのか、私は見たことがない.
里山に住むとあるが、生息地域が異なるのかもしれない.
ただ、写真で見ると、タヌキと似た姿をしている.
そして、擬死、つまり、死んだ真似をする点でも似ている.
2016年7月13日
Up
Down
#169
「広辞苑」によると、ムジナはアナグマのことである.
1970年代には年間7000頭のアナグマが狩猟されたとあるので、そう珍しい生き物ではなかったらしい.
それが80年代には、年間2000頭となっているので、それなりに数を減らしているようである.
そして、アナグマは、その名の通り、穴の中に住んでいる.
したがって、人目に触れることが少ないのか、私は見たことがない.
里山に住むとあるが、生息地域が異なるのかもしれない.
ただ、写真で見ると、タヌキと似た姿をしている.
そして、擬死、つまり、死んだ真似をする点でも似ている.
2016年7月13日
Up Down
#170
1924年2月29日、栃木県の猟師がタヌキ2匹を洞窟に追い込み、入口を塞いで逃げられないようにした.
そして、3月3日になって洞窟を開いて、これを狩った.
ところが、狩猟法は、3月1日以降、タヌキを捕獲してはならないと定められていたため、猟師は逮捕された.
しかし、猟師は、自分が捕らえたのはムジナであって、タヌキではないと主張したのである.
というのは、この猟師の住む地域では、タヌキをムジナと呼び、アナグマをタヌキと呼んでいたからである.
このため、アナグマはだめだが、タヌキは捕ってもよいと考えていたと主張し、大審院まで争った.
翌年、出た判決は無罪であった.
実質的に、3月1日以前に捕獲していたこともあるが、猟師の主張が全面的に認められたからである.
2016年7月18日
Up
Down
#170
1924年2月29日、栃木県の猟師がタヌキ2匹を洞窟に追い込み、入口を塞いで逃げられないようにした.
そして、3月3日になって洞窟を開いて、これを狩った.
ところが、狩猟法は、3月1日以降、タヌキを捕獲してはならないと定められていたため、猟師は逮捕された.
しかし、猟師は、自分が捕らえたのはムジナであって、タヌキではないと主張したのである.
というのは、この猟師の住む地域では、タヌキをムジナと呼び、アナグマをタヌキと呼んでいたからである.
このため、アナグマはだめだが、タヌキは捕ってもよいと考えていたと主張し、大審院まで争った.
翌年、出た判決は無罪であった.
実質的に、3月1日以前に捕獲していたこともあるが、猟師の主張が全面的に認められたからである.
2016年7月18日
Up Down
#171
この判決のせいか、「広辞苑」には、ムジナの説明として、「混同してタヌキをムジナと呼ぶこともある」と記してある.
しかし、タヌキとムジナ、それにアナグマの区別は混沌としている.
ムジナは、地域によって、タヌキだったり、アナグマだったりするからだが、場合によってはハクビシンをムジナと呼ぶことすらある.
ただ、ムジナは東日本での使用例が目立ち、西日本、特に近畿圏はタヌキが多いが、西日本、特に九州南部はムジナが優勢である.
柳田国男が「蝸牛考」で述べている方言周圏論、つまり、方言というのは昔の都言葉であるという考えで行くと、
ムジナはタヌキに先行する言葉であるということになる.
2016年7月27日
Up
Down
#171
この判決のせいか、「広辞苑」には、ムジナの説明として、「混同してタヌキをムジナと呼ぶこともある」と記してある.
しかし、タヌキとムジナ、それにアナグマの区別は混沌としている.
ムジナは、地域によって、タヌキだったり、アナグマだったりするからだが、場合によってはハクビシンをムジナと呼ぶことすらある.
ただ、ムジナは東日本での使用例が目立ち、西日本、特に近畿圏はタヌキが多いが、西日本、特に九州南部はムジナが優勢である.
柳田国男が「蝸牛考」で述べている方言周圏論、つまり、方言というのは昔の都言葉であるという考えで行くと、
ムジナはタヌキに先行する言葉であるということになる.
2016年7月27日
Up Down
#172
実際、ムジナという言葉の歴史は長い.
芥川も紹介しているのだが、「日本書紀」、垂仁天皇の87年2月5日の条には「牟士那」と出ている.
垂仁というと、第10代天皇とされる人物であり、推古は第33代なので、随分と前の天皇ということになる.
文面は「是犬咋山獣名牟士那而殺之(是の犬、山の獣、名を牟士那というを咋いて殺しつ)」というものである.
物語は、この牟士那の腹から勾玉が出てきたというのだが、これがタヌキなのかアナグマなのかは分からない.
また、「山獣」とあるだけなので、この両者のどちらでもない可能性もある.
ただ、犬に食い殺されたとあるので、猪や鹿、あるいは、熊や狼のような大型獣や肉食獣よりも可能性は高いと思われる.
また、牟士那とは部族の名であり、これを打倒して宝物を奪ったということを述べたものだという説もあるが、
とりあえず、動物名としておく.
2016年8月4日
Up
Down
#172
実際、ムジナという言葉の歴史は長い.
芥川も紹介しているのだが、「日本書紀」、垂仁天皇の87年2月5日の条には「牟士那」と出ている.
垂仁というと、第10代天皇とされる人物であり、推古は第33代なので、随分と前の天皇ということになる.
文面は「是犬咋山獣名牟士那而殺之(是の犬、山の獣、名を牟士那というを咋いて殺しつ)」というものである.
物語は、この牟士那の腹から勾玉が出てきたというのだが、これがタヌキなのかアナグマなのかは分からない.
また、「山獣」とあるだけなので、この両者のどちらでもない可能性もある.
ただ、犬に食い殺されたとあるので、猪や鹿、あるいは、熊や狼のような大型獣や肉食獣よりも可能性は高いと思われる.
また、牟士那とは部族の名であり、これを打倒して宝物を奪ったということを述べたものだという説もあるが、
とりあえず、動物名としておく.
2016年8月4日
Up Down
#173
一方、タヌキという語の登場は随分と遅れる.
一応、平安時代初期に成立したとされる「霊異記」には狸という文字が出てくる.
しかし、904年に書写された記された興福寺本の該当箇所には、不思議なことが書いてある.
第30縁の最後のところ、狸の部分に「弥こ」と書いてあるのだ.
つまり、この狸という文字はネコと読めというのである.
しかし、タヌキがネコであるというのは奇妙な話である.
2016年8月26日
Up
Down
#173
一方、タヌキという語の登場は随分と遅れる.
一応、平安時代初期に成立したとされる「霊異記」には狸という文字が出てくる.
しかし、904年に書写された記された興福寺本の該当箇所には、不思議なことが書いてある.
第30縁の最後のところ、狸の部分に「弥こ」と書いてあるのだ.
つまり、この狸という文字はネコと読めというのである.
しかし、タヌキがネコであるというのは奇妙な話である.
2016年8月26日
Up Down
#174
ただ、「新撰字鏡」という平安時代の漢和辞典には「貍力疑反猫也似虎小亡交反祢古」とある.
ここでは、狸ではなく貍が使われているが、猫であると明確に記され、「祢古(ねこ)」と読むと記されている.
しかも、「似虎小(虎に似て小さし)」であるので、タヌキよりもネコのほうがふさわしい.
(なお、力疑反、亡交反は漢字の読み方を記したもので、貍はリ、猫はミャオと読む意)
また、「本草和名」という同時代の本草書には「家狸 一名猫 和名祢古末(ねこま)」とある.
そして、ねこまというのはネコの別名であるので、狸は、平安時代においてはネコだったと考えるしかない.
2016年8月18日
Up
Down
#174
ただ、「新撰字鏡」という平安時代の漢和辞典には「貍力疑反猫也似虎小亡交反祢古」とある.
ここでは、狸ではなく貍が使われているが、猫であると明確に記され、「祢古(ねこ)」と読むと記されている.
しかも、「似虎小(虎に似て小さし)」であるので、タヌキよりもネコのほうがふさわしい.
(なお、力疑反、亡交反は漢字の読み方を記したもので、貍はリ、猫はミャオと読む意)
また、「本草和名」という同時代の本草書には「家狸 一名猫 和名祢古末(ねこま)」とある.
そして、ねこまというのはネコの別名であるので、狸は、平安時代においてはネコだったと考えるしかない.
2016年8月18日
Up Down
#175
ところで、「霊異記」上巻第30は、次のような物語である.
膳臣宏国が地獄に行き、父親と出遭ったが、その際、大蛇、赤狗、狸になって家に行ったと言う.
大蛇や赤狗の時には邪慳に扱われたが、狸になった際には御馳走をもらえた.
それで、3年間の空腹を癒やすことができたと言うのである.
しかし、この狸がタヌキであったならば、食べ物をもらえただろうか.
家に入っていった時点で追い払われるのではないだろうか.
たとえば、蛇になった時には杖で追い払われている.
これは、蛇を嫌う人が多いので、当然のことであろう.
しかし、赤狗になった時には、他の犬をけしかけれて退散せざるを得なかったのである.
狗と犬が使い分けられているが、狗は仔犬の意味である.
仔犬が追い払われるのに、タヌキが歓迎されるということがあるのだろうか.
ないとは言わないが、ここはネコのほうが読者の共感を得やすい.
したがって、この狸はネコである.
2016年9月7日
Up
Down
#175
ところで、「霊異記」上巻第30は、次のような物語である.
膳臣宏国が地獄に行き、父親と出遭ったが、その際、大蛇、赤狗、狸になって家に行ったと言う.
大蛇や赤狗の時には邪慳に扱われたが、狸になった際には御馳走をもらえた.
それで、3年間の空腹を癒やすことができたと言うのである.
しかし、この狸がタヌキであったならば、食べ物をもらえただろうか.
家に入っていった時点で追い払われるのではないだろうか.
たとえば、蛇になった時には杖で追い払われている.
これは、蛇を嫌う人が多いので、当然のことであろう.
しかし、赤狗になった時には、他の犬をけしかけれて退散せざるを得なかったのである.
狗と犬が使い分けられているが、狗は仔犬の意味である.
仔犬が追い払われるのに、タヌキが歓迎されるということがあるのだろうか.
ないとは言わないが、ここはネコのほうが読者の共感を得やすい.
したがって、この狸はネコである.
2016年9月7日
Up Down
#176
もちろん、昔はタヌキのことをネコと言ったのだという考え方もできる.
しかし、それでは「新撰字鏡」にある「似虎小(虎に似て小さし)」と合わない.
タヌキが虎に似ているとは思えないからである.
また、「霊異記」より先に書かれた奈良時代の「新訳華厳経音義私記」に「猫狸、猫捕鼠也、貍狸也、又云野貍、倭言上尼古、下多々既」とある.
「猫狸、猫は鼠を捕る也.貍狸也.又野貍と云う.倭言上は尼古、下は多々既)」であるので、狸は「尼古(ネコ)」と呼ばれており、「鼠を捕る」のである.
しかし、タヌキがネズミを捕るというのは、寡聞にして聞かない.
したがって、タヌキはムジナであり、ネコとは言わなかったということになる.
2016年9月11日
Up
Down
#176
もちろん、昔はタヌキのことをネコと言ったのだという考え方もできる.
しかし、それでは「新撰字鏡」にある「似虎小(虎に似て小さし)」と合わない.
タヌキが虎に似ているとは思えないからである.
また、「霊異記」より先に書かれた奈良時代の「新訳華厳経音義私記」に「猫狸、猫捕鼠也、貍狸也、又云野貍、倭言上尼古、下多々既」とある.
「猫狸、猫は鼠を捕る也.貍狸也.又野貍と云う.倭言上は尼古、下は多々既)」であるので、狸は「尼古(ネコ)」と呼ばれており、「鼠を捕る」のである.
しかし、タヌキがネズミを捕るというのは、寡聞にして聞かない.
したがって、タヌキはムジナであり、ネコとは言わなかったということになる.
2016年9月11日
Up Down
#177
もっとも、「広辞苑」で「たたけ」という語を引くと、「タヌキの異称」とあり、その出典が前回述べた「華厳経音義私記」となっている.
日本語で下賤の者は「多々既(タタケ)」と呼ぶとあり、狸の文字があることからそのようにしたのであろう.
しかし、前述のように、タヌキがネズミを捕ると特筆される存在であるのかとかという問題がある.
そして、「又野貍と云う」という言葉が気になる.
野ネズミという言葉は、家ネズミ、つまり、通常、我々がネズミという言葉で想起するネズミと分けた語である.
そして、野猪という言葉は豚に対するものである.
野犬だとか、野ウサギという言葉も同様である.
しかし、野ジカとか、野ギツネというような言葉は聞かない.
シカにしろ、キツネにしろ、家にいる動物ではないからである.
したがって、わざわざ、野という言葉を冠する必要性がない.
タヌキも、また、同様である.
だとすれば、貍をタヌキと解する限り、野貍というという言葉は意味をなさない.
にもかかわらず、野貍と書かれているのは、貍がタヌキを指す語ではないからである.
2016年9月24日
Up
Down
#177
もっとも、「広辞苑」で「たたけ」という語を引くと、「タヌキの異称」とあり、その出典が前回述べた「華厳経音義私記」となっている.
日本語で下賤の者は「多々既(タタケ)」と呼ぶとあり、狸の文字があることからそのようにしたのであろう.
しかし、前述のように、タヌキがネズミを捕ると特筆される存在であるのかとかという問題がある.
そして、「又野貍と云う」という言葉が気になる.
野ネズミという言葉は、家ネズミ、つまり、通常、我々がネズミという言葉で想起するネズミと分けた語である.
そして、野猪という言葉は豚に対するものである.
野犬だとか、野ウサギという言葉も同様である.
しかし、野ジカとか、野ギツネというような言葉は聞かない.
シカにしろ、キツネにしろ、家にいる動物ではないからである.
したがって、わざわざ、野という言葉を冠する必要性がない.
タヌキも、また、同様である.
だとすれば、貍をタヌキと解する限り、野貍というという言葉は意味をなさない.
にもかかわらず、野貍と書かれているのは、貍がタヌキを指す語ではないからである.
2016年9月24日
Up Down
#178
では、「野ネコ」はいたのだろうか.
現在では野良猫というものがおり、猫好きの人を和ませ、そうでない人達の顰蹙を買っている.
しかし、そういう野良猫が昔からいたかというと、そうでもなさそうである.
というのは、ネコは奈良時代に伝わったものとされ、舶来の貴重な動物として珍重されたとなっているからである.
実際、「源氏物語」には女三宮の飼うネコが重要な役割をする.
また、「枕草子」には「命婦のおとど」と名付けられた一条天皇の飼猫が登場する.
一条天皇はもちろん帝だが、女三宮も朱雀院の第3皇女という高貴な出であるという設定である.
そういう高貴な身分の人達が飼うもの、それがネコだったのである.
そして、貴重な存在であったがゆえに紐に結ばれて飼われていたのである.
これに対して、イヌはその辺りを適当にさ迷っていた.
つまり、現代と飼い方が逆なのだが、そこに野良猫の出現する余地はなさそうである.
2016年10月15日
Up
Down
#178
では、「野ネコ」はいたのだろうか.
現在では野良猫というものがおり、猫好きの人を和ませ、そうでない人達の顰蹙を買っている.
しかし、そういう野良猫が昔からいたかというと、そうでもなさそうである.
というのは、ネコは奈良時代に伝わったものとされ、舶来の貴重な動物として珍重されたとなっているからである.
実際、「源氏物語」には女三宮の飼うネコが重要な役割をする.
また、「枕草子」には「命婦のおとど」と名付けられた一条天皇の飼猫が登場する.
一条天皇はもちろん帝だが、女三宮も朱雀院の第3皇女という高貴な出であるという設定である.
そういう高貴な身分の人達が飼うもの、それがネコだったのである.
そして、貴重な存在であったがゆえに紐に結ばれて飼われていたのである.
これに対して、イヌはその辺りを適当にさ迷っていた.
つまり、現代と飼い方が逆なのだが、そこに野良猫の出現する余地はなさそうである.
2016年10月15日
Up Down
#179
しかし、本当に奈良時代以前にはネコはいなかったのだろうか.
一応、紀元前1世紀、弥生時代中期のネコの骨は出ている.
ただし、壱岐島でである.
壱岐と朝鮮半島の距離は近いので、そちらから誰かが連れてきたものではないかと思う.
したがって、壱岐から出たからといって、本土にネコが生息していたとはいえない.
ただし、中国大陸にネコがやってきたのは5世紀だそうである.
したがって、紀元前1世紀の日本でネコの骨が出土するというのがおかしい.
ただ、「礼記(らいき)」という本には、「迎猫為其食田鼠也(猫を迎えるは、それ田の鼠を食べる為なり)」という一文がある.
田のネズミを食べるからネコを迎えて祭るというのだから、「礼記」の時代にはネコはいたと考えるほうがよい.
そして、この本と同じ内容の竹簡が中国の墓から出土しているが、この墓の年代は紀元前300年頃のものとされるのである.
したがって、壱岐でネコの骨が見つかっても不思議はない.
しかし、だからといって、弥生時代に日本本土にネコが住んでいたということにはならないのである.
そして、その次に古いネコの骨が出土するのは、鎌倉時代のものなのである.
2016年10月24日
Up
Down
#179
しかし、本当に奈良時代以前にはネコはいなかったのだろうか.
一応、紀元前1世紀、弥生時代中期のネコの骨は出ている.
ただし、壱岐島でである.
壱岐と朝鮮半島の距離は近いので、そちらから誰かが連れてきたものではないかと思う.
したがって、壱岐から出たからといって、本土にネコが生息していたとはいえない.
ただし、中国大陸にネコがやってきたのは5世紀だそうである.
したがって、紀元前1世紀の日本でネコの骨が出土するというのがおかしい.
ただ、「礼記(らいき)」という本には、「迎猫為其食田鼠也(猫を迎えるは、それ田の鼠を食べる為なり)」という一文がある.
田のネズミを食べるからネコを迎えて祭るというのだから、「礼記」の時代にはネコはいたと考えるほうがよい.
そして、この本と同じ内容の竹簡が中国の墓から出土しているが、この墓の年代は紀元前300年頃のものとされるのである.
したがって、壱岐でネコの骨が見つかっても不思議はない.
しかし、だからといって、弥生時代に日本本土にネコが住んでいたということにはならないのである.
そして、その次に古いネコの骨が出土するのは、鎌倉時代のものなのである.
2016年10月24日
Up Down
#180
一般に、ネコは仏教伝来とともに日本に伝わったとされる.
そして、ネズミを捕るものとして重視された.
「新訳華厳経音義私記」に「鼠を捕る」と注記されたのはそのせいである.
また、ネズミは経典を齧る.
つまり、仏教の側から考えると、ネコは殺生するものではあるが、経典を守るものでもある.
「霊異記」で狸が食べ物を漁れたのは、このためである.
そして、それは奈良時代のことであったとされる.
しかし、この奈良時代渡来説はひょんなことからひっくり返る.
2016年11月4日
Up
Down
#180
一般に、ネコは仏教伝来とともに日本に伝わったとされる.
そして、ネズミを捕るものとして重視された.
「新訳華厳経音義私記」に「鼠を捕る」と注記されたのはそのせいである.
また、ネズミは経典を齧る.
つまり、仏教の側から考えると、ネコは殺生するものではあるが、経典を守るものでもある.
「霊異記」で狸が食べ物を漁れたのは、このためである.
そして、それは奈良時代のことであったとされる.
しかし、この奈良時代渡来説はひょんなことからひっくり返る.
2016年11月4日
Up Down
#181
2007年、出土した須恵器を洗っていた大学生が、表面に足跡を見つけた.
鑑定の結果、これはネコのものであるとされた.
そして、この須恵器は6世紀末から7世紀前半のものと考えられている.
つまり、100年ほどではあるが、奈良時代より前に、日本にネコがいたということになる.
出土地は兵庫県姫路市の古墳である.
畿内とはいえ、都から離れた場所にネコがいたということになる.
2016年11月11日
#182
もっとも、足跡がついたのは焼く前である.
完成品の上を歩いた跡なら、洗った時に流される.
当然、乾かしている最中にネコが通り、そのまま焼いたということだろう.
したがって、発見地は姫路だが、焼かれたのは姫路とは限らない.
2016年11月19日
Up
Down
#181
2007年、出土した須恵器を洗っていた大学生が、表面に足跡を見つけた.
鑑定の結果、これはネコのものであるとされた.
そして、この須恵器は6世紀末から7世紀前半のものと考えられている.
つまり、100年ほどではあるが、奈良時代より前に、日本にネコがいたということになる.
出土地は兵庫県姫路市の古墳である.
畿内とはいえ、都から離れた場所にネコがいたということになる.
2016年11月11日
#182
もっとも、足跡がついたのは焼く前である.
完成品の上を歩いた跡なら、洗った時に流される.
当然、乾かしている最中にネコが通り、そのまま焼いたということだろう.
したがって、発見地は姫路だが、焼かれたのは姫路とは限らない.
2016年11月19日
Up Down
#183
古代の窯跡は人里離れた場所で見つかることが多い.
大量の薪が必要だったからである.
また、材料となる粘土が入手できることも必要だった.
登り窯で焼くのなら、起伏のない傾斜地も必要である.
そのような条件を満たすには、人里の近辺では難しい.
だとすれば、この足跡をつけたネコは、野良という可能性もある.
2016年11月22日
Up
Down
#183
古代の窯跡は人里離れた場所で見つかることが多い.
大量の薪が必要だったからである.
また、材料となる粘土が入手できることも必要だった.
登り窯で焼くのなら、起伏のない傾斜地も必要である.
そのような条件を満たすには、人里の近辺では難しい.
だとすれば、この足跡をつけたネコは、野良という可能性もある.
2016年11月22日
Up Down
#184
もちろん、それがヤマネコであったという可能性はある.
ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコというのが、現在も生息しているからである.
オオヤマネコの骨も本土から出土する.
ただし、青森県で弥生時代のものが出土しているが、それ以外は縄文時代までのものである.
そして、ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコは島の固有種であって、日本本土産ではない.
しかも、ヤマネコは、イエネコよりもピューマのほうが近いといわれる生き物である.
よしんば、その当時に生き残っていたとしても、人家の近くをうろつき、須恵器に足跡を残すような可能性は薄い.
2016年12月1日
Up
Down
#184
もちろん、それがヤマネコであったという可能性はある.
ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコというのが、現在も生息しているからである.
オオヤマネコの骨も本土から出土する.
ただし、青森県で弥生時代のものが出土しているが、それ以外は縄文時代までのものである.
そして、ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコは島の固有種であって、日本本土産ではない.
しかも、ヤマネコは、イエネコよりもピューマのほうが近いといわれる生き物である.
よしんば、その当時に生き残っていたとしても、人家の近くをうろつき、須恵器に足跡を残すような可能性は薄い.
2016年12月1日
Up Down
#185
したがって、奈良時代より前、山野を自由にネコが徘徊していたということになる.
ただし、そのネコが野良猫であったとは簡単には言えない.
須恵器を焼く職人が飼っていたという可能性があるからである.
しかも、須恵器は朝鮮半島から伝わってきたものである.
そして、職人も渡来系の人々が多かった.
そして、その職人がかの国からネコを連れてきたという可能性があるのである.
奈良時代以前からネコはいたが、野良になるほどたくさんいたとは限らないというのが、穏当なところであろう.
2016年12月7日
Up
Down
#185
したがって、奈良時代より前、山野を自由にネコが徘徊していたということになる.
ただし、そのネコが野良猫であったとは簡単には言えない.
須恵器を焼く職人が飼っていたという可能性があるからである.
しかも、須恵器は朝鮮半島から伝わってきたものである.
そして、職人も渡来系の人々が多かった.
そして、その職人がかの国からネコを連れてきたという可能性があるのである.
奈良時代以前からネコはいたが、野良になるほどたくさんいたとは限らないというのが、穏当なところであろう.
2016年12月7日
Up Down
#186
しかし、まだ、「たたけ」という言葉が残っているではないかと言われそうである.
前述のように、「華厳経音義私記」には、下賤の者は狸を「多々既(タタケ)」と呼ぶとある.
そして、この語はタヌキのほうがネコよりも音が近い.
ただ、ネコの方言を調べると、岩手県に「たた」というのはあるが、タヌキを意味する方言には、「たたけ」に似た言葉は見当たらないそうである.
この間、ネコがえずいてと言う人がいたので、それはどういう意味の言葉かと聞いたら、ネコが吐いたという意味だそうだ.
「せぐる」とは言うが、「えずく」とは言わないと言うと、「せぐる」のほうが言わないと突っ込まれたのだが、実は「えずく」も「せぐる」も古い日本語である.
また、うちの田舎では、ヘビのことを「くちなわ」と言うが、これも「枕草子」に登場する言葉である.
前にも書いたが、方言は昔の日本語の面影を遺しているからである.
したがって、「たたけ」がタヌキの意味であるのなら、どこかにそういう方言が残っていてもいいはずである.
しかし、実際にはネコの方言としか残っていないのだから、「たたけ」はタヌキではないということになる.
2016年12月14日
Up
Down
#186
しかし、まだ、「たたけ」という言葉が残っているではないかと言われそうである.
前述のように、「華厳経音義私記」には、下賤の者は狸を「多々既(タタケ)」と呼ぶとある.
そして、この語はタヌキのほうがネコよりも音が近い.
ただ、ネコの方言を調べると、岩手県に「たた」というのはあるが、タヌキを意味する方言には、「たたけ」に似た言葉は見当たらないそうである.
この間、ネコがえずいてと言う人がいたので、それはどういう意味の言葉かと聞いたら、ネコが吐いたという意味だそうだ.
「せぐる」とは言うが、「えずく」とは言わないと言うと、「せぐる」のほうが言わないと突っ込まれたのだが、実は「えずく」も「せぐる」も古い日本語である.
また、うちの田舎では、ヘビのことを「くちなわ」と言うが、これも「枕草子」に登場する言葉である.
前にも書いたが、方言は昔の日本語の面影を遺しているからである.
したがって、「たたけ」がタヌキの意味であるのなら、どこかにそういう方言が残っていてもいいはずである.
しかし、実際にはネコの方言としか残っていないのだから、「たたけ」はタヌキではないということになる.
2016年12月14日
Up Down
#187
江戸時代、1776年に鳥山石燕が描いた「画図百鬼夜行」に狸の絵が収められている.
しかし、この絵の生物は、タヌキには見えない.
まず、尻尾が長い.
顔つきも、毛色も、タヌキと異なる.
だいたい、タヌキを特徴づけている目の下の黒い部分がない.
脚も黒くない.
イヌでなければ、ネコであるが、尻尾の形状はネコのほうが近い.
にもかかわらず、この絵では月に向かって腹鼓を撃っている.
そして、そのようなことをするとされる動物はタヌキであって、ネコではない.
この矛盾を解消するためには、狸という漢字が、タヌキではなく、ネコを意味していたとするしかない.
しかも、この絵は、1000年前の平安時代ではなく二百数十年前という、比較的近年に描かれたものなのである.
2016年12月19日
Up
Down
#187
江戸時代、1776年に鳥山石燕が描いた「画図百鬼夜行」に狸の絵が収められている.
しかし、この絵の生物は、タヌキには見えない.
まず、尻尾が長い.
顔つきも、毛色も、タヌキと異なる.
だいたい、タヌキを特徴づけている目の下の黒い部分がない.
脚も黒くない.
イヌでなければ、ネコであるが、尻尾の形状はネコのほうが近い.
にもかかわらず、この絵では月に向かって腹鼓を撃っている.
そして、そのようなことをするとされる動物はタヌキであって、ネコではない.
この矛盾を解消するためには、狸という漢字が、タヌキではなく、ネコを意味していたとするしかない.
しかも、この絵は、1000年前の平安時代ではなく二百数十年前という、比較的近年に描かれたものなのである.
2016年12月19日
Up Down
#188
その上、この絵には、「たぬき」と読み方が示されている.
したがって、狸という漢字だけでなく、たぬきという日本語も、ネコを意味する語であったということになる.
実際、「和名類聚抄」という平安時代中期の辞書には、それらしいことが書いてある.
写本の一部に、狸の項のところに、「搏鳥為粮者也」とあるからである.
鳥を搏(う)ちて粮(かて)と為(な)す者なりというのだから、鳥を捕まえて食べるということだろう.
しかも、その狸の項には、「多(太)奴岐(たぬき)」と読みが付してある.
これが「たぬき」という語の初出なのであるが、タヌキは鳥を捕まえて食べるだろうか.
2016年12月21日
#189
Up
Down
#188
その上、この絵には、「たぬき」と読み方が示されている.
したがって、狸という漢字だけでなく、たぬきという日本語も、ネコを意味する語であったということになる.
実際、「和名類聚抄」という平安時代中期の辞書には、それらしいことが書いてある.
写本の一部に、狸の項のところに、「搏鳥為粮者也」とあるからである.
鳥を搏(う)ちて粮(かて)と為(な)す者なりというのだから、鳥を捕まえて食べるということだろう.
しかも、その狸の項には、「多(太)奴岐(たぬき)」と読みが付してある.
これが「たぬき」という語の初出なのであるが、タヌキは鳥を捕まえて食べるだろうか.
2016年12月21日
#189
Up Down
タヌキは雑食である.
ドングリも食べれば、虫も食べる.
意外に思われる方も多いかと思うが、鳥も食べる.
ニワトリを襲うこともある.
2013年に放鳥されたトキの死骸が散乱しているのが見つかったが、食べたのはタヌキだと言われている.
また、イヌ科の動物にしては珍しく、木登りもできる.
ただし、器用さや敏捷性は持ち合わせていない.
したがって、木に止まっている鳥を襲うなどということはできない.
ニワトリは、飛べない上に、動きが緩慢だから襲われるのである.
トキも、弱っていたのを襲われたのだろう.
もしかしたら、食べられた時には死んでいたのかもしれない.
大型哺乳類の死骸をタヌキが漁る場合もあるからである.
しかし、鳥を搏ちて粮と為す者というイメージからはほど遠い.
2016年12月24日
Up
Down
タヌキは雑食である.
ドングリも食べれば、虫も食べる.
意外に思われる方も多いかと思うが、鳥も食べる.
ニワトリを襲うこともある.
2013年に放鳥されたトキの死骸が散乱しているのが見つかったが、食べたのはタヌキだと言われている.
また、イヌ科の動物にしては珍しく、木登りもできる.
ただし、器用さや敏捷性は持ち合わせていない.
したがって、木に止まっている鳥を襲うなどということはできない.
ニワトリは、飛べない上に、動きが緩慢だから襲われるのである.
トキも、弱っていたのを襲われたのだろう.
もしかしたら、食べられた時には死んでいたのかもしれない.
大型哺乳類の死骸をタヌキが漁る場合もあるからである.
しかし、鳥を搏ちて粮と為す者というイメージからはほど遠い.
2016年12月24日
Up Down
#190
以前、我が家で飼っていたネコは、半分野良であったので、時折、鳥を咥えてきた.
知人が飼っていたネコも、ハトを咥えてきたそうだ.
現在のネコは室内飼いだが、窓辺に鳥が来ると、欲しそうに眺めては、低く唸っている.
また、相方の実家はニワトリを飼育していたが、ある日、飼っていたネコがそれを襲ったことがあるらしい.
そこで、可哀想だが、ネコをどうにかしたらしい.
ニワトリの味を覚えたネコは、また、襲うからだそうだ.
つまり、ネコは鳥を搏ちて粮と為す者である.
2016年12月27日
Up
Down
#190
以前、我が家で飼っていたネコは、半分野良であったので、時折、鳥を咥えてきた.
知人が飼っていたネコも、ハトを咥えてきたそうだ.
現在のネコは室内飼いだが、窓辺に鳥が来ると、欲しそうに眺めては、低く唸っている.
また、相方の実家はニワトリを飼育していたが、ある日、飼っていたネコがそれを襲ったことがあるらしい.
そこで、可哀想だが、ネコをどうにかしたらしい.
ニワトリの味を覚えたネコは、また、襲うからだそうだ.
つまり、ネコは鳥を搏ちて粮と為す者である.
2016年12月27日
Up Down
これに対して、呉を「くれ」と読むのは歴史がある.
遣唐使の吉士長丹(きしのながに)が、功績により呉氏という姓を与えられているからである.
中国の正史である「旧唐書(くとうじょ)」には、「日本国者倭国之別種也(日本国は倭国の別種なり)」とある.日本国というのは、倭国の別名であるというのである.そして、日の昇る場所にあるから、倭という言葉を憎んだから、あるいは、日本という小国が倭国を併合したからと、その改名の理由を忖度している.
Down
これに対して、呉を「くれ」と読むのは歴史がある.
遣唐使の吉士長丹(きしのながに)が、功績により呉氏という姓を与えられているからである.
中国の正史である「旧唐書(くとうじょ)」には、「日本国者倭国之別種也(日本国は倭国の別種なり)」とある.日本国というのは、倭国の別名であるというのである.そして、日の昇る場所にあるから、倭という言葉を憎んだから、あるいは、日本という小国が倭国を併合したからと、その改名の理由を忖度している.
「旧唐書」は945年の完成である.したがって、中国のこの国に対する理解は深まっていたはずである.にもかかわらず、このような諸説が並べられているのは、改名が編纂より前であったからである.実際、「旧唐書」を書き改めた「新唐書」では、「咸亨元年遣使賀平高麗後稍習夏音悪倭名更号日本(咸亨元年、高麗を平らげるを賀して遣いし、後稍ありて夏音を習い、倭の名を悪んで、日本と号す)」とある.咸亨元年、唐が高麗を併合したのを祝って使いを送ってきた際に、中国語を習って
咸亨元年とは670年である
南洋諸島と呼ばないで
「蒙古襲来絵詞」
2015
PREVIOUS ☆ NEXT


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
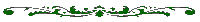 Sasayaki004.
Sasayaki004.
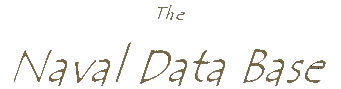 Ver.1.21a.
Ver.1.21a.
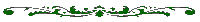 Copyright
(c)
hush ,2001-21. Allrights Reserved.
Copyright
(c)
hush ,2001-21. Allrights Reserved.
Up
動画