Down
無用録
1-
51- 101-
150- 191-
229- 255-
293- 311-
333- 361-
383-
trivia's
trivia
Up Down
#191
伊勢神宮に参拝した最初の天皇は、明治天皇である.
2017年1月1日
Up
Down
#191
伊勢神宮に参拝した最初の天皇は、明治天皇である.
2017年1月1日
Up Down
#192
初詣が行われるようになったのは明治時代中期のことであり、初詣という言葉が一般化したのは大正時代である.
2017年1月3日
Up
Down
#192
初詣が行われるようになったのは明治時代中期のことであり、初詣という言葉が一般化したのは大正時代である.
2017年1月3日
Up Down
#193
Down
#193
 コヴェントリーの市章は城を背負った象である.
城はコヴェントリーの城であるが、象は大きな力を象徴するものであったらしい.
ただ、この紋章は中世に定められたものであるが、この時代のイギリスに象がいたとは思えない.
2017年1月4日
Up
コヴェントリーの市章は城を背負った象である.
城はコヴェントリーの城であるが、象は大きな力を象徴するものであったらしい.
ただ、この紋章は中世に定められたものであるが、この時代のイギリスに象がいたとは思えない.
2017年1月4日
Up Down
#194
「聖書」にも象は登場しない.
ただ、ベヒモスと呼ばれる巨獣は、象がモデルだとも、カバからだともいわれる.
「聖書」におけるこの架空の生物は、どちらかというと聖獣のイメージであったが、中世には悪魔の眷属になった.
そして、しばしば、その姿は象、もしくは象の頭を持った人として捉えられている.
2017年1月5日
Up
Down
#194
「聖書」にも象は登場しない.
ただ、ベヒモスと呼ばれる巨獣は、象がモデルだとも、カバからだともいわれる.
「聖書」におけるこの架空の生物は、どちらかというと聖獣のイメージであったが、中世には悪魔の眷属になった.
そして、しばしば、その姿は象、もしくは象の頭を持った人として捉えられている.
2017年1月5日
Up Down
#195
もっとも、聖書に登場しないからといって、中世ヨーロッパの人々が象を知らなかったわけではない.
実際、「中世 ヨーロッパ 象」で検索すると、いくつもの画像が登場する.
その中には、かなり奇妙なものも混じっているが、特徴は捉えられている.
2017年1月8日
Up
Down
#195
もっとも、聖書に登場しないからといって、中世ヨーロッパの人々が象を知らなかったわけではない.
実際、「中世 ヨーロッパ 象」で検索すると、いくつもの画像が登場する.
その中には、かなり奇妙なものも混じっているが、特徴は捉えられている.
2017年1月8日
Up Down
#196
これは、ハンニバルが象を使って攻め込んだということに由来するのかもしれない.
しかし、それ以上に、「聖書」に象は登場しないが、象牙は出てくるからではないかと思う.
というのは、「middle
ages elephant」で画像検索すると、もっといろいろと出てくるが、
鼻が長い、長い牙を持つという点では、概ね共通しているからである.
2017年1月10日
Up
Down
#196
これは、ハンニバルが象を使って攻め込んだということに由来するのかもしれない.
しかし、それ以上に、「聖書」に象は登場しないが、象牙は出てくるからではないかと思う.
というのは、「middle
ages elephant」で画像検索すると、もっといろいろと出てくるが、
鼻が長い、長い牙を持つという点では、概ね共通しているからである.
2017年1月10日
Up Down
#197
その他の部分は、実際の象とは異なっている.
たとえば、象の特徴である巨大な耳は非常に小さく描かれていたり、なかったりする.
そして、足も、4本指が描かれていたり、蹄があったりする.
それでも、牙が描かれているのは、象牙というのは、象の牙だという知識があったからであろう.
もっとも、その牙は、実際の象とは逆に、下から上に伸びているのだが.
2017年1月12日
Up
Down
#197
その他の部分は、実際の象とは異なっている.
たとえば、象の特徴である巨大な耳は非常に小さく描かれていたり、なかったりする.
そして、足も、4本指が描かれていたり、蹄があったりする.
それでも、牙が描かれているのは、象牙というのは、象の牙だという知識があったからであろう.
もっとも、その牙は、実際の象とは逆に、下から上に伸びているのだが.
2017年1月12日
Up Down
#198
興味深いのは、図の中に、背に構造物を載せた象がいることである.
これは、背の上にいる兵員を守るための櫓である.
兵員は、ここに隠れて矢を射るのである.
つまり、この象は、戦闘用の象、戦象である.
2017年1月13日
#199
ハンニバルが連れて行った象が、このような装備を持っていたかどうかは知らない.
ただ、1567年に描かれたザマの戦いの絵では、そのようになっている.
そして、コヴェントリーの紋章に描かれた城が、この櫓の直接の後裔であることは、疑う必要もないであろう.
この紋章を描いた人物は、象が大きいと聞いて、ありえないほどに大きくしたのである.
2017年1月14日
Up
Down
#198
興味深いのは、図の中に、背に構造物を載せた象がいることである.
これは、背の上にいる兵員を守るための櫓である.
兵員は、ここに隠れて矢を射るのである.
つまり、この象は、戦闘用の象、戦象である.
2017年1月13日
#199
ハンニバルが連れて行った象が、このような装備を持っていたかどうかは知らない.
ただ、1567年に描かれたザマの戦いの絵では、そのようになっている.
そして、コヴェントリーの紋章に描かれた城が、この櫓の直接の後裔であることは、疑う必要もないであろう.
この紋章を描いた人物は、象が大きいと聞いて、ありえないほどに大きくしたのである.
2017年1月14日
Up Down
#200
イギリスに象が渡来したのが、いつなのかは知らない.
ただ、象を意味する英語olifauntは13世紀あたりに登場している.
したがって、この頃には、象というものがいるということになったのだろう.
ところで、今の英語で、象はelephantだから、このolifauntが変化したものであろう.
これは、今でも、フランス語で象をolifantと言うように、フランス語由来の語である.
ただ、これより先、英語にはolfendという、olifauntとよく似た単語もあった.
2017年1月17日
Up
Down
#200
イギリスに象が渡来したのが、いつなのかは知らない.
ただ、象を意味する英語olifauntは13世紀あたりに登場している.
したがって、この頃には、象というものがいるということになったのだろう.
ところで、今の英語で、象はelephantだから、このolifauntが変化したものであろう.
これは、今でも、フランス語で象をolifantと言うように、フランス語由来の語である.
ただ、これより先、英語にはolfendという、olifauntとよく似た単語もあった.
2017年1月17日
Up Down
#201
このolfendの語源は、ギリシャ語のelephantである.
もちろん、意味は象である.
それがラテン語になってelephantus、さらにゲルマン語に入り、古英語ではolfend、古高地ドイツ語ではolbentaとなった.
ところが、この2つの語の意味は、象ではなく、ラクダなのである.
もっとも、ラクダにはcamelという、今と同じ綴りの英語はあった.
しかし、どちらにしろ、実物がいなかったので、象がラクダになってしまったのである.
つまり、中世のイギリスでは、象もラクダも一緒くたの動物であり、その姿は、想像するしかなかったのである.
2017年1月19日
Up
Down
#201
このolfendの語源は、ギリシャ語のelephantである.
もちろん、意味は象である.
それがラテン語になってelephantus、さらにゲルマン語に入り、古英語ではolfend、古高地ドイツ語ではolbentaとなった.
ところが、この2つの語の意味は、象ではなく、ラクダなのである.
もっとも、ラクダにはcamelという、今と同じ綴りの英語はあった.
しかし、どちらにしろ、実物がいなかったので、象がラクダになってしまったのである.
つまり、中世のイギリスでは、象もラクダも一緒くたの動物であり、その姿は、想像するしかなかったのである.
2017年1月19日
Up Down
#202
olifauntはフランス語起源だと書いたが、こちらもラテン語のelephantusに由来する.
したがって、olifauntとolfendという似た単語があったのも仕方はない.
ただ、片方は象を、もう一方はラクダを意味していたのである.
そこで、camelがラクダを意味する語として一般的となり、olfendは消えていった.
そう、古英語の研究家であるイギリスのトールキンが書いている.
もちろん、このトールキンは、「指輪物語」の作者のトールキンのことである.
2017年1月21日
Up
Down
#202
olifauntはフランス語起源だと書いたが、こちらもラテン語のelephantusに由来する.
したがって、olifauntとolfendという似た単語があったのも仕方はない.
ただ、片方は象を、もう一方はラクダを意味していたのである.
そこで、camelがラクダを意味する語として一般的となり、olfendは消えていった.
そう、古英語の研究家であるイギリスのトールキンが書いている.
もちろん、このトールキンは、「指輪物語」の作者のトールキンのことである.
2017年1月21日
Up Down
#203
秋田県にかほ市、鳥海山の北麓に象潟という潟湖(せきこ)があった.
過去形になっているのは、1804年の地震で陸地化したからである.
しかし、それ以前には潟の中に多数の小島が浮かぶ景勝地であった.
現在は水田でしかないが、今でも、その中に102の小島が残されている.
そして、その名を有名にしたのは松尾芭蕉であろう.
1689年の「奥の細道」紀行で訪れ、「象潟や雨に西施がねぶの花」の一句を残している.
また、「松島は笑ふが如く、象潟は憾(うら)むが如し」と、松島と並べている.
しかし、象潟を「きさかた」と読むのはなぜだろうか.
2017年1月21日
Up
Down
#203
秋田県にかほ市、鳥海山の北麓に象潟という潟湖(せきこ)があった.
過去形になっているのは、1804年の地震で陸地化したからである.
しかし、それ以前には潟の中に多数の小島が浮かぶ景勝地であった.
現在は水田でしかないが、今でも、その中に102の小島が残されている.
そして、その名を有名にしたのは松尾芭蕉であろう.
1689年の「奥の細道」紀行で訪れ、「象潟や雨に西施がねぶの花」の一句を残している.
また、「松島は笑ふが如く、象潟は憾(うら)むが如し」と、松島と並べている.
しかし、象潟を「きさかた」と読むのはなぜだろうか.
2017年1月21日
Up Down
#204
象を日本語で言うとと聞くと、ゾウ以外にあるのと言われそうだが、象潟の「きさ」は象の古名である.
たとえば、「和名類聚鈔」には象のところに「和名伎左(きさ)」とあり、「獣名似水牛大耳長鼻眼細牙長者也」とある.
水牛に似て、大耳、長鼻で、目が細く、牙の長い獣の名とあるので、かなり特徴をつかんでいる.
しかし、日本には象はいない.
一応、ナウマンゾウと呼ばれる象が、闊歩していた時代もあるが、それは2万年前である.
そして、その頃の日本は旧石器時代であり、人々の記憶に残るにしても、古すぎる.
また、実際の象が来日した最古の記録は室町時代、1408年のことである
(徳川吉宗の時代に来たのが初来日とするものも多いが、実際には、上記以外にも何度か来ている).
したがって、この平安時代の辞書の記述は、実物を見ずに書かれたものである.
2017年1月27日
Up
Down
#204
象を日本語で言うとと聞くと、ゾウ以外にあるのと言われそうだが、象潟の「きさ」は象の古名である.
たとえば、「和名類聚鈔」には象のところに「和名伎左(きさ)」とあり、「獣名似水牛大耳長鼻眼細牙長者也」とある.
水牛に似て、大耳、長鼻で、目が細く、牙の長い獣の名とあるので、かなり特徴をつかんでいる.
しかし、日本には象はいない.
一応、ナウマンゾウと呼ばれる象が、闊歩していた時代もあるが、それは2万年前である.
そして、その頃の日本は旧石器時代であり、人々の記憶に残るにしても、古すぎる.
また、実際の象が来日した最古の記録は室町時代、1408年のことである
(徳川吉宗の時代に来たのが初来日とするものも多いが、実際には、上記以外にも何度か来ている).
したがって、この平安時代の辞書の記述は、実物を見ずに書かれたものである.
2017年1月27日
Up Down
#205
「和名類聚鈔」を書いたのは源順(したごう)である.
「百人一首」に選ばれていないので、あまり知られていないかもしれないが、有名な歌人である.
三十六歌仙の一人であり、「後撰和歌集」の撰者でもある.
前者はもちろんのことであるが、勅撰和歌集の撰者になるというのは、歌人としての最高の名誉である.
と同時に、当時を代表する漢学者であった.
漢詩文を自在に書いただけではない.
「万葉集」に訓点をつけたのである.
2017年1月31日
Up
Down
#205
「和名類聚鈔」を書いたのは源順(したごう)である.
「百人一首」に選ばれていないので、あまり知られていないかもしれないが、有名な歌人である.
三十六歌仙の一人であり、「後撰和歌集」の撰者でもある.
前者はもちろんのことであるが、勅撰和歌集の撰者になるというのは、歌人としての最高の名誉である.
と同時に、当時を代表する漢学者であった.
漢詩文を自在に書いただけではない.
「万葉集」に訓点をつけたのである.
2017年1月31日
Up Down
#206
当時、「万葉集」は謎の書であった.
万葉仮名という漢字で日本語を表しているからである.
たとえば、「東野炎立所見而反見為者月西渡」と書かれたものを読めるだろうか.
訓点をつけるというのは、これを
東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ
と読むと示すということである.
和漢に通じた一流の学者にしかできないことである.
それをやったのである.
したがって、実際の象を知らなかったはずの順が、このようなものを書けたというのは、中国の文献によるものであろう.
では、中国に象はいたのだろうか.
答えは是である.
象という漢字があるからである.
2017年2月1日
Up
Down
#206
当時、「万葉集」は謎の書であった.
万葉仮名という漢字で日本語を表しているからである.
たとえば、「東野炎立所見而反見為者月西渡」と書かれたものを読めるだろうか.
訓点をつけるというのは、これを
東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ
と読むと示すということである.
和漢に通じた一流の学者にしかできないことである.
それをやったのである.
したがって、実際の象を知らなかったはずの順が、このようなものを書けたというのは、中国の文献によるものであろう.
では、中国に象はいたのだろうか.
答えは是である.
象という漢字があるからである.
2017年2月1日
Up Down
#207
古代の中国人は、動物の漢字を作る際に、その特徴をもとにして作った.
たとえば、牛や羊という甲骨文字を見ると、両者の角の形状で分けたというのがよく分かる.
象形という手法である.
しかし、それは、鼠、虎、兎、馬、犬、熊、鹿、亀等、彼らの身近にいた動物だけである.
これらに対して、狼、猫、猪、狐等は、けもの偏で表されている.
けもの偏は、部首では犬部に置かれるように、本来は犬を表すものである.
そして、主要な漢字が出そろった後に、形声や会意の手法で作られたものである.
2017年2月5日
Up
Down
#207
古代の中国人は、動物の漢字を作る際に、その特徴をもとにして作った.
たとえば、牛や羊という甲骨文字を見ると、両者の角の形状で分けたというのがよく分かる.
象形という手法である.
しかし、それは、鼠、虎、兎、馬、犬、熊、鹿、亀等、彼らの身近にいた動物だけである.
これらに対して、狼、猫、猪、狐等は、けもの偏で表されている.
けもの偏は、部首では犬部に置かれるように、本来は犬を表すものである.
そして、主要な漢字が出そろった後に、形声や会意の手法で作られたものである.
2017年2月5日
Up Down
#208
したがって、けもの偏のつくこれらの動物は、重要視されなかったか、後に中国に入ってきたかである.
たとえば、猫という漢字は、けもの偏と苗でできている.
苗は、今は名字と書く人のほうが多いが、苗字が本来であるように、「ミョウ」と読む(ビョウとも読む).
この字ができた時の発音は分からないが、おそらくはネコの鳴声をまねたものであろう
(稲の守り神だったからというのは、後付であろう).
そして、十二支にも含まれていないことからも分かるように
(ブルガリアとベトナムでは、卯と寅のところに入っているが)、猫の中国伝来は新しい.
一般には5世紀と言われるが、もっと古いのではないかという疑念はタヌキのところで書いた.
狐も、日本ではコンコンと鳴くとされるので、これもそうかもしれない.
2017年2月6日
Up
Down
#208
したがって、けもの偏のつくこれらの動物は、重要視されなかったか、後に中国に入ってきたかである.
たとえば、猫という漢字は、けもの偏と苗でできている.
苗は、今は名字と書く人のほうが多いが、苗字が本来であるように、「ミョウ」と読む(ビョウとも読む).
この字ができた時の発音は分からないが、おそらくはネコの鳴声をまねたものであろう
(稲の守り神だったからというのは、後付であろう).
そして、十二支にも含まれていないことからも分かるように
(ブルガリアとベトナムでは、卯と寅のところに入っているが)、猫の中国伝来は新しい.
一般には5世紀と言われるが、もっと古いのではないかという疑念はタヌキのところで書いた.
狐も、日本ではコンコンと鳴くとされるので、これもそうかもしれない.
2017年2月6日
Up Down
#209
これに対し、象という漢字は、甲骨文字を見ると、象の姿形を如実にとらえている.
それだけではない.
為という漢字も、本来は象+手であり、象を使役するという意味であった.
これは、かつて、黄河周辺は暖かく、象が居住していたからである.
実際、甲骨文に「(王は)象を隻(獲)んか」と読めるものがある.
漢代の気候変動と乱獲により絶滅するまで、中国人にとって、象は身近な動物であったのである.
2017年2月10日
Up
Down
#209
これに対し、象という漢字は、甲骨文字を見ると、象の姿形を如実にとらえている.
それだけではない.
為という漢字も、本来は象+手であり、象を使役するという意味であった.
これは、かつて、黄河周辺は暖かく、象が居住していたからである.
実際、甲骨文に「(王は)象を隻(獲)んか」と読めるものがある.
漢代の気候変動と乱獲により絶滅するまで、中国人にとって、象は身近な動物であったのである.
2017年2月10日
Up Down
#210
また、黄河周辺に象がいなくなっても、近隣にはいた.
このため、これ以降の中国の歴史書の中には、しばしば象が登場する.
多くは戦象で、後代、元が現在のミャンマー(ビルマ)と戦った際にも登場する.
しかし、一般民衆にとって象は馴染みのないものとなっていった.
このため、象という漢字は、象形という言葉のように、「かたち」という意味に転用されたが、
これは、像という文字のほうが先行するようである.
2017年2月11日
Up
Down
#210
また、黄河周辺に象がいなくなっても、近隣にはいた.
このため、これ以降の中国の歴史書の中には、しばしば象が登場する.
多くは戦象で、後代、元が現在のミャンマー(ビルマ)と戦った際にも登場する.
しかし、一般民衆にとって象は馴染みのないものとなっていった.
このため、象という漢字は、象形という言葉のように、「かたち」という意味に転用されたが、
これは、像という文字のほうが先行するようである.
2017年2月11日
Up Down
#211
したがって、源順が象を正確に説明できたのは、中国の書にあるからだと言える.
しかし、なぜ、「伎左(きさ)」という和語を示したのかという説明にはならない.
念のために書いておくと、この和語というのは、古来の日本語のことである.
漢字の読み方で言えば訓読みである.
たとえば、菊は和語ではない.
菊という漢字には訓読みがないからである.
つまり、「キク」は音読みで、中国語の音をそのまま日本語として使っている.
梅、馬、竹なども中国語で呼んでいるうちに、ウメ、ウマ、タケとなったのだという説もある.
ならば、象もゾウでよかったはずである.
2017年2月14日
Up
Down
#211
したがって、源順が象を正確に説明できたのは、中国の書にあるからだと言える.
しかし、なぜ、「伎左(きさ)」という和語を示したのかという説明にはならない.
念のために書いておくと、この和語というのは、古来の日本語のことである.
漢字の読み方で言えば訓読みである.
たとえば、菊は和語ではない.
菊という漢字には訓読みがないからである.
つまり、「キク」は音読みで、中国語の音をそのまま日本語として使っている.
梅、馬、竹なども中国語で呼んでいるうちに、ウメ、ウマ、タケとなったのだという説もある.
ならば、象もゾウでよかったはずである.
2017年2月14日
Up Down
#212
「魏志倭人伝」には「其地無牛馬虎豹羊鵲」とある.
倭国には牛、馬、虎、豹、羊、カササギがいないというのである.
にもかかわらず、豹を除いて和語の名がある.
ただ、中国の故事に「豹死留皮」というのがあり、「十訓抄」という本の中で、これを「虎は死して皮を留め」と訳している.
豹が虎に変わったわけであるが、これは、日本では、豹は虎の雌だと考えられていたからである.
したがって、豹にも「とら」という訓があることになる.
もっとも、豹と書いて「とら」と読ます例は知らないが、やはりヒョウを意味する彪という漢字は「とら」と読む場合がある.
たとえば、川名彪雄海軍少将の名は、「現役海軍士官名簿、将官履歴」によるとトラヲである.
ただし、トラという言葉も、昔の韓国語からの転用だとされるので、純粋な和語とは言えないのかもしれないが
(韓国に残る最古の史料は「三国史記」であり、これは12世紀のものなので、安易に古代韓国語云々と言いにくいのも事実だが).
2017年2月17日
Up
Down
#212
「魏志倭人伝」には「其地無牛馬虎豹羊鵲」とある.
倭国には牛、馬、虎、豹、羊、カササギがいないというのである.
にもかかわらず、豹を除いて和語の名がある.
ただ、中国の故事に「豹死留皮」というのがあり、「十訓抄」という本の中で、これを「虎は死して皮を留め」と訳している.
豹が虎に変わったわけであるが、これは、日本では、豹は虎の雌だと考えられていたからである.
したがって、豹にも「とら」という訓があることになる.
もっとも、豹と書いて「とら」と読ます例は知らないが、やはりヒョウを意味する彪という漢字は「とら」と読む場合がある.
たとえば、川名彪雄海軍少将の名は、「現役海軍士官名簿、将官履歴」によるとトラヲである.
ただし、トラという言葉も、昔の韓国語からの転用だとされるので、純粋な和語とは言えないのかもしれないが
(韓国に残る最古の史料は「三国史記」であり、これは12世紀のものなので、安易に古代韓国語云々と言いにくいのも事実だが).
2017年2月17日
Up Down
#213
「魏志倭人伝」に取り上げられた動物は、中国、あるいは朝鮮半島で一般的な動物である.
日本でも、牛や馬は、その後導入されたものらしいが、一般的な動物である.
また、カササギも佐賀県あたりでは繁殖している.
もっとも、これは秀吉の時代に朝鮮半島から持ち帰られたものの子孫である.
したがって、平安時代には、実物を見ることはまずなかったと思われる.
にもかかわらず、「百人一首」には、奈良時代の歌人大伴家持(おおとものやかもち)の作として、
かささぎの渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞふけにける
という一首が収められており、実物を知らなくとも、名前だけは知られている.
2017年2月19日
Up
Down
#213
「魏志倭人伝」に取り上げられた動物は、中国、あるいは朝鮮半島で一般的な動物である.
日本でも、牛や馬は、その後導入されたものらしいが、一般的な動物である.
また、カササギも佐賀県あたりでは繁殖している.
もっとも、これは秀吉の時代に朝鮮半島から持ち帰られたものの子孫である.
したがって、平安時代には、実物を見ることはまずなかったと思われる.
にもかかわらず、「百人一首」には、奈良時代の歌人大伴家持(おおとものやかもち)の作として、
かささぎの渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞふけにける
という一首が収められており、実物を知らなくとも、名前だけは知られている.
2017年2月19日
Up Down
#214
このカササギの橋は、「淮南子」という中国の本にある、七夕の夜、烏鵲(カササギ)が天の川に橋を渡すという話に由来する.
牽牛、織女は、逢瀬を邪魔する天の川を、この橋を使って渡るのである
(日本では、牽牛が渡ることになっているが、原話は織女で、当時の日本が通い婚であったために変わったものと思われる).
もっとも、この歌は、七夕を歌ったものではない.
「かささぎの渡せる橋」で、七夕、当時は乞巧奠(きっこうでん)、の歌と思わせておいて、実は冬の風景を詠んでいるのである.
しかも、宮中の階段を「かささぎの橋」と呼んでいたので、この「かささぎの渡せる橋」も、宮中のそれである.
つまり、天上界の話だと思わせておいて、宮中で宿直(とのい)をしながら霜の白さを眺めている歌だったということになる.
2017年2月22日
Up
Down
#214
このカササギの橋は、「淮南子」という中国の本にある、七夕の夜、烏鵲(カササギ)が天の川に橋を渡すという話に由来する.
牽牛、織女は、逢瀬を邪魔する天の川を、この橋を使って渡るのである
(日本では、牽牛が渡ることになっているが、原話は織女で、当時の日本が通い婚であったために変わったものと思われる).
もっとも、この歌は、七夕を歌ったものではない.
「かささぎの渡せる橋」で、七夕、当時は乞巧奠(きっこうでん)、の歌と思わせておいて、実は冬の風景を詠んでいるのである.
しかも、宮中の階段を「かささぎの橋」と呼んでいたので、この「かささぎの渡せる橋」も、宮中のそれである.
つまり、天上界の話だと思わせておいて、宮中で宿直(とのい)をしながら霜の白さを眺めている歌だったということになる.
2017年2月22日
Up Down
#215
もっとも、家持がこういう技巧を使うというのは似合わない話である.
彼は「万葉集」の時代の歌人であり(撰者でもある)、そのような技巧を弄する歌がほとんどなかった時代の人だからである.
たとえば、代表作とされる「海ゆかば」など、海を渡れば死体が浮いている、
山中を行けば死骸から草が生えているという、散文的なものである
(これが国民歌になったのは、それでも天皇の傍で死ねるのなら振り返りはしないと続くからで、
「玉砕」を伝える際の音楽として使われた).
また、もっとも著名なのは、「春の園紅にほふ桃の花下照る道に出で立つをとめ」という一首であろうが、
これも、当時の日本では珍しかった桃の花を使った点以外、新奇なものはない.
赤い桃の花の下に少女が立っている春の園であることよ以外に意味はないし、花下照るぐらいにしか工夫もない.
それでも、率直に少女を歌ったおおらかさは楽しいのだが、技巧をもてあそぶ人でなかったようである.
2017年2月25日
Up
Down
#215
もっとも、家持がこういう技巧を使うというのは似合わない話である.
彼は「万葉集」の時代の歌人であり(撰者でもある)、そのような技巧を弄する歌がほとんどなかった時代の人だからである.
たとえば、代表作とされる「海ゆかば」など、海を渡れば死体が浮いている、
山中を行けば死骸から草が生えているという、散文的なものである
(これが国民歌になったのは、それでも天皇の傍で死ねるのなら振り返りはしないと続くからで、
「玉砕」を伝える際の音楽として使われた).
また、もっとも著名なのは、「春の園紅にほふ桃の花下照る道に出で立つをとめ」という一首であろうが、
これも、当時の日本では珍しかった桃の花を使った点以外、新奇なものはない.
赤い桃の花の下に少女が立っている春の園であることよ以外に意味はないし、花下照るぐらいにしか工夫もない.
それでも、率直に少女を歌ったおおらかさは楽しいのだが、技巧をもてあそぶ人でなかったようである.
2017年2月25日
Up Down
#216
しかも、この歌の初出は「万葉集」ではない.
「新古今集」なのである.
念のために書いておくと、「新古今集」は1205年の完成である(その後も歌の入れ替えがある).
つまり、鎌倉時代である.
そして、家持は奈良時代の人で、平安遷都のほぼ10年前である785年に没している.
その間、400年以上あるが、この歌は、この間、いくつも作られた他の歌集に収められなかったのである.
つまり、400年以上の時を越えて、家持の知られざる和歌が出てきたということになる.
しかも、この歌は、「百人一首」に採られているのである
(「百人一首」が代表作や有名歌人ばかりを集めているかというと疑問だが).
したがって、これが家持の作品であるとは考えにくいし、たとえ、そうであったとしても、大幅に改作されたと考えるしかない.
2017年2月
Up
Down
#216
しかも、この歌の初出は「万葉集」ではない.
「新古今集」なのである.
念のために書いておくと、「新古今集」は1205年の完成である(その後も歌の入れ替えがある).
つまり、鎌倉時代である.
そして、家持は奈良時代の人で、平安遷都のほぼ10年前である785年に没している.
その間、400年以上あるが、この歌は、この間、いくつも作られた他の歌集に収められなかったのである.
つまり、400年以上の時を越えて、家持の知られざる和歌が出てきたということになる.
しかも、この歌は、「百人一首」に採られているのである
(「百人一首」が代表作や有名歌人ばかりを集めているかというと疑問だが).
したがって、これが家持の作品であるとは考えにくいし、たとえ、そうであったとしても、大幅に改作されたと考えるしかない.
2017年2月
Up Down
#217
「大和物語」という歌物語に、「かささぎの渡せる橋の霜の上を夜半にふみわけことさらにこそ」という歌が載っている.
この壬生忠岑(みぶのただみね)作とされる歌と家持の歌は、歌い出しがかささぎの渡せる橋までが一緒で、
夜の霜を詠んでいる点も同一である.
現在ならば盗作と言われかねないが、これは本歌取りという技法の一種である.
そして、一般に「大和物語」のこの歌は、家持の歌を本歌にしてと解説されていることが多い.
しかし、家持のこの歌が、後世の作であるとしたら、忠岑の歌を本歌にしたということになる.
2017年2月28日
Up
Down
#217
「大和物語」という歌物語に、「かささぎの渡せる橋の霜の上を夜半にふみわけことさらにこそ」という歌が載っている.
この壬生忠岑(みぶのただみね)作とされる歌と家持の歌は、歌い出しがかささぎの渡せる橋までが一緒で、
夜の霜を詠んでいる点も同一である.
現在ならば盗作と言われかねないが、これは本歌取りという技法の一種である.
そして、一般に「大和物語」のこの歌は、家持の歌を本歌にしてと解説されていることが多い.
しかし、家持のこの歌が、後世の作であるとしたら、忠岑の歌を本歌にしたということになる.
2017年2月28日
Up Down
#218
本歌取りは「古今集」の時代からあったが、流行したのは「新古今集」の時代である.
そして、「古今集」の時代の人である忠岑の場合、本歌取りをされることは多いが、したという話は聞かない.
これは、やはり、忠岑の歌を本にして、誰かが作ったと考えるべきであろう.
少なくとも、この歌を詠んだのは、家持ではないし、奈良時代のものではない.
では、いつかというと、「新古今集」が初出であるのなら、その時代である可能性が高い.
本歌取りが一番盛んな時代だからである.
つまり、奈良時代どころか、平安時代を飛び越して、鎌倉時代に、家持に擬して詠まれたということになる.
2017年3月4日
Up
Down
#218
本歌取りは「古今集」の時代からあったが、流行したのは「新古今集」の時代である.
そして、「古今集」の時代の人である忠岑の場合、本歌取りをされることは多いが、したという話は聞かない.
これは、やはり、忠岑の歌を本にして、誰かが作ったと考えるべきであろう.
少なくとも、この歌を詠んだのは、家持ではないし、奈良時代のものではない.
では、いつかというと、「新古今集」が初出であるのなら、その時代である可能性が高い.
本歌取りが一番盛んな時代だからである.
つまり、奈良時代どころか、平安時代を飛び越して、鎌倉時代に、家持に擬して詠まれたということになる.
2017年3月4日
Up Down
#219
歌壇の重鎮、藤原清輔は、本歌取りとは盗作であると非難した.
これに対し、彼と勢力争いをしてきた藤原俊成、定家父子は本歌取りを重視した.
当時の貴族であるのなら、古歌のほとんどを知っている.
したがって、本歌取りをした場合、その歌だけでなく、本歌の中身、詠まれた状況等を思い浮かべるはずである.
この結果、単独で詠むより重層的に世界が広がるというのである.
たとえば、忠岑の歌を本歌とするのなら、霜の降る夜にやって来て、ずっと待っていますよという意味になる.
2017年3月6日
Up
Down
#219
歌壇の重鎮、藤原清輔は、本歌取りとは盗作であると非難した.
これに対し、彼と勢力争いをしてきた藤原俊成、定家父子は本歌取りを重視した.
当時の貴族であるのなら、古歌のほとんどを知っている.
したがって、本歌取りをした場合、その歌だけでなく、本歌の中身、詠まれた状況等を思い浮かべるはずである.
この結果、単独で詠むより重層的に世界が広がるというのである.
たとえば、忠岑の歌を本歌とするのなら、霜の降る夜にやって来て、ずっと待っていますよという意味になる.
2017年3月6日
Up Down
#220
「百人一首」を語句等の関連順に並べると、10x10枚がきちんと並ぶように出来ている.
そして、この歌は、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の
心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花
という1首を引き出すように出来ているが、実は、この躬恒の歌は「百人一首」に収められた中で、菊を詠んだ唯一の歌である.
詳しくは省略するが、この白菊に象徴される人物は「新古今集」編纂を命じた後鳥羽院といわれる.
したがって、この後鳥羽院をずっと待っていますという心を込めて、
他ならぬ「新古今集、百人一首」の選者、藤原定家が改作したのではないかと思っている.
2017年3月7日
Up
Down
#220
「百人一首」を語句等の関連順に並べると、10x10枚がきちんと並ぶように出来ている.
そして、この歌は、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の
心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花
という1首を引き出すように出来ているが、実は、この躬恒の歌は「百人一首」に収められた中で、菊を詠んだ唯一の歌である.
詳しくは省略するが、この白菊に象徴される人物は「新古今集」編纂を命じた後鳥羽院といわれる.
したがって、この後鳥羽院をずっと待っていますという心を込めて、
他ならぬ「新古今集、百人一首」の選者、藤原定家が改作したのではないかと思っている.
2017年3月7日
Up Down
#221
ずっと書き連ねてきたが、日本文学に関心がなければ、どうでもよい話であろう.
ただ、当時の貴族にとって、「かささぎの渡せる橋」で、七夕(乞巧奠)を思うのは自然なことであったということは押さえておきたい.
つまり、「魏志倭人伝」で倭国にはいないとされ、おそらくは当時も国内にはいなかった鵲は、
貴族という限られた範囲の中ではあるが、存在を知っておくべき鳥だったのである.
かささぎという和名がついているのも、また、当然であったのである.
2017年3月9日
Up
Down
#221
ずっと書き連ねてきたが、日本文学に関心がなければ、どうでもよい話であろう.
ただ、当時の貴族にとって、「かささぎの渡せる橋」で、七夕(乞巧奠)を思うのは自然なことであったということは押さえておきたい.
つまり、「魏志倭人伝」で倭国にはいないとされ、おそらくは当時も国内にはいなかった鵲は、
貴族という限られた範囲の中ではあるが、存在を知っておくべき鳥だったのである.
かささぎという和名がついているのも、また、当然であったのである.
2017年3月9日
Up Down
#222
鵲がそうであるのなら、虎に和名があるのは当然ということになる.
十二支に登場するからである.
また、白虎は四神の一つであり、少なくとも当時の特権階級にとって、知らないということはありえない.
実際、法隆寺の玉虫厨子には虎が描かれている.
捨身飼虎図と呼ばれる、釈迦が前世において、飢えた虎に身を与えたという話を絵にしたものである.
キトラ古墳、高松塚古墳にも描かれている.
もっとも、四神としての白虎であるので、有翼であり、実際の虎とはあまり似ていない.
薬師寺の薬師如来坐像台座にも白虎が描かれているが、これと似ているので、これが当時の標準的な白虎であったのだろう.
また、キトラ古墳には十二支像が描かれており、こちらの虎は、かなり実際と似ている.
2017年3月12日
Up
Down
#222
鵲がそうであるのなら、虎に和名があるのは当然ということになる.
十二支に登場するからである.
また、白虎は四神の一つであり、少なくとも当時の特権階級にとって、知らないということはありえない.
実際、法隆寺の玉虫厨子には虎が描かれている.
捨身飼虎図と呼ばれる、釈迦が前世において、飢えた虎に身を与えたという話を絵にしたものである.
キトラ古墳、高松塚古墳にも描かれている.
もっとも、四神としての白虎であるので、有翼であり、実際の虎とはあまり似ていない.
薬師寺の薬師如来坐像台座にも白虎が描かれているが、これと似ているので、これが当時の標準的な白虎であったのだろう.
また、キトラ古墳には十二支像が描かれており、こちらの虎は、かなり実際と似ている.
2017年3月12日
Up Down
#223
「日本書紀」や「万葉集」にも虎は登場する.
ただし、日本に虎は生息しない.
静岡県から虎の化石が発見され、一緒に噛まれた痕跡のある人骨が発見されたことはある.
しかし、それは2万年前の地層からであり、縄文時代よりずっと前のことである.
したがって、これは文献による知識でなければ、異国での知識である.
実際、「日本書紀」にある記録というのは、膳臣巴提便(かしわでのおみはすび)が百済で虎を殺す話である.
546年のことである.
2017年3月14日
Up
Down
#223
「日本書紀」や「万葉集」にも虎は登場する.
ただし、日本に虎は生息しない.
静岡県から虎の化石が発見され、一緒に噛まれた痕跡のある人骨が発見されたことはある.
しかし、それは2万年前の地層からであり、縄文時代よりずっと前のことである.
したがって、これは文献による知識でなければ、異国での知識である.
実際、「日本書紀」にある記録というのは、膳臣巴提便(かしわでのおみはすび)が百済で虎を殺す話である.
546年のことである.
2017年3月14日
Up Down
#224
その前年、545年に百済から虎の皮が贈られている.
これが記録に残る最初のものであるが、以後、虎の皮は何度も伝来している.
虎の皮の需要が大きかったからである.
最初は皇族、貴族の専有物であったが、平安後期には武士もこぞって求めるようになった.
霊力があるとされたからである.
平治の乱の際、平清盛の長男重盛は、8代にわたって平家の嫡男に受け継がれてきた唐皮という鎧をつけていたが、
矢が当たっても刺さらなかったという伝承がある.
唐皮とは、中国伝来の皮という意味で、虎の皮のことである.
そして、この名は、縅(おどし)が虎皮でできていたからと解される.
その後も、虎の皮の需要は大きく、かなりの数が伝えられたようである.
もっとも、あまりにも多いので、他の皮を虎皮のように染色したものも含まれているのではないかと言われている.
2017年3月17日
Up
Down
#224
その前年、545年に百済から虎の皮が贈られている.
これが記録に残る最初のものであるが、以後、虎の皮は何度も伝来している.
虎の皮の需要が大きかったからである.
最初は皇族、貴族の専有物であったが、平安後期には武士もこぞって求めるようになった.
霊力があるとされたからである.
平治の乱の際、平清盛の長男重盛は、8代にわたって平家の嫡男に受け継がれてきた唐皮という鎧をつけていたが、
矢が当たっても刺さらなかったという伝承がある.
唐皮とは、中国伝来の皮という意味で、虎の皮のことである.
そして、この名は、縅(おどし)が虎皮でできていたからと解される.
その後も、虎の皮の需要は大きく、かなりの数が伝えられたようである.
もっとも、あまりにも多いので、他の皮を虎皮のように染色したものも含まれているのではないかと言われている.
2017年3月17日
Up Down
#225
虎の頭(かしら)というものもある.
たとえば、「紫式部日記」には、「虎の頭、宮の内侍(ないし)とりて御先に参る」とある.
これは、一条天皇の第2皇子敦成(あつひら)の産湯の情景を描いた一節で、
宮の内侍が虎の頭を持って、初湯に行く皇子を先導したというのである.
内侍は天皇の近辺で奉仕していた女官である.
当然、貴族の娘であり、天皇の命令を伝える役割をしていたので、才がないといけない.
また、天皇の傍にいるのだから、見目麗しくないといけない.
つまり、才色兼備なのだが、そのような女性が持つのに、虎の頭は、実に異様な代物である.
しかし、この虎の頭は大変な呪物なのである.
これを煮た湯で産湯にすると、その子は生涯無病であるとされたからである.
2017年3月20日
Up
Down
#225
虎の頭(かしら)というものもある.
たとえば、「紫式部日記」には、「虎の頭、宮の内侍(ないし)とりて御先に参る」とある.
これは、一条天皇の第2皇子敦成(あつひら)の産湯の情景を描いた一節で、
宮の内侍が虎の頭を持って、初湯に行く皇子を先導したというのである.
内侍は天皇の近辺で奉仕していた女官である.
当然、貴族の娘であり、天皇の命令を伝える役割をしていたので、才がないといけない.
また、天皇の傍にいるのだから、見目麗しくないといけない.
つまり、才色兼備なのだが、そのような女性が持つのに、虎の頭は、実に異様な代物である.
しかし、この虎の頭は大変な呪物なのである.
これを煮た湯で産湯にすると、その子は生涯無病であるとされたからである.
2017年3月20日
Up Down
#226
この虎の頭を調べてみると、虎の頭の形に模した作り物とある.
しかし、この時の虎の頭は、本物かもしれない.
というのは、一条天皇の伯父にあたる冷泉天皇の出産の際に、虎首一頭を枕上に置いたとあり、
その冷泉帝の祖父、藤原師輔の日記「九暦」には、「自今以降、皇子懐任、予先可儲件等物、臨其時雖求、忽難具」と注されているからである.
皇子を懐妊した場合は、そのようなものを先に用意しておくべきである.
出産の際に求めてもなかなか手に入らないからであるというのである.
しかし、師輔と言えば、摂政、関白にこそならなかったが、3人もの内親王を嫁に迎え、冷泉、円融両帝の外戚となった一大権力者である.
そのような人物をもってしても、入手しがたいものが、作り物であるはずがない.
日本に産しない虎の、その頭であるがゆえに、入手困難であると解するほうが自然なのである.
2017年3月24日
Up
Down
#226
この虎の頭を調べてみると、虎の頭の形に模した作り物とある.
しかし、この時の虎の頭は、本物かもしれない.
というのは、一条天皇の伯父にあたる冷泉天皇の出産の際に、虎首一頭を枕上に置いたとあり、
その冷泉帝の祖父、藤原師輔の日記「九暦」には、「自今以降、皇子懐任、予先可儲件等物、臨其時雖求、忽難具」と注されているからである.
皇子を懐妊した場合は、そのようなものを先に用意しておくべきである.
出産の際に求めてもなかなか手に入らないからであるというのである.
しかし、師輔と言えば、摂政、関白にこそならなかったが、3人もの内親王を嫁に迎え、冷泉、円融両帝の外戚となった一大権力者である.
そのような人物をもってしても、入手しがたいものが、作り物であるはずがない.
日本に産しない虎の、その頭であるがゆえに、入手困難であると解するほうが自然なのである.
2017年3月24日
Up Down
#227
敦成(あつひら)親王の祖父になる藤原道長は、師輔の子兼家の子である.
そして、道長と言えば、
「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」という和歌でも知られるように、栄耀栄華を極めた人物である.
しかし、意外なことに、彼は兼家の五男である.
そして、兼家も師輔の三男である.
もっとも、長子相続制になったのは、武家社会になってからであり、太郎とか、次郎とかいう名も、武家のもので、貴族の名ではない.
ただ、それでも、三男の五男というのは不利であったと思われるが、その出世のきっかけを生んだのは、麻疹(はしか)であった.
長兄道隆は大酒により死亡したというが、間の兄弟は麻疹によって死亡したのである.
このことにより、道長に道が開いたのだが、競争相手として立ちふさがったのが、道隆の嫡男伊周(これちか)であった.
2017年4月1日
Up
Down
#227
敦成(あつひら)親王の祖父になる藤原道長は、師輔の子兼家の子である.
そして、道長と言えば、
「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」という和歌でも知られるように、栄耀栄華を極めた人物である.
しかし、意外なことに、彼は兼家の五男である.
そして、兼家も師輔の三男である.
もっとも、長子相続制になったのは、武家社会になってからであり、太郎とか、次郎とかいう名も、武家のもので、貴族の名ではない.
ただ、それでも、三男の五男というのは不利であったと思われるが、その出世のきっかけを生んだのは、麻疹(はしか)であった.
長兄道隆は大酒により死亡したというが、間の兄弟は麻疹によって死亡したのである.
このことにより、道長に道が開いたのだが、競争相手として立ちふさがったのが、道隆の嫡男伊周(これちか)であった.
2017年4月1日
Up Down
#228
2017年4月
ロンドンには、その名もエレファント&カースルという町があり、同名の駅もある
(IWM、帝国戦争博物館の最寄り駅である).
そして、この名は、実はスペイン語であるという説がある.
カスティーリャの王女を意味するLa
Infanta de Castillaを聞き間違ったというのだ.
イギリス王室に嫁入りした王女が、ここで花嫁衣裳に着替えたというのである.
カステラの語源はカスティーリャ風のパンを意味するポルトガル語pao
de Castillaだそうだから、ありそうな話である.
2017年1月
Wikipediaによると、この名は、同地にあったコーチ・イン、四輪馬車用の宿屋の名に由来するそうだ.
現在も同名のパブがあるそうだが
Up
Down
#228
2017年4月
ロンドンには、その名もエレファント&カースルという町があり、同名の駅もある
(IWM、帝国戦争博物館の最寄り駅である).
そして、この名は、実はスペイン語であるという説がある.
カスティーリャの王女を意味するLa
Infanta de Castillaを聞き間違ったというのだ.
イギリス王室に嫁入りした王女が、ここで花嫁衣裳に着替えたというのである.
カステラの語源はカスティーリャ風のパンを意味するポルトガル語pao
de Castillaだそうだから、ありそうな話である.
2017年1月
Wikipediaによると、この名は、同地にあったコーチ・イン、四輪馬車用の宿屋の名に由来するそうだ.
現在も同名のパブがあるそうだが
Up Down
#200
長野県は中野県から改名された.
Down
#200
長野県は中野県から改名された.
PREVIOUS ☆ NEXT


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
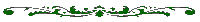 Sasayaki005.
Sasayaki005.
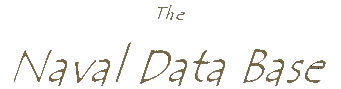 Ver.1.21a.
Ver.1.21a.
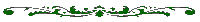 Copyright
(c)
hush ,2001-21. Allrights Reserved.
Copyright
(c)
hush ,2001-21. Allrights Reserved.
Up
動画
