Down
無用録
1-
51- 101-
150- 191-
229- 255-
293- 311-
333- 361-
383-
trivia's
trivia
Up
Down
#229
表紙の写真からリンク先に飛んだ人はギンコウという表記に、かの国では公孫樹のことをそういうのかと驚かれた人もいるかもしれない.
発音は異なるが、フランス語でもドイツ語でも英語と同じginkgoであり、スペイン、ポルトガル、スウェーデン、ノルウェー、オランダの諸語もそうである.
また、ロシア語のгинкгоも音価はginkgoであるので、ヨーロッパの主要言語はすべて同一である.
これはラテン語に由来するからだが、同時にヨーロッパにイチョウがなかったことを意味する.
もし、自生していたのなら、もっと各種の名があるはずだからである.
2020.11/27
Up Down
#230
もっとも、イチョウは北半球を中心とした全世界に分布していた植物である.
ただし、それは古生代後期から氷河期にかけてである.
特に中生代ジュラ紀には全盛期を迎えているので、恐龍はイチョウを食べていたのかもしれない.
それが、氷河期の寒気によってほぼ絶滅し、比較的温暖だった中国南部でのみ生き延びた.
メタセコイアも、この地で生き延びた古代の植物で1946に四川省で発見されるまで絶滅したものと思われていた.
これに対し、イチョウが一般に知られるのはもっと早い.
三国時代とか、唐代いう説もあるが、確実なところでは宋代である.
今から1000年ほどの昔のことである.
2020.11/29
Up
Down
#230
もっとも、イチョウは北半球を中心とした全世界に分布していた植物である.
ただし、それは古生代後期から氷河期にかけてである.
特に中生代ジュラ紀には全盛期を迎えているので、恐龍はイチョウを食べていたのかもしれない.
それが、氷河期の寒気によってほぼ絶滅し、比較的温暖だった中国南部でのみ生き延びた.
メタセコイアも、この地で生き延びた古代の植物で1946に四川省で発見されるまで絶滅したものと思われていた.
これに対し、イチョウが一般に知られるのはもっと早い.
三国時代とか、唐代いう説もあるが、確実なところでは宋代である.
今から1000年ほどの昔のことである.
2020.11/29
Up Down
#231
「万葉集」に登場する「ちちの実(知智乃実)」がイチョウだという説がある.
たしかに、イチョウの大木には乳頭とか乳根とか呼ばれる円錐状の気根が生じることがある.
また、この気根に触れると乳の出がよくなるという伝承もあり、「ちちのき」と呼ぶ地方もある.
しかし、これは実ではなく木なので、「ちちの実」は乳液の出るイヌビワの実のこととされる.
そして、平安時代までの文献では、「万葉集」のこの部分以外にイチョウらしいものは登場しない.
イチョウは大木にもなるし、特徴の多い木でもあるので、他に一切出てこないというのはあり得ないであろう.
したがって、古代の日本にイチョウは存在していなかったということになる.
2020.11/30
Up
Down
#231
「万葉集」に登場する「ちちの実(知智乃実)」がイチョウだという説がある.
たしかに、イチョウの大木には乳頭とか乳根とか呼ばれる円錐状の気根が生じることがある.
また、この気根に触れると乳の出がよくなるという伝承もあり、「ちちのき」と呼ぶ地方もある.
しかし、これは実ではなく木なので、「ちちの実」は乳液の出るイヌビワの実のこととされる.
そして、平安時代までの文献では、「万葉集」のこの部分以外にイチョウらしいものは登場しない.
イチョウは大木にもなるし、特徴の多い木でもあるので、他に一切出てこないというのはあり得ないであろう.
したがって、古代の日本にイチョウは存在していなかったということになる.
2020.11/30
Up Down
#232
イチョウの日本への渡来は鎌倉時代とされていたが、文献に登場するのは「異制庭訓往来」が最初である.
これは、往復書簡形式の初学者向けの学習書で、江戸時代、寺子屋で盛んに使われた「庭訓往来」と同様の書である.
ただし、書かれたのは「庭訓往来」より少し早く1356-75頃とされる.
つまり、南北朝期であって、鎌倉時代より後である.
その2月の項に「金柑柑子温州橘枇杷林檎楊梅柘榴桃杏梅李梨鉛桃銀杏柏実椎榛栗烏芋生栗干栗鬻栗」と列挙されており、銀杏はその中ほどにある.
これらはすべて果実であり、酒肴である.
酒肴というのは、この本に載せられた書簡が、架空の酒席の案内状で、あり得ないほどの御馳走が並べられているからである.
当然、この銀杏はイチョウの木ではなく、実のほうであり、滅多に口にすることのできない珍味であったということになる.
2020.12/1
Up
Down
#232
イチョウの日本への渡来は鎌倉時代とされていたが、文献に登場するのは「異制庭訓往来」が最初である.
これは、往復書簡形式の初学者向けの学習書で、江戸時代、寺子屋で盛んに使われた「庭訓往来」と同様の書である.
ただし、書かれたのは「庭訓往来」より少し早く1356-75頃とされる.
つまり、南北朝期であって、鎌倉時代より後である.
その2月の項に「金柑柑子温州橘枇杷林檎楊梅柘榴桃杏梅李梨鉛桃銀杏柏実椎榛栗烏芋生栗干栗鬻栗」と列挙されており、銀杏はその中ほどにある.
これらはすべて果実であり、酒肴である.
酒肴というのは、この本に載せられた書簡が、架空の酒席の案内状で、あり得ないほどの御馳走が並べられているからである.
当然、この銀杏はイチョウの木ではなく、実のほうであり、滅多に口にすることのできない珍味であったということになる.
2020.12/1
Up Down
#233
1977年に韓国で発見された沈没船から銀杏が見つかっている.
発見地から新安沈船と呼ばれるこの船からは、至治3(1323)年という元の年号と博多の東福寺の権利物であることを示す木簡が見つかっている.
この船は28tにも及ぶ銅銭を積んでいたことで知られるが、同時に2万個以上の陶器、1000本以上の紫檀も積載していた.
これらは当時の日本で、非常な高価で取引されていたもので1319年に火災に遭った東福寺等の復興資金をつくるためのものだったと推定されている.
そのような中で、銀杏が積荷に含まれているということは、輸入するだけの意味があったということになる.
つまり、当時の日本にはイチョウの木はなく、あったとしても実がなるほどには成長していなかったということである.
イチョウは公孫樹と書くように、実がなるまでに数十年かかるからである.
したがって、その数十年後に「異制庭訓往来」に銀杏が酒肴として登場した頃には、まだ目新しい食べ物であったということになる.
実際、有史以来、鎌倉時代までの日本で、イチョウの遺物が見つかったことはないし、彫刻や建築物に使われた例も知られていない.
この時代、実としての銀杏は知られていたが、イチョウの木はまだ日本にはなかったと考えるべきである.
*
本来、この#233を先に載せるはずであったが、誤って下の234を先に掲載してしまった.
原稿を先に作るという滅多にしないことをやってしまった結果であるので、慣れないことはすべきではないと思ったような次第である.
Up
Down
#233
1977年に韓国で発見された沈没船から銀杏が見つかっている.
発見地から新安沈船と呼ばれるこの船からは、至治3(1323)年という元の年号と博多の東福寺の権利物であることを示す木簡が見つかっている.
この船は28tにも及ぶ銅銭を積んでいたことで知られるが、同時に2万個以上の陶器、1000本以上の紫檀も積載していた.
これらは当時の日本で、非常な高価で取引されていたもので1319年に火災に遭った東福寺等の復興資金をつくるためのものだったと推定されている.
そのような中で、銀杏が積荷に含まれているということは、輸入するだけの意味があったということになる.
つまり、当時の日本にはイチョウの木はなく、あったとしても実がなるほどには成長していなかったということである.
イチョウは公孫樹と書くように、実がなるまでに数十年かかるからである.
したがって、その数十年後に「異制庭訓往来」に銀杏が酒肴として登場した頃には、まだ目新しい食べ物であったということになる.
実際、有史以来、鎌倉時代までの日本で、イチョウの遺物が見つかったことはないし、彫刻や建築物に使われた例も知られていない.
この時代、実としての銀杏は知られていたが、イチョウの木はまだ日本にはなかったと考えるべきである.
*
本来、この#233を先に載せるはずであったが、誤って下の234を先に掲載してしまった.
原稿を先に作るという滅多にしないことをやってしまった結果であるので、慣れないことはすべきではないと思ったような次第である.
Up Down
#234
では、樹木としてのイチョウが確認できる最初は何かというと、「下学集」という国語辞典である(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58).
「銀杏、異名鴨脚、葉形如鴨脚、山谷句風林収鴨脚」とあり、銀杏の異名は鴨脚で葉の形が鴨の脚に似ているからであるとなっている.
なお、山谷云々は山谷道人(黄庭堅)の詩句に「風林鴨脚を収む」があるの意味であるが、これらはイチョウが樹木であることを理解していないと書けないことである.
また、樒(シキミ)だとか、槐(エンジュ)、梓のように食用にしない樹木が同列に並んでいることも、そのことを示している.
そして、この辞書の版本の刊行は1617年だが、成立は1444年である.
つまり、室町時代である.
しかし、それだと、公暁が鶴岡八幡宮の大イチョウに隠れて源実朝を討ったという話はどうなるのだとなりそうである.
実朝暗殺は1219年で「下学集」成立より200年以上前のことだからである.
ただ、「吾妻鏡」には石階の所であるのみである.
2020.12/2
Up
Down
#234
では、樹木としてのイチョウが確認できる最初は何かというと、「下学集」という国語辞典である(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58).
「銀杏、異名鴨脚、葉形如鴨脚、山谷句風林収鴨脚」とあり、銀杏の異名は鴨脚で葉の形が鴨の脚に似ているからであるとなっている.
なお、山谷云々は山谷道人(黄庭堅)の詩句に「風林鴨脚を収む」があるの意味であるが、これらはイチョウが樹木であることを理解していないと書けないことである.
また、樒(シキミ)だとか、槐(エンジュ)、梓のように食用にしない樹木が同列に並んでいることも、そのことを示している.
そして、この辞書の版本の刊行は1617年だが、成立は1444年である.
つまり、室町時代である.
しかし、それだと、公暁が鶴岡八幡宮の大イチョウに隠れて源実朝を討ったという話はどうなるのだとなりそうである.
実朝暗殺は1219年で「下学集」成立より200年以上前のことだからである.
ただ、「吾妻鏡」には石階の所であるのみである.
2020.12/2
Up Down
#235
もちろん、石階とは石段のことだが、後発の「増鏡」は女装してとある.
しかし、「吾妻鏡」には「当宮別当阿闍梨公暁窺来干石階之際取剣奉侵丞相」とある.
当宮別当阿闍梨である公暁が石段の所で剣を取って丞相(大臣)実朝を襲ったというのである.
当宮とは鶴岡八幡宮、別当は長官、阿闍梨は高僧である.
そして、神仏混淆の時代なので、神社の長官が僧侶であるというのは不思議ではない.
むしろ、鶴岡八幡宮に将軍が参拝するのに、その長官が木陰に隠れているというほうがおかしい.
先導役として近傍にいてもいいと思う.
その上、公暁は、実朝の甥であり、猶子である.
ヤマトタケルの故事にちなんだのかもしれないが、女装するというような策を弄する必要もない.
僧衣を着ているのが一番目立たない方法だからである.
ただ、神域なので、誰もが武装していない.
そういう中で、刀を持つ必要があるという点だけが問題なのである.
しかし、自分が長官を務める神社なのだから、刀を隠せる場所ぐらいは分かるはずである.
また、暗殺当日は2尺(60㎝)ほども雪が積もっていたのだから、その中に隠すだけでもよい.
イチョウの大木の陰に隠れてとか、女装してという必要性はないのである.
2020.12/3
Up
Down
#235
もちろん、石階とは石段のことだが、後発の「増鏡」は女装してとある.
しかし、「吾妻鏡」には「当宮別当阿闍梨公暁窺来干石階之際取剣奉侵丞相」とある.
当宮別当阿闍梨である公暁が石段の所で剣を取って丞相(大臣)実朝を襲ったというのである.
当宮とは鶴岡八幡宮、別当は長官、阿闍梨は高僧である.
そして、神仏混淆の時代なので、神社の長官が僧侶であるというのは不思議ではない.
むしろ、鶴岡八幡宮に将軍が参拝するのに、その長官が木陰に隠れているというほうがおかしい.
先導役として近傍にいてもいいと思う.
その上、公暁は、実朝の甥であり、猶子である.
ヤマトタケルの故事にちなんだのかもしれないが、女装するというような策を弄する必要もない.
僧衣を着ているのが一番目立たない方法だからである.
ただ、神域なので、誰もが武装していない.
そういう中で、刀を持つ必要があるという点だけが問題なのである.
しかし、自分が長官を務める神社なのだから、刀を隠せる場所ぐらいは分かるはずである.
また、暗殺当日は2尺(60㎝)ほども雪が積もっていたのだから、その中に隠すだけでもよい.
イチョウの大木の陰に隠れてとか、女装してという必要性はないのである.
2020.12/3
Up Down
#236
もっとも、その翌年に成立した「愚管抄」には次のように書かれている.
「法師ノケウサウ、トキント云物シタル、馳カゝリテ下ガサネノ尻ノ上ニノボリテ、カシラヲ一ノカタナニハ切テ、タフレケレバ、頸ヲウチヲトシテ取テケリ」
ケウサウがよく分からないが、叫騒だとすれば、兜巾をつけた法師が騒ぎながら実朝の服の裾を踏みつけて頭に切りつけ、倒れたところで首級を取ったということになる.
兜巾というのは修行中の僧が被る頭巾のことなので、何らかの変装をしていたようにも思えるが、公暁にその必要はないはずである.
しかし、「此法師ハ、頼家ガ子ヲ其八幡ノ別当ニナシテオキタリケル」とあり、「一ノ刀ノ時、ヲヤノ敵ハカクウツゾト云ケル」とある.
頼家の子で、八幡宮の別当、さらには「親の敵はこのように討つもの」と言っているので、同時に襲った数人の配下ではなく、公暁本人である.
事件当時、「愚管抄」の作者慈円は現場にはいなかったが、居合わせた公家の話をまとめたのだろう.
もっとも、「吾妻鏡」には「ヲヤノ敵」などという話はなく、実朝の首級は行方不明となったとするが、「愚管抄」は雪の中から見つかったとする.
「吾妻鏡」には一定のバイアスがかかっているというのは有名な話であるが、現場に居合わせた公家が突然の惨劇に冷静な観察ができたかどうかも不分明である.
どちらが正しいかは分からないが、大イチョウに隠れてというのはどちらにも載っていない.
2020.12/4
Up
Down
#236
もっとも、その翌年に成立した「愚管抄」には次のように書かれている.
「法師ノケウサウ、トキント云物シタル、馳カゝリテ下ガサネノ尻ノ上ニノボリテ、カシラヲ一ノカタナニハ切テ、タフレケレバ、頸ヲウチヲトシテ取テケリ」
ケウサウがよく分からないが、叫騒だとすれば、兜巾をつけた法師が騒ぎながら実朝の服の裾を踏みつけて頭に切りつけ、倒れたところで首級を取ったということになる.
兜巾というのは修行中の僧が被る頭巾のことなので、何らかの変装をしていたようにも思えるが、公暁にその必要はないはずである.
しかし、「此法師ハ、頼家ガ子ヲ其八幡ノ別当ニナシテオキタリケル」とあり、「一ノ刀ノ時、ヲヤノ敵ハカクウツゾト云ケル」とある.
頼家の子で、八幡宮の別当、さらには「親の敵はこのように討つもの」と言っているので、同時に襲った数人の配下ではなく、公暁本人である.
事件当時、「愚管抄」の作者慈円は現場にはいなかったが、居合わせた公家の話をまとめたのだろう.
もっとも、「吾妻鏡」には「ヲヤノ敵」などという話はなく、実朝の首級は行方不明となったとするが、「愚管抄」は雪の中から見つかったとする.
「吾妻鏡」には一定のバイアスがかかっているというのは有名な話であるが、現場に居合わせた公家が突然の惨劇に冷静な観察ができたかどうかも不分明である.
どちらが正しいかは分からないが、大イチョウに隠れてというのはどちらにも載っていない.
2020.12/4
Up Down
#237
もし、公暁が暗殺を試みかねない危険人物とされていたというのなら、大イチョウに隠れてというのも、必然性はあるだろう.
しかし、その危険人物がいる鶴岡八幡宮に将軍が護衛もつけずに参拝するだろうか.
武士として最初の右大臣昇進を、源氏の崇敬を集めるこの宮に報告するという大事な儀式であったから、どうしても参らねばならなかった.
であるからと考える人もおられると思うが、であるなら、公暁を別当阿闍梨の地位に置いておく必要はない.
当日のみ、別の場所に置いてもよいし、武装した警護役を隠しておいてもよい.
このため、黒幕がいたのだという話になるのだが、その点についてはよく分からない.
ただ、鶴岡八幡宮で目立たないようにするには僧衣を着るのが一番である.
そして、大イチョウが登場するのは、中川喜雲という人が書いた「鎌倉物語」が確認できる最初である.
もっとも、「いちゃうの木陰まで公暁伺い来て丞相を害し奉り」とあるばかりで、イチョウの木に隠れてと書いてあるわけではない.
ただ、大イチョウに隠れてというのが伝承として広まった契機であることには間違いないだろう.
そして、この本が書かれたのは万治年間1658-60である.
つまり、江戸時代になって登場した話である.
したがって、実朝暗殺の時、大イチョウはなく、国内にイチョウは存在してなかったと考えるべきである.
2020.12/5
Up
Down
#237
もし、公暁が暗殺を試みかねない危険人物とされていたというのなら、大イチョウに隠れてというのも、必然性はあるだろう.
しかし、その危険人物がいる鶴岡八幡宮に将軍が護衛もつけずに参拝するだろうか.
武士として最初の右大臣昇進を、源氏の崇敬を集めるこの宮に報告するという大事な儀式であったから、どうしても参らねばならなかった.
であるからと考える人もおられると思うが、であるなら、公暁を別当阿闍梨の地位に置いておく必要はない.
当日のみ、別の場所に置いてもよいし、武装した警護役を隠しておいてもよい.
このため、黒幕がいたのだという話になるのだが、その点についてはよく分からない.
ただ、鶴岡八幡宮で目立たないようにするには僧衣を着るのが一番である.
そして、大イチョウが登場するのは、中川喜雲という人が書いた「鎌倉物語」が確認できる最初である.
もっとも、「いちゃうの木陰まで公暁伺い来て丞相を害し奉り」とあるばかりで、イチョウの木に隠れてと書いてあるわけではない.
ただ、大イチョウに隠れてというのが伝承として広まった契機であることには間違いないだろう.
そして、この本が書かれたのは万治年間1658-60である.
つまり、江戸時代になって登場した話である.
したがって、実朝暗殺の時、大イチョウはなく、国内にイチョウは存在してなかったと考えるべきである.
2020.12/5
Up Down
#238
鶴岡八幡宮の大イチョウは樹齢1000年と称しており、全国には1200年を称するイチョウもある.
これが鎌倉時代にイチョウがあったという説の根拠だが、樹木の年齢を測るというのはなかなか難しい.
たとえば、青森県深浦町にあり国の天然記念物に指定されている北金ヶ沢のイチョウは樹齢1000年以上と称されているが、環境省の公表は300年以上と慎重である.
また、戦後の住宅不足により、国の政策で杉を植えることになったが、我が家の場合、寒冷地のため、通常は30年で出荷できる太さになるのが2倍の年数がかかった.
このため、出荷できる頃には杉は余っており、新建材に押されて売れるものではなかったわけだが、環境によって樹木の生育は大きく変わる.
山一つどころか、同じ山でも異なるぐらいである.
したがって、最終的には年輪を数えるしかないのだが、そのためには伐採が必要である.
しかし、樹齢何百年という老樹を簡単に伐り倒すわけにもいかないので、伝承ではということになる.
ただ、鶴岡八幡宮の大イチョウについては計測可能なのではないかと思われる方もおられると思う.
2010年に倒壊しているからである.
2020.12/6
Up
Down
#238
鶴岡八幡宮の大イチョウは樹齢1000年と称しており、全国には1200年を称するイチョウもある.
これが鎌倉時代にイチョウがあったという説の根拠だが、樹木の年齢を測るというのはなかなか難しい.
たとえば、青森県深浦町にあり国の天然記念物に指定されている北金ヶ沢のイチョウは樹齢1000年以上と称されているが、環境省の公表は300年以上と慎重である.
また、戦後の住宅不足により、国の政策で杉を植えることになったが、我が家の場合、寒冷地のため、通常は30年で出荷できる太さになるのが2倍の年数がかかった.
このため、出荷できる頃には杉は余っており、新建材に押されて売れるものではなかったわけだが、環境によって樹木の生育は大きく変わる.
山一つどころか、同じ山でも異なるぐらいである.
したがって、最終的には年輪を数えるしかないのだが、そのためには伐採が必要である.
しかし、樹齢何百年という老樹を簡単に伐り倒すわけにもいかないので、伝承ではということになる.
ただ、鶴岡八幡宮の大イチョウについては計測可能なのではないかと思われる方もおられると思う.
2010年に倒壊しているからである.
2020.12/6
Up Down
#239
しかし、この木の中心部は腐ってなくなっている.
したがって、正確な樹齢は分からない.
若木と老樹では成長の速度が異なるからである.
ただ、「倒壊した鎌倉・鶴岡八幡宮の大イチョウ」にある精緻な分析によると、実際の樹齢は500年程度ではないかということである.
これが正しいのなら、「鎌倉物語」が書かれた江戸時代初期には樹齢150年以上である.
そこで、樹齢150年程度のイチョウの大きさを検索してみると、胸高直径1.6mというものがあった.
もちろん、樹木の生長は周囲の環境に大きく左右されるので150年でそこまで成長するとは限らない.
ただ、それなりの大木に育っていたと思われるので、人が隠れるには充分な太さである.
もっとも、「鎌倉物語」のイチョウの図では人が隠れるには不充分な太さだと思うが、
階段も実際のものより明らかに狭く、この当時の絵に正確さを求めるわけにもいかないと思う.
2020.12/7
Up
Down
#239
しかし、この木の中心部は腐ってなくなっている.
したがって、正確な樹齢は分からない.
若木と老樹では成長の速度が異なるからである.
ただ、「倒壊した鎌倉・鶴岡八幡宮の大イチョウ」にある精緻な分析によると、実際の樹齢は500年程度ではないかということである.
これが正しいのなら、「鎌倉物語」が書かれた江戸時代初期には樹齢150年以上である.
そこで、樹齢150年程度のイチョウの大きさを検索してみると、胸高直径1.6mというものがあった.
もちろん、樹木の生長は周囲の環境に大きく左右されるので150年でそこまで成長するとは限らない.
ただ、それなりの大木に育っていたと思われるので、人が隠れるには充分な太さである.
もっとも、「鎌倉物語」のイチョウの図では人が隠れるには不充分な太さだと思うが、
階段も実際のものより明らかに狭く、この当時の絵に正確さを求めるわけにもいかないと思う.
2020.12/7
Up Down
#240
このイチョウを西洋に紹介したのはケンペル(ケンプファー)Engelbert
Kampfer、1651-1716である.
1690年にこのオランダ商館付医師として来日しているが、オランダ人ではなく、シーボルトと同じくドイツ人である.
医者であると同時に博物学者であり、彼の死後の1727年にイギリスで出版された「日本誌The
History of Japan」によって知られる.
しかし、生前の1712年にも「廻国奇観Amoenitates
Exoticae」という本を発表しており、イチョウはこちらで紹介されている.
この本は、彼が訪日前に訪れた当時のペルシャを中心とするものであるが、第5巻は日本植物誌ともいうべき内容であった.
これは、日本の植物に関する研究書としては、西洋人による最初のもので、この中でGinkgoとして図版付きで紹介されている.
そして、イチョウは生きてる化石として評判になった.
滅びたと思われていた古代の植物が、恐龍やマンモスの絶滅した時代を乗り越えて、極東の島国に残っていたからである.
もっとも、ケンペルが1692年の離日の際に、実物なり、その種、つまり銀杏を持ち帰ったかどうかは分からない.
ただ、1700年頃にはバタヴィア経由でオランダに持ち込まれ、各地に広がっているので、持ち帰った可能性はある.
2020.12/8
Up
Down
#240
このイチョウを西洋に紹介したのはケンペル(ケンプファー)Engelbert
Kampfer、1651-1716である.
1690年にこのオランダ商館付医師として来日しているが、オランダ人ではなく、シーボルトと同じくドイツ人である.
医者であると同時に博物学者であり、彼の死後の1727年にイギリスで出版された「日本誌The
History of Japan」によって知られる.
しかし、生前の1712年にも「廻国奇観Amoenitates
Exoticae」という本を発表しており、イチョウはこちらで紹介されている.
この本は、彼が訪日前に訪れた当時のペルシャを中心とするものであるが、第5巻は日本植物誌ともいうべき内容であった.
これは、日本の植物に関する研究書としては、西洋人による最初のもので、この中でGinkgoとして図版付きで紹介されている.
そして、イチョウは生きてる化石として評判になった.
滅びたと思われていた古代の植物が、恐龍やマンモスの絶滅した時代を乗り越えて、極東の島国に残っていたからである.
もっとも、ケンペルが1692年の離日の際に、実物なり、その種、つまり銀杏を持ち帰ったかどうかは分からない.
ただ、1700年頃にはバタヴィア経由でオランダに持ち込まれ、各地に広がっているので、持ち帰った可能性はある.
2020.12/8
Up Down
#241
「廻国奇観」の中で、ケンペルは"銀杏
Ginkgo, vel Gin an, vulgo Itsjo.Arbor nucifera folio Adiantino"とラテン語で書いている.
Ginkgoとして紹介したページの最下段がそれで、"銀杏"が"杏銀"となってるのは、縦書きの日本語を写したからである.
Arbor nucifera folio AdiantinoのArbor
nuciferaをGoogle翻訳すると庭木と出てくるが、Arborは樹木、学名nucifera folioと解すべきであろう.
nuciferaは堅果、folioは葉の意味で、イチョウの実と特殊な形状の葉の特徴を捉えたものであろう.
AdiantinoはAsantinoだと解すればアジア産の意味かと思う.
中国伝来のものであると知って、日本産としなかったということであろう.
直前の絲(糸)瓜にSikwa, vulgo Fitzmaとシクヮ(シカ)、フィツマ(ヘチマ)とあるように、
銀杏 Ginkgo, vel Gin an, vulgo Itsjoは、漢名銀杏、Ginkgo、別名Gin
an、一般名Itsjoという意味である.
Gin anは銀杏、Itsjoはイチョウであろうが、問題はGinkgoである.
2020.12/9
Up
Down
#241
「廻国奇観」の中で、ケンペルは"銀杏
Ginkgo, vel Gin an, vulgo Itsjo.Arbor nucifera folio Adiantino"とラテン語で書いている.
Ginkgoとして紹介したページの最下段がそれで、"銀杏"が"杏銀"となってるのは、縦書きの日本語を写したからである.
Arbor nucifera folio AdiantinoのArbor
nuciferaをGoogle翻訳すると庭木と出てくるが、Arborは樹木、学名nucifera folioと解すべきであろう.
nuciferaは堅果、folioは葉の意味で、イチョウの実と特殊な形状の葉の特徴を捉えたものであろう.
AdiantinoはAsantinoだと解すればアジア産の意味かと思う.
中国伝来のものであると知って、日本産としなかったということであろう.
直前の絲(糸)瓜にSikwa, vulgo Fitzmaとシクヮ(シカ)、フィツマ(ヘチマ)とあるように、
銀杏 Ginkgo, vel Gin an, vulgo Itsjoは、漢名銀杏、Ginkgo、別名Gin
an、一般名Itsjoという意味である.
Gin anは銀杏、Itsjoはイチョウであろうが、問題はGinkgoである.
2020.12/9
Up Down
#242
ケンペルは、2度の江戸城訪問を除くと、ずっと出島に閉じ込められていた.
このため、彼は通訳を通じて、実物や書物を融通してもらっていた.
ただし、1828年のシーボルト事件を見るまでもなく、これは国禁を犯すことに繋がりかねなかった.
このため、彼は無料で西洋の知識を教え、酒等を提供して、通訳を懐柔したのである.
そうして得た本の中に「訓蒙図彙」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569352?tocOpened=1)があった.
上記のURLの12コマ目を見てもらうと「銀杏 俗云ぎん あん
杏従唐音 一名白果 ○銀杏樹 一名鴨脚樹 いちやう」と、漢名、俗名、和名(一般名)と並んでいるのが分かると思う.
つまり、「廻国奇観」と同じ順番である.
図版は同一ではないが、この本を参考にしてケンペルは「廻国奇観」を書いたのでる.
さらに興味深いのはこの本の銀杏に振られた「きんきやう」という振り仮名である.
ケンペルは日本語を解しなかったが、通訳を通じて、これはギンキョウ(表記通りならキンキョウ)という植物だと知ったのである.
Ginkgoはその音訳である.
2020.12/10
Up
Down
#242
ケンペルは、2度の江戸城訪問を除くと、ずっと出島に閉じ込められていた.
このため、彼は通訳を通じて、実物や書物を融通してもらっていた.
ただし、1828年のシーボルト事件を見るまでもなく、これは国禁を犯すことに繋がりかねなかった.
このため、彼は無料で西洋の知識を教え、酒等を提供して、通訳を懐柔したのである.
そうして得た本の中に「訓蒙図彙」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569352?tocOpened=1)があった.
上記のURLの12コマ目を見てもらうと「銀杏 俗云ぎん あん
杏従唐音 一名白果 ○銀杏樹 一名鴨脚樹 いちやう」と、漢名、俗名、和名(一般名)と並んでいるのが分かると思う.
つまり、「廻国奇観」と同じ順番である.
図版は同一ではないが、この本を参考にしてケンペルは「廻国奇観」を書いたのでる.
さらに興味深いのはこの本の銀杏に振られた「きんきやう」という振り仮名である.
ケンペルは日本語を解しなかったが、通訳を通じて、これはギンキョウ(表記通りならキンキョウ)という植物だと知ったのである.
Ginkgoはその音訳である.
2020.12/10
Up Down
#243
「ぎんあん」の「あん」は、「杏従唐音(杏は唐音に従う)」とあるように、唐音である.
唐音というのは、幕末までに入ってきた、比較的新しい中国語の音である.
和尚、行脚、椅子、外郎、箪笥、(湯)湯婆、提灯、暖簾、布団、饅頭等と、その例は多くはないが、杏を「アン」と読むのもその一つである.
このため、杏子と書いて、アンズとも読み、キョウコという人名にもなる.
もちろん、杏が、唐音の入る前は「キョウ」と読まれていたからである.
ところで、現在の中国でも、北方の北京語と、広東語、上海語等に代表される南方の言葉では、互いに意思疎通ができないくらい発音が異なる.
たとえば、北京語で日本人はリーベンレンだが、広東語ではヤッパンヤンとなるし、文法も若干違う.
これは、中国が広大だからということもあるが、別々の国だった時代があるからである.
このため、北京語をベースにした「普通話」と呼ばれる共通語が使われるようになったが、それ以前には筆談したほうが早かったはずである.
もっとも、日本に入ってきた初期の中国語は、現在の南京あたりで話されていたものが基本である.
これを呉音というが、遣隋使、遣唐使を通じて日本に入ってきた中国語は、北方語の系統で、漢音と呼ばれる.
そして、南京が比較的北方にあるためか、呉音と漢音との差は比較的少ない.
ところが、唐音はさらに南方、しかも、もっと新しい時代の発音である.
このため、漢音、呉音とは全然違う音になる.
これは、守旧派の人々には受け入れがたいものがあったのかもしれない.
「訓蒙図彙」の作者は、銀杏を「ぎんあん(または連声してギンナン)」と唐音で読むのは俗説であり、「キョウ」が正しいと主張しているわけである.
2020.12/11
Up
Down
#243
「ぎんあん」の「あん」は、「杏従唐音(杏は唐音に従う)」とあるように、唐音である.
唐音というのは、幕末までに入ってきた、比較的新しい中国語の音である.
和尚、行脚、椅子、外郎、箪笥、(湯)湯婆、提灯、暖簾、布団、饅頭等と、その例は多くはないが、杏を「アン」と読むのもその一つである.
このため、杏子と書いて、アンズとも読み、キョウコという人名にもなる.
もちろん、杏が、唐音の入る前は「キョウ」と読まれていたからである.
ところで、現在の中国でも、北方の北京語と、広東語、上海語等に代表される南方の言葉では、互いに意思疎通ができないくらい発音が異なる.
たとえば、北京語で日本人はリーベンレンだが、広東語ではヤッパンヤンとなるし、文法も若干違う.
これは、中国が広大だからということもあるが、別々の国だった時代があるからである.
このため、北京語をベースにした「普通話」と呼ばれる共通語が使われるようになったが、それ以前には筆談したほうが早かったはずである.
もっとも、日本に入ってきた初期の中国語は、現在の南京あたりで話されていたものが基本である.
これを呉音というが、遣隋使、遣唐使を通じて日本に入ってきた中国語は、北方語の系統で、漢音と呼ばれる.
そして、南京が比較的北方にあるためか、呉音と漢音との差は比較的少ない.
ところが、唐音はさらに南方、しかも、もっと新しい時代の発音である.
このため、漢音、呉音とは全然違う音になる.
これは、守旧派の人々には受け入れがたいものがあったのかもしれない.
「訓蒙図彙」の作者は、銀杏を「ぎんあん(または連声してギンナン)」と唐音で読むのは俗説であり、「キョウ」が正しいと主張しているわけである.
2020.12/11
Up Down
#244
しかし、先述の「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)には、銀杏の文字に「ギンアン」と振られている.
また、菅見の限りでは、江戸時代より前に「ギンキヤウ」という読み方を示すものはない.
そして、「下学集」は室町時代、「訓蒙図彙」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569352?tocOpened=1)は江戸時代の辞書である.
したがって、これが後代の補筆でなければ、室町時代には「ギンキヤウ」という読み方はなく、「ギンアン」が正しいと考えるべきである.
ところが、1617(元和3)年に最初の版本として出された「下学集」には「ギンキヤウ」とあるらしい.
らしいと書いたのは、実物を見ていないからだが、早稲田大学所収の1669年出版の「増補下学集」は「イチヤウ、ギンアン」とあるように、
「ギンキヤウ」とするのは、上記の元和3年本の「下学集」だけらしい.
したがって、確かめもせずに書くのは気が引けるのだが、「ギンアン」は唐音であるので、本来、「ギンキヤウ」と読まれていたはずだと考えた人がいたということになのだろうと思う.
しかし、唐音は江戸時代に日本に伝わってきた音と考える人が多いが、平安中期以降に入ってきたものもある.
というのは、日宋貿易というものがあるからだ.
2020.12/13
Up
Down
#244
しかし、先述の「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)には、銀杏の文字に「ギンアン」と振られている.
また、菅見の限りでは、江戸時代より前に「ギンキヤウ」という読み方を示すものはない.
そして、「下学集」は室町時代、「訓蒙図彙」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569352?tocOpened=1)は江戸時代の辞書である.
したがって、これが後代の補筆でなければ、室町時代には「ギンキヤウ」という読み方はなく、「ギンアン」が正しいと考えるべきである.
ところが、1617(元和3)年に最初の版本として出された「下学集」には「ギンキヤウ」とあるらしい.
らしいと書いたのは、実物を見ていないからだが、早稲田大学所収の1669年出版の「増補下学集」は「イチヤウ、ギンアン」とあるように、
「ギンキヤウ」とするのは、上記の元和3年本の「下学集」だけらしい.
したがって、確かめもせずに書くのは気が引けるのだが、「ギンアン」は唐音であるので、本来、「ギンキヤウ」と読まれていたはずだと考えた人がいたということになのだろうと思う.
しかし、唐音は江戸時代に日本に伝わってきた音と考える人が多いが、平安中期以降に入ってきたものもある.
というのは、日宋貿易というものがあるからだ.
2020.12/13
Up Down
#245
宋は1127年に北方を女真族の金に奪われ、南遷して南宋と呼ばれた.
その首都臨安は現在の杭州であり、杭州湾上陸で知られるように上海の南方に位置する.
そして、日宋貿易は平清盛の父忠盛が注目したことにより広まるが、この時、宋はすでに南遷している.
しかも、宋が対等な国交を結ぶことを許さず、朝貢以外は認めていなかったので、これらはすべて私貿易である.
このため、元が宋を滅ぼし、日本に侵攻してきても、私貿易は続いており、明になってからは足利義満が日本国王として冊封を受けても続いた.
臨安の宮中では南遷後も北方系の中国語が使われていたのではないかと思うが、公貿易ではないので、この貿易により入ってくる中国語は現地のそれである.
そういうふうに入ってきた音も唐音と呼ぶが、宋音とか、唐宋音と呼ぶ人もいる.
そして、その中には、行灯の行(アン)、和尚の和(ヲ)、看経の経(キン)、塔頭の頭(チュウ)等、仏教関係のものが多い.
そういう中に、銀杏が含まれるのは不思議な気もするが、当時、中国の寺院に植栽されていたのだろう.
そして、新しい食べ物であったので、中国名をそのまま使ったのだろうと思う.
したがって、銀杏がギンキョウと呼ばれたこと可能性は極めて低い.
なお、杏の呉音はギョウ、漢音はコウであり、ギョウという読み方は日本で作られた慣用音と呼ばれるものである.
2020.12/14
Up
Down
#245
宋は1127年に北方を女真族の金に奪われ、南遷して南宋と呼ばれた.
その首都臨安は現在の杭州であり、杭州湾上陸で知られるように上海の南方に位置する.
そして、日宋貿易は平清盛の父忠盛が注目したことにより広まるが、この時、宋はすでに南遷している.
しかも、宋が対等な国交を結ぶことを許さず、朝貢以外は認めていなかったので、これらはすべて私貿易である.
このため、元が宋を滅ぼし、日本に侵攻してきても、私貿易は続いており、明になってからは足利義満が日本国王として冊封を受けても続いた.
臨安の宮中では南遷後も北方系の中国語が使われていたのではないかと思うが、公貿易ではないので、この貿易により入ってくる中国語は現地のそれである.
そういうふうに入ってきた音も唐音と呼ぶが、宋音とか、唐宋音と呼ぶ人もいる.
そして、その中には、行灯の行(アン)、和尚の和(ヲ)、看経の経(キン)、塔頭の頭(チュウ)等、仏教関係のものが多い.
そういう中に、銀杏が含まれるのは不思議な気もするが、当時、中国の寺院に植栽されていたのだろう.
そして、新しい食べ物であったので、中国名をそのまま使ったのだろうと思う.
したがって、銀杏がギンキョウと呼ばれたこと可能性は極めて低い.
なお、杏の呉音はギョウ、漢音はコウであり、ギョウという読み方は日本で作られた慣用音と呼ばれるものである.
2020.12/14
Up Down
#246
したがって、ケンペルの記した和名は漢名であり、しかも、当時の日本人のほとんどが聞いたことのないような発音のものだったということになる.
その上、彼はギンキョウをGinkgoと音写したのである.
しかし、この綴りは、綴字法が定まっていなかった当時においても、不思議なものであった.
というのは、ゲーテがイチョウの葉という詩を書いているからである.
この詩の原題は、手稿では"Ginkgo biloba"であったが、印刷された際には"Gingo
biloba"と、"Ginkgo"からkが抜けた形になっていた.
そして、これはゲーテ自身の指示であったというのである.
kがあると美しくないという理由だったようだ.
このため、この綴りについては、様々な説が出ている.
たとえば、ケンペルの記述をもとにリンネが学名をつけた際に誤記したとか、植字工が間違ったとかである.
ただ、ケンペルの自筆ノートを調べた結果、彼自身がGinkgoと記述していることが判明している.
このため、ギンギョウのギンの部分が、Ginではなく、鼻音でGinkと読まれていた可能性を指摘する人もいる.
というのは、ケンペルはイチゴをItzingoと表記しているからである.
つまり、ケンペルは日本語を通詞に読んでもらっていたが、当時の長崎では銀は鼻音で発音されており、彼はそれを聞き取っていたのだという考えである.
ただし、それだとギンゴウとなるし、銀杏をGink anではなくGin
anと書いているので、疑問は残る.
2020.12/15
Up
Down
#246
したがって、ケンペルの記した和名は漢名であり、しかも、当時の日本人のほとんどが聞いたことのないような発音のものだったということになる.
その上、彼はギンキョウをGinkgoと音写したのである.
しかし、この綴りは、綴字法が定まっていなかった当時においても、不思議なものであった.
というのは、ゲーテがイチョウの葉という詩を書いているからである.
この詩の原題は、手稿では"Ginkgo biloba"であったが、印刷された際には"Gingo
biloba"と、"Ginkgo"からkが抜けた形になっていた.
そして、これはゲーテ自身の指示であったというのである.
kがあると美しくないという理由だったようだ.
このため、この綴りについては、様々な説が出ている.
たとえば、ケンペルの記述をもとにリンネが学名をつけた際に誤記したとか、植字工が間違ったとかである.
ただ、ケンペルの自筆ノートを調べた結果、彼自身がGinkgoと記述していることが判明している.
このため、ギンギョウのギンの部分が、Ginではなく、鼻音でGinkと読まれていた可能性を指摘する人もいる.
というのは、ケンペルはイチゴをItzingoと表記しているからである.
つまり、ケンペルは日本語を通詞に読んでもらっていたが、当時の長崎では銀は鼻音で発音されており、彼はそれを聞き取っていたのだという考えである.
ただし、それだとギンゴウとなるし、銀杏をGink anではなくGin
anと書いているので、疑問は残る.
2020.12/15
Up Down
#247
このため、ケンペルの生まれたヴェストファーレンではjをgと書いていたからだという説が、もっとも説得力があるように思う.
つまり、Ginkjoと書くはずだったのである.
ケンペルは、イチョウをItsjoと音写しているように、拗音をjoで表しているので、このスペルで間違いはないだろう.
もっとも、「訓蒙図彙(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569352?tocOpened=1)」の他の部分ではjとgを取り間違えていないので、それは違うという人もいる.
しかし、Ginkgoだけは、日頃の癖で間違ってしまい、校正の段階でも気づかなかったというのは大いにあり得ると思う.
結果、この不思議な綴りのまま書籍となり、リンネが学名として採用した.
しかし、一度ついた学名は綴りが間違っていても訂正できないので、そのままになってしまったのであろう.
各国語でGinkgoと呼ばれる植物の語源は日本語だと書かれているが、これをそうだと確信を持って答えられる人は稀であろう.
まして、英語読みのギンコウとなると、どこをどういじったらとなるだろうと思う.
私自身がそうであったので、調べてみたが、思いがけず大部となった.
つきあって下さった方々には感謝申し上げる次第である.
2020.12/16
Up
Down
#247
このため、ケンペルの生まれたヴェストファーレンではjをgと書いていたからだという説が、もっとも説得力があるように思う.
つまり、Ginkjoと書くはずだったのである.
ケンペルは、イチョウをItsjoと音写しているように、拗音をjoで表しているので、このスペルで間違いはないだろう.
もっとも、「訓蒙図彙(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569352?tocOpened=1)」の他の部分ではjとgを取り間違えていないので、それは違うという人もいる.
しかし、Ginkgoだけは、日頃の癖で間違ってしまい、校正の段階でも気づかなかったというのは大いにあり得ると思う.
結果、この不思議な綴りのまま書籍となり、リンネが学名として採用した.
しかし、一度ついた学名は綴りが間違っていても訂正できないので、そのままになってしまったのであろう.
各国語でGinkgoと呼ばれる植物の語源は日本語だと書かれているが、これをそうだと確信を持って答えられる人は稀であろう.
まして、英語読みのギンコウとなると、どこをどういじったらとなるだろうと思う.
私自身がそうであったので、調べてみたが、思いがけず大部となった.
つきあって下さった方々には感謝申し上げる次第である.
2020.12/16
Up Down
#248
イチョウの語源は、鴨脚だとされる.
234に述べたように「銀杏、異名鴨脚、葉形如鴨脚、山谷句風林収鴨脚」と「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)にあるからである.
鴨は水鳥であるので、水掻きがついている.
その形状がイチョウの葉と似ていたからであり、これを中国語で発音した音からイチョウという言葉が出たという考えである.
たしかに、現在の中国語で鴨脚はya jiaoとなる.
しかし、これは北京語であって、南方の音ではない.
銀杏をギンアンと唐宋音で読むのであれば、鴨脚も南方の音で読みたい.
実際、イチョウは一葉から来たと考える人もいるし、銀杏の転訛であるとする人もいる.
2020.12/17
Up
Down
#248
イチョウの語源は、鴨脚だとされる.
234に述べたように「銀杏、異名鴨脚、葉形如鴨脚、山谷句風林収鴨脚」と「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)にあるからである.
鴨は水鳥であるので、水掻きがついている.
その形状がイチョウの葉と似ていたからであり、これを中国語で発音した音からイチョウという言葉が出たという考えである.
たしかに、現在の中国語で鴨脚はya jiaoとなる.
しかし、これは北京語であって、南方の音ではない.
銀杏をギンアンと唐宋音で読むのであれば、鴨脚も南方の音で読みたい.
実際、イチョウは一葉から来たと考える人もいるし、銀杏の転訛であるとする人もいる.
2020.12/17
Up Down
#249
#230に書いたように、イチョウは中国南部にのみ生き残っていた植物である.
まず、一般に知られるようになったのは、食用としてのイチョウの種である.
銀杏という言葉がそれを表している.
「金色のちひさき鳥のかたちして」と与謝野晶子の短歌を引き合いに出すまでもなく、イチョウを特徴づける色は黄色、または金色である.
葉もそうであるが、実も黄色い.
また、胚乳部は緑色であるが、放置しておくと、短期間で黄色く褪色する.
加熱すると緑色になるが、さらに加熱すると黄色になる.
食品として見かける銀杏はこの色である.
銀というイメージとはほど遠い.
にも関わらず、銀杏と名付けられたのは、内種皮と呼ばれる殻の部分が白いからである.
というのは、銀杏の外種皮は軟らかく、悪臭があり、その上、素手で触るとかぶれるからである.
このため、銀杏の採集は、落ちている実を土の中で腐らせ、その後で殻に覆われたまま保存し、殻を割ってから調理する.
そして、殻のままだと長期にわたって保存できるので、多くの人々が見るのはこの状態になる.
2020.12/18
Up
Down
#249
#230に書いたように、イチョウは中国南部にのみ生き残っていた植物である.
まず、一般に知られるようになったのは、食用としてのイチョウの種である.
銀杏という言葉がそれを表している.
「金色のちひさき鳥のかたちして」と与謝野晶子の短歌を引き合いに出すまでもなく、イチョウを特徴づける色は黄色、または金色である.
葉もそうであるが、実も黄色い.
また、胚乳部は緑色であるが、放置しておくと、短期間で黄色く褪色する.
加熱すると緑色になるが、さらに加熱すると黄色になる.
食品として見かける銀杏はこの色である.
銀というイメージとはほど遠い.
にも関わらず、銀杏と名付けられたのは、内種皮と呼ばれる殻の部分が白いからである.
というのは、銀杏の外種皮は軟らかく、悪臭があり、その上、素手で触るとかぶれるからである.
このため、銀杏の採集は、落ちている実を土の中で腐らせ、その後で殻に覆われたまま保存し、殻を割ってから調理する.
そして、殻のままだと長期にわたって保存できるので、多くの人々が見るのはこの状態になる.
2020.12/18
Up Down
#250
つまり、イチョウの生き残っていた地域以外の人達にとって、木を見ることはなかったが、殻に覆われたものを見ることはあり得たのである.
ところで、実際にイチョウを見た人なら、銀という言葉を使うのに躊躇うと思う.
銀杏という言葉は、実、それも殻に覆われた内種皮以外には見たことのない人物のものである.
それが、移植されたのか、実生なのかは知らないが、実際の木が周囲にあるようになると、銀杏という言葉に違和感を感じる人が出てくる.
そこで名付けられたのが鴨脚であり、鴨脚樹である.
鴨は中国ではアヒルを指すが、アヒルの水掻きは黄色いからである.
また、実がなるまでに長い年月が必要なことから、公孫樹という名も生まれた.
これも、実際のイチョウを知らないと出てこない言葉である.
2020.12/19
Up
Down
#250
つまり、イチョウの生き残っていた地域以外の人達にとって、木を見ることはなかったが、殻に覆われたものを見ることはあり得たのである.
ところで、実際にイチョウを見た人なら、銀という言葉を使うのに躊躇うと思う.
銀杏という言葉は、実、それも殻に覆われた内種皮以外には見たことのない人物のものである.
それが、移植されたのか、実生なのかは知らないが、実際の木が周囲にあるようになると、銀杏という言葉に違和感を感じる人が出てくる.
そこで名付けられたのが鴨脚であり、鴨脚樹である.
鴨は中国ではアヒルを指すが、アヒルの水掻きは黄色いからである.
また、実がなるまでに長い年月が必要なことから、公孫樹という名も生まれた.
これも、実際のイチョウを知らないと出てこない言葉である.
2020.12/19
Up Down
#251
日本語で、植物と、可食部であるその種や実の名が大きく違うというのは、稲と米以外には、このイチョウとギンナンぐらいしか思いつかない.
稲と米の場合は、信仰に近いぐらいの扱いを考えると分からないでもないが、イチョウとギンナンの場合、そのようなものはない.
しかし、二つの呼び名が中国から別々に入ってきて、それぞれが植物と実の名前に当てはめられたとしたらどうだろう.
というのは、中国の場合と同じく、最初に日本に渡ってきたのも、イチョウそのものではなく、実のほうであると思われるからである.
新安沈船に実が載せられているし、「異制庭訓往来」に酒肴として銀杏が載っているからである.
これに対し、「異制庭訓往来」の100年ほど後に成立した「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)には、鴨脚という言葉が載っている.
そして、この100年の間に何が起きたかというと、元の滅亡である.
2020.12/20
Up
Down
#251
日本語で、植物と、可食部であるその種や実の名が大きく違うというのは、稲と米以外には、このイチョウとギンナンぐらいしか思いつかない.
稲と米の場合は、信仰に近いぐらいの扱いを考えると分からないでもないが、イチョウとギンナンの場合、そのようなものはない.
しかし、二つの呼び名が中国から別々に入ってきて、それぞれが植物と実の名前に当てはめられたとしたらどうだろう.
というのは、中国の場合と同じく、最初に日本に渡ってきたのも、イチョウそのものではなく、実のほうであると思われるからである.
新安沈船に実が載せられているし、「異制庭訓往来」に酒肴として銀杏が載っているからである.
これに対し、「異制庭訓往来」の100年ほど後に成立した「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)には、鴨脚という言葉が載っている.
そして、この100年の間に何が起きたかというと、元の滅亡である.
2020.12/20
Up Down
#252
新安沈船からは1323年の元号のついた木簡が見つかっている.
「異制庭訓往来」の成立は1350年頃である.
弘安の役は1281年なので、元寇の後である.
したがって、首都のある華北との貿易は無理なので、華南との私貿易しかない.
当然、入ってきたイチョウの実は、ギンアンと宋唐音で呼ばれる.
しかし、元は明に滅ぼされ1401年には日明貿易が始まる.
これは遣唐使以来の公貿易である.
したがって、鴨脚という言葉が華北の音とともに伝わった可能性が高い.
もっとも、#251に書いたように「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)には、
鴨脚という言葉は載っているが、見出し語は銀杏であり、鴨脚は別名として記されている.
ただ、銀杏という見出しの右にイチヤウ(イチョウ)、左にギンアンと振られている.
これは銀杏の日本での読み方が分かる最初の例であり、イチョウという言葉の出てくる最初である.
2020.12/21
Up
Down
#252
新安沈船からは1323年の元号のついた木簡が見つかっている.
「異制庭訓往来」の成立は1350年頃である.
弘安の役は1281年なので、元寇の後である.
したがって、首都のある華北との貿易は無理なので、華南との私貿易しかない.
当然、入ってきたイチョウの実は、ギンアンと宋唐音で呼ばれる.
しかし、元は明に滅ぼされ1401年には日明貿易が始まる.
これは遣唐使以来の公貿易である.
したがって、鴨脚という言葉が華北の音とともに伝わった可能性が高い.
もっとも、#251に書いたように「下学集」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58)には、
鴨脚という言葉は載っているが、見出し語は銀杏であり、鴨脚は別名として記されている.
ただ、銀杏という見出しの右にイチヤウ(イチョウ)、左にギンアンと振られている.
これは銀杏の日本での読み方が分かる最初の例であり、イチョウという言葉の出てくる最初である.
2020.12/21
Up Down
#253
鴨脚には「アフキヤク(オウキャク)」と振られているので、これをイチョウと読んだわけではないという説がある.
国立国会図書館の場合、リンクができないので、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58とURLを示すが、
こちらの「下学集」には「アフキヤク」とは記されていない.
版本にはあるのだろうとは思うが、鴨脚に読み方が書いてないのは、別の理由がある可能性もある.
普通にオウキャクと読んだので、あえて読み方を記さなかったという可能性である.
同じではないかと言われそうだが、後者だと鴨脚がイチョウの漢字表記だと気づかなかった可能性が出てくる.
つまり、イチョウという音が入ってきたが、それと鴨脚と結びつけては考えなかったということである.
2020.12/22
Up
Down
#253
鴨脚には「アフキヤク(オウキャク)」と振られているので、これをイチョウと読んだわけではないという説がある.
国立国会図書館の場合、リンクができないので、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532290/58とURLを示すが、
こちらの「下学集」には「アフキヤク」とは記されていない.
版本にはあるのだろうとは思うが、鴨脚に読み方が書いてないのは、別の理由がある可能性もある.
普通にオウキャクと読んだので、あえて読み方を記さなかったという可能性である.
同じではないかと言われそうだが、後者だと鴨脚がイチョウの漢字表記だと気づかなかった可能性が出てくる.
つまり、イチョウという音が入ってきたが、それと鴨脚と結びつけては考えなかったということである.
2020.12/22
Up Down
#254
鴨脚という漢字からイチョウという音を想起するのは難しい.
したがって、イチョウ、もしくはそれ近い中国語を聞いて、鴨脚と結びつけた人は少ないはずである.
ただ、中国では銀杏のなる木をそう呼ぶのだという知識と、鴨脚という漢字表記が別々に入ってきたがために、結びつけられなかったのである.
そのように考えていくと、銀杏は南方系、イチョウは北方系の中国語に由来するというのは、無理な話ではない.
日本に入ってくる時代に差異があり、金と銀という特徴づけられる色が大きく異なったためだと考えると、納得できると思う.
2020.12/23
Down
#254
鴨脚という漢字からイチョウという音を想起するのは難しい.
したがって、イチョウ、もしくはそれ近い中国語を聞いて、鴨脚と結びつけた人は少ないはずである.
ただ、中国では銀杏のなる木をそう呼ぶのだという知識と、鴨脚という漢字表記が別々に入ってきたがために、結びつけられなかったのである.
そのように考えていくと、銀杏は南方系、イチョウは北方系の中国語に由来するというのは、無理な話ではない.
日本に入ってくる時代に差異があり、金と銀という特徴づけられる色が大きく異なったためだと考えると、納得できると思う.
2020.12/23
PREVIOUS ☆ NEXT
Since 27 Nov.
2020.
Last up-dated,
13 Jan. 2021.


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
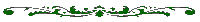 Sasayaki006.
Sasayaki006.
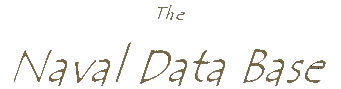 Ver.1.21a.
Ver.1.21a.
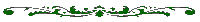 Copyright
(c)
hush ,2001-21. Allrights Reserved.
Copyright
(c)
hush ,2001-21. Allrights Reserved.
Up
動画