Down
無用録
1-
51- 101-
150- 191-
229- 255-
293- 311-
333- 361-
383-
trivia's
trivia
Up
Down
#333
古代の人々は、肉をどのようにして食べたのだろうか.
焼肉という意見が多いだろうと思うが、日本の焼肉の歴史は存外に遅い.
1968年にエバラ食品工業が焼肉のたれを発売して一挙に普遍化したが、それまでは一般的ではなかったからである.
もちろん、韓国料理としての焼肉はあったが、韓国のそれは、プルコギと呼ばれる、たれに漬け込んだ肉を焼くものである.
プルコギというのは火肉という熟語の韓国読みだが、どちらかというと、焼肉よりすき焼きに近い.
しかも、それが日本に入ってきたのは1930年代である.
もっとも、バーベキュー、もちろん、これは数時間から丸1日かけて燻製する本来のものではなく、
英語でグリルgrillと呼ばれる直火焼きの意味だが、そういうものがあった可能性は否定できない.
実際、各地の遺跡から焼けた痕跡のある動物の骨が出土している.
ただ、古代、味付けに使えるものは限られていた.
醤油の前身、現在、ショッツルと呼ばれている魚醤に近いものは、弥生時代から存在したという説もあるが、文献上は701年の「大宝律令」に登場するのが最初である.
色利(いろり)と呼ばれる鰹の煮汁を煮立てたものもあり、平安中期の「和名類聚抄」に堅魚煎汁(かつおいろり)として登場するが、これも7世紀ぐらいまでしか遡れない.
味噌も弥生時代にあったという説もある.
ただ、未醤、つまり、醤油になっていないものを意味する語が味噌の語源とされ、液体状のものが奈良時代にはあった程度である.
酢の伝来も4-5世紀である.
砂糖も、鑑真が伝えたとあるが医療用であり、甘味料としては果物、甘茶や甘草などが使用していた.
しかしながら、こういったものから甘味分を抽出するのは、サトウキビのような糖分の多いものと違って、かなり大変だったようである.
つまり、これらは貴重品であり、有史以前において一般に使用できたとは限らない.
2021.9/1
Up Down
#334
したがって、古代の日本人が使用できた調味料は、もしかすると、塩だけかもしれない.
実際、「日本書紀」には鹿肉を塩蔵したと思われる記述がある.
ただ、岩塩がほとんどない日本では、海水に頼るしかないが、山間部では運んでくるしかない.
そして、鹿や猪が獲れるのは山間部である.
また、獲れた鹿や猪の肉を塩蔵するには、かなり大量の塩が必要だと思われるが、古代日本の製塩法は直煮製塩である.
たとえば、伊勢神宮に塩を奉納している内宮管轄の御塩殿神社のやり方は、濃くした海水をひたすら煮詰めて塩を取る方法である.
奈良時代に始まった藻塩を焼く方法ですらないので、古代日本の製塩法はこれであろうが、重労働である上に、生産量も多くない.
そのような貴重品を惜しみなく使う塩蔵は、中央に租税として送るというような事態がない限りしないであろう.
したがって、焼肉に使う程度の余裕はあったとしても、塩すら使わないものであったという可能性もある.
もちろん、「魏志倭人伝」には、山椒、生姜の類いが倭国に自生しているとあるし、大蒜(ニンニク)は4世紀の伝来と言われるが、蒜(ヒル)はあった.
ただ、「魏志倭人伝」には、倭人はこれらの使い方を知らないとするが、使い方を教えられれば使っただろうとは思う.
しかし、そういう味付けもしない焼肉がおいしいのだろうか.
2021.9/3
Up
Down
#334
したがって、古代の日本人が使用できた調味料は、もしかすると、塩だけかもしれない.
実際、「日本書紀」には鹿肉を塩蔵したと思われる記述がある.
ただ、岩塩がほとんどない日本では、海水に頼るしかないが、山間部では運んでくるしかない.
そして、鹿や猪が獲れるのは山間部である.
また、獲れた鹿や猪の肉を塩蔵するには、かなり大量の塩が必要だと思われるが、古代日本の製塩法は直煮製塩である.
たとえば、伊勢神宮に塩を奉納している内宮管轄の御塩殿神社のやり方は、濃くした海水をひたすら煮詰めて塩を取る方法である.
奈良時代に始まった藻塩を焼く方法ですらないので、古代日本の製塩法はこれであろうが、重労働である上に、生産量も多くない.
そのような貴重品を惜しみなく使う塩蔵は、中央に租税として送るというような事態がない限りしないであろう.
したがって、焼肉に使う程度の余裕はあったとしても、塩すら使わないものであったという可能性もある.
もちろん、「魏志倭人伝」には、山椒、生姜の類いが倭国に自生しているとあるし、大蒜(ニンニク)は4世紀の伝来と言われるが、蒜(ヒル)はあった.
ただ、「魏志倭人伝」には、倭人はこれらの使い方を知らないとするが、使い方を教えられれば使っただろうとは思う.
しかし、そういう味付けもしない焼肉がおいしいのだろうか.
2021.9/3
Up Down
#335
「雄略記」に「膳臣長野能作宍膾(膳(かしはでの)臣(おみ)長野能(よ)く宍(しし)膾(なます)を作)」るので、宍人部(ししひとべ)にしたとある.
記事は、膳、つまり、食料調達や調理を担当する臣である長野は、肉膾をうまく作るので、宍人部という獣肉の調理を担当する役職に就けたというものである.
この記事の前には、肉をうまく料理できる人がいないので、雄略が怒って御者を斬り殺したという物騒な話が前段にあるのだが、
当時の肉料理の代表は膾であったということになる.
もっとも、膾というと、大根と人参で作る紅白膾を想像する人も多いと思うが、この膾は、生肉を細く切ったものである.
実際、膾は、肉を表す月偏がついているように、中国では肉料理である.
この月は、#324で少し書いたが、天体の月ではなく、肉を意味する甲骨文字が変化したものである.
したがって、獣肉ではなく、魚を使う場合は鱠と魚偏になる.
「なます」という言葉も、「なましし」が変化したものと言われるので、日本語においても肉料理であった.
韓国でもそうで、肉膾と書いてユッケと読ます.
韓国の生肉料理として有名なあれである.
2021.9/5
Up
Down
#335
「雄略記」に「膳臣長野能作宍膾(膳(かしはでの)臣(おみ)長野能(よ)く宍(しし)膾(なます)を作)」るので、宍人部(ししひとべ)にしたとある.
記事は、膳、つまり、食料調達や調理を担当する臣である長野は、肉膾をうまく作るので、宍人部という獣肉の調理を担当する役職に就けたというものである.
この記事の前には、肉をうまく料理できる人がいないので、雄略が怒って御者を斬り殺したという物騒な話が前段にあるのだが、
当時の肉料理の代表は膾であったということになる.
もっとも、膾というと、大根と人参で作る紅白膾を想像する人も多いと思うが、この膾は、生肉を細く切ったものである.
実際、膾は、肉を表す月偏がついているように、中国では肉料理である.
この月は、#324で少し書いたが、天体の月ではなく、肉を意味する甲骨文字が変化したものである.
したがって、獣肉ではなく、魚を使う場合は鱠と魚偏になる.
「なます」という言葉も、「なましし」が変化したものと言われるので、日本語においても肉料理であった.
韓国でもそうで、肉膾と書いてユッケと読ます.
韓国の生肉料理として有名なあれである.
2021.9/5
Up Down
#336
これより先、「景行記」に登場する磐鹿六雁(いわかむつかり)は、本邦初の料理人とされる人である.
この人物が天皇に調進したのは、白蛤(しろうむぎ)の膾である.
白蛤は、ハマグリであるとか、アワビであるとか言われるが、どちらにしろ貝であるので、魚偏の鱠のほうが正しいのかもしれない.
ただし、「日本書紀」には「白蛤為膾而進之(白蛤の膾を為(つく)りて進(たてまつ)る)」と、肉月の膾が使われている.
そこまで漢字の使い分けをしなかったのだろうが、この話は、磐鹿六雁の子孫とされる高橋氏が789年に奏上したとされる「高橋氏文(うじぶみ)」にも載っている.
もっとも、こちらでは、白蛤が8尺(20cm強)と巨大なものとなっており、さらに、鰹も加わっているが、
「為膾及煮焼雑造(膾を為り及(また)煮焼きして雑(くさぐさ)造り)」と記されている.
膾以外にも、煮焼きして様々なものを出したというのである.
したがって、肉もまた、膾以外にも煮焼きした可能性がある.
もっとも、古代の食事の形態を最も残しているのは、神社の供え物、神饌と呼ばれるものだと思うが、
これらは火を通さないのが普通であると言われる方もあるかもしれない.
しかし、これらは明治時代の祭式次第が定められてからのことである.
以前、別のところでも述べたが、2礼2拍手1礼もこの時に定められたものであり、社殿の向きが南向きか東向きになったのも、そうである.
しかしながら、出雲大社のように2礼4拍手1礼を正式とし、例祭では8拍手とするように、現在も古式に則って煮炊きされたものを供えるところはある.
これを熟饌とか、特殊神饌、古神饌と呼ぶが、上賀茂、下鴨神社、石清水八幡宮、春日大社、率川(大神)神社等の例が知られる.
2021.9/7
Up
Down
#336
これより先、「景行記」に登場する磐鹿六雁(いわかむつかり)は、本邦初の料理人とされる人である.
この人物が天皇に調進したのは、白蛤(しろうむぎ)の膾である.
白蛤は、ハマグリであるとか、アワビであるとか言われるが、どちらにしろ貝であるので、魚偏の鱠のほうが正しいのかもしれない.
ただし、「日本書紀」には「白蛤為膾而進之(白蛤の膾を為(つく)りて進(たてまつ)る)」と、肉月の膾が使われている.
そこまで漢字の使い分けをしなかったのだろうが、この話は、磐鹿六雁の子孫とされる高橋氏が789年に奏上したとされる「高橋氏文(うじぶみ)」にも載っている.
もっとも、こちらでは、白蛤が8尺(20cm強)と巨大なものとなっており、さらに、鰹も加わっているが、
「為膾及煮焼雑造(膾を為り及(また)煮焼きして雑(くさぐさ)造り)」と記されている.
膾以外にも、煮焼きして様々なものを出したというのである.
したがって、肉もまた、膾以外にも煮焼きした可能性がある.
もっとも、古代の食事の形態を最も残しているのは、神社の供え物、神饌と呼ばれるものだと思うが、
これらは火を通さないのが普通であると言われる方もあるかもしれない.
しかし、これらは明治時代の祭式次第が定められてからのことである.
以前、別のところでも述べたが、2礼2拍手1礼もこの時に定められたものであり、社殿の向きが南向きか東向きになったのも、そうである.
しかしながら、出雲大社のように2礼4拍手1礼を正式とし、例祭では8拍手とするように、現在も古式に則って煮炊きされたものを供えるところはある.
これを熟饌とか、特殊神饌、古神饌と呼ぶが、上賀茂、下鴨神社、石清水八幡宮、春日大社、率川(大神)神社等の例が知られる.
2021.9/7
Up Down
#337
では、神社に肉を奉納などするのかと言われそうだが、ないわけではない.
たとえば、宮崎県西都市の銀鏡(しろみ)神社、ここは#328で出した磐長姫が己の姿を映した鏡を放り投げ、それが落ちた地とされるが、猪の頭が奉納される.
現在もこの風俗は続いており、画像で見ると、なかなか立派な猪である.
私のように、庭先に猪が四肢を括られてぶら下がっている風景を見て育ったような田舎者は別として、大抵の人は引いてしまうのではないかと思うぐらいである.
しかし、これは古代から連綿として続いてきたものであろう.
というのは、ここは、江戸時代には人吉の相良家の領地であったが、1000m級の山に囲まれた交通隔絶の地であり、農地もないため、存在すら忘れられてきたからである.
実際、米良神楽とも呼ばれる銀鏡神楽は、宮崎県で最初に国の重要無形民俗文化財に指定されたほどの由緒を持っている.
したがって、この肉を奉納する行為というのは、古代の神社で当たり前に行われていた可能性がある.
実際、全国、約5700社とも2万5千社といわれる諏訪神社の中には、肉を奉納する風俗が残っているところがある.
たとえば、熊本県玉名市滑石の諏訪神社の猪喰(ししくい)祭では、現在では剥製になったが、猪を奉納し、直会の汁には、必ず、猪肉が入る.
また、千葉県君津市の諏訪神社の御狩祭(しし切りまち)では、現在は鶏肉に変わっているが、桶の中の獣肉を奪い合う.
2021.9/10
Up
Down
#337
では、神社に肉を奉納などするのかと言われそうだが、ないわけではない.
たとえば、宮崎県西都市の銀鏡(しろみ)神社、ここは#328で出した磐長姫が己の姿を映した鏡を放り投げ、それが落ちた地とされるが、猪の頭が奉納される.
現在もこの風俗は続いており、画像で見ると、なかなか立派な猪である.
私のように、庭先に猪が四肢を括られてぶら下がっている風景を見て育ったような田舎者は別として、大抵の人は引いてしまうのではないかと思うぐらいである.
しかし、これは古代から連綿として続いてきたものであろう.
というのは、ここは、江戸時代には人吉の相良家の領地であったが、1000m級の山に囲まれた交通隔絶の地であり、農地もないため、存在すら忘れられてきたからである.
実際、米良神楽とも呼ばれる銀鏡神楽は、宮崎県で最初に国の重要無形民俗文化財に指定されたほどの由緒を持っている.
したがって、この肉を奉納する行為というのは、古代の神社で当たり前に行われていた可能性がある.
実際、全国、約5700社とも2万5千社といわれる諏訪神社の中には、肉を奉納する風俗が残っているところがある.
たとえば、熊本県玉名市滑石の諏訪神社の猪喰(ししくい)祭では、現在では剥製になったが、猪を奉納し、直会の汁には、必ず、猪肉が入る.
また、千葉県君津市の諏訪神社の御狩祭(しし切りまち)では、現在は鶏肉に変わっているが、桶の中の獣肉を奪い合う.
2021.9/10
Up Down
#338
しかしながら、諏訪神社本宮である諏訪大社の御頭(おんとう)祭は、鹿肉を供える上に、その名前通り、切り取った5頭の鹿の頭を並べるという古式豊かなものである.
現在では、さすがに、生首ではなく、剥製を並べており、同時に供えられる雉なども、神社で飼っているものを使い、祭祀後は野に放っている.
しかし、これは本来の形であるはずがない.
というのは、この神社は鹿食免(かじきめん)と呼ばれる、肉を食べてもよいという免罪符を出していたからである.
そのような神社で行われる祭に使われる鹿の頭が剥製であるはずはなく、放鳥されるはずもないからである.
また、同大社では、元旦に川床を掘り返して捕まえた赤蛙を、社前で矢を射って殺すという神事を行っている.
これに対しては、動物保護団体から残酷であると抗議も出されているが、その抗議文への回答の中で、明治までは生首を使っていたと答えている.
実際、1784年にこの祭を見学した菅江真澄は「洲輪(すわ)の海」という記録を残しているが、その中に「鹿の頭七十五、真名板のうへにならぶ」との記述がある.
5頭どころか、75頭もの生首が並んでいたわけである.
当然、現在は冷凍のものが使われている鹿肉も、生肉であったはずである.
2021.9/13
Up
Down
#338
しかしながら、諏訪神社本宮である諏訪大社の御頭(おんとう)祭は、鹿肉を供える上に、その名前通り、切り取った5頭の鹿の頭を並べるという古式豊かなものである.
現在では、さすがに、生首ではなく、剥製を並べており、同時に供えられる雉なども、神社で飼っているものを使い、祭祀後は野に放っている.
しかし、これは本来の形であるはずがない.
というのは、この神社は鹿食免(かじきめん)と呼ばれる、肉を食べてもよいという免罪符を出していたからである.
そのような神社で行われる祭に使われる鹿の頭が剥製であるはずはなく、放鳥されるはずもないからである.
また、同大社では、元旦に川床を掘り返して捕まえた赤蛙を、社前で矢を射って殺すという神事を行っている.
これに対しては、動物保護団体から残酷であると抗議も出されているが、その抗議文への回答の中で、明治までは生首を使っていたと答えている.
実際、1784年にこの祭を見学した菅江真澄は「洲輪(すわ)の海」という記録を残しているが、その中に「鹿の頭七十五、真名板のうへにならぶ」との記述がある.
5頭どころか、75頭もの生首が並んでいたわけである.
当然、現在は冷凍のものが使われている鹿肉も、生肉であったはずである.
2021.9/13
Up Down
#339
前回、諏訪大社の御頭祭を古式豊かと書いたが、これには理由がある.
神籬(ひもろぎ)を、胙、膰とか、月+辰というように、肉月を含む漢字で表すからである.
特に胙は、本邦初の漢和辞典として平安時代に完成した「新撰字鏡(28コマ)」に、肉+乍の字形で載っており、「神祭余肉也」と記されている.
神祭の余肉、すなわち、祭祀時に神に供えた肉の残りというのだから、これは直会である.
また、神籬は祭祀の場という意味なので、祭で肉を供えるのは当たり前のことであったということになる.
もちろん、これらの字は、中国での祭祀の際に犠牲として捧げられた肉を指すために造字されたものである.
したがって、それを転用したと考えるのなら、肉月がつくのも当然ではないかという反論は可能である.
ただ、それならそれで、なぜ、字を変えなかったのだろうか.
「古事記」の大国主が須勢理毘売に歌う場面、その情景にある「繋御馬之鞍(繋げし御馬の鞍)」の鞍は、原文(48-9)では木+安と書いてある.
活字化する際に鞍に直したので、活字はもちろん、インターネット上にもほとんど見つからないと思うが、当時の日本では、鞍は皮革製ではなく、木製だったのである.
また、「御馬」と書いているが、御は中国では「車を走らせる」の意味である.
したがって、昔、運動会で御婦人席と書いてあるのを見つけた中国人が、日本人はあんな公開の場で婦人を御するのかと驚いたという話がある.
しかしながら、日本では、中国にはない敬語を表すために、御の字を転用しているわけで、馬を御するという意味ではない.
「日本書紀」は中国語が分かる人が書いたと言われるが、「古事記」はそうではないらしく、漢字の使用法は奔放である.
そして、「新撰字鏡」では肉+乍という字まで作っているのである.
もし、神籬に肉が出されないのなら、肉月や肉偏を改めればよいだけなのである.
*月+辰、肉+乍等は肉月に辰、肉偏に乍を意味する(月+辰は、ひもろぎを単漢字変換すれば出てくるが、環境依存文字であるため、表示されない場合に備えてこのように表記した).
2021.9/16
Up
Down
#339
前回、諏訪大社の御頭祭を古式豊かと書いたが、これには理由がある.
神籬(ひもろぎ)を、胙、膰とか、月+辰というように、肉月を含む漢字で表すからである.
特に胙は、本邦初の漢和辞典として平安時代に完成した「新撰字鏡(28コマ)」に、肉+乍の字形で載っており、「神祭余肉也」と記されている.
神祭の余肉、すなわち、祭祀時に神に供えた肉の残りというのだから、これは直会である.
また、神籬は祭祀の場という意味なので、祭で肉を供えるのは当たり前のことであったということになる.
もちろん、これらの字は、中国での祭祀の際に犠牲として捧げられた肉を指すために造字されたものである.
したがって、それを転用したと考えるのなら、肉月がつくのも当然ではないかという反論は可能である.
ただ、それならそれで、なぜ、字を変えなかったのだろうか.
「古事記」の大国主が須勢理毘売に歌う場面、その情景にある「繋御馬之鞍(繋げし御馬の鞍)」の鞍は、原文(48-9)では木+安と書いてある.
活字化する際に鞍に直したので、活字はもちろん、インターネット上にもほとんど見つからないと思うが、当時の日本では、鞍は皮革製ではなく、木製だったのである.
また、「御馬」と書いているが、御は中国では「車を走らせる」の意味である.
したがって、昔、運動会で御婦人席と書いてあるのを見つけた中国人が、日本人はあんな公開の場で婦人を御するのかと驚いたという話がある.
しかしながら、日本では、中国にはない敬語を表すために、御の字を転用しているわけで、馬を御するという意味ではない.
「日本書紀」は中国語が分かる人が書いたと言われるが、「古事記」はそうではないらしく、漢字の使用法は奔放である.
そして、「新撰字鏡」では肉+乍という字まで作っているのである.
もし、神籬に肉が出されないのなら、肉月や肉偏を改めればよいだけなのである.
*月+辰、肉+乍等は肉月に辰、肉偏に乍を意味する(月+辰は、ひもろぎを単漢字変換すれば出てくるが、環境依存文字であるため、表示されない場合に備えてこのように表記した).
2021.9/16
Up Down
#340
祝と書いて「はふり」と読む.
「日本国語大辞典」には「神社に属して神に仕える職」とある.
神職である.
歴史学者の喜田貞吉は、この「ハフリ」は「ホフリ」の義であると述べている.
ホフリは、屠るに由来する語である.
この語は「古事記」に「亦斬波布理其軍士、故号其地謂波布理曽能(亦、其の軍士を斬波布理(きりハフリ)き.故、其地を号けて波布理曽能と謂ふ)」と出てくる.
また、その軍兵を斬り屠(ほふ)ったので、その地を「はふりその」と名付けたというのである.
この「はふりその」は、「日本書紀」には羽振苑と出ているが、読み方は一緒である.
今、JR奈良線と、近鉄京都線の併走区間に、JR祝園(ほうその)駅と近鉄新祝園駅が位置する辺りであるが、「はふり」とは「殺す」という意味を持っていたことになる.
「日本国語大辞典」には「はふる」について、「ほふる(放)の連用形の名詞化したもの」とあるが、さらに、屠(はふ)る、葬(はぶ)るも同根であるとする.
「離れる、離れさせる」という意味で共通しているからである.
屠ると葬るは、動物と命との違いはあるが、その命を体から離れさすことであり、放るは棄てる、投げるの意味で、これも離れていく動きである.
祝は示偏と兄からなる.
示偏は、戦後の改革でネという字形に変わってしまったが、本来は示で、テーブルの形からきた象形文字である.
#324にも書いたが、祭という字はテーブルの上に肉を置く図であり、神が示+雷or電からなっているように、示は神に関係する文字につく.
そして、兄は頭の大きな人である.
頭は、頭(かしら)である.
ヘッドである.
つまり、祭の主催者である.
もっとも、兄はひざまずく人物で、世話をする人だという語源説もあるが、この場合でも、祭祀を行う人と考えられる.
つまり、祝は祭を行う人であり、同時に屠る人である.
何を屠るかというと、平安末期の「色葉字類抄https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1885583(122コマ)」に「切肉鳥也」とある.
肉や鳥を切るのだから、獣から肉を「離れさせる」存在である.
つまり、古代の祭では、肉を出し、神とともに共食していたのである.
諏訪大社の御頭祭が古式豊かと称したのはこのためである.
2021.9/19
Up
Down
#340
祝と書いて「はふり」と読む.
「日本国語大辞典」には「神社に属して神に仕える職」とある.
神職である.
歴史学者の喜田貞吉は、この「ハフリ」は「ホフリ」の義であると述べている.
ホフリは、屠るに由来する語である.
この語は「古事記」に「亦斬波布理其軍士、故号其地謂波布理曽能(亦、其の軍士を斬波布理(きりハフリ)き.故、其地を号けて波布理曽能と謂ふ)」と出てくる.
また、その軍兵を斬り屠(ほふ)ったので、その地を「はふりその」と名付けたというのである.
この「はふりその」は、「日本書紀」には羽振苑と出ているが、読み方は一緒である.
今、JR奈良線と、近鉄京都線の併走区間に、JR祝園(ほうその)駅と近鉄新祝園駅が位置する辺りであるが、「はふり」とは「殺す」という意味を持っていたことになる.
「日本国語大辞典」には「はふる」について、「ほふる(放)の連用形の名詞化したもの」とあるが、さらに、屠(はふ)る、葬(はぶ)るも同根であるとする.
「離れる、離れさせる」という意味で共通しているからである.
屠ると葬るは、動物と命との違いはあるが、その命を体から離れさすことであり、放るは棄てる、投げるの意味で、これも離れていく動きである.
祝は示偏と兄からなる.
示偏は、戦後の改革でネという字形に変わってしまったが、本来は示で、テーブルの形からきた象形文字である.
#324にも書いたが、祭という字はテーブルの上に肉を置く図であり、神が示+雷or電からなっているように、示は神に関係する文字につく.
そして、兄は頭の大きな人である.
頭は、頭(かしら)である.
ヘッドである.
つまり、祭の主催者である.
もっとも、兄はひざまずく人物で、世話をする人だという語源説もあるが、この場合でも、祭祀を行う人と考えられる.
つまり、祝は祭を行う人であり、同時に屠る人である.
何を屠るかというと、平安末期の「色葉字類抄https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1885583(122コマ)」に「切肉鳥也」とある.
肉や鳥を切るのだから、獣から肉を「離れさせる」存在である.
つまり、古代の祭では、肉を出し、神とともに共食していたのである.
諏訪大社の御頭祭が古式豊かと称したのはこのためである.
2021.9/19
Up Down
#341
#337の玉名市の諏訪神社では猪、君津市の諏訪神社では鶏肉となっており、前者では汁として、後者では生肉の形で参拝者に供される.
そして、後者の場合、家に持ち帰って調理するそうだが、諏訪大社の場合、直会の鹿肉はそのまま出てくる.
一応、同大社の資料館である神(じん)長官守矢(もりや)史料館によると、直会に出されるものは、ミシャグジ神に捧げるものも含めて調理されているとのことである.
もっとも、若干、茹でたとか、炙ったとか、塩を振ったとかいうのも調理の一種である.
どの程度の調理だったのか分からないし、古くからそうであったかどうかも分からない.
ただ、君津市の諏訪神社の鶏肉が生であるのなら、これも、本来は生であったのかもしれない.
少なくとも、インターネット上の画像では生のように見えるが、膾にしたようにも見えない.
また、御頭祭の際には、御贄柱が立てられ、そこに御贄串に串刺しにされた鹿肉2kgが25本、合計で50kgが1ヶ月間置かれた後に削って供えられる.
削ってという部分でも分かるが、これは干し肉である.
干し肉は、脯、「ほしし」とか「ほじし」とか読むが、干し宍(ほししし)からきた語で、木簡等に登場しており、古代から知られていた.
ところで、学生さんが実際に作ってみた研究報告によると、生肉をそのまま干したのでは雑菌が発生するので、
塩蔵したり、茹でた物に塩をかけてから干したほうがよいとある.
つまり、この諏訪大社の方法ではいけないということになる.
しかも、先述のように、古代は塩も貴重品であったので、そのまま干していた可能性が高い.
もちろん、古代人の食品衛生に関する知識は薄く、それぐらいものともしなかったという考えもあるが、
実は、そのような下ごしらえをしなくても大丈夫だったのではないかと思っている.
2021.9/28
Up
Down
#341
#337の玉名市の諏訪神社では猪、君津市の諏訪神社では鶏肉となっており、前者では汁として、後者では生肉の形で参拝者に供される.
そして、後者の場合、家に持ち帰って調理するそうだが、諏訪大社の場合、直会の鹿肉はそのまま出てくる.
一応、同大社の資料館である神(じん)長官守矢(もりや)史料館によると、直会に出されるものは、ミシャグジ神に捧げるものも含めて調理されているとのことである.
もっとも、若干、茹でたとか、炙ったとか、塩を振ったとかいうのも調理の一種である.
どの程度の調理だったのか分からないし、古くからそうであったかどうかも分からない.
ただ、君津市の諏訪神社の鶏肉が生であるのなら、これも、本来は生であったのかもしれない.
少なくとも、インターネット上の画像では生のように見えるが、膾にしたようにも見えない.
また、御頭祭の際には、御贄柱が立てられ、そこに御贄串に串刺しにされた鹿肉2kgが25本、合計で50kgが1ヶ月間置かれた後に削って供えられる.
削ってという部分でも分かるが、これは干し肉である.
干し肉は、脯、「ほしし」とか「ほじし」とか読むが、干し宍(ほししし)からきた語で、木簡等に登場しており、古代から知られていた.
ところで、学生さんが実際に作ってみた研究報告によると、生肉をそのまま干したのでは雑菌が発生するので、
塩蔵したり、茹でた物に塩をかけてから干したほうがよいとある.
つまり、この諏訪大社の方法ではいけないということになる.
しかも、先述のように、古代は塩も貴重品であったので、そのまま干していた可能性が高い.
もちろん、古代人の食品衛生に関する知識は薄く、それぐらいものともしなかったという考えもあるが、
実は、そのような下ごしらえをしなくても大丈夫だったのではないかと思っている.
2021.9/28
Up Down
#342
この研究報告では猪肉の薄切りを使用しているが、串刺しにされる鹿肉は2kgの肉塊である.
この肉塊と、実験に使われた薄肉では、条件が随分と異なる.
肉が駄目になるのは表面からだからである.
このため、レストランによっては、枝肉を仕入れてくる場合がある.
枝肉とは、皮と内臓を取り除いた肉のことで、木の枝に似てことからこの名があるが、1頭分あるので、かなり巨大である.
枝肉までいかなくても、肉塊で仕入れるレストランは多い.
もちろん、大抵のレストランでは、肉屋からその日の分か、数日分を仕入れるのだが、このような大きな肉塊だと、腐敗しても、表面を削るだけで食べられる.
そのようなことをするのは、屠殺してすぐの肉は硬くて食べられないからである.
死後硬直である.
このため、屠殺して数時間ならまだしも、それを越えるとかなり硬くなる.
したがって、ユッケのように生肉を食する場合でも、貯蔵した肉を使用するのである.
しかし、薄肉でそのようなことをしたら、可食部がなくなる.
また、熟成と呼ぶが、肉塊を長期間貯蔵することにより味がよくなるという効果もある.
場合によっては100日以上熟成する場合もあり、その場合、腐敗により3割以上が食用にならなくなるが、それを売り物にする所もある.
ただ、この熟成には、低温、高湿度と空気の循環が不可欠であり、素人の手を出せるようなものではない.
諏訪大社の場合、厳冬期の野外に串に刺して干すことによって条件をクリアさせていると思うが、鹿肉だからこそ可能なのであり、油脂分や水分の多い猪肉の場合は難しいであろう.
2021.10/4
Up
Down
#342
この研究報告では猪肉の薄切りを使用しているが、串刺しにされる鹿肉は2kgの肉塊である.
この肉塊と、実験に使われた薄肉では、条件が随分と異なる.
肉が駄目になるのは表面からだからである.
このため、レストランによっては、枝肉を仕入れてくる場合がある.
枝肉とは、皮と内臓を取り除いた肉のことで、木の枝に似てことからこの名があるが、1頭分あるので、かなり巨大である.
枝肉までいかなくても、肉塊で仕入れるレストランは多い.
もちろん、大抵のレストランでは、肉屋からその日の分か、数日分を仕入れるのだが、このような大きな肉塊だと、腐敗しても、表面を削るだけで食べられる.
そのようなことをするのは、屠殺してすぐの肉は硬くて食べられないからである.
死後硬直である.
このため、屠殺して数時間ならまだしも、それを越えるとかなり硬くなる.
したがって、ユッケのように生肉を食する場合でも、貯蔵した肉を使用するのである.
しかし、薄肉でそのようなことをしたら、可食部がなくなる.
また、熟成と呼ぶが、肉塊を長期間貯蔵することにより味がよくなるという効果もある.
場合によっては100日以上熟成する場合もあり、その場合、腐敗により3割以上が食用にならなくなるが、それを売り物にする所もある.
ただ、この熟成には、低温、高湿度と空気の循環が不可欠であり、素人の手を出せるようなものではない.
諏訪大社の場合、厳冬期の野外に串に刺して干すことによって条件をクリアさせていると思うが、鹿肉だからこそ可能なのであり、油脂分や水分の多い猪肉の場合は難しいであろう.
2021.10/4
Up Down
#343
干し肉の場合は湿度は少ない方がいいので、より作りやすいと思う.
では、その干し肉を、古代の日本人はどのようにして食べていたのだろうか.
たとえば、「もののけ姫」というアニメーション映画では、干し肉をそのまま囓っていたそうであるが、同様の食べ方をしていたのではないかと思われる.
もっとも、思うだけではいけないので、多少の考察は必要だと思うが、資料がない.
ただ、中華料理のように、乾物を戻して食べるというような手間のかかることはしていないと思う.
和食で、そのようなことをするのは干椎茸、干大根、乾瓢、海藻類等であるが、動物性のものでは金子(キンコ)ぐらいしか思いつかないからである.
しかも、金子の場合、光参と書いてもキンコと読むように、この調理法は、中国伝来のものであろうと思われる.
そして、これ以外の動物性の乾物は干物の類いになるので、干し肉も、戻して食べるというような手間はかけていないと思われる.
実際、平安末期から鎌倉時代に書かれた日本最古の料理書「厨事類記」にも、乾物を水で戻すような料理は載せられていない.
ただ、この本は料理書というより儀礼書であって、料理をどのように並べるかということには詳しいが、調理方法についてはあまり記載はない.
2021.10/7
Up
Down
#343
干し肉の場合は湿度は少ない方がいいので、より作りやすいと思う.
では、その干し肉を、古代の日本人はどのようにして食べていたのだろうか.
たとえば、「もののけ姫」というアニメーション映画では、干し肉をそのまま囓っていたそうであるが、同様の食べ方をしていたのではないかと思われる.
もっとも、思うだけではいけないので、多少の考察は必要だと思うが、資料がない.
ただ、中華料理のように、乾物を戻して食べるというような手間のかかることはしていないと思う.
和食で、そのようなことをするのは干椎茸、干大根、乾瓢、海藻類等であるが、動物性のものでは金子(キンコ)ぐらいしか思いつかないからである.
しかも、金子の場合、光参と書いてもキンコと読むように、この調理法は、中国伝来のものであろうと思われる.
そして、これ以外の動物性の乾物は干物の類いになるので、干し肉も、戻して食べるというような手間はかけていないと思われる.
実際、平安末期から鎌倉時代に書かれた日本最古の料理書「厨事類記」にも、乾物を水で戻すような料理は載せられていない.
ただ、この本は料理書というより儀礼書であって、料理をどのように並べるかということには詳しいが、調理方法についてはあまり記載はない.
2021.10/7
Up Down
#344
それでも、乾物(からもの)とも呼ばれた干物については、国立公文書館デジタルアーカイブで公開されている群書類従本「厨事類記」の37-8コマに記述がある.
たとえば、焼蛸、蒸蚫、楚割である.
うち、焼蛸は名前通り、石で焼いたタコの脚である.
蒸蚫については、なぜ蒸し物がと思われる方も多いと思うが、蒸した後に干したアワビである.
そして、楚割は「すはやり」とか「そはやり」とか読むが、「すわえ」、つまり、小枝のように細長く削いだ魚、
「延喜式」には鯛だとか鮫だとかが出てくるが、それを干したものである.
また、39コマには、「海月、酒と塩とにて、めでたく洗ひて、方に切りて、鰹を酒にひたして、其汁にてあふべし(原文片仮名)」とある.
クラゲは洗って四角く切り、カツオを浸した酒で和えるというわけなので、このカツオは生ではなく、干したものではないかといわれている.
つまり、今の鰹節の原型であるが、これらはすべて魚介類であって、獣肉ではない.
しかたなく、37コマの干鳥を見ると、雉を塩をつけずに干し、削って食べるとある.
これだけで考えるのはいささか苦しいが、干し肉も塩蔵ではなく、そのまま干したものであり、薄く削いで食べていたのではないかと思う.
つまり、茹でたり、炙ったり、もちろん、戻したものではなく、味付けをしたものでもなさそうである.
2021.10/12
Up
Down
#344
それでも、乾物(からもの)とも呼ばれた干物については、国立公文書館デジタルアーカイブで公開されている群書類従本「厨事類記」の37-8コマに記述がある.
たとえば、焼蛸、蒸蚫、楚割である.
うち、焼蛸は名前通り、石で焼いたタコの脚である.
蒸蚫については、なぜ蒸し物がと思われる方も多いと思うが、蒸した後に干したアワビである.
そして、楚割は「すはやり」とか「そはやり」とか読むが、「すわえ」、つまり、小枝のように細長く削いだ魚、
「延喜式」には鯛だとか鮫だとかが出てくるが、それを干したものである.
また、39コマには、「海月、酒と塩とにて、めでたく洗ひて、方に切りて、鰹を酒にひたして、其汁にてあふべし(原文片仮名)」とある.
クラゲは洗って四角く切り、カツオを浸した酒で和えるというわけなので、このカツオは生ではなく、干したものではないかといわれている.
つまり、今の鰹節の原型であるが、これらはすべて魚介類であって、獣肉ではない.
しかたなく、37コマの干鳥を見ると、雉を塩をつけずに干し、削って食べるとある.
これだけで考えるのはいささか苦しいが、干し肉も塩蔵ではなく、そのまま干したものであり、薄く削いで食べていたのではないかと思う.
つまり、茹でたり、炙ったり、もちろん、戻したものではなく、味付けをしたものでもなさそうである.
2021.10/12
Up Down
#345
そのようなものがおいしいのかと思われるだろうが、肉の味がするだけで充分だったのではないかと思う.
デフォーの「ロビンソン漂流記」の中にフライディーという先住民が登場する.
他の部族に食われそうになった時にロビンソンに救われて召使いになるのだが、彼は調味料を拒否していた.
食物は、それだけで本来の味を持っており、わざわざ味付けをする必要はないというのである.
そして、その言葉を真に受けたのが私である.
小学生であったということもあるのだが、調味料というものを使わなくなったのである.
そして、これは今日まで続いているので、肉は肉、魚は魚で、そのものの味があるというフライディーの言葉には大いに頷くものがある.
もっとも、野菜などは、昨今のものは、調味料を使用する前提で栽培されているので、きわめて水っぽいものに成り果てている.
したがって、ほとんどの人は野菜本来の濃厚な味をご存じないと思うが、農家の出なので、夏の太陽の下で完熟したトマトのあくどいまでの味の濃さとかは覚えている.
このため、赤茄子(トマト)を村で最初に食ったが、あまりのまずさに石垣にぶつけて遊んだという祖母の話は、カゴメの創業者の蟹江一太郎の逸話とともに懐かしい.
陸軍を満期除隊になった蟹江は、上官に勧められて洋野菜の栽培に向かうが、トマトだけは売れなかった.
これをトマト・ソースに加工したのが躍進のきっかけだったという話だが、
これが20世紀初頭の話だから、日露戦争の提灯行列に参加したという祖母の話と時代が合致するからである.
それはともかくとして、熟成によって肉の味が複雑化するように、干し肉も、その製造の過程で味が変化していく.
それを楽しむのであれば、調味料は必要なかったと思う.
2021.10/17
Up
Down
#345
そのようなものがおいしいのかと思われるだろうが、肉の味がするだけで充分だったのではないかと思う.
デフォーの「ロビンソン漂流記」の中にフライディーという先住民が登場する.
他の部族に食われそうになった時にロビンソンに救われて召使いになるのだが、彼は調味料を拒否していた.
食物は、それだけで本来の味を持っており、わざわざ味付けをする必要はないというのである.
そして、その言葉を真に受けたのが私である.
小学生であったということもあるのだが、調味料というものを使わなくなったのである.
そして、これは今日まで続いているので、肉は肉、魚は魚で、そのものの味があるというフライディーの言葉には大いに頷くものがある.
もっとも、野菜などは、昨今のものは、調味料を使用する前提で栽培されているので、きわめて水っぽいものに成り果てている.
したがって、ほとんどの人は野菜本来の濃厚な味をご存じないと思うが、農家の出なので、夏の太陽の下で完熟したトマトのあくどいまでの味の濃さとかは覚えている.
このため、赤茄子(トマト)を村で最初に食ったが、あまりのまずさに石垣にぶつけて遊んだという祖母の話は、カゴメの創業者の蟹江一太郎の逸話とともに懐かしい.
陸軍を満期除隊になった蟹江は、上官に勧められて洋野菜の栽培に向かうが、トマトだけは売れなかった.
これをトマト・ソースに加工したのが躍進のきっかけだったという話だが、
これが20世紀初頭の話だから、日露戦争の提灯行列に参加したという祖母の話と時代が合致するからである.
それはともかくとして、熟成によって肉の味が複雑化するように、干し肉も、その製造の過程で味が変化していく.
それを楽しむのであれば、調味料は必要なかったと思う.
2021.10/17
Up Down
#346
難波宮跡から「斯々一古」と書かれた7世紀中葉の国内最古級の木簡が出ている.
この木簡は荷札で、難波宮に送られたものであるが、「斯々一古」は「宍一籠」の意味ではないかと言われている.
それが正しいとするのなら、この肉は肉塊であろう.
籠に入れれば、通気性がよくなるからである.
もちろん、どこから、いつ頃の季節に運ばれたのか分からない.
ただ、仮に、冬期に運ばれてきたのだとしたら、通気性をよくすることによって#342で述べたように、表面を削れば、腐敗していても食べられるようになったはずである.
そして、それが可能であるのなら、塩蔵だとか、御頭祭のように、干し肉にする必要もなかったということになる.
実際、中世の肉屋で画像検索をすると、動物の死体が店頭にぶら下がっている風景を見ることができる.
冷蔵、冷凍、さらには真空パックという保存技術が登場した近代でも、一昔前のパリ市街の写真などを見ていると、同様の景色を見つけることができる.
現在でも似たような景色は見られるが、あれは生ハムの類いであろう.
もっとも、ヨーロッパのような寒冷地ならともかく、日本の気候で同様のことが可能かどうかは知らない.
ただ、内臓を塩辛にしたものもあったようだし、脳味噌の和え物という現代人の感覚では見るのも憚れるようなものまであった.
そういうものはもっと腐敗しやすいわけだから、近郊から運ばれたものだろうが、存外に塩蔵もされていない生肉が食材として運び込まれてきていた可能性はある.
2021.10/23
Up
Down
#346
難波宮跡から「斯々一古」と書かれた7世紀中葉の国内最古級の木簡が出ている.
この木簡は荷札で、難波宮に送られたものであるが、「斯々一古」は「宍一籠」の意味ではないかと言われている.
それが正しいとするのなら、この肉は肉塊であろう.
籠に入れれば、通気性がよくなるからである.
もちろん、どこから、いつ頃の季節に運ばれたのか分からない.
ただ、仮に、冬期に運ばれてきたのだとしたら、通気性をよくすることによって#342で述べたように、表面を削れば、腐敗していても食べられるようになったはずである.
そして、それが可能であるのなら、塩蔵だとか、御頭祭のように、干し肉にする必要もなかったということになる.
実際、中世の肉屋で画像検索をすると、動物の死体が店頭にぶら下がっている風景を見ることができる.
冷蔵、冷凍、さらには真空パックという保存技術が登場した近代でも、一昔前のパリ市街の写真などを見ていると、同様の景色を見つけることができる.
現在でも似たような景色は見られるが、あれは生ハムの類いであろう.
もっとも、ヨーロッパのような寒冷地ならともかく、日本の気候で同様のことが可能かどうかは知らない.
ただ、内臓を塩辛にしたものもあったようだし、脳味噌の和え物という現代人の感覚では見るのも憚れるようなものまであった.
そういうものはもっと腐敗しやすいわけだから、近郊から運ばれたものだろうが、存外に塩蔵もされていない生肉が食材として運び込まれてきていた可能性はある.
2021.10/23
Up Down
#347
西洋人は、レア、表面だけ焼いたステーキを好む.
いわゆる、血の滴るようなと表現されるものであるが、あの赤い液体は血ではなく、肉汁である.
和牛のような、脂がところ構わず入っているようなものならいざ知らず、西洋の牛肉は赤身で、脂はほとんど入っていない.
当然、焼きすぎると、硬くて食べられたものではないし、肉汁が飛んでパサパサになってしまう.
このため、西洋人はレアのステーキを好むのである.
実際、アメリカ流のミニッツ・ステーキは、油を敷かずに熱したフライパンの上で、厚切りの赤身の牛肉を1分間弱火で焼き、
裏返して30秒焼くだけというものであるが、肉汁が多く、実に柔らかい.
これを和牛肉でやったことはないが、多分、脂が溶け、全体に熱が回って、かなり違ったものになるだろうと思う.
しかし、それでは、食中毒が怖いと言われそうである.
ただ、昔、AIDS患者の食事について聞いたところでは、ステーキは食べてもよいが、ハンバーグは駄目なのだそうだ.
AIDSは免疫がなくなるという病気だから、黴菌とかヴィールスとかが体内に入るとまずい.
このため、衛生には気を遣うのだが、肉の場合、表面にしか菌はつかないので、レアであっても、すべての面が焼いてあればよいということになる.
熟成肉の表面を削り取って食べるのも同様の理由である.
これに対し、ハンバーグはミンチなので、すべての表面を焼くのは難しい.
したがって、レアなんてと思う人は、基本的には、生の肉の感触を気持ち悪いと感じるかどうかという問題なのだろうと思う.
2021.10/30
Up
Down
#347
西洋人は、レア、表面だけ焼いたステーキを好む.
いわゆる、血の滴るようなと表現されるものであるが、あの赤い液体は血ではなく、肉汁である.
和牛のような、脂がところ構わず入っているようなものならいざ知らず、西洋の牛肉は赤身で、脂はほとんど入っていない.
当然、焼きすぎると、硬くて食べられたものではないし、肉汁が飛んでパサパサになってしまう.
このため、西洋人はレアのステーキを好むのである.
実際、アメリカ流のミニッツ・ステーキは、油を敷かずに熱したフライパンの上で、厚切りの赤身の牛肉を1分間弱火で焼き、
裏返して30秒焼くだけというものであるが、肉汁が多く、実に柔らかい.
これを和牛肉でやったことはないが、多分、脂が溶け、全体に熱が回って、かなり違ったものになるだろうと思う.
しかし、それでは、食中毒が怖いと言われそうである.
ただ、昔、AIDS患者の食事について聞いたところでは、ステーキは食べてもよいが、ハンバーグは駄目なのだそうだ.
AIDSは免疫がなくなるという病気だから、黴菌とかヴィールスとかが体内に入るとまずい.
このため、衛生には気を遣うのだが、肉の場合、表面にしか菌はつかないので、レアであっても、すべての面が焼いてあればよいということになる.
熟成肉の表面を削り取って食べるのも同様の理由である.
これに対し、ハンバーグはミンチなので、すべての表面を焼くのは難しい.
したがって、レアなんてと思う人は、基本的には、生の肉の感触を気持ち悪いと感じるかどうかという問題なのだろうと思う.
2021.10/30
Up Down
#348
鹿肉も赤身である.
その上、野生動物なので、家畜と違って、脂はほとんどないので、焼きすぎれば硬くなる.
当然、焼き加減はレアかミディアムとなる.
もっとも、生肉は食うなと書いてあるサイトもあるが、部位によっては刺身でいけるとする記述も多い.
したがって、食うなというのは、食中毒の危険性が高いという意味であろう.
ただ、鹿肉の調理法を見ると、結構な加熱時間をとっている割に、アルミ箔に包んでというように、直火で焼かないようにしていることが多い.
結局、どっちなのだろうかとなるのだが、日本人は、刺身や寿司がそうであるように、世界有数の、生食を好む民族である.
したがって、古代の日本人が鹿肉を食べるのなら、レアとかミディアムとかではなく、生食を選択していた可能性が高いと思う.
もっとも、明確に鹿肉を生で食べたというような既述はないようである.
ただ、中国には「人口に膾炙(かいしゃ)する」という言葉がある.
膾炙の膾は既述のように「なます」、炙は、月(肉)+火なので、炙(あぶ)り肉である.
これは、唐詩に由来する言葉で、膾や、炙り肉のように誰もが知っているという意味だが、この「炙」という文字が記紀に登場しない.
「古事記」に1ヶ所、「見炙而病臥在(見炙(やかえ)て病み臥(こ)やせり)」と出てくるばかりである.
しかも、これはイザナミが火の神を産んだ際に陰部を焼いて病み伏せったというのだから、炙り肉は関係ない.
しかしながら、「人口に膾炙する」は当時の中国の肉料理として、膾と炙り肉は誰でも知っている、
というより、中華料理、中国料理という言葉で我々が想起すると思われる揚げ物、炒め物の出現は、実は、今から約600年前に過ぎない.
宋代にコークスと鉄鍋が使われるようになってからなのである.
つまり、この当時は、この調理法以外では茹でるぐらいしか残らないので、膾しか登場しないというのは不可解なのである.
2021.12/9
Up
Down
#348
鹿肉も赤身である.
その上、野生動物なので、家畜と違って、脂はほとんどないので、焼きすぎれば硬くなる.
当然、焼き加減はレアかミディアムとなる.
もっとも、生肉は食うなと書いてあるサイトもあるが、部位によっては刺身でいけるとする記述も多い.
したがって、食うなというのは、食中毒の危険性が高いという意味であろう.
ただ、鹿肉の調理法を見ると、結構な加熱時間をとっている割に、アルミ箔に包んでというように、直火で焼かないようにしていることが多い.
結局、どっちなのだろうかとなるのだが、日本人は、刺身や寿司がそうであるように、世界有数の、生食を好む民族である.
したがって、古代の日本人が鹿肉を食べるのなら、レアとかミディアムとかではなく、生食を選択していた可能性が高いと思う.
もっとも、明確に鹿肉を生で食べたというような既述はないようである.
ただ、中国には「人口に膾炙(かいしゃ)する」という言葉がある.
膾炙の膾は既述のように「なます」、炙は、月(肉)+火なので、炙(あぶ)り肉である.
これは、唐詩に由来する言葉で、膾や、炙り肉のように誰もが知っているという意味だが、この「炙」という文字が記紀に登場しない.
「古事記」に1ヶ所、「見炙而病臥在(見炙(やかえ)て病み臥(こ)やせり)」と出てくるばかりである.
しかも、これはイザナミが火の神を産んだ際に陰部を焼いて病み伏せったというのだから、炙り肉は関係ない.
しかしながら、「人口に膾炙する」は当時の中国の肉料理として、膾と炙り肉は誰でも知っている、
というより、中華料理、中国料理という言葉で我々が想起すると思われる揚げ物、炒め物の出現は、実は、今から約600年前に過ぎない.
宋代にコークスと鉄鍋が使われるようになってからなのである.
つまり、この当時は、この調理法以外では茹でるぐらいしか残らないので、膾しか登場しないというのは不可解なのである.
2021.12/9
Up Down
#349
ただし、現代の中国で膾は好まれていない.
たとえば、日本の寿司や刺身のような生魚を食べる料理が中国で流行り出すのは、ごく最近のことである.
もっとも、膾は紀元前5世紀の「礼記」や「論語」に登場する.
「論語」などは「膾不厭細(膾は細きを厭わず)」だから、膾はどれだけ細く切ってあっても構わないとか書いてあるぐらいである.
また、「史記」の「鴻門の会」で樊會(はんかい)*が項羽に食べさせられたのは大きな豚の生の肩肉である.
樊會は与えられた肉を盾の上で剣で切ってそのまま食べ、豪傑ぶりを示したが、彼は劉邦に仕える前は犬の屠殺を行っていた.
つまり、肉屋であったので、その彼が生肉を与えられ、そのまま切って食べたということは、膾にしたということである.
また、漢代の「楚辞」には「懲於羹而吹齏兮(羮(あつもの)に懲りて齏(せい)を吹く)」とある.
齏は膾であるので、熱いスープに懲りたからといって膾にまで息を吹いて冷ますことはないという意味になる
(もっとも、「楚辞」の本来の意味は、それぐらいの注意をすべきであるだが).
つまり、漢代においては普通に食べられていたわけである.
また、前回述べた「人口に膾炙する」は、唐代の詩に由来するのだから、唐代にも盛んに食べていたことになる.
これが下火になったのは、明の李時珍の「本草綱目」に
「魚膾肉生損人尤甚為○○為痼疾為奇病不可不知
(魚膾、肉生、人を損ねること尤も甚だし.○○を為し、痼疾を為し、奇病を為す.知らざるべからず)」と生食の害が記されたからである.
○○はともに病垂のある徴と假から人偏を取った字で、病気の名である.
したがって、生肉料理や、魚を膾にしたものは、腹の中に出来物ができるということになる.
おそらくは、食中毒が発生したのだろう.
膾は、確認出来るところでは、明代に書かれた「水滸伝」あたりまでは普通に食べられている.
その後、徐々に消えていき、現在では、膾は中国東北部や南部の一部地域で生き残っているに過ぎない.
*樊會の會は口偏があるが、環境依存文字であるので會で代用した.
2021.12/11
Up
Down
#349
ただし、現代の中国で膾は好まれていない.
たとえば、日本の寿司や刺身のような生魚を食べる料理が中国で流行り出すのは、ごく最近のことである.
もっとも、膾は紀元前5世紀の「礼記」や「論語」に登場する.
「論語」などは「膾不厭細(膾は細きを厭わず)」だから、膾はどれだけ細く切ってあっても構わないとか書いてあるぐらいである.
また、「史記」の「鴻門の会」で樊會(はんかい)*が項羽に食べさせられたのは大きな豚の生の肩肉である.
樊會は与えられた肉を盾の上で剣で切ってそのまま食べ、豪傑ぶりを示したが、彼は劉邦に仕える前は犬の屠殺を行っていた.
つまり、肉屋であったので、その彼が生肉を与えられ、そのまま切って食べたということは、膾にしたということである.
また、漢代の「楚辞」には「懲於羹而吹齏兮(羮(あつもの)に懲りて齏(せい)を吹く)」とある.
齏は膾であるので、熱いスープに懲りたからといって膾にまで息を吹いて冷ますことはないという意味になる
(もっとも、「楚辞」の本来の意味は、それぐらいの注意をすべきであるだが).
つまり、漢代においては普通に食べられていたわけである.
また、前回述べた「人口に膾炙する」は、唐代の詩に由来するのだから、唐代にも盛んに食べていたことになる.
これが下火になったのは、明の李時珍の「本草綱目」に
「魚膾肉生損人尤甚為○○為痼疾為奇病不可不知
(魚膾、肉生、人を損ねること尤も甚だし.○○を為し、痼疾を為し、奇病を為す.知らざるべからず)」と生食の害が記されたからである.
○○はともに病垂のある徴と假から人偏を取った字で、病気の名である.
したがって、生肉料理や、魚を膾にしたものは、腹の中に出来物ができるということになる.
おそらくは、食中毒が発生したのだろう.
膾は、確認出来るところでは、明代に書かれた「水滸伝」あたりまでは普通に食べられている.
その後、徐々に消えていき、現在では、膾は中国東北部や南部の一部地域で生き残っているに過ぎない.
*樊會の會は口偏があるが、環境依存文字であるので會で代用した.
2021.12/11
Up Down
#350
中国東北部や南部の一部地域で膾が生き残ったのは、これらが僻遠の地であったからであろう.
ならば、#335で少し示した韓国の肉膾(ユッケ)も、同様の理由で生き延びたもののように思われるが、それは正解であると同時に間違いである.
というのは、韓国の場合、今日まで食べられ続けられたのは、その理由によると思われるが、仏教の影響で早くに肉食文化が消え失せているからである.
したがって、ユッケは、膾の変形ではなく、高麗が元に服属した際に遊牧民族の生肉料理が入ってきたものである.
いわゆる、タルタル・ステーキである.
タルタルとは、タタール人のことで、タタール人とはかなり広い民族の呼称として使われるが、モンゴル、つまり元朝と関係ある人々のことである.
彼らは、軍として行動する時は、多数の馬とともに移動していたが、その馬は乗用であると同時に食用でもあった.
ただ、乗用であるということは、筋肉が発達するということである.
このため、屠殺された馬の肉は、微塵切りにして袋に入れ、鞍の下に置いた.
体重と馬の運動により柔らかくしたのである.
これがヨーロッパに入るとともに、馬肉が牛肉になり、さらに挽き肉(ミンチ)となった.
これを焼いたのがハンバーグであるが、硬く、それゆえに安価な肩肉を労働者階級に提供するための工夫であったといわれる.
このタルタルというのは異国のという意味でつけられたという説もあるが、ユッケの場合は、元の影響下に出来た料理であると言いたくはなかったからかもしれない.
また、現在のユッケも牛肉がメインであるが、もともとは馬肉だったのかもしれない.
熊本は馬刺しを多く食べるが、これは韓国に出兵した加藤清正が持ってきたといわれるからである.
もっとも、兵糧攻めにあって、しかたなく馬肉を食べたのがもとだとなっているが、それだけでは焼き肉や鍋ではなく、馬刺しにする理由がない.
李氏朝鮮の時代、馬肉のユッケが一般的であったのであろう.
2021.12/13
Up
Down
#350
中国東北部や南部の一部地域で膾が生き残ったのは、これらが僻遠の地であったからであろう.
ならば、#335で少し示した韓国の肉膾(ユッケ)も、同様の理由で生き延びたもののように思われるが、それは正解であると同時に間違いである.
というのは、韓国の場合、今日まで食べられ続けられたのは、その理由によると思われるが、仏教の影響で早くに肉食文化が消え失せているからである.
したがって、ユッケは、膾の変形ではなく、高麗が元に服属した際に遊牧民族の生肉料理が入ってきたものである.
いわゆる、タルタル・ステーキである.
タルタルとは、タタール人のことで、タタール人とはかなり広い民族の呼称として使われるが、モンゴル、つまり元朝と関係ある人々のことである.
彼らは、軍として行動する時は、多数の馬とともに移動していたが、その馬は乗用であると同時に食用でもあった.
ただ、乗用であるということは、筋肉が発達するということである.
このため、屠殺された馬の肉は、微塵切りにして袋に入れ、鞍の下に置いた.
体重と馬の運動により柔らかくしたのである.
これがヨーロッパに入るとともに、馬肉が牛肉になり、さらに挽き肉(ミンチ)となった.
これを焼いたのがハンバーグであるが、硬く、それゆえに安価な肩肉を労働者階級に提供するための工夫であったといわれる.
このタルタルというのは異国のという意味でつけられたという説もあるが、ユッケの場合は、元の影響下に出来た料理であると言いたくはなかったからかもしれない.
また、現在のユッケも牛肉がメインであるが、もともとは馬肉だったのかもしれない.
熊本は馬刺しを多く食べるが、これは韓国に出兵した加藤清正が持ってきたといわれるからである.
もっとも、兵糧攻めにあって、しかたなく馬肉を食べたのがもとだとなっているが、それだけでは焼き肉や鍋ではなく、馬刺しにする理由がない.
李氏朝鮮の時代、馬肉のユッケが一般的であったのであろう.
2021.12/13
Up Down
#351
では、日本の寿司や刺身もそうなのかというと、明確な答えはない.
これらが、膾(魚だから鱠とすべきかもしれないが)の影響の元に成立したものか、それ以前に成立していたかというような疑問に答える方法が見いだせないからである.
ただ、「魏志倭人伝」には「倭地温暖冬夏食生菜(倭地温暖にして、冬夏生菜を食す)」とある.
一般に、この部分は、倭の地は温暖で、冬でも夏でも生野菜を食べるという意味に理解されている.
その後に「皆徒跣」、皆、裸足であると続くからである.
中国で生野菜は好まれないどころか、サラダを食べたことのない人も多い.
倭国の人達が、生野菜を食べるとしたら、奇異に写り、特筆されるのも当然だという考えである.
靴を履かずに、裸足でいるというのも同様である.
これに対し、この「生菜」の菜を副食の意味にとって、倭人は生食をしていたと考える人がいる.
たしかに、中国語の「菜単」がメニューを意味するように、食物全体を指す場合もある.
もっとも、「魏志」の時代にそのような用法があったかどうかは分からない.
実際、「三国志」全文を検索できるサイトで調べると、「菜」はここ以外に7例あるが、その意味に取れそうなのはこれだけである.
したがって、このように訳すのは少数派で、大抵は文字通りに生野菜を食べるとなっている.
ただし、倭国で食べられていた生野菜が何かという疑問がある.
また、華北よりも、倭国のほうが温暖だっただろうと思うが、冬季でも収穫できるような生野菜はあったのかという疑問も生じる.
2021.12/15
Up
Down
#351
では、日本の寿司や刺身もそうなのかというと、明確な答えはない.
これらが、膾(魚だから鱠とすべきかもしれないが)の影響の元に成立したものか、それ以前に成立していたかというような疑問に答える方法が見いだせないからである.
ただ、「魏志倭人伝」には「倭地温暖冬夏食生菜(倭地温暖にして、冬夏生菜を食す)」とある.
一般に、この部分は、倭の地は温暖で、冬でも夏でも生野菜を食べるという意味に理解されている.
その後に「皆徒跣」、皆、裸足であると続くからである.
中国で生野菜は好まれないどころか、サラダを食べたことのない人も多い.
倭国の人達が、生野菜を食べるとしたら、奇異に写り、特筆されるのも当然だという考えである.
靴を履かずに、裸足でいるというのも同様である.
これに対し、この「生菜」の菜を副食の意味にとって、倭人は生食をしていたと考える人がいる.
たしかに、中国語の「菜単」がメニューを意味するように、食物全体を指す場合もある.
もっとも、「魏志」の時代にそのような用法があったかどうかは分からない.
実際、「三国志」全文を検索できるサイトで調べると、「菜」はここ以外に7例あるが、その意味に取れそうなのはこれだけである.
したがって、このように訳すのは少数派で、大抵は文字通りに生野菜を食べるとなっている.
ただし、倭国で食べられていた生野菜が何かという疑問がある.
また、華北よりも、倭国のほうが温暖だっただろうと思うが、冬季でも収穫できるような生野菜はあったのかという疑問も生じる.
2021.12/15
Up Down
#352
現代中国語で「生菜」は、生野菜という意味と、レタスという意味があるそうだが、レタスの日本への伝来は意外と早い.
レタスの漢字名は萵苣(ちしゃ)で、平安時代の辞書である「新撰字鏡https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2556147?tocOpened=1(13コマ)」に「苣、知佐(ちさ)」として載っているからである.
江戸時代には結球しない種が掻き萵苣の名で普及しており、この名前は、家が農家だったので、小さい頃に聞いたことがある.
また、菠薐草(ホウレンソウ)は赤ジシャ、エンダイヴはオランダジシャ、紅毛ジシャ、菊ジシャと呼ばれていたが、もちろん、このジシャは萵苣の変形である.
原産地は地中海から西アジアなので、中国への伝来も早かったように思うが、文献によると7世紀の伝来とあり、日本には間を置かずに伝わったようである.
また、現在、サラダとして食べられている葉菜類は西洋野菜で、これらも、倭人が食べたとは思えない.
あと、「魏志倭人伝」に登場する植物で生食できそうなのは茗荷(ミョウガ)か山椒ぐらいであるが、大量に食べるようなものではない.
しかも、これらは、同書に「不知以為滋味(もって滋味となすを知らず)」と書かれているぐらいだから、食用にされていないことになる.
この他、葱(ネギ)は奈良時代、胡瓜(キュウリ)は平安時代、菠薐草は江戸時代、白菜に至っては明治になってからの伝来である.
また、春の七草として知られるいくつかの植物はあったはずだが、七草粥の名称が示すように煮て食べていた.
もっとも、この風習は6世紀の中国の「荊楚歳時記」に正月7日に7種の野菜を食べるとあるのが由来であり、平安時代に始まったものである.
したがって、この本が伝わる以前、倭人がこれらを生で食べていた可能性はある.
中でも、スズナ、スズシロとして知られる蕪(カブ)や大根は、生食可能である.
ただ、「徒然草」に「土大根を万(よろず)にいみじき薬とて、朝ごとに二つづゝ焼きて食ひける」人が出てくる.
毎朝2本ずつ大根を焼いて食べきれるはずもないので、昔の大根は、今よりずっと小さかったことになる.
大根(オホネ)という名前から考えると、他の植物より根が大きかった可能性はあるが、
現在の二十日大根や英語でラディッシュと呼ばれるものぐらいの大きさであったのではないのだろうか.
蕪にしてもそうだが、品種改良によって太く大きくなったのであって、旧来のものはかなり小さい.
これを食べていたからといって、中国人が倭人は生野菜を食べるとわざわざ記すほどのインパクトはないと思う.
あと、イメージとして合うのは芹(セリ)ぐらいだが、本来、香草であり、「生菜を食す」と書かれるほどの量を食べられるのだろうかと思う.
2021.12/16
Up
Down
#352
現代中国語で「生菜」は、生野菜という意味と、レタスという意味があるそうだが、レタスの日本への伝来は意外と早い.
レタスの漢字名は萵苣(ちしゃ)で、平安時代の辞書である「新撰字鏡https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2556147?tocOpened=1(13コマ)」に「苣、知佐(ちさ)」として載っているからである.
江戸時代には結球しない種が掻き萵苣の名で普及しており、この名前は、家が農家だったので、小さい頃に聞いたことがある.
また、菠薐草(ホウレンソウ)は赤ジシャ、エンダイヴはオランダジシャ、紅毛ジシャ、菊ジシャと呼ばれていたが、もちろん、このジシャは萵苣の変形である.
原産地は地中海から西アジアなので、中国への伝来も早かったように思うが、文献によると7世紀の伝来とあり、日本には間を置かずに伝わったようである.
また、現在、サラダとして食べられている葉菜類は西洋野菜で、これらも、倭人が食べたとは思えない.
あと、「魏志倭人伝」に登場する植物で生食できそうなのは茗荷(ミョウガ)か山椒ぐらいであるが、大量に食べるようなものではない.
しかも、これらは、同書に「不知以為滋味(もって滋味となすを知らず)」と書かれているぐらいだから、食用にされていないことになる.
この他、葱(ネギ)は奈良時代、胡瓜(キュウリ)は平安時代、菠薐草は江戸時代、白菜に至っては明治になってからの伝来である.
また、春の七草として知られるいくつかの植物はあったはずだが、七草粥の名称が示すように煮て食べていた.
もっとも、この風習は6世紀の中国の「荊楚歳時記」に正月7日に7種の野菜を食べるとあるのが由来であり、平安時代に始まったものである.
したがって、この本が伝わる以前、倭人がこれらを生で食べていた可能性はある.
中でも、スズナ、スズシロとして知られる蕪(カブ)や大根は、生食可能である.
ただ、「徒然草」に「土大根を万(よろず)にいみじき薬とて、朝ごとに二つづゝ焼きて食ひける」人が出てくる.
毎朝2本ずつ大根を焼いて食べきれるはずもないので、昔の大根は、今よりずっと小さかったことになる.
大根(オホネ)という名前から考えると、他の植物より根が大きかった可能性はあるが、
現在の二十日大根や英語でラディッシュと呼ばれるものぐらいの大きさであったのではないのだろうか.
蕪にしてもそうだが、品種改良によって太く大きくなったのであって、旧来のものはかなり小さい.
これを食べていたからといって、中国人が倭人は生野菜を食べるとわざわざ記すほどのインパクトはないと思う.
あと、イメージとして合うのは芹(セリ)ぐらいだが、本来、香草であり、「生菜を食す」と書かれるほどの量を食べられるのだろうかと思う.
2021.12/16
Up Down
#353
海藻類はどうであろう.
藻類を「菜」と呼ぶかという疑問はあるが、念のため、この点も考えてみたい.
#316に書いたように、欧米では海藻をほとんど食べない.
それどころか、海のゴミのように思われているので、日本人が海藻を食べるというと驚かれる.
もっとも、海藻食は日本の専売特許ではなく、ヨーロッパではアイルランド料理にあり、フランスのブルターニュ地方や南イタリアにもある.
アジアではもっと一般的で、南の方ではフィリピンとインドネシアで食べられているが、一人あたりの年間海藻消費量世界一は、海苔で有名な韓国である.
また、人口がはるかに多いので一人あたりでは少なくなるが、中国の食用海藻の消費量は世界一である.
その中心は昆布で、戦前は日本から大量に輸入されていた.
現在では、沿岸部で乾燥重量で60万t、現在の日本の昆布使用量の約30倍という世界一の海藻養殖量を誇る.
その半分はヨード類の原料になるが、残りは食用である.
また、ホンダワラは、昆布とともに漢方薬の材料として昔から重要視されていた.
あと、華南では海藻スープが食べられている.
したがって、中国人は、日本人が海藻を食べるといっても、西洋人のようには驚かないはずである.
また、昆布にしろ、海苔にしろ、乾燥させたり、佃煮にして食べるものである.
海藻スープも生食とは言いがたい.
ということは、「魏志倭人伝」の「生菜」には当てはまらない.
もっとも、生の海苔を消化できるのは日本人だけといわれており、古来、日本人は生海苔を食べてきたからだという説はある.
したがって、倭人が生海苔を食べるのを見た中国人が、それを報告した可能性はありそうである.
しかし、フランスの微生物研究チームが2010年に発表したのは、生海苔を分解できる酵素を持つ細菌が数人の日本人の腸内からのみから発見されたである.
つまり、すべての日本人がそうであるわけではない.
また、海苔の細胞膜は非常に硬いので、その非常に高い栄養分は、そのまま食べても体外に放出されるだけである.
つまり、生で食べても栄養価は低いが、格段の問題があるわけではないということなのだろう.
しかし、この細胞膜は熱に弱いので、加熱によって簡単に壊れる.
生海苔でも乾燥海苔でも、加熱すると風味が増すのはこのためである.
したがって、生海苔であっても、そのまま食べるより、味噌汁に入れたり、麺類と絡めて食べるという調理法が多く、生食されているわけではない.
実際、現在はほとんど食用にされない海松(ミル)を含めて、日本人は多くの海藻を食べてきたが、生食されるのは海葡萄ぐらいではないかと思う.
しかし、これも今世紀に入ってからの沖縄食ブームで知られるようになったものであり、倭人が常食していたとは思えない.
むしろ、湯通し、あるいは軽く茹でるという下拵えが必要なものばかりである.
また、日本では1980年代に定着したものであるが、海藻サラダも下処理が必要であり、生若布と呼ばれるものも同様である.
つまり、倭人も海藻を食べてはいただろうが、そのまま食べてはいないので、「生菜」を海藻だとすることはできない.
2021.12/18
Up
Down
#353
海藻類はどうであろう.
藻類を「菜」と呼ぶかという疑問はあるが、念のため、この点も考えてみたい.
#316に書いたように、欧米では海藻をほとんど食べない.
それどころか、海のゴミのように思われているので、日本人が海藻を食べるというと驚かれる.
もっとも、海藻食は日本の専売特許ではなく、ヨーロッパではアイルランド料理にあり、フランスのブルターニュ地方や南イタリアにもある.
アジアではもっと一般的で、南の方ではフィリピンとインドネシアで食べられているが、一人あたりの年間海藻消費量世界一は、海苔で有名な韓国である.
また、人口がはるかに多いので一人あたりでは少なくなるが、中国の食用海藻の消費量は世界一である.
その中心は昆布で、戦前は日本から大量に輸入されていた.
現在では、沿岸部で乾燥重量で60万t、現在の日本の昆布使用量の約30倍という世界一の海藻養殖量を誇る.
その半分はヨード類の原料になるが、残りは食用である.
また、ホンダワラは、昆布とともに漢方薬の材料として昔から重要視されていた.
あと、華南では海藻スープが食べられている.
したがって、中国人は、日本人が海藻を食べるといっても、西洋人のようには驚かないはずである.
また、昆布にしろ、海苔にしろ、乾燥させたり、佃煮にして食べるものである.
海藻スープも生食とは言いがたい.
ということは、「魏志倭人伝」の「生菜」には当てはまらない.
もっとも、生の海苔を消化できるのは日本人だけといわれており、古来、日本人は生海苔を食べてきたからだという説はある.
したがって、倭人が生海苔を食べるのを見た中国人が、それを報告した可能性はありそうである.
しかし、フランスの微生物研究チームが2010年に発表したのは、生海苔を分解できる酵素を持つ細菌が数人の日本人の腸内からのみから発見されたである.
つまり、すべての日本人がそうであるわけではない.
また、海苔の細胞膜は非常に硬いので、その非常に高い栄養分は、そのまま食べても体外に放出されるだけである.
つまり、生で食べても栄養価は低いが、格段の問題があるわけではないということなのだろう.
しかし、この細胞膜は熱に弱いので、加熱によって簡単に壊れる.
生海苔でも乾燥海苔でも、加熱すると風味が増すのはこのためである.
したがって、生海苔であっても、そのまま食べるより、味噌汁に入れたり、麺類と絡めて食べるという調理法が多く、生食されているわけではない.
実際、現在はほとんど食用にされない海松(ミル)を含めて、日本人は多くの海藻を食べてきたが、生食されるのは海葡萄ぐらいではないかと思う.
しかし、これも今世紀に入ってからの沖縄食ブームで知られるようになったものであり、倭人が常食していたとは思えない.
むしろ、湯通し、あるいは軽く茹でるという下拵えが必要なものばかりである.
また、日本では1980年代に定着したものであるが、海藻サラダも下処理が必要であり、生若布と呼ばれるものも同様である.
つまり、倭人も海藻を食べてはいただろうが、そのまま食べてはいないので、「生菜」を海藻だとすることはできない.
2021.12/18
Up Down
#354
倭人が皆裸足であるという記述は、中国と文化が違うと述べたいためのものである.
より正確に書けば、異国は野蛮であり、中国と同じなのは、我々の教化に従った結果であるということを言いたいがためである.
つまり、中華思想であり、周囲は東夷、西戎、南蛮、北狄の夷狄であるという考えである.
このため、「魏志倭人伝」に限らず、「三国志」の異国の風習の記述は、当時の中国と同じものである場合はあまり書かない.
また、同じであると書く時は、他の異国と同じであるとする.
たとえば、「倭地温暖にして、冬夏生菜を食す」の直前の「所有無与詹*耳朱崖同(有無する所、詹耳(たんじ)、朱崖(しゅがい)と同じ)」の「詹耳、朱崖」は、海南島の郡名である.
もちろん、海南島は中国の一部であるが、この両郡は前漢の時代に成立したものの反乱が多く、紀元前46年に放棄されており、その後、南朝の粱が7世紀頃に復活させている.
つまり、「三国志」の書かれた3世紀には、版図に含まれていなかったのである.
したがって、倭人は皆裸足であるという記述には、我々、中華の民は東夷と違ってきちんと靴を履くがという言葉が、省略されているということになる.
当時の倭人が、刺青を彫り、水中に潜って漁をしていたというのも同様である.
もっとも、刺青については、「夏后少康之子封於会稽断髪文身以避蛟龍之害(夏后少康の子、会稽(かいけい)に封ぜられしに断髪文身し、もって蛟龍の害を避く)」、
夏王少康の子が長江下流部の会稽に封ぜられた際、髪を切り、刺青をすることによって蛟の害を避けたがとあって、倭人も刺青をして「大魚水禽」の害を防ぐとはある.
そして、倭は会稽の東にあるとするのだが、風俗が同じであるとは書かない.
会稽が中国であるからである.
にもかかわらず、倭が同じ風習を持っていたことを記したのは、臥薪嘗胆の嘗胆の方の越王勾践で知られるこの王朝が、数百年前に滅んでいるからである.
そして、刺青が取り上げられたのは、秦代にこれが犯罪者に対する刑罰に使われるようになったからである.
「三国志」の側としては、倭が中国では刑罰として使用する刺青を喜んでしているのを蛮習として書きたいが、古代の中国にも同様の風習があったのがネックになる.
そこで、古代にはそうであったが、今もやっているのは、倭と海南島であるとしたのである.
詹*は人偏があるが、環境依存文字であるので詹で代用した.
2021.12/19
Up
Down
#354
倭人が皆裸足であるという記述は、中国と文化が違うと述べたいためのものである.
より正確に書けば、異国は野蛮であり、中国と同じなのは、我々の教化に従った結果であるということを言いたいがためである.
つまり、中華思想であり、周囲は東夷、西戎、南蛮、北狄の夷狄であるという考えである.
このため、「魏志倭人伝」に限らず、「三国志」の異国の風習の記述は、当時の中国と同じものである場合はあまり書かない.
また、同じであると書く時は、他の異国と同じであるとする.
たとえば、「倭地温暖にして、冬夏生菜を食す」の直前の「所有無与詹*耳朱崖同(有無する所、詹耳(たんじ)、朱崖(しゅがい)と同じ)」の「詹耳、朱崖」は、海南島の郡名である.
もちろん、海南島は中国の一部であるが、この両郡は前漢の時代に成立したものの反乱が多く、紀元前46年に放棄されており、その後、南朝の粱が7世紀頃に復活させている.
つまり、「三国志」の書かれた3世紀には、版図に含まれていなかったのである.
したがって、倭人は皆裸足であるという記述には、我々、中華の民は東夷と違ってきちんと靴を履くがという言葉が、省略されているということになる.
当時の倭人が、刺青を彫り、水中に潜って漁をしていたというのも同様である.
もっとも、刺青については、「夏后少康之子封於会稽断髪文身以避蛟龍之害(夏后少康の子、会稽(かいけい)に封ぜられしに断髪文身し、もって蛟龍の害を避く)」、
夏王少康の子が長江下流部の会稽に封ぜられた際、髪を切り、刺青をすることによって蛟の害を避けたがとあって、倭人も刺青をして「大魚水禽」の害を防ぐとはある.
そして、倭は会稽の東にあるとするのだが、風俗が同じであるとは書かない.
会稽が中国であるからである.
にもかかわらず、倭が同じ風習を持っていたことを記したのは、臥薪嘗胆の嘗胆の方の越王勾践で知られるこの王朝が、数百年前に滅んでいるからである.
そして、刺青が取り上げられたのは、秦代にこれが犯罪者に対する刑罰に使われるようになったからである.
「三国志」の側としては、倭が中国では刑罰として使用する刺青を喜んでしているのを蛮習として書きたいが、古代の中国にも同様の風習があったのがネックになる.
そこで、古代にはそうであったが、今もやっているのは、倭と海南島であるとしたのである.
詹*は人偏があるが、環境依存文字であるので詹で代用した.
2021.12/19
Up Down
#355
中国は、中華一番と崇め奉られるのなら、あとはどうでもよいというところがある.
面子が守られればよいのである.
このため、他国が献上してきたら、それに数倍する価値のものを返礼とすることにより、鷹揚さを示す.
朝貢である.
これに対して、中国側が求めたのは権威の承認であり、これがために中国の年号を使わせた.
したがって、「日出処天子致書日没処天子無恙(日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す.恙(つつが)無しや)」と、
東方の蛮国が自分達だけが使用できる「天子」という言葉を使う、対等の地位を求めるなどということはありえない話である.
それ以前に、倭は、与えられた国号を勝手に日本と改名する、独自の年号を使用すると、中華体制の異端児となっていたが、この当時は従順であった.
正始4(243)年、卑弥呼は北魏に衣服や布等の献上品を贈っているが、よいものがなかったのか、最初に載せられているのは生口(奴隷)である.
うい奴よと思ったかどうかは知らないが、このため、「倭人伝」の記述は丁寧であり、正確であるはずである.
たとえば、この刺青等も、今日的視点ではやにわに信じがたいかもしれない.
しかし、これは化粧だという説もあるが、日本の土偶には刺青が施されていると思われるものがある.
埴輪にも刺青と思われる線刻が施されたものがある.
また、水中に潜る日本の海女は有名である.
さらに、森鴎外とナウマンの「論争」が有名だが、戦後のかなりの遅くまで日本人は衣服をまとうのを好まなかったし、裸足で歩くのも奇異なことではなかった.
実際、「国技」とされる相撲をはじめとして、柔道、剣道、空手、薙刀等の武道はすべて裸足である.
しかしながら、「冬夏生菜を食す」とあるのは変である.
この時代、中国人は膾を食べていたからである.
つまり、生食は珍しくない.
これでは、倭は中国と同じで、差異はないということになってしまうので、書く必要性がなくなってしまう.
もし、「生菜」が生食を意味するのなら、同じであるのなら、書くはずがないし、東夷の証明にならない.
また、「生菜」が生野菜の意味ならば、当時の倭にあったものは中国にあっただろうし、もし、中国にないようなものであれば記述されるはずである.
したがって、倭でだけ食べられていた生野菜など存在しない.
#352から長々と書いてきたが、そもそも論として、生野菜説は成立しないのである.
しかし、生食説も上記の理由で成立しない.
ただし、「冬夏」を「冬でも夏でも」ではなく、「冬だけなく夏も」と解したらとどうだろうか.
というのは、韓国では、冷麺は冬場に、焼肉は夏場に食べるものだったからである.
2021.12/19
Up
Down
#355
中国は、中華一番と崇め奉られるのなら、あとはどうでもよいというところがある.
面子が守られればよいのである.
このため、他国が献上してきたら、それに数倍する価値のものを返礼とすることにより、鷹揚さを示す.
朝貢である.
これに対して、中国側が求めたのは権威の承認であり、これがために中国の年号を使わせた.
したがって、「日出処天子致書日没処天子無恙(日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す.恙(つつが)無しや)」と、
東方の蛮国が自分達だけが使用できる「天子」という言葉を使う、対等の地位を求めるなどということはありえない話である.
それ以前に、倭は、与えられた国号を勝手に日本と改名する、独自の年号を使用すると、中華体制の異端児となっていたが、この当時は従順であった.
正始4(243)年、卑弥呼は北魏に衣服や布等の献上品を贈っているが、よいものがなかったのか、最初に載せられているのは生口(奴隷)である.
うい奴よと思ったかどうかは知らないが、このため、「倭人伝」の記述は丁寧であり、正確であるはずである.
たとえば、この刺青等も、今日的視点ではやにわに信じがたいかもしれない.
しかし、これは化粧だという説もあるが、日本の土偶には刺青が施されていると思われるものがある.
埴輪にも刺青と思われる線刻が施されたものがある.
また、水中に潜る日本の海女は有名である.
さらに、森鴎外とナウマンの「論争」が有名だが、戦後のかなりの遅くまで日本人は衣服をまとうのを好まなかったし、裸足で歩くのも奇異なことではなかった.
実際、「国技」とされる相撲をはじめとして、柔道、剣道、空手、薙刀等の武道はすべて裸足である.
しかしながら、「冬夏生菜を食す」とあるのは変である.
この時代、中国人は膾を食べていたからである.
つまり、生食は珍しくない.
これでは、倭は中国と同じで、差異はないということになってしまうので、書く必要性がなくなってしまう.
もし、「生菜」が生食を意味するのなら、同じであるのなら、書くはずがないし、東夷の証明にならない.
また、「生菜」が生野菜の意味ならば、当時の倭にあったものは中国にあっただろうし、もし、中国にないようなものであれば記述されるはずである.
したがって、倭でだけ食べられていた生野菜など存在しない.
#352から長々と書いてきたが、そもそも論として、生野菜説は成立しないのである.
しかし、生食説も上記の理由で成立しない.
ただし、「冬夏」を「冬でも夏でも」ではなく、「冬だけなく夏も」と解したらとどうだろうか.
というのは、韓国では、冷麺は冬場に、焼肉は夏場に食べるものだったからである.
2021.12/19
Up Down
#356
中国人は体を冷やすことを嫌がり、夏でも温かい飲み物を飲む.
これは、日本では医食同源、中国では薬食同源というが、食事は薬であるという考え方が強いからである.
このため、中国人の好む飲食物は妙に漢方薬ぽいものが多いが、その根本にあるのは、旬のものを食べると体によいという考えである.
たとえば、春には芽を、夏に葉を、秋は実を、冬になったら根を食べるのがよいというものである.
そして、この流れの上にあるのが、夏は暑いので温かいものを飲食すべきである.
たしかに、夏場に冷たいものを飲むと気持ちはよいが、汗になるだけで、飲み過ぎで体調を壊す人も多い.
食欲不振にも陥りやすい.
しかし、温かい飲み物を摂ると、体温が上がり、外気温との差が少なくなって涼しくなるというのである.
本当かなと思うが、実際に試してみると、この方法は存外に効果がある.
冷たい飲み物より汗をかく量は少なくなるし、摂取する水分の量も減る.
日本で、水分の大量摂取を勧めるのは、大量に汗をかき、体内の水分が不足して熱中症になりやすいからである.
したがって、汗の量が減れば、水分も少なくてよいのは当然である.
また、中国人は冷たいご飯を食べない.
弁当を持ってくる場合でも、スティームの上で温めていたそうである.
しかも、この話を聞いたのは台湾人からである.
同様のことは、日本の学校でもやっていたようだが、台湾は暑い.
30年前の話だから、今だと電子レンジを使用するのかもしれないが、亜熱帯に属する台湾でも、暑いから、温かいものを食べようとなっているわけである.
したがって、中国では夏場に温かい物を摂取するのは当然のことと考えてよい.
もちろん、火鍋と呼ばれる中国の鍋料理は、夏のスタミナ料理である.
2021.12/21
Up
Down
#356
中国人は体を冷やすことを嫌がり、夏でも温かい飲み物を飲む.
これは、日本では医食同源、中国では薬食同源というが、食事は薬であるという考え方が強いからである.
このため、中国人の好む飲食物は妙に漢方薬ぽいものが多いが、その根本にあるのは、旬のものを食べると体によいという考えである.
たとえば、春には芽を、夏に葉を、秋は実を、冬になったら根を食べるのがよいというものである.
そして、この流れの上にあるのが、夏は暑いので温かいものを飲食すべきである.
たしかに、夏場に冷たいものを飲むと気持ちはよいが、汗になるだけで、飲み過ぎで体調を壊す人も多い.
食欲不振にも陥りやすい.
しかし、温かい飲み物を摂ると、体温が上がり、外気温との差が少なくなって涼しくなるというのである.
本当かなと思うが、実際に試してみると、この方法は存外に効果がある.
冷たい飲み物より汗をかく量は少なくなるし、摂取する水分の量も減る.
日本で、水分の大量摂取を勧めるのは、大量に汗をかき、体内の水分が不足して熱中症になりやすいからである.
したがって、汗の量が減れば、水分も少なくてよいのは当然である.
また、中国人は冷たいご飯を食べない.
弁当を持ってくる場合でも、スティームの上で温めていたそうである.
しかも、この話を聞いたのは台湾人からである.
同様のことは、日本の学校でもやっていたようだが、台湾は暑い.
30年前の話だから、今だと電子レンジを使用するのかもしれないが、亜熱帯に属する台湾でも、暑いから、温かいものを食べようとなっているわけである.
したがって、中国では夏場に温かい物を摂取するのは当然のことと考えてよい.
もちろん、火鍋と呼ばれる中国の鍋料理は、夏のスタミナ料理である.
2021.12/21
Up Down
#357
では、逆に、冬場は冷たいものを摂りなさいとなるはずだが、そちらは実践したことがないし、中国人の書いたものでも、冬場は温かいものをである.
それどころか、冷たいものの摂取を拒否する文化が中国にはある.
実際、中国でビールを注文すると、常温で出てくるそうだ.
もっとも、日本が冷やしすぎで、イギリス等の多くの国で常温のビールを飲んでいるというのも事実だが、ラガー・ビールでそれはないよとなりそうである.
実際、ドイツなども常温で飲むようだが、夏場は冷やすものらしい.
また、中国人に氷を入れた飲み物を出すと驚かれるそうだ.
もちろん、冷やし中華なる食べ物は日本発祥で、中華版Wikipediaには項目すらない.
ともかく、体を冷やすことは罪悪だと信じている感じさえあって、果物は体を冷やすからあまり食べないと、石田三成のようなことを言う人もいる.
これは、食品を温性、涼性、平性に分類しており、水分が多くて柔らかいものは涼性となっているからである.
もっとも、アイス・クリームは食べる.
ただし、老人は嫌がる
(もっとも、昨今の中国人は平気で冷たいものを飲食するらしい).
したがって、冷麺の存在は、中国人にとって信じがたいものであろうし、それを寒い冬に食べるというのはさらに信じがたい話であろう.
もっとも、現在の韓国で、冷麺の季節は夏であり、冬の食べ物とは思われていない.
ただ、冷麺の初出は、李氏朝鮮の洪錫謨という人が記した「東国歳時記」であるが、それが記載されているのは11月の項である.
もちろん、この11月は旧暦なので12月である.
そして、「関西之麺最良」、関西の麺が最もよいとあるが、この関西は今の平壌付近である.
というより、北側の地域料理であったらしく、朝鮮戦争時に南に脱出した人々が伝えるまで、全土で知られた料理ではなかったようである.
ところで、平壌の12月の平均気温は1~-7゚Cである.
したがって、冷やすには充分な気候であるが、冷麺も麺類であるので、製麺後に茹でる必要がある.
にもかかわらず、冷麺はそれを冷やして食べるのである.
氷点下の12月にである.
2021.12/23
Up
Down
#357
では、逆に、冬場は冷たいものを摂りなさいとなるはずだが、そちらは実践したことがないし、中国人の書いたものでも、冬場は温かいものをである.
それどころか、冷たいものの摂取を拒否する文化が中国にはある.
実際、中国でビールを注文すると、常温で出てくるそうだ.
もっとも、日本が冷やしすぎで、イギリス等の多くの国で常温のビールを飲んでいるというのも事実だが、ラガー・ビールでそれはないよとなりそうである.
実際、ドイツなども常温で飲むようだが、夏場は冷やすものらしい.
また、中国人に氷を入れた飲み物を出すと驚かれるそうだ.
もちろん、冷やし中華なる食べ物は日本発祥で、中華版Wikipediaには項目すらない.
ともかく、体を冷やすことは罪悪だと信じている感じさえあって、果物は体を冷やすからあまり食べないと、石田三成のようなことを言う人もいる.
これは、食品を温性、涼性、平性に分類しており、水分が多くて柔らかいものは涼性となっているからである.
もっとも、アイス・クリームは食べる.
ただし、老人は嫌がる
(もっとも、昨今の中国人は平気で冷たいものを飲食するらしい).
したがって、冷麺の存在は、中国人にとって信じがたいものであろうし、それを寒い冬に食べるというのはさらに信じがたい話であろう.
もっとも、現在の韓国で、冷麺の季節は夏であり、冬の食べ物とは思われていない.
ただ、冷麺の初出は、李氏朝鮮の洪錫謨という人が記した「東国歳時記」であるが、それが記載されているのは11月の項である.
もちろん、この11月は旧暦なので12月である.
そして、「関西之麺最良」、関西の麺が最もよいとあるが、この関西は今の平壌付近である.
というより、北側の地域料理であったらしく、朝鮮戦争時に南に脱出した人々が伝えるまで、全土で知られた料理ではなかったようである.
ところで、平壌の12月の平均気温は1~-7゚Cである.
したがって、冷やすには充分な気候であるが、冷麺も麺類であるので、製麺後に茹でる必要がある.
にもかかわらず、冷麺はそれを冷やして食べるのである.
氷点下の12月にである.
2021.12/23
Up Down
#358
「東国歳時記」の冷麺の記述は「用蕎麦麺沮*沈菁沮菘沮和猪肉名曰冷麺」、蕎麦に大根と白菜のキムチを乗せ、豚肉を和えたものを冷麺というだけの短いものである.
その後、「又和雑菜梨栗牛猪切肉油醤於麺名曰骨董麺」と、雑菜と梨、栗、牛、豚肉を油醤で和えた麺を骨董麺というとあるが、これも冷麺の一種である.
その後、関西の麺が最もよいで終わりである.
つまり、旧暦11月にそのようなものをなぜ食べるのかという説明は一切ない.
したがって、想像するしかないのだが、幸い、同書の6月の項に「三伏」と題する文章がある.
三伏とは、夏至以降の3回の庚(かのえ)の日で、一年を通じてもっとも暑いとされる.
そして、この日、韓国では暑気払いを行う.
日本の暑気払いは、土用の丑の日に鰻をとなるが、「東国歳時記」には「烹狗和葱爛蒸名曰狗醤」、狗肉を葱と煮た狗醤と称するとあり、これを食べるとなっている.
ただし、作者は鶏を使う方がよいとするが、前者は補身湯(ポシンタン)、後者は参鶏湯(サムゲタン)と呼ばれる現在の韓国で食べられている暑気払いの料理である.
そして、湯(スープ)の字が示すように、鍋料理であり、温かい料理である.
つまり、暑い時に温かいものをという中国の薬食同源の考えに基づくものであるが、
夏至の反対が冬至であり、冬至を含む11月に冷麺の記載があるということは、逆の考えもあったということである.
旧暦11月は、子月(しげつ、ねづき)と呼ばれる.
子は十二支の最初であるので、正月に配当されそうだが、冬至を過ぎると、一日ごとに昼間の時間が長くなる上に、かつては正月だったといわれるので、この名がある.
いわゆる一陽来復であるが、別の言い方をすれば、一年で最も暗い月である.
陰陽の考えでいえば、陰気の極まる月である.
そして、陰気の極まるとは、一年で最も寒いということである.
そこに冷麺が配されるということは、寒い時に冷たいものを摂るという考えがあったということである.
ただし、現在の中国にはそのような考えはないので、古代にそのように考えられていたが、早くに消滅し、冬至の冷麺はその名残であると考えられることも可能である.
そして、3世紀、「三国志」の書かれた時代にもこの考えがあったとしたら、中国の辺境部や外周に膾(なます)が残ったように、韓国に冷麺が残ったということなる.
しかしながら、「東国歳時記」は1849年、つまり、19世紀中葉という、つい最近に書かれたものである.
したがって、これだけで決めつけるわけにはいかない.
*沮は草冠がある
2021.12/27
Up
Down
#358
「東国歳時記」の冷麺の記述は「用蕎麦麺沮*沈菁沮菘沮和猪肉名曰冷麺」、蕎麦に大根と白菜のキムチを乗せ、豚肉を和えたものを冷麺というだけの短いものである.
その後、「又和雑菜梨栗牛猪切肉油醤於麺名曰骨董麺」と、雑菜と梨、栗、牛、豚肉を油醤で和えた麺を骨董麺というとあるが、これも冷麺の一種である.
その後、関西の麺が最もよいで終わりである.
つまり、旧暦11月にそのようなものをなぜ食べるのかという説明は一切ない.
したがって、想像するしかないのだが、幸い、同書の6月の項に「三伏」と題する文章がある.
三伏とは、夏至以降の3回の庚(かのえ)の日で、一年を通じてもっとも暑いとされる.
そして、この日、韓国では暑気払いを行う.
日本の暑気払いは、土用の丑の日に鰻をとなるが、「東国歳時記」には「烹狗和葱爛蒸名曰狗醤」、狗肉を葱と煮た狗醤と称するとあり、これを食べるとなっている.
ただし、作者は鶏を使う方がよいとするが、前者は補身湯(ポシンタン)、後者は参鶏湯(サムゲタン)と呼ばれる現在の韓国で食べられている暑気払いの料理である.
そして、湯(スープ)の字が示すように、鍋料理であり、温かい料理である.
つまり、暑い時に温かいものをという中国の薬食同源の考えに基づくものであるが、
夏至の反対が冬至であり、冬至を含む11月に冷麺の記載があるということは、逆の考えもあったということである.
旧暦11月は、子月(しげつ、ねづき)と呼ばれる.
子は十二支の最初であるので、正月に配当されそうだが、冬至を過ぎると、一日ごとに昼間の時間が長くなる上に、かつては正月だったといわれるので、この名がある.
いわゆる一陽来復であるが、別の言い方をすれば、一年で最も暗い月である.
陰陽の考えでいえば、陰気の極まる月である.
そして、陰気の極まるとは、一年で最も寒いということである.
そこに冷麺が配されるということは、寒い時に冷たいものを摂るという考えがあったということである.
ただし、現在の中国にはそのような考えはないので、古代にそのように考えられていたが、早くに消滅し、冬至の冷麺はその名残であると考えられることも可能である.
そして、3世紀、「三国志」の書かれた時代にもこの考えがあったとしたら、中国の辺境部や外周に膾(なます)が残ったように、韓国に冷麺が残ったということなる.
しかしながら、「東国歳時記」は1849年、つまり、19世紀中葉という、つい最近に書かれたものである.
したがって、これだけで決めつけるわけにはいかない.
*沮は草冠がある
2021.12/27
Up Down
#359
「東国歳時記」に寒食という項がある.
この寒食は、寒食節のことで、冬至から105日目を指す.
冬至は12月21日か22日なので105日目は4月初めということになる.
現在の中国では、清明節と呼ばれ、郊外の墓に出かけて掃除をする習慣になっている.
韓国でも墓参の日となっているが、本来の清明節は寒食節の翌日であったという.
そして、寒食節は、その名の通り、火を使わず、冷めた料理を食べるというものである.
その期間は、文献によって異なるが、3日間から1ヶ月間となっている.
また、「周礼」に「中春以木鐸修火禁于国中(中春に木鐸を以って火を修め国中に禁ず)とあり、火を更新するために一斉に火を消すとあるのが起源だという説がある.
中春(仲春)は旧暦2月なので、今の3月である.
それが正しいとすれば、春とはいえ、まだ寒いうちに冷たいものを食べていたことになる.
これが廃れたのは、曹操が老人や子どもには負担が大きいとして禁じたからである.
しかし、遣唐使として唐に渡った円仁の「入唐求法巡礼行記」の開成4、5(839-40)両年の2月の記録に、世間は煙を出さずにして寒食を摂るとある.
したがって、3世紀に禁止されたが、唐代には普通に行われていたことになる.
その後、明代には廃れ、時期のよく似た清明節と混同されていったようである.
したがって、新しい火に切り替えるからという理由であるが、冬季に冷たいものを食べるということになる.
もっとも、寒い華北で、そのようなことするというのは、暑い時節に熱いものを摂るのとは違って、体によいとはとても思えない.
しかし、禁令にもかかわらず、寒食節は明代まで続いたのである.
その上、寒食節の名は、現在でもベトナムに残っており、この日、ベトナムでは火を使うのを忌み、前日に用意した冷たいものを食べる.
また、「東国歳時記」には記載はなく、現在では薄れているようだが、韓国でも前日に用意したナムルという料理や、寒食麺と呼ばれる蕎麦を食べていた.
そして、#356に書いたように、冷たいものを好まない台湾人が、清明節には潤餅と呼ばれる揚げてない生の春巻を食べるのである.
2021.12/30
Up
Down
#359
「東国歳時記」に寒食という項がある.
この寒食は、寒食節のことで、冬至から105日目を指す.
冬至は12月21日か22日なので105日目は4月初めということになる.
現在の中国では、清明節と呼ばれ、郊外の墓に出かけて掃除をする習慣になっている.
韓国でも墓参の日となっているが、本来の清明節は寒食節の翌日であったという.
そして、寒食節は、その名の通り、火を使わず、冷めた料理を食べるというものである.
その期間は、文献によって異なるが、3日間から1ヶ月間となっている.
また、「周礼」に「中春以木鐸修火禁于国中(中春に木鐸を以って火を修め国中に禁ず)とあり、火を更新するために一斉に火を消すとあるのが起源だという説がある.
中春(仲春)は旧暦2月なので、今の3月である.
それが正しいとすれば、春とはいえ、まだ寒いうちに冷たいものを食べていたことになる.
これが廃れたのは、曹操が老人や子どもには負担が大きいとして禁じたからである.
しかし、遣唐使として唐に渡った円仁の「入唐求法巡礼行記」の開成4、5(839-40)両年の2月の記録に、世間は煙を出さずにして寒食を摂るとある.
したがって、3世紀に禁止されたが、唐代には普通に行われていたことになる.
その後、明代には廃れ、時期のよく似た清明節と混同されていったようである.
したがって、新しい火に切り替えるからという理由であるが、冬季に冷たいものを食べるということになる.
もっとも、寒い華北で、そのようなことするというのは、暑い時節に熱いものを摂るのとは違って、体によいとはとても思えない.
しかし、禁令にもかかわらず、寒食節は明代まで続いたのである.
その上、寒食節の名は、現在でもベトナムに残っており、この日、ベトナムでは火を使うのを忌み、前日に用意した冷たいものを食べる.
また、「東国歳時記」には記載はなく、現在では薄れているようだが、韓国でも前日に用意したナムルという料理や、寒食麺と呼ばれる蕎麦を食べていた.
そして、#356に書いたように、冷たいものを好まない台湾人が、清明節には潤餅と呼ばれる揚げてない生の春巻を食べるのである.
2021.12/30
Up Down
#360
膾は生ものであるから、温めることはない.
冷たいままである.
そして、冷たい料理であるということは、寒い時期に食べるべきものとなる.
ただ、そうなると、曹操が寒食の禁止を行ったのはどうなるのだということになる.
曹操は、他ならぬ三国時代の魏の基礎を作った王だからである.
ただ、この禁令が載っているのは、魏より後の隋代の「玉燭宝典」である.
つまり、この禁令が実際に出されたかどうかは分からない.
したがって、「魏志倭人伝」の「倭地温暖にして、冬夏生菜を食す」は、にもかかわらず、倭人は暑い夏場でも生ものを食べるでよい.
これならば、「生菜」を生野菜と解するより意味が通じる.
倭人は、食べる時期も知らない野蛮人であるというのである.
そして、「三国志」全文で「冬夏」を使用しているのは、ここだけである.
つまり、冬だけでなく、夏にも食べられているという指摘が必要だったのである.
もっとも、「冬夏生菜を食す」の前に「倭地温暖」の語が入るのはなぜかという疑問は残る.
「生菜」を生野菜と考えたとしても、倭は温暖だから冬でも生野菜を食べられるという理由はつくからである.
その上、#354に示したように、倭は海南島と風俗が同じであると書かれている.
しかし、この島は沖縄、台湾のはるか南方、香港より南のベトナム北部とフィリピン、ルソン島との間に位置する.
つまり、熱帯である.
もし、倭が海南島と同じような熱帯だと考えられていたのなら、さらに生野菜の範囲が広がる.
たとえば、バナナやマンゴーのような果樹も野菜と考えるのなら、生野菜とすることは可能だからである.
しかし、3世紀の日本の気候は今より冷涼であったとされる.
したがって、海南島のように暑くはなかっただろうし、似ているというのが「その地に牛馬虎豹羊鵲なし」までを含むのなら、おかしなことになる.
この島には、すでに絶滅したが、高砂豹とも高砂虎とも称された雲豹(ウンピョウ)が生息していたからである.
したがって、「倭人伝」の記述は正確なものばかりではないということになるのだが、
当時、中国でない土地で、一番、倭に近い風俗を持っていたのが海南島であったのであろう.
もちろん、倭が会稽の東にあると書いているぐらいだから、海南島がはるか南方にあるということぐらいは承知していた.
しかし、「三国志」の異国の見方は蛮族であり、中華は素晴らしいなので、そちらが優先された結果、地理的な問題は無視されたのである.
つまり、「冬夏生菜を食す」の前に「倭地温暖」という文言が挟まっているのは、倭の地は温暖なのに、冬だけなく、夏も生食するという意味なのである.
それでは、皆様、よいお年を.
2021.12/31
Up
Down
#360
膾は生ものであるから、温めることはない.
冷たいままである.
そして、冷たい料理であるということは、寒い時期に食べるべきものとなる.
ただ、そうなると、曹操が寒食の禁止を行ったのはどうなるのだということになる.
曹操は、他ならぬ三国時代の魏の基礎を作った王だからである.
ただ、この禁令が載っているのは、魏より後の隋代の「玉燭宝典」である.
つまり、この禁令が実際に出されたかどうかは分からない.
したがって、「魏志倭人伝」の「倭地温暖にして、冬夏生菜を食す」は、にもかかわらず、倭人は暑い夏場でも生ものを食べるでよい.
これならば、「生菜」を生野菜と解するより意味が通じる.
倭人は、食べる時期も知らない野蛮人であるというのである.
そして、「三国志」全文で「冬夏」を使用しているのは、ここだけである.
つまり、冬だけでなく、夏にも食べられているという指摘が必要だったのである.
もっとも、「冬夏生菜を食す」の前に「倭地温暖」の語が入るのはなぜかという疑問は残る.
「生菜」を生野菜と考えたとしても、倭は温暖だから冬でも生野菜を食べられるという理由はつくからである.
その上、#354に示したように、倭は海南島と風俗が同じであると書かれている.
しかし、この島は沖縄、台湾のはるか南方、香港より南のベトナム北部とフィリピン、ルソン島との間に位置する.
つまり、熱帯である.
もし、倭が海南島と同じような熱帯だと考えられていたのなら、さらに生野菜の範囲が広がる.
たとえば、バナナやマンゴーのような果樹も野菜と考えるのなら、生野菜とすることは可能だからである.
しかし、3世紀の日本の気候は今より冷涼であったとされる.
したがって、海南島のように暑くはなかっただろうし、似ているというのが「その地に牛馬虎豹羊鵲なし」までを含むのなら、おかしなことになる.
この島には、すでに絶滅したが、高砂豹とも高砂虎とも称された雲豹(ウンピョウ)が生息していたからである.
したがって、「倭人伝」の記述は正確なものばかりではないということになるのだが、
当時、中国でない土地で、一番、倭に近い風俗を持っていたのが海南島であったのであろう.
もちろん、倭が会稽の東にあると書いているぐらいだから、海南島がはるか南方にあるということぐらいは承知していた.
しかし、「三国志」の異国の見方は蛮族であり、中華は素晴らしいなので、そちらが優先された結果、地理的な問題は無視されたのである.
つまり、「冬夏生菜を食す」の前に「倭地温暖」という文言が挟まっているのは、倭の地は温暖なのに、冬だけなく、夏も生食するという意味なのである.
それでは、皆様、よいお年を.
2021.12/31
Up Down
#361
明けましておめでとうございます.
本年もよろしくお願いいたします.
ところで、この日本で、寒季に冷たいまま食べていたものがある.
他ならぬ正月のおせち料理である.
一応、正月ぐらい、料理する人が休めるようにという理由はついているが、作る側としては、どれほどの手間がかかるか分かっているのとなるだろう.
それよりも、寒い時期に冷たい料理をという古代中国の考えが残っているのではと考えたほうが筋が通ると思うのは、当方だけだろうか.
いやいや、江戸時代におせち料理などはなくて、関西で蓬莱、関東で食積(くいつみ)と呼ばれたものがもとだとか言う人も出そうである.
三方に白米を敷いたところに松竹梅を植え、そこへ伊勢海老やら鮑やらめでたそうなものを飾ったものである.
当初は食べていたが、段々と飾り物になっていき、明治頃には廃れたが、鏡餅はその後身だという.
関西で、正月3ヶ日の間、箸をつけないという睨み鯛もそうかもしれない.
おせちと呼ばれたのは、そういう飾り物を見ながら食べた煮しめのことである.
1836年に出た「日用惣菜俎(にちようそうざいまないた)」には、年始重詰として「初重かずのこ二重ごまあへたたき牛蒡(ごぼう)三重鮒昆布巻四重黒煮豆またはてりごまめ」とある.
最後の「てりごまめ」は、炒った片口鰯の稚魚を飴煮にしたもので、今の「たづくり」である.
数の子を除くと妙に黒っぽいものが多いが、黒や魚は、江戸時代に流行した五行では、冬の象徴.
年末の煤払いもそうだが、黒いものを除去したり、食べたりして冬を捨て去り、春を迎えるのである.
その上、庶民でも作れる.
汁がこぼれる場合もあるので、当初は大きな丼に入れていたが、幕末から明治期に重箱に入れるようになった.
おせちという名称が広まったのは戦後だそうである.
つまり、おせちもそれほど長い歴史を持っているわけではない.
したがって、古代中国のなどという話にならないよう思うが、おせちという言葉は、御節供(おせちく)に由来する.
そして、御節供は、節日(せちにち)の供御(くご)の意味で、
節日は1/7の人日(じんじつ)、3/3の上巳(じょうし)、5/5の端午、7/7の七夕、9/9の重陽の五節供(節句)、供御は貴人の食事である.
つまり、節供の祝いの膳である.
もともとは宮中のものであるから、これを入れると平安以前に遡れるのである.
2022.1/1
Down
#361
明けましておめでとうございます.
本年もよろしくお願いいたします.
ところで、この日本で、寒季に冷たいまま食べていたものがある.
他ならぬ正月のおせち料理である.
一応、正月ぐらい、料理する人が休めるようにという理由はついているが、作る側としては、どれほどの手間がかかるか分かっているのとなるだろう.
それよりも、寒い時期に冷たい料理をという古代中国の考えが残っているのではと考えたほうが筋が通ると思うのは、当方だけだろうか.
いやいや、江戸時代におせち料理などはなくて、関西で蓬莱、関東で食積(くいつみ)と呼ばれたものがもとだとか言う人も出そうである.
三方に白米を敷いたところに松竹梅を植え、そこへ伊勢海老やら鮑やらめでたそうなものを飾ったものである.
当初は食べていたが、段々と飾り物になっていき、明治頃には廃れたが、鏡餅はその後身だという.
関西で、正月3ヶ日の間、箸をつけないという睨み鯛もそうかもしれない.
おせちと呼ばれたのは、そういう飾り物を見ながら食べた煮しめのことである.
1836年に出た「日用惣菜俎(にちようそうざいまないた)」には、年始重詰として「初重かずのこ二重ごまあへたたき牛蒡(ごぼう)三重鮒昆布巻四重黒煮豆またはてりごまめ」とある.
最後の「てりごまめ」は、炒った片口鰯の稚魚を飴煮にしたもので、今の「たづくり」である.
数の子を除くと妙に黒っぽいものが多いが、黒や魚は、江戸時代に流行した五行では、冬の象徴.
年末の煤払いもそうだが、黒いものを除去したり、食べたりして冬を捨て去り、春を迎えるのである.
その上、庶民でも作れる.
汁がこぼれる場合もあるので、当初は大きな丼に入れていたが、幕末から明治期に重箱に入れるようになった.
おせちという名称が広まったのは戦後だそうである.
つまり、おせちもそれほど長い歴史を持っているわけではない.
したがって、古代中国のなどという話にならないよう思うが、おせちという言葉は、御節供(おせちく)に由来する.
そして、御節供は、節日(せちにち)の供御(くご)の意味で、
節日は1/7の人日(じんじつ)、3/3の上巳(じょうし)、5/5の端午、7/7の七夕、9/9の重陽の五節供(節句)、供御は貴人の食事である.
つまり、節供の祝いの膳である.
もともとは宮中のものであるから、これを入れると平安以前に遡れるのである.
2022.1/1
PREVIOUS ☆ NEXT
Since 30 Oct.
2021.
Last up-dated,
1 Jan. 2022.


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
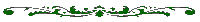 Sasayaki010.
Sasayaki010.
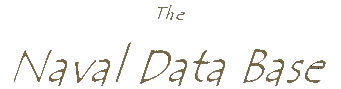 Ver.1.22a.
Ver.1.22a.
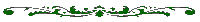 Copyright
(c)
hush ,2001-22. Allrights Reserved.
Copyright
(c)
hush ,2001-22. Allrights Reserved.
Up
動画