Down
無用録
1-
51- 101-
150- 191-
229- 255-
293- 311-
333- 361-
383-
trivia's
trivia
Up
Down
#361
明けましておめでとうございます.
本年もよろしくお願いいたします.
ところで、この日本で、寒季に冷たいまま食べていたものがある.
他ならぬ正月のおせち料理である.
一応、正月ぐらい、料理する人が休めるようにという理由はついているが、作る側としては、どれほどの手間がかかるか分かっているのとなるだろう.
それよりも、寒い時期に冷たい料理をという古代中国の考えが残っているのではと考えたほうが筋が通ると思うのは、当方だけだろうか.
いやいや、江戸時代におせち料理などはなくて、関西で蓬莱、関東で食積(くいつみ)と呼ばれたものがもとだとか言う人も出そうである.
三方に白米を敷いたところに松竹梅を植え、そこへ伊勢海老やら鮑やらめでたそうなものを飾ったものである.
当初は食べていたが、段々と飾り物になっていき、明治頃には廃れたが、鏡餅はその後身だという.
関西で、正月3ヶ日の間、箸をつけないという睨み鯛もそうかもしれない.
おせちと呼ばれたのは、そういう飾り物を見ながら食べた煮しめのことである.
1836年に出た「日用惣菜俎(にちようそうざいまないた)」には、年始重詰として「初重かずのこ二重ごまあへたたき牛蒡(ごぼう)三重鮒昆布巻四重黒煮豆またはてりごまめ」とある.
最後の「てりごまめ」は、炒った片口鰯の稚魚を飴煮にしたもので、今の「たづくり」である.
数の子を除くと妙に黒っぽいものが多いが、黒や魚は、江戸時代に流行した五行では、冬の象徴.
年末の煤払いもそうだが、黒いものを除去したり、食べたりして冬を捨て去り、春を迎えるのである.
その上、庶民でも作れる.
汁がこぼれる場合もあるので、当初は大きな丼に入れていたが、幕末から明治期に重箱に入れるようになった.
おせちという名称が広まったのは戦後だそうである.
つまり、おせちもそれほど長い歴史を持っているわけではない.
したがって、古代中国のなどという話にならないよう思うが、おせちという言葉は、御節供(おせちく)に由来する.
そして、御節供は、節日(せちにち)の供御(くご)の意味で、
節日は1/7の人日(じんじつ)、3/3の上巳(じょうし)、5/5の端午、7/7の七夕、9/9の重陽の五節供(節句)、供御は貴人の食事である.
つまり、節供の祝いの膳である.
もともとは宮中のものであるから、これを入れると平安以前に遡れるのである.
2022.1/1
Up Down
#362
意外なことに、この五節供の中に正月が含まれていない.
では、江戸時代、正月はどうしていたかというと、ちゃんとある.
ただ、初詣は明治以降に出てきたものなので、初日の出を見に出る人はいても、基本は寝正月である.
掃除をしてもいかんというのだから、安息日である.
もっとも、子供は遊びで忙しい.
これは、若いが、五行では木気である春に含まれるからで、子供が遊ぶのは春迎えの行事になるからである.
したがって、江戸時代にはそれなりの労働力であった子供が一日中遊んでいても、誰も怒らない.
それどころか、お年玉までもらう.
戦後のように金を貰うということはないが、歳神に祭られていた餅が下げ渡される.
特別扱いである.
しかし、木気を上げる一方だけではいけない.
冬の象徴である水気を殺すため、前回、黒っぽいものや魚を食べると書いたが、一つだけ色の違うものがある.
数の子である.
色は黄色.
五行では土気に配当される.
中国、特に華北は、黄河の運ぶ土砂で黄色く染まっているためであろう.
季節は土用である.
土用というのは、季節と季節の間に置かれるもので、春夏秋冬それぞれの間に置かれる.
一番有名なのは春から夏の土用で、酷暑の頃ですので水気を取りましょうとなる.
しかし、ここで水分補給なんてやっても江戸っ子には受けないので、黒いものを摂ろうとなる.
丑の日だから、今だったら黒毛和牛の肉となるのだろうが、江戸時代にはそうもいかず、牛と同じ「う」で始まる鰻で代用した.
魚であり、黒いからでもある.
そして、細長いというのは木気の特質である.
木気を葬り去って、順調に夏が来るようにするには、よい呪物となる.
かくして、鰻の受難日が定められたわけだが、同様に土気の黄色も食べようというのが数の子の意味である.
ただ、数の子は鰊の卵なので、丸い.
これを金色の球とみると、土気ではなく、金気となる.
そして、金気は木気の最大の敵である.
木を切り倒すのは金属の斧だからである.
ところで、土用というのは土気であるので、金気を生むとされた.
金属は土中に産するからである.
このため、江戸時代の人々は、羽根衝きをした.
金気というと、形は球形、方角は西であり、西は酉である.
したがって、羽根衝きとは、球形で羽根のついたものを、木製の板で叩いていると考えると、木気で金気を痛めつける構図となるのである.
しかし、羽根衝きの球が黒いではないかと言われそうだが、黒に象徴される水気である冬を同時に追い払おうとするのである.
一方、凧揚げは、木気の象徴である細長いものである.
羽根衝きも凧揚げも正月限定の遊びであるというのは、このためなのである.
2022.1/4
Up
Down
#362
意外なことに、この五節供の中に正月が含まれていない.
では、江戸時代、正月はどうしていたかというと、ちゃんとある.
ただ、初詣は明治以降に出てきたものなので、初日の出を見に出る人はいても、基本は寝正月である.
掃除をしてもいかんというのだから、安息日である.
もっとも、子供は遊びで忙しい.
これは、若いが、五行では木気である春に含まれるからで、子供が遊ぶのは春迎えの行事になるからである.
したがって、江戸時代にはそれなりの労働力であった子供が一日中遊んでいても、誰も怒らない.
それどころか、お年玉までもらう.
戦後のように金を貰うということはないが、歳神に祭られていた餅が下げ渡される.
特別扱いである.
しかし、木気を上げる一方だけではいけない.
冬の象徴である水気を殺すため、前回、黒っぽいものや魚を食べると書いたが、一つだけ色の違うものがある.
数の子である.
色は黄色.
五行では土気に配当される.
中国、特に華北は、黄河の運ぶ土砂で黄色く染まっているためであろう.
季節は土用である.
土用というのは、季節と季節の間に置かれるもので、春夏秋冬それぞれの間に置かれる.
一番有名なのは春から夏の土用で、酷暑の頃ですので水気を取りましょうとなる.
しかし、ここで水分補給なんてやっても江戸っ子には受けないので、黒いものを摂ろうとなる.
丑の日だから、今だったら黒毛和牛の肉となるのだろうが、江戸時代にはそうもいかず、牛と同じ「う」で始まる鰻で代用した.
魚であり、黒いからでもある.
そして、細長いというのは木気の特質である.
木気を葬り去って、順調に夏が来るようにするには、よい呪物となる.
かくして、鰻の受難日が定められたわけだが、同様に土気の黄色も食べようというのが数の子の意味である.
ただ、数の子は鰊の卵なので、丸い.
これを金色の球とみると、土気ではなく、金気となる.
そして、金気は木気の最大の敵である.
木を切り倒すのは金属の斧だからである.
ところで、土用というのは土気であるので、金気を生むとされた.
金属は土中に産するからである.
このため、江戸時代の人々は、羽根衝きをした.
金気というと、形は球形、方角は西であり、西は酉である.
したがって、羽根衝きとは、球形で羽根のついたものを、木製の板で叩いていると考えると、木気で金気を痛めつける構図となるのである.
しかし、羽根衝きの球が黒いではないかと言われそうだが、黒に象徴される水気である冬を同時に追い払おうとするのである.
一方、凧揚げは、木気の象徴である細長いものである.
羽根衝きも凧揚げも正月限定の遊びであるというのは、このためなのである.
2022.1/4
Up Down
#363
明治6(1873)年1月4日太政官第1号布告で、五節句は廃止されている.
もともとは宮中の行事であったが、幕府が定めたものであったからである.
したがって、五節句に由来する御節供は由来を失ったことになる.
ちなみに、布告第2号は1月7日に出ており、その中で12/29-1/3までを休日とする規定が定められている.
もっとも、これは官吏対象であり、現行の「行政機関の休日に関する法律」も、法律名で明らかなように、行政機関に関するものであり、公務員対象である.
しかしながら、戦前、四方拝(元旦)、紀元節(>廃止>建国記念日)、天長節(>明治節>天皇誕生日>みどりの日>昭和の日)、
明治節(明治期は天長節>廃止>文化の日)には学校に児童が集められ、式典で餅が配られているので、教職員については例外規定があったのかもしれない.
そして、同年10月14日太政官第344号布告「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」で
1/3元始祭1/5新年宴会(>廃止)1/30孝明天皇祭(>廃止)2/11紀元節4/3神武天皇祭(>廃止)9/17神嘗祭(>廃止)11/3天長節11/23新嘗祭(>勤労感謝の日)の8祝日が定められた.
ただし、五節句、祝日規定双方ともに定められなかったせいか、正月は生き残った.
つまり、御節供は正月料理に集約され、おせち料理になったのである.
では、御節供がは冷たい料理だったのかというと、実は分からない.
一応、「平安時代の貴族の宴会料理である大饗は、冷たい料理が多かった」と書かれたサイトは見つけたが、その根拠が何か分からない.
ただし、平安時代の御節供は高盛りした御飯だとあるのは、現在でも幾つかの神事でそのような形で供されており、
かつては産飯、婚礼の高盛飯、葬儀の枕飯がこの形状であったので、多分、そうであったのだろう.
また、仏壇に供える御飯が炊きたてのものに限るのに対して、神棚の場合はそうではなく、
米であってもよいことを考えると、御節供の高盛り飯も冷めたものだったのかもしれない.
米は当時の貴重品であり、高く盛るというのは最上級の贅沢だったのである.
2022.1/5
Up
Down
#363
明治6(1873)年1月4日太政官第1号布告で、五節句は廃止されている.
もともとは宮中の行事であったが、幕府が定めたものであったからである.
したがって、五節句に由来する御節供は由来を失ったことになる.
ちなみに、布告第2号は1月7日に出ており、その中で12/29-1/3までを休日とする規定が定められている.
もっとも、これは官吏対象であり、現行の「行政機関の休日に関する法律」も、法律名で明らかなように、行政機関に関するものであり、公務員対象である.
しかしながら、戦前、四方拝(元旦)、紀元節(>廃止>建国記念日)、天長節(>明治節>天皇誕生日>みどりの日>昭和の日)、
明治節(明治期は天長節>廃止>文化の日)には学校に児童が集められ、式典で餅が配られているので、教職員については例外規定があったのかもしれない.
そして、同年10月14日太政官第344号布告「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」で
1/3元始祭1/5新年宴会(>廃止)1/30孝明天皇祭(>廃止)2/11紀元節4/3神武天皇祭(>廃止)9/17神嘗祭(>廃止)11/3天長節11/23新嘗祭(>勤労感謝の日)の8祝日が定められた.
ただし、五節句、祝日規定双方ともに定められなかったせいか、正月は生き残った.
つまり、御節供は正月料理に集約され、おせち料理になったのである.
では、御節供がは冷たい料理だったのかというと、実は分からない.
一応、「平安時代の貴族の宴会料理である大饗は、冷たい料理が多かった」と書かれたサイトは見つけたが、その根拠が何か分からない.
ただし、平安時代の御節供は高盛りした御飯だとあるのは、現在でも幾つかの神事でそのような形で供されており、
かつては産飯、婚礼の高盛飯、葬儀の枕飯がこの形状であったので、多分、そうであったのだろう.
また、仏壇に供える御飯が炊きたてのものに限るのに対して、神棚の場合はそうではなく、
米であってもよいことを考えると、御節供の高盛り飯も冷めたものだったのかもしれない.
米は当時の貴重品であり、高く盛るというのは最上級の贅沢だったのである.
2022.1/5
Up Down
#364
おせち料理が冷たいまま供されるのは、火の神に休んでもらうためであると書いたものがある.
これについては、新春正月は木気であるので、木を燃やす火気を禁じた結果と考えることもできる.
実際、#362で幾つか書いた迎春行事の中でも、火気に関するものはない.
ただ、それだと釈然としないことがある.
近年のものは別として、おせち料理の中身はさほど地域差はないのに、雑煮の場合は非常に大きい.
丸餅か角餅かについては、角餅が江戸で発生したものだからであり、東と西で截然と分かれる.
しかし、焼くのかそのまま煮るのか、仕立てはすましか味噌か、味噌なら赤か白か合わせか、
具には何を入れるのかとかいうような細かな点については、地域差が非常に大きい.
中には、香川のように白味噌に餡餅とか、徳川将軍家のように兎の肉を入れる場合もあるし、餅の代わりに芋や蕎麦を使うところも多い.
うち、餅を入れない理由としては、その分布が近畿地方周縁部から同心円状に広がっているので、古い風俗であったということになる.
米が採れない山間部や寒冷部だったということもあるだろうが、非稲作文化が継承された結果であろう.
雑煮自体は、室町時代の文献に現れるが、一般庶民が食べるようになったのは江戸時代であろうといわれる.
このため、江戸時代後期に作られるようになったおせち料理に競べると変化が激しいのも当然なのだが、にもかかわらず、各地の雑煮に共通する点がある.
冷たい雑煮は食べないということである.
つまり、火の神に休んでもらうのならば、同じく正月料理である雑煮も冷たいはずである.
しかしながら、近年、冷やし雑煮なるものが登場しているものの、管見の限りではそのような例はないのである.
このため、火の神ではなく、竈の神を休ませるためであり、囲炉裏で餅を焼き、七輪で雑煮を作ったというような書き方をしているところもあるが、これは苦しい.
もちろん、冷たい餅など食べられるわけがないから、仕方なく火を使うのだという考え方もできるのだが、餅を入れない雑煮でも温めて食べている.
つまり、火の神に休んでもらうというのは後付けであり、豆はマメになるように、豊作になるように田作りなどというのと同じく、語呂合わせやこじつけの類いである.
したがって、冷たいおせちについては、別の理由を考える必要がある.
2022.1/7
Up
Down
#364
おせち料理が冷たいまま供されるのは、火の神に休んでもらうためであると書いたものがある.
これについては、新春正月は木気であるので、木を燃やす火気を禁じた結果と考えることもできる.
実際、#362で幾つか書いた迎春行事の中でも、火気に関するものはない.
ただ、それだと釈然としないことがある.
近年のものは別として、おせち料理の中身はさほど地域差はないのに、雑煮の場合は非常に大きい.
丸餅か角餅かについては、角餅が江戸で発生したものだからであり、東と西で截然と分かれる.
しかし、焼くのかそのまま煮るのか、仕立てはすましか味噌か、味噌なら赤か白か合わせか、
具には何を入れるのかとかいうような細かな点については、地域差が非常に大きい.
中には、香川のように白味噌に餡餅とか、徳川将軍家のように兎の肉を入れる場合もあるし、餅の代わりに芋や蕎麦を使うところも多い.
うち、餅を入れない理由としては、その分布が近畿地方周縁部から同心円状に広がっているので、古い風俗であったということになる.
米が採れない山間部や寒冷部だったということもあるだろうが、非稲作文化が継承された結果であろう.
雑煮自体は、室町時代の文献に現れるが、一般庶民が食べるようになったのは江戸時代であろうといわれる.
このため、江戸時代後期に作られるようになったおせち料理に競べると変化が激しいのも当然なのだが、にもかかわらず、各地の雑煮に共通する点がある.
冷たい雑煮は食べないということである.
つまり、火の神に休んでもらうのならば、同じく正月料理である雑煮も冷たいはずである.
しかしながら、近年、冷やし雑煮なるものが登場しているものの、管見の限りではそのような例はないのである.
このため、火の神ではなく、竈の神を休ませるためであり、囲炉裏で餅を焼き、七輪で雑煮を作ったというような書き方をしているところもあるが、これは苦しい.
もちろん、冷たい餅など食べられるわけがないから、仕方なく火を使うのだという考え方もできるのだが、餅を入れない雑煮でも温めて食べている.
つまり、火の神に休んでもらうというのは後付けであり、豆はマメになるように、豊作になるように田作りなどというのと同じく、語呂合わせやこじつけの類いである.
したがって、冷たいおせちについては、別の理由を考える必要がある.
2022.1/7
Up Down
#365
「食物服用之巻https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936509(159コマ)」という
室町時代の小笠原流の食事作法を記した本に「式三献はいづれもくはざるもの也.はしをもいろはず」とある.
式三献はどれも食べるものではなく、箸で触ったりもしないというのである.
式三献というのは、宴会で、献杯されるたびに酒を勧めて飲み干すことを3度繰り返すという武家の儀礼である.
さらに、三献は吸物や肴(さかな)を添えて、大・中・小の杯で一杯ずつ三度繰り返して計九杯の酒を勧めることと辞書にある.
つまり、式三献に添えてある吸物や肴は飾り物だというのである.
その上、辞書の説明にはないが、初献、二献、三献と、3つの膳が取り換えられていく.
箸もつけられないのにである.
宴会で、乾杯まで膳に箸をつけていけないという珍妙な風習や駆けつけ三杯というのはこの名残であろうし、三献は、結婚式の三三九度の杯の原型であろう.
しかし、もっと興味深いのは、#361で紹介した蓬莱とか食積とか呼ばれているものと同じく、見るだけで食べないということである.
式三献にどのような肴が出たかは「食物服用之巻」https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936509(159コマ)に図入りで出ている.
分かりづらいところもあるので、他書で補って書くと、初献に海月、梅干、打鮑、二献が鯉の刺身、三献は鯉の内臓の味噌煎り煮である「わたいり」となっている.
「徒然草」に「鯉ばかりこそ、御前にても切らるる物なれば、やんごとなき魚なり」、
鯉は天皇の前でも切られるぐらい高貴な魚であると書かれたように、鯉がもっとも珍重された魚だからである.
江戸時代になって、鯛が尊ばれるようになるが、この時代、海から遠い所に都が位置していたので、淡水魚の地位が高かったのである.
にもかかわらず、その鯉ですら下げられてしまう.
そして、ジョアン・ロドリゲスの「日本教会史」には、信長や太閤の時代から行われ始めた当世風の宴会料理として次のように書かれている.
「ただ装飾用に見るためだけに出されたものと、冷たいものとを棄て去って、
その代わりに暖かくて十分に調理された料理が適当な時に食台に出され」(岩波書店大航海時代叢書IXp553)と.
つまり、織豊期に滅び去った宴会料理の残滓が、#361で紹介した蓬莱とか食積なのである.
その後裔であるおせち料理が冷たいのは、式三献時代の名残ということになる.
2022.1/9
Up
Down
#365
「食物服用之巻https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936509(159コマ)」という
室町時代の小笠原流の食事作法を記した本に「式三献はいづれもくはざるもの也.はしをもいろはず」とある.
式三献はどれも食べるものではなく、箸で触ったりもしないというのである.
式三献というのは、宴会で、献杯されるたびに酒を勧めて飲み干すことを3度繰り返すという武家の儀礼である.
さらに、三献は吸物や肴(さかな)を添えて、大・中・小の杯で一杯ずつ三度繰り返して計九杯の酒を勧めることと辞書にある.
つまり、式三献に添えてある吸物や肴は飾り物だというのである.
その上、辞書の説明にはないが、初献、二献、三献と、3つの膳が取り換えられていく.
箸もつけられないのにである.
宴会で、乾杯まで膳に箸をつけていけないという珍妙な風習や駆けつけ三杯というのはこの名残であろうし、三献は、結婚式の三三九度の杯の原型であろう.
しかし、もっと興味深いのは、#361で紹介した蓬莱とか食積とか呼ばれているものと同じく、見るだけで食べないということである.
式三献にどのような肴が出たかは「食物服用之巻」https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936509(159コマ)に図入りで出ている.
分かりづらいところもあるので、他書で補って書くと、初献に海月、梅干、打鮑、二献が鯉の刺身、三献は鯉の内臓の味噌煎り煮である「わたいり」となっている.
「徒然草」に「鯉ばかりこそ、御前にても切らるる物なれば、やんごとなき魚なり」、
鯉は天皇の前でも切られるぐらい高貴な魚であると書かれたように、鯉がもっとも珍重された魚だからである.
江戸時代になって、鯛が尊ばれるようになるが、この時代、海から遠い所に都が位置していたので、淡水魚の地位が高かったのである.
にもかかわらず、その鯉ですら下げられてしまう.
そして、ジョアン・ロドリゲスの「日本教会史」には、信長や太閤の時代から行われ始めた当世風の宴会料理として次のように書かれている.
「ただ装飾用に見るためだけに出されたものと、冷たいものとを棄て去って、
その代わりに暖かくて十分に調理された料理が適当な時に食台に出され」(岩波書店大航海時代叢書IXp553)と.
つまり、織豊期に滅び去った宴会料理の残滓が、#361で紹介した蓬莱とか食積なのである.
その後裔であるおせち料理が冷たいのは、式三献時代の名残ということになる.
2022.1/9
Up Down
#366
おせち料理に関する話しが長くなったが、日本人は倭国の時代から生ものを好んだというのが、年末の結論だった.
これが正解であるのなら、中国から膾(なます)が伝わる前から、日本人は生食を好んだということになる.
また、#318で書いたように、あり得ない話であるが、弟猾(おとうかし)が神武の軍勢に牛を屠って食べさしたのも、#321の大地主神と大歳神との争いの原因となった牛肉も、生肉であった可能性が高い.
だとすれば、記紀に炙り肉が出てこない理由も分かるが、日本人がそこまで生食にこだわったのはなぜだろう.
その理由として、海に近い上に、豊かな漁場があり、新鮮な魚が手に入ったからという説明がされることが多いが、そのような国は他にもある.
たとえば、イギリスにはドッガー・バンクのような好漁場があるが、あまり生食を好むようには思えない.
もっとも、かの地は我々がメキシコ湾流と習った北大西洋海流のおかげで比較的温暖であるが、樺太や、カナダと並ぶ高緯度にあるため、冷涼である.
したがって、生で食べるより、暖かい食事のほうが好まれると思う.
これに対し、日本はずっと温暖であり、変化に富んでいる.
このため、古代の日本人は、他の地の人よりも食べるものに不自由しなかったのではないかと考えられる.
狩猟も、農作もしたが、基本は採集でいけたのである.
もちろん、飢饉もあっただろうし、大変な季節もあっただろうが、生きていけないということは少なかったのである.
もちろん、そんなに恵まれた国はほとんど存在しないだろうが、採集することで生きていけるのなら、よりよいものを選ぼうとするであろう.
新しいもの、おいしいもの、珍しいものが優先され、他のものは排斥されたのではないかと思う.
そういう中で、生肉はおいしいと気付いたのであろう.
では、なぜ、日本人は肉食しなくなったのだろうか.
2022.1/11
Up
Down
#366
おせち料理に関する話しが長くなったが、日本人は倭国の時代から生ものを好んだというのが、年末の結論だった.
これが正解であるのなら、中国から膾(なます)が伝わる前から、日本人は生食を好んだということになる.
また、#318で書いたように、あり得ない話であるが、弟猾(おとうかし)が神武の軍勢に牛を屠って食べさしたのも、#321の大地主神と大歳神との争いの原因となった牛肉も、生肉であった可能性が高い.
だとすれば、記紀に炙り肉が出てこない理由も分かるが、日本人がそこまで生食にこだわったのはなぜだろう.
その理由として、海に近い上に、豊かな漁場があり、新鮮な魚が手に入ったからという説明がされることが多いが、そのような国は他にもある.
たとえば、イギリスにはドッガー・バンクのような好漁場があるが、あまり生食を好むようには思えない.
もっとも、かの地は我々がメキシコ湾流と習った北大西洋海流のおかげで比較的温暖であるが、樺太や、カナダと並ぶ高緯度にあるため、冷涼である.
したがって、生で食べるより、暖かい食事のほうが好まれると思う.
これに対し、日本はずっと温暖であり、変化に富んでいる.
このため、古代の日本人は、他の地の人よりも食べるものに不自由しなかったのではないかと考えられる.
狩猟も、農作もしたが、基本は採集でいけたのである.
もちろん、飢饉もあっただろうし、大変な季節もあっただろうが、生きていけないということは少なかったのである.
もちろん、そんなに恵まれた国はほとんど存在しないだろうが、採集することで生きていけるのなら、よりよいものを選ぼうとするであろう.
新しいもの、おいしいもの、珍しいものが優先され、他のものは排斥されたのではないかと思う.
そういう中で、生肉はおいしいと気付いたのであろう.
では、なぜ、日本人は肉食しなくなったのだろうか.
2022.1/11
Up Down
#367
一般に、仏教の伝来により、日本人は肉食しなくなったとされる.
仏教の不殺生戒に触れるというのである.
不殺生戒は仏教の五戒の一つで、きわめて重要、かつ、基本となる戒律である.
しかし、だとすれば不可解な点がある.
肉食を禁じられたのなら、魚も食べてはいけないはずである.
魚だけではない.
あまり知られていないようだが、日本人は鳥を食べた.
鶏ではない.
すべての鳥をである.
中でも、鶴であるとか、白鳥であるとかは、最高級の食材であった.
また、このため、兎も食べた.
私には耳にしか見えないが、たとえば、江戸時代の人はこれを羽根と見た(てた).
しかも、兎は飛ぶ(跳ぶ)のである.
今でも、兎を一頭、二頭ではなく、一羽、二羽と数えるのはこのせいである.
また、鯨も、魚の一種とみられていたから、これも食べる.
昆虫食も盛んであった.
しかし、仏教の精進料理には、獣肉は出ないし、鳥も、魚も出ない.
卵も駄目である.
やはり、仏教の不殺生戒は、鳥も魚も(多分、虫も)殺してはならないのである.
ただし、この戒律については、真言宗の寺の訳は「いかなる生き物も、故意に殺傷しない」とあり、「故意に」という言葉が入っている.
さらに書くのなら、不殺生戒とは殺してはいけないであって、食べてはいけないではない.
このため、小乗仏教と呼ばれることの多い上座部仏教では、僧侶であっても、自分のために殺されたと聞いていない、知らない、
殺すところを見ていないのなら肉食できるとなっている.
というのは、托鉢で貰ったものは、すべて食べなくてはならないからである.
この規定がないと、貰ったカレーの中に肉片が入っていたら食べられなくなってしまう.
ところで、手塚治虫の「ブッダ」の冒頭で、修行僧のために何も食べ物を手に入れられなかった兎が、
火の中に飛び込んで、自らの肉体を僧に食べさせようとするシーンがある.
これは、ジャータカとか、本生経と呼ばれる経典に載っており、日本の「今昔物語集」にも載っている有名な話である.
しかし、兎の意志には反するだろうが、この肉は食べられない.
僧のために死んでいるからである.
したがって、帝釈天という本性を現した修行僧は、件の兎を月に葬ってはいるが、食べてはいない.
しかし、一定条件下であったとしても、僧でも肉食できるという考えは、大乗仏教、特に中国のそれでは否定されることになる.
2022.1/13
Up
Down
#367
一般に、仏教の伝来により、日本人は肉食しなくなったとされる.
仏教の不殺生戒に触れるというのである.
不殺生戒は仏教の五戒の一つで、きわめて重要、かつ、基本となる戒律である.
しかし、だとすれば不可解な点がある.
肉食を禁じられたのなら、魚も食べてはいけないはずである.
魚だけではない.
あまり知られていないようだが、日本人は鳥を食べた.
鶏ではない.
すべての鳥をである.
中でも、鶴であるとか、白鳥であるとかは、最高級の食材であった.
また、このため、兎も食べた.
私には耳にしか見えないが、たとえば、江戸時代の人はこれを羽根と見た(てた).
しかも、兎は飛ぶ(跳ぶ)のである.
今でも、兎を一頭、二頭ではなく、一羽、二羽と数えるのはこのせいである.
また、鯨も、魚の一種とみられていたから、これも食べる.
昆虫食も盛んであった.
しかし、仏教の精進料理には、獣肉は出ないし、鳥も、魚も出ない.
卵も駄目である.
やはり、仏教の不殺生戒は、鳥も魚も(多分、虫も)殺してはならないのである.
ただし、この戒律については、真言宗の寺の訳は「いかなる生き物も、故意に殺傷しない」とあり、「故意に」という言葉が入っている.
さらに書くのなら、不殺生戒とは殺してはいけないであって、食べてはいけないではない.
このため、小乗仏教と呼ばれることの多い上座部仏教では、僧侶であっても、自分のために殺されたと聞いていない、知らない、
殺すところを見ていないのなら肉食できるとなっている.
というのは、托鉢で貰ったものは、すべて食べなくてはならないからである.
この規定がないと、貰ったカレーの中に肉片が入っていたら食べられなくなってしまう.
ところで、手塚治虫の「ブッダ」の冒頭で、修行僧のために何も食べ物を手に入れられなかった兎が、
火の中に飛び込んで、自らの肉体を僧に食べさせようとするシーンがある.
これは、ジャータカとか、本生経と呼ばれる経典に載っており、日本の「今昔物語集」にも載っている有名な話である.
しかし、兎の意志には反するだろうが、この肉は食べられない.
僧のために死んでいるからである.
したがって、帝釈天という本性を現した修行僧は、件の兎を月に葬ってはいるが、食べてはいない.
しかし、一定条件下であったとしても、僧でも肉食できるという考えは、大乗仏教、特に中国のそれでは否定されることになる.
2022.1/13
Up Down
#368
一般に「涅槃(ねはん)経」として知られる「大般(だいはつ)涅槃経」に、
「一切衆生悉有仏性」、一切の衆生(しゅじょう=すべての生物)は、ことごとく仏性を有するとある.
もっとも、この言葉は中国で生まれたようで、最初にインドで書かれた時には、そのようなことは書いてないそうである.
というより、「涅槃経」の名通り、本来は釈迦の入滅の状況だけを描いたものであり、中国に入ってからさまざまな教理を含むようになったそうである.
したがって、一切の生物はすべて仏性を持っている、つまり、仏になる可能性があるという考えは、インドではなく、中国で起きたことになる.
この変容がどうして起きたかについては、私の能力を超えるし、本稿の目的でもない.
したがって、考察は加えないものとするが、仏になる、つまり、成仏するということは、輪廻転生から抜け出すことである.
しかしながら、この世の人間は仏になっていないので、動物を食べるということは、
自分の親兄弟が転生した動物を食べてしまう可能性があるということになる.
不殺生戒はインドで生まれたものなので、これに由来するものではない.
しかし、このことから、僧侶だけでなく、他の人々にも不殺生戒が広まった可能性は高い.
もっとも、この「一切衆生悉有仏性」は日本に入ると、さらに変容する.
空海が「草木国土悉皆成仏」を唱え、その姪の子といわれる円珍等を通じて天台宗にも広がったのである.
空海なので、おそらくは中国から持ち込んだものではないかと思われるが、
これ以前の真言・天台以前の南都六宗では「一切衆生悉有仏性」すら、無条件に認めているわけではない.
たとえば、法相宗等ではすべてに仏性があるとは認めてはいないし、華厳宗は精神性のないものは仏性はないとする.
まして、「草木国土悉皆成仏」となると無機物である国土も成仏できるとなる.
しかしながら、この言葉は、土着のアニミズムの性だろうと思われるが、当時の人々には抵抗なく受け入れられたようで、
山川草木悉皆成仏という出所不明の言葉で知られるようになる.
山も川も草木も成仏できるというのである.
つまり、すべてのものに仏性を認めるわけだから、すべてのものは不殺生戒の対象となる.
それでは、生きていくことができなくなるので、一部の動物だけに留めたのが、仏教による肉食禁止に繋がったという考えはできる.
ただ、その場合、魚も鳥も含む、すべての生物を食べてはいけないとなるはずである.
したがって、仏教は禁止の原因にはならない.
2022.1/15
Up
Down
#368
一般に「涅槃(ねはん)経」として知られる「大般(だいはつ)涅槃経」に、
「一切衆生悉有仏性」、一切の衆生(しゅじょう=すべての生物)は、ことごとく仏性を有するとある.
もっとも、この言葉は中国で生まれたようで、最初にインドで書かれた時には、そのようなことは書いてないそうである.
というより、「涅槃経」の名通り、本来は釈迦の入滅の状況だけを描いたものであり、中国に入ってからさまざまな教理を含むようになったそうである.
したがって、一切の生物はすべて仏性を持っている、つまり、仏になる可能性があるという考えは、インドではなく、中国で起きたことになる.
この変容がどうして起きたかについては、私の能力を超えるし、本稿の目的でもない.
したがって、考察は加えないものとするが、仏になる、つまり、成仏するということは、輪廻転生から抜け出すことである.
しかしながら、この世の人間は仏になっていないので、動物を食べるということは、
自分の親兄弟が転生した動物を食べてしまう可能性があるということになる.
不殺生戒はインドで生まれたものなので、これに由来するものではない.
しかし、このことから、僧侶だけでなく、他の人々にも不殺生戒が広まった可能性は高い.
もっとも、この「一切衆生悉有仏性」は日本に入ると、さらに変容する.
空海が「草木国土悉皆成仏」を唱え、その姪の子といわれる円珍等を通じて天台宗にも広がったのである.
空海なので、おそらくは中国から持ち込んだものではないかと思われるが、
これ以前の真言・天台以前の南都六宗では「一切衆生悉有仏性」すら、無条件に認めているわけではない.
たとえば、法相宗等ではすべてに仏性があるとは認めてはいないし、華厳宗は精神性のないものは仏性はないとする.
まして、「草木国土悉皆成仏」となると無機物である国土も成仏できるとなる.
しかしながら、この言葉は、土着のアニミズムの性だろうと思われるが、当時の人々には抵抗なく受け入れられたようで、
山川草木悉皆成仏という出所不明の言葉で知られるようになる.
山も川も草木も成仏できるというのである.
つまり、すべてのものに仏性を認めるわけだから、すべてのものは不殺生戒の対象となる.
それでは、生きていくことができなくなるので、一部の動物だけに留めたのが、仏教による肉食禁止に繋がったという考えはできる.
ただ、その場合、魚も鳥も含む、すべての生物を食べてはいけないとなるはずである.
したがって、仏教は禁止の原因にはならない.
2022.1/15
Up Down
#369
儒教には、釈奠というものがある.
「しゃくてん」とも、「さくてん」とも読むが、通常は「せきてん」と読む.
釈に「置く」の意味があり、奠は「据える」で、お供えをすることで、孔子等の先聖先師を祭ることである.
儒教における最重要の儀式である.
釈は、字の中に米を含むように、本来、種子を選別することで、そこから解釈の意味が生じるが、穀類を供える意味も出てくる.
したがって、釈菜、釈幣のように、野菜や幣を供える意味に使う.
一方、奠は、酉という字を内包することからも分かるように、酒を供えることであった.
しかし、今は香典と書く、葬式の香奠は、線香代を供えるの意味であるので、酒とは限らなかったようである.
実際、中国では牛、羊、豚を犠牲として捧げた.
日本でも、「延喜式」に釈奠の記述があり、三牲として「大鹿小鹿豕各加五臓」とある.
牛と羊を、大小の鹿と猪で代用しているが、「五臓を加え」とあるので、内臓とともに供えていたことになる.
これらの供物は、最終的に参加者が食べているので、儒教も肉食禁忌の理由にはなりえない.
中国では五虫といって、すべての動物を、鱗虫(りんちゅう)、羽虫、裸虫、毛虫、甲(介)虫に分ける.
鱗のあるもの、羽のあるもの、裸のもの、毛のあるもの、甲羅のあるものであり、この場合の虫(蟲)は動物の意味である、
鱗虫は鱗あるものの総称だから、魚も蛇も蜥蜴も、そして、想像上の生物であるが、龍もこの仲間である.
人間は毛があるが、裸虫に分類されており、蛙とか、蛞蝓(ナメクジ)とか、蚯蚓(ミミズ)とかと同じである.
もちろん、牛馬は、毛に覆われているので、毛虫である.
したがって、これは、毛虫類を食べてはいけないという禁忌だったとも考えられる.
つまり、五虫という言葉に、五を含むことから分かるように、五行に由来するものである.
であるならば、土気である裸虫は、金気である毛虫に触れるとよくないということがあったのではないかという考えられるが、残念ながらそのようなことはない.
2022.1/17
Up
Down
#369
儒教には、釈奠というものがある.
「しゃくてん」とも、「さくてん」とも読むが、通常は「せきてん」と読む.
釈に「置く」の意味があり、奠は「据える」で、お供えをすることで、孔子等の先聖先師を祭ることである.
儒教における最重要の儀式である.
釈は、字の中に米を含むように、本来、種子を選別することで、そこから解釈の意味が生じるが、穀類を供える意味も出てくる.
したがって、釈菜、釈幣のように、野菜や幣を供える意味に使う.
一方、奠は、酉という字を内包することからも分かるように、酒を供えることであった.
しかし、今は香典と書く、葬式の香奠は、線香代を供えるの意味であるので、酒とは限らなかったようである.
実際、中国では牛、羊、豚を犠牲として捧げた.
日本でも、「延喜式」に釈奠の記述があり、三牲として「大鹿小鹿豕各加五臓」とある.
牛と羊を、大小の鹿と猪で代用しているが、「五臓を加え」とあるので、内臓とともに供えていたことになる.
これらの供物は、最終的に参加者が食べているので、儒教も肉食禁忌の理由にはなりえない.
中国では五虫といって、すべての動物を、鱗虫(りんちゅう)、羽虫、裸虫、毛虫、甲(介)虫に分ける.
鱗のあるもの、羽のあるもの、裸のもの、毛のあるもの、甲羅のあるものであり、この場合の虫(蟲)は動物の意味である、
鱗虫は鱗あるものの総称だから、魚も蛇も蜥蜴も、そして、想像上の生物であるが、龍もこの仲間である.
人間は毛があるが、裸虫に分類されており、蛙とか、蛞蝓(ナメクジ)とか、蚯蚓(ミミズ)とかと同じである.
もちろん、牛馬は、毛に覆われているので、毛虫である.
したがって、これは、毛虫類を食べてはいけないという禁忌だったとも考えられる.
つまり、五虫という言葉に、五を含むことから分かるように、五行に由来するものである.
であるならば、土気である裸虫は、金気である毛虫に触れるとよくないということがあったのではないかという考えられるが、残念ながらそのようなことはない.
2022.1/17
Up Down
#370
日本で肉食禁止が出された最初は、天武天皇が675年4月17日に出したものである.
「日本書紀」から全文を掲げると、
詔諸国曰「自今以後、制諸漁猟者、莫造檻穽及施機槍等之類.亦四月朔以後九月卅日以前莫置比弥沙伎理梁.且莫食牛馬犬猿鶏之宍.以外不在禁例.若有犯者罪之
諸国に詔(みことのり)して曰く「今より以降、諸(もろもろ)の漁猟者を制(いさ)めて、檻穽(かんせい)を造り機槍(ふみはなち)等の類を施(お)くことなかれ.
亦四月朔(ついたち)より九月三十日以前に比弥沙伎理(ひみさかり)梁(やな)を置くことなかれ.
かつ、牛馬犬猿鶏の宍を食うなかれ.以外は禁令にあらず.もし犯すことあらば罪せむ」とのたまふ」となる.
落とし穴や、機槍のような罠を設置するな.
4月1日から9月30日までは比弥沙伎理や、梁もダメである.
牛馬犬猿鶏の肉を食ってはいけない.
これ以外は禁止しない.
もし、禁令を犯すことがあれば処罰するというのである.
機槍と比弥沙伎理についてはよく分からないが、前者は機械仕掛けの槍、後者は目の詰んだ網ではないかといわれる.
アイヌ民族には、アマッポと呼ばれる道具があり、動物が仕掛け糸に触れると毒矢が発射される.
機槍というのは、これに類するものではないかと思うが、槍という字を含むところを見ると、矢よりも太い、先を尖らした杭のようなものを発射するのかもしれない.
また、「牛馬犬猿鶏」ということは、当時の日本人は、犬だけではなく、猿も食べていたのかと思うわけだが、奇妙なことに、この中には、鹿も猪も含まれていない.
つまり、古代の日本人が食べていた2大食肉が含まれていない.
もし、今の日本で、牛豚以外の獣肉の食用禁止令が出たとしても、困る人はそれほどいないと思うが、天武の命令も、それに類するものである.
これを食肉禁止令と呼んでよいか迷うほどである.
しかも、4月1日から9月30日に限定するということは、農繁期である.
農閑期なら捕って食べてもよいのである.
その上、「以外は禁令にあらず」とわざわざ記している.
ということは、比弥沙伎理や梁は駄目でも、釣りはよいということになる.
もっとも、江戸時代にテグス(天蚕糸)の利用が広まるまで、馬の毛や、通常の糸を使っていたようで、釣り糸がすぐに切れるそうである.
このため、本職の漁師でないと釣るのは難しかったとあるが、海幸、山幸の話を上げるまでもなく、神話時代から釣りは行われていた.
また、これは罠を使って大量に捕ってはいけないという意味でもないはずである.
陥穽や機槍を禁止しても、よほど大規模なものでないと、一度に何頭も捕れるはずがないからである.
しかも、この禁令は弓矢を禁止していない.
「諸の漁猟者」に含まれているとも思えないが、皇族・貴族の狩りを妨げぬためかと邪推してしまう.
もっとも、一般の猟師も弓矢を使っていたのではないかと思うし、猿を殺しても、食べねばよいということになる.
また、機槍を矢を発射するものではないと考えたのもこのためである.
機械仕掛けの矢はいけないが、人間が発射するのならよいというのは、理解できないからである.
また、このように不可解な点があるため、4月から9月というのは魚採りだけにかかり、獣肉禁止にはかからないという説もあるぐらいである.
しかし、この禁令は、「牛馬犬猿鶏」に着目すれば、無理なく理解できる.
2022.1/19
Up
Down
#370
日本で肉食禁止が出された最初は、天武天皇が675年4月17日に出したものである.
「日本書紀」から全文を掲げると、
詔諸国曰「自今以後、制諸漁猟者、莫造檻穽及施機槍等之類.亦四月朔以後九月卅日以前莫置比弥沙伎理梁.且莫食牛馬犬猿鶏之宍.以外不在禁例.若有犯者罪之
諸国に詔(みことのり)して曰く「今より以降、諸(もろもろ)の漁猟者を制(いさ)めて、檻穽(かんせい)を造り機槍(ふみはなち)等の類を施(お)くことなかれ.
亦四月朔(ついたち)より九月三十日以前に比弥沙伎理(ひみさかり)梁(やな)を置くことなかれ.
かつ、牛馬犬猿鶏の宍を食うなかれ.以外は禁令にあらず.もし犯すことあらば罪せむ」とのたまふ」となる.
落とし穴や、機槍のような罠を設置するな.
4月1日から9月30日までは比弥沙伎理や、梁もダメである.
牛馬犬猿鶏の肉を食ってはいけない.
これ以外は禁止しない.
もし、禁令を犯すことがあれば処罰するというのである.
機槍と比弥沙伎理についてはよく分からないが、前者は機械仕掛けの槍、後者は目の詰んだ網ではないかといわれる.
アイヌ民族には、アマッポと呼ばれる道具があり、動物が仕掛け糸に触れると毒矢が発射される.
機槍というのは、これに類するものではないかと思うが、槍という字を含むところを見ると、矢よりも太い、先を尖らした杭のようなものを発射するのかもしれない.
また、「牛馬犬猿鶏」ということは、当時の日本人は、犬だけではなく、猿も食べていたのかと思うわけだが、奇妙なことに、この中には、鹿も猪も含まれていない.
つまり、古代の日本人が食べていた2大食肉が含まれていない.
もし、今の日本で、牛豚以外の獣肉の食用禁止令が出たとしても、困る人はそれほどいないと思うが、天武の命令も、それに類するものである.
これを食肉禁止令と呼んでよいか迷うほどである.
しかも、4月1日から9月30日に限定するということは、農繁期である.
農閑期なら捕って食べてもよいのである.
その上、「以外は禁令にあらず」とわざわざ記している.
ということは、比弥沙伎理や梁は駄目でも、釣りはよいということになる.
もっとも、江戸時代にテグス(天蚕糸)の利用が広まるまで、馬の毛や、通常の糸を使っていたようで、釣り糸がすぐに切れるそうである.
このため、本職の漁師でないと釣るのは難しかったとあるが、海幸、山幸の話を上げるまでもなく、神話時代から釣りは行われていた.
また、これは罠を使って大量に捕ってはいけないという意味でもないはずである.
陥穽や機槍を禁止しても、よほど大規模なものでないと、一度に何頭も捕れるはずがないからである.
しかも、この禁令は弓矢を禁止していない.
「諸の漁猟者」に含まれているとも思えないが、皇族・貴族の狩りを妨げぬためかと邪推してしまう.
もっとも、一般の猟師も弓矢を使っていたのではないかと思うし、猿を殺しても、食べねばよいということになる.
また、機槍を矢を発射するものではないと考えたのもこのためである.
機械仕掛けの矢はいけないが、人間が発射するのならよいというのは、理解できないからである.
また、このように不可解な点があるため、4月から9月というのは魚採りだけにかかり、獣肉禁止にはかからないという説もあるぐらいである.
しかし、この禁令は、「牛馬犬猿鶏」に着目すれば、無理なく理解できる.
2022.1/19
Up Down
#371
「牛馬犬猿鶏」うち、「犬猿鶏」は、桃太郎の連れていた犬、猿、雉子と同一構成である.
雉子が鶏になっているだけで、どちらも鳥類だからである.
偶然ではないかといわれそうだが、申、酉、戌は西方金気を意味する3種の動物である.
そして、猿の孫悟空が、西王母から盗んだのは桃である.
また、桃太郎は吉備団子を持っているが、白または金色の丸い餅は、金気の象徴であり、金気は強さの象徴である.
したがって、桃太郎は、金太郎と同じく、金気であるがゆえに強いのである.
と同時に、金気は実であり、収穫を意味する.
すなわち、4月の播種から9月の収穫までの期間の内に金気を取り除くということは、五行的には、収穫できないということになる.
したがって、犬猿鶏を食べるなということは、農作物の実りを確実にする呪術である.
ならば、この期間に魚獲りを禁止するということは、#361で書いた水気を除いて春を迎える呪術の逆である.
すなわち、水気である魚を保護して、農作物の育成に絶対重要な水を保全しようとしたのである.
特に、水中に伸びる網のイメージは木気の伸びるという形態に合うし、梁は、木か竹でできている.
つまり、農作物の属する木気が水気を邪魔するという構図になり、よろしくないということになる.
これに対し、釣針は古墳時代から金属製のものが使われている.
金気であるため適用が除外されたのであろう.
また、当然、水気に属する亥、子、丑も保護の対象となるが、猪は、重要な食肉動物であると同時に、農作物を荒らす.
鼠も、農作物を守る観点からいって保護はできない.
というわけで、牛だけが残ったのであろう.
あと、火気の中心に位置する午も守る必要がある.
充分な日照がないと農作物は育たないからである.
牛馬がここに登場するのはこのためであろう.
したがって、順調な季節の推移を願うためには、土気に穴を開ける檻穽、
農作物の順調な生育を願うためには、木気である木の槍を投げる機槍は、使ってはいけないことになる.
そして、弓矢は、全体が木や竹なので微妙だが、鏃が金属であったために除外されたのであろう.
しかし、このように考えた最大の理由は、この禁令が天武によって出されているからである.
2022.1/21
Up
Down
#371
「牛馬犬猿鶏」うち、「犬猿鶏」は、桃太郎の連れていた犬、猿、雉子と同一構成である.
雉子が鶏になっているだけで、どちらも鳥類だからである.
偶然ではないかといわれそうだが、申、酉、戌は西方金気を意味する3種の動物である.
そして、猿の孫悟空が、西王母から盗んだのは桃である.
また、桃太郎は吉備団子を持っているが、白または金色の丸い餅は、金気の象徴であり、金気は強さの象徴である.
したがって、桃太郎は、金太郎と同じく、金気であるがゆえに強いのである.
と同時に、金気は実であり、収穫を意味する.
すなわち、4月の播種から9月の収穫までの期間の内に金気を取り除くということは、五行的には、収穫できないということになる.
したがって、犬猿鶏を食べるなということは、農作物の実りを確実にする呪術である.
ならば、この期間に魚獲りを禁止するということは、#361で書いた水気を除いて春を迎える呪術の逆である.
すなわち、水気である魚を保護して、農作物の育成に絶対重要な水を保全しようとしたのである.
特に、水中に伸びる網のイメージは木気の伸びるという形態に合うし、梁は、木か竹でできている.
つまり、農作物の属する木気が水気を邪魔するという構図になり、よろしくないということになる.
これに対し、釣針は古墳時代から金属製のものが使われている.
金気であるため適用が除外されたのであろう.
また、当然、水気に属する亥、子、丑も保護の対象となるが、猪は、重要な食肉動物であると同時に、農作物を荒らす.
鼠も、農作物を守る観点からいって保護はできない.
というわけで、牛だけが残ったのであろう.
あと、火気の中心に位置する午も守る必要がある.
充分な日照がないと農作物は育たないからである.
牛馬がここに登場するのはこのためであろう.
したがって、順調な季節の推移を願うためには、土気に穴を開ける檻穽、
農作物の順調な生育を願うためには、木気である木の槍を投げる機槍は、使ってはいけないことになる.
そして、弓矢は、全体が木や竹なので微妙だが、鏃が金属であったために除外されたのであろう.
しかし、このように考えた最大の理由は、この禁令が天武によって出されているからである.
2022.1/21
Up Down
#372
天武は道教に関心を持っていた.
持っていたどころではない.
大君(おおきみ)を、当時の道教の最高神である天皇(てんこう)上帝から天皇という言葉に代えたといわれている.
そして、天皇上帝は北極星の化身であることから、天文台の設置を命じ、自ら星の運行による占いを実施している.
これについては、天武紀の冒頭の一節に「能天文遁甲(天文遁甲を能くす)」と特記されているが、遁甲は式盤を見て行う占いである.
夢占いをしたとも書かれている.
また、名を天渟中原(あまのぬなはら)瀛真人(おきのまひとの)天皇(すめらみこと)という.
この瀛という見慣れぬ漢字は、瀛洲(えいしゅう)とその関連語ぐらいにしか使わないが、
瀛洲は、蓬莱、方丈とともに、古代中国で東方海上にあるとされた神仙の島である.
そして、真人は、天武が定めた八色(やくさ)の姓(かばね)の最高位であるが、これを「しんじん」と音で読むと神に次ぐ神仙世界の第2位である
(道教に関係するものとしては、他に道士という位もある).
もちろん、この名は和風諡号(しごう)とされているが、
死後に贈られた諡(おくりな)であることが文献上で確認できるのは、后で皇位を継承した次の持統天皇からである.
したがって、大海人(おおあまの)皇子が即位にあたってそのように呼べとした可能性もある.
また、諡号だとしても、死後の殯(もがり)の間につけられているはずなので、
生前の行いを反映しているはずであるが、道教や神仙に関する和風諡号を持つ天皇は天武のみである.
さらに、「天皇祈之曰天神地祇扶朕者雷雨息矣言訖即雷雨止之
(天皇祈(うけ)ひて曰はく「天神地祇、朕(われ)を扶(たす)けたまはば雷なり雨ふること息(や)めむ」」と「日本書紀」にある.
天神地祇が私を助けてくれるのなら、ただちに雷雨を止めて下さいと述べ、天武のこの言葉に応じたかのように雷雨が止んだとある.
魔術師ですかと聞いてみたくなるような内容なので、実話ではないであろう.
実際、「日本書紀」の第14〜21巻(雄略〜用明)、24〜7巻(皇極〜天智)と、それ以外は書き手が違う.
前者は中国人の書く漢文だが、残りは和習と呼ばれる日本語の癖のついた漢文だからである.
そして、第22〜3巻、つまり、推古、舒明紀に和習があり、その前後が中国語に堪能な者の書いたものであるということは、この2巻が書き直されたからであるといわれる.
そして、天武記は第28〜9巻なので、後で書き足したのではないかとなる.
したがって、「天文遁甲を能くする」というのもどこまで信用できるかとは思うし、雷雨が止んだのも創作であろうということになる.
2022.1/24
Up
Down
#372
天武は道教に関心を持っていた.
持っていたどころではない.
大君(おおきみ)を、当時の道教の最高神である天皇(てんこう)上帝から天皇という言葉に代えたといわれている.
そして、天皇上帝は北極星の化身であることから、天文台の設置を命じ、自ら星の運行による占いを実施している.
これについては、天武紀の冒頭の一節に「能天文遁甲(天文遁甲を能くす)」と特記されているが、遁甲は式盤を見て行う占いである.
夢占いをしたとも書かれている.
また、名を天渟中原(あまのぬなはら)瀛真人(おきのまひとの)天皇(すめらみこと)という.
この瀛という見慣れぬ漢字は、瀛洲(えいしゅう)とその関連語ぐらいにしか使わないが、
瀛洲は、蓬莱、方丈とともに、古代中国で東方海上にあるとされた神仙の島である.
そして、真人は、天武が定めた八色(やくさ)の姓(かばね)の最高位であるが、これを「しんじん」と音で読むと神に次ぐ神仙世界の第2位である
(道教に関係するものとしては、他に道士という位もある).
もちろん、この名は和風諡号(しごう)とされているが、
死後に贈られた諡(おくりな)であることが文献上で確認できるのは、后で皇位を継承した次の持統天皇からである.
したがって、大海人(おおあまの)皇子が即位にあたってそのように呼べとした可能性もある.
また、諡号だとしても、死後の殯(もがり)の間につけられているはずなので、
生前の行いを反映しているはずであるが、道教や神仙に関する和風諡号を持つ天皇は天武のみである.
さらに、「天皇祈之曰天神地祇扶朕者雷雨息矣言訖即雷雨止之
(天皇祈(うけ)ひて曰はく「天神地祇、朕(われ)を扶(たす)けたまはば雷なり雨ふること息(や)めむ」」と「日本書紀」にある.
天神地祇が私を助けてくれるのなら、ただちに雷雨を止めて下さいと述べ、天武のこの言葉に応じたかのように雷雨が止んだとある.
魔術師ですかと聞いてみたくなるような内容なので、実話ではないであろう.
実際、「日本書紀」の第14〜21巻(雄略〜用明)、24〜7巻(皇極〜天智)と、それ以外は書き手が違う.
前者は中国人の書く漢文だが、残りは和習と呼ばれる日本語の癖のついた漢文だからである.
そして、第22〜3巻、つまり、推古、舒明紀に和習があり、その前後が中国語に堪能な者の書いたものであるということは、この2巻が書き直されたからであるといわれる.
そして、天武記は第28〜9巻なので、後で書き足したのではないかとなる.
したがって、「天文遁甲を能くする」というのもどこまで信用できるかとは思うし、雷雨が止んだのも創作であろうということになる.
2022.1/24
Up Down
#373
ただ、斉明紀には「復於嶺上両槻樹邊起観号為両槻宮亦曰天宮
(嶺の上の両(ふた)つの槻の樹の辺に、観(たかどの)を起つ.
両槻(ふたつきの)宮と号す.
また天宮と曰ふ)」とある.
観を「たかどの」と読むのは、道教の施設を道観と呼ぶからであり、現在でも、台湾人貿易商が1995年に埼玉県に建てた聖天宮等、道観には天宮と呼ぶものが多い.
したがって、斉明(皇極)天皇は道教に関心を持っていたわけで、飛鳥に残る酒船石や亀石等の石造物はその名残ではないかといわれる.
実際、斉明天皇やその子である天智、天武天皇等の墓は、八角形をしている.
これは、東西南北に、北東(艮=うしとら)、東南(巽)、南西(坤=ひつじさる)、北西(乾)を足した八方位を表すが、これは道教で重要視されているものである.
もともと日本には8を極数として見る習慣があり、八百万(やおよろず)の神という言い方等は、それに由来する.
これは、親指を除く4本の指で数えていたからではないかといわれ、一つと五つ、四つと八つの音韻が似通っているのはその証拠であるという説がある.
たまたま、奇数を重んじる中国にしては珍しく、道教では八方位の他には八卦のように8が多出するので、これを被せて聖数化したのだろう.
八色の姓の八もこれに由来するのではないかといわれるが、八方向の遠い果てという意味で、八荒という言葉が「史紀」に登場する.
「神武紀」には「八紘為宇(八紘(あめのした)をおおいて宇(いえ)と為(せ)ん)」の語が登場するが、これは八荒に由来するものであろう.
もちろん、日本の植民地政策の旗印となった「八紘一宇」の由来がこれである.
「日本書紀」は、天武の次の持統天皇で終わっていることから考えると、この時代に書かれており、「八紘一宇」も道教の影響下に出来た言葉といえる.
そして、第26巻である斉明紀は、前回、述べたように、中国語に堪能な者が書いているオリジナルと考えられる巻であり、
この時代に道教が広く取り入れられていたのは確かであろう.
したがって、#371に述べた道教に基づく呪術を、天武が行ったとしても不思議はない.
2022.1/26
Up
Down
#373
ただ、斉明紀には「復於嶺上両槻樹邊起観号為両槻宮亦曰天宮
(嶺の上の両(ふた)つの槻の樹の辺に、観(たかどの)を起つ.
両槻(ふたつきの)宮と号す.
また天宮と曰ふ)」とある.
観を「たかどの」と読むのは、道教の施設を道観と呼ぶからであり、現在でも、台湾人貿易商が1995年に埼玉県に建てた聖天宮等、道観には天宮と呼ぶものが多い.
したがって、斉明(皇極)天皇は道教に関心を持っていたわけで、飛鳥に残る酒船石や亀石等の石造物はその名残ではないかといわれる.
実際、斉明天皇やその子である天智、天武天皇等の墓は、八角形をしている.
これは、東西南北に、北東(艮=うしとら)、東南(巽)、南西(坤=ひつじさる)、北西(乾)を足した八方位を表すが、これは道教で重要視されているものである.
もともと日本には8を極数として見る習慣があり、八百万(やおよろず)の神という言い方等は、それに由来する.
これは、親指を除く4本の指で数えていたからではないかといわれ、一つと五つ、四つと八つの音韻が似通っているのはその証拠であるという説がある.
たまたま、奇数を重んじる中国にしては珍しく、道教では八方位の他には八卦のように8が多出するので、これを被せて聖数化したのだろう.
八色の姓の八もこれに由来するのではないかといわれるが、八方向の遠い果てという意味で、八荒という言葉が「史紀」に登場する.
「神武紀」には「八紘為宇(八紘(あめのした)をおおいて宇(いえ)と為(せ)ん)」の語が登場するが、これは八荒に由来するものであろう.
もちろん、日本の植民地政策の旗印となった「八紘一宇」の由来がこれである.
「日本書紀」は、天武の次の持統天皇で終わっていることから考えると、この時代に書かれており、「八紘一宇」も道教の影響下に出来た言葉といえる.
そして、第26巻である斉明紀は、前回、述べたように、中国語に堪能な者が書いているオリジナルと考えられる巻であり、
この時代に道教が広く取り入れられていたのは確かであろう.
したがって、#371に述べた道教に基づく呪術を、天武が行ったとしても不思議はない.
2022.1/26
Up Down
#374
しかしながら、天武天皇は、この肉食禁止令の翌676年8月には諸国に、同年11月には近京諸国に放生会(ほうじょうえ)を命じている.
放生会は、家畜類を野に放つという仏教行事である.
今までの説明だと、天武は道教の徒だと思われた方もおられるかもしれないが、実は、兄天智から逃れて、吉野に下った際に出家をしている.
また、即位翌年の673年には高市大寺の造営を命じ、晩年には、死後の完成となったが、薬師寺の建立も命じている.
と同時に、仏教を国家の統制下に置こうとした天皇でもある.
寺院の持っていた土地や封戸(ふこ)を取り上げ、国家が収入を決めるようにしたり、僧綱制の復活や、僧侶に加えて僧尼の服装まで規定したりしている.
また、伊勢神宮を現在地に持ってきたのは彼であり、アマテラスを現在の皇祖神の地位に持ってきたのもそうではないかといわれる.
式年遷宮も、斎宮も、他の説もあるが、天武である.
つまり、道教、仏教に神道と、様々な宗教の改革や統合を進めながら、治世のためには、どれがよいかを考えていたのであろう.
結果として、天武が選んだのは仏教であったようである.
その遺志は、天武の后であった持統天皇に皇位とともに継承されたようで、天皇として初めて火葬に付されている.
その後も、この傾向は受け継がれ、聖武天皇の時代には、廬舎那仏の造立にまで至るのだが、この間、肉食禁止令は1回だけ出ている.
691年6月、持統天皇が出した「其令公卿百寮人等禁断酒宍摂心悔過(其の公卿百寮人等をして酒宍を禁断し摂心(せっしん)悔過(けか)せしめ)」というものである.
長雨が続いて被害が出そうなので、公卿、役人等に酒や肉食を禁じ、摂心悔過を命じたというものであるが、摂心も悔過も仏教用語である.
摂心は、接心とも書くが、精神を集中することであり、悔過は自らの罪や過ちを悔い改めることである.
また、この直後に「京及畿内諸寺梵衆亦当五日誦経(京及び畿内諸寺の梵衆は亦た当に五日誦経せよ)」とあり、都や機内の寺には5日間の読経を命じている.
つまり、仏教によってこの災害を乗り越えようとしているわけであるが、この肉食禁止令が仏教の考えから出されたとは限らない.
2022.1/28
Up
Down
#374
しかしながら、天武天皇は、この肉食禁止令の翌676年8月には諸国に、同年11月には近京諸国に放生会(ほうじょうえ)を命じている.
放生会は、家畜類を野に放つという仏教行事である.
今までの説明だと、天武は道教の徒だと思われた方もおられるかもしれないが、実は、兄天智から逃れて、吉野に下った際に出家をしている.
また、即位翌年の673年には高市大寺の造営を命じ、晩年には、死後の完成となったが、薬師寺の建立も命じている.
と同時に、仏教を国家の統制下に置こうとした天皇でもある.
寺院の持っていた土地や封戸(ふこ)を取り上げ、国家が収入を決めるようにしたり、僧綱制の復活や、僧侶に加えて僧尼の服装まで規定したりしている.
また、伊勢神宮を現在地に持ってきたのは彼であり、アマテラスを現在の皇祖神の地位に持ってきたのもそうではないかといわれる.
式年遷宮も、斎宮も、他の説もあるが、天武である.
つまり、道教、仏教に神道と、様々な宗教の改革や統合を進めながら、治世のためには、どれがよいかを考えていたのであろう.
結果として、天武が選んだのは仏教であったようである.
その遺志は、天武の后であった持統天皇に皇位とともに継承されたようで、天皇として初めて火葬に付されている.
その後も、この傾向は受け継がれ、聖武天皇の時代には、廬舎那仏の造立にまで至るのだが、この間、肉食禁止令は1回だけ出ている.
691年6月、持統天皇が出した「其令公卿百寮人等禁断酒宍摂心悔過(其の公卿百寮人等をして酒宍を禁断し摂心(せっしん)悔過(けか)せしめ)」というものである.
長雨が続いて被害が出そうなので、公卿、役人等に酒や肉食を禁じ、摂心悔過を命じたというものであるが、摂心も悔過も仏教用語である.
摂心は、接心とも書くが、精神を集中することであり、悔過は自らの罪や過ちを悔い改めることである.
また、この直後に「京及畿内諸寺梵衆亦当五日誦経(京及び畿内諸寺の梵衆は亦た当に五日誦経せよ)」とあり、都や機内の寺には5日間の読経を命じている.
つまり、仏教によってこの災害を乗り越えようとしているわけであるが、この肉食禁止令が仏教の考えから出されたとは限らない.
2022.1/28
Up Down
#375
肉食を禁止するというだけなら、仏教の不殺生戒による肉食禁止令のようにも見えるが、そこに酒が入ると、それは違うと思う.
肉を食べ、酒を飲むというのは、この時代、かなりの贅沢だからである.
実際、そういうことを毎日できるのは「公卿百寮人等」とあるように、貴族や高級官僚だけであったと思う.
奈良時代、日本の人口は約700万人と推定され、平城京には約20万人が住んでいた.
しかし、皇族や高位の貴族は百数十人程度であり、約1万人の下級役人が彼等の生活を支えるとともに、実務を負っていた.
したがって、下級役人の数百倍の人民にかけられた税が、彼等の豪奢な生活を支えていたということになる.
また、「百寮人」の百というのは実数であり、一般庶民が肉食することはあったかもしれないが、常にとはいかなかった.
酒肉禁止を行うのなら、一般人民にではなく、高級官僚を対象にするしかなかったのである.
ただ、この記述は、まるで、この長雨は、彼等に仏罰が下ったからであり、各自、身を慎んで、美食するなかれと言っているようにも思える.
しかし、官僚の美食が原因で長雨が続くというのは、神罰なら分かるが、仏罰というのは違和感がある.
不殺生戒を守らなかった.
だから、畜生道に堕ちたというのなら仏罰かもしれないが、それは、因果応報というものであり、あくまでも個人の身の上に起きることである.
誰かが不殺生戒を犯したから、長雨が続くというものではない.
これに対し、神が怒りを覚えた時には、天変地異をもって示すことが多い.
したがって、これは、美食をせず、身を清めて、摂心悔過をせよという命令であっても、不殺生戒による肉食禁止令ではない.
むしろ、神の祟りを許して貰うのに、仏法の力を借りようとしたようにさえ見える.
また、雨が止めば酒肉も復活するだろうから、恒久的な禁令でもない.
つまり、肉食禁止令ではなく、美食禁止令である上に、一時的なものであったということになる.
2022.1/30
Up
Down
#375
肉食を禁止するというだけなら、仏教の不殺生戒による肉食禁止令のようにも見えるが、そこに酒が入ると、それは違うと思う.
肉を食べ、酒を飲むというのは、この時代、かなりの贅沢だからである.
実際、そういうことを毎日できるのは「公卿百寮人等」とあるように、貴族や高級官僚だけであったと思う.
奈良時代、日本の人口は約700万人と推定され、平城京には約20万人が住んでいた.
しかし、皇族や高位の貴族は百数十人程度であり、約1万人の下級役人が彼等の生活を支えるとともに、実務を負っていた.
したがって、下級役人の数百倍の人民にかけられた税が、彼等の豪奢な生活を支えていたということになる.
また、「百寮人」の百というのは実数であり、一般庶民が肉食することはあったかもしれないが、常にとはいかなかった.
酒肉禁止を行うのなら、一般人民にではなく、高級官僚を対象にするしかなかったのである.
ただ、この記述は、まるで、この長雨は、彼等に仏罰が下ったからであり、各自、身を慎んで、美食するなかれと言っているようにも思える.
しかし、官僚の美食が原因で長雨が続くというのは、神罰なら分かるが、仏罰というのは違和感がある.
不殺生戒を守らなかった.
だから、畜生道に堕ちたというのなら仏罰かもしれないが、それは、因果応報というものであり、あくまでも個人の身の上に起きることである.
誰かが不殺生戒を犯したから、長雨が続くというものではない.
これに対し、神が怒りを覚えた時には、天変地異をもって示すことが多い.
したがって、これは、美食をせず、身を清めて、摂心悔過をせよという命令であっても、不殺生戒による肉食禁止令ではない.
むしろ、神の祟りを許して貰うのに、仏法の力を借りようとしたようにさえ見える.
また、雨が止めば酒肉も復活するだろうから、恒久的な禁令でもない.
つまり、肉食禁止令ではなく、美食禁止令である上に、一時的なものであったということになる.
2022.1/30
Up Down
#376
701年制定の「大宝律令」にも肉食を禁止する規定がある.
もっとも、「大宝律令」そのものは残っていないので、「養老令」から引用すると、
神祇令、散斎(あらいみ)条に「不得弔喪問病食宍(喪を弔い、病を問い、宍を食うを得ず)」と書かれている.
散斎は、新嘗祭のような大祭に参加する人の斎戒規定のうち、祭の1ヶ月前から守るべき条項である.
死人を弔ったり、病人を見舞ったりしてはいけないのと同列で、肉食してはいけならないと記されている.
当然、死や病と同じく、不浄であるがために禁止されていると考えるべきであろう.
神祇令とあるように、神道の観点からの肉食禁止令であるため、余計である.
しかし、この条の最後に「不預穢悪事(穢悪(えお)の事に預からず)」、穢悪、つまり、不浄なものに関係しないこととある.
これが「喪を弔い、病を問い、宍を食うを得ず」から先の全ての条文にかかるとは考えにくい.
その間に「亦不判刑殺不決罰罪人不作音楽(亦刑殺判(ことわ)らず、罪人を決罰せず、音楽を作(な)さず)」とあり、亦以下が並列に続いているからである.
つまり、肉食は、「穢悪の事に預からず」にかからず、不浄ではないと考えられていたことになる.
さらに、死刑を実施せず、刑罰を言い渡さずはともかくとして、音楽をなさずが、穢悪にあたるとは思えない.
というのは、新嘗祭には雅楽が演奏されるからである.
特に、五節舞として知られるものは、「続日本紀」天平15(743)年5月癸卯(5日)の条に「皇太子親舞五節(皇太子(後の孝謙天皇)親しく五節を舞う)」とあり、
この記事の中で橘諸兄が元正上皇に、天武天皇が始めた舞であると伝えている.
これが事実であるのなら、天武の在位は「大宝律令」以前であり、記事中に礼と楽とあるので、演奏されていたことになる.
もっとも、「大宝律令」は、中国の律令の丸写しである.
当時の中国の律令も失われているので、「唐律疏議」という書に引用されているものを示すと、「諸大祀在散斎而弔喪問疾判署刑殺文書及決罰者」とはあるが、肉食も、音楽もない.
穢悪に関係するなという規定もない.
条文が欠落している可能性もあるが、それよりは、日本で追加したと考えるべきである.
したがって、祭祀にあたって肉食してはいけないというのは、日本独自のものとなり、しかも、不浄だからではないということになる.
その上、この禁令も大祭がすめば関係はないし、大祭に関係する人々だけに限定されるものである.
2022.2/3
Up
Down
#376
701年制定の「大宝律令」にも肉食を禁止する規定がある.
もっとも、「大宝律令」そのものは残っていないので、「養老令」から引用すると、
神祇令、散斎(あらいみ)条に「不得弔喪問病食宍(喪を弔い、病を問い、宍を食うを得ず)」と書かれている.
散斎は、新嘗祭のような大祭に参加する人の斎戒規定のうち、祭の1ヶ月前から守るべき条項である.
死人を弔ったり、病人を見舞ったりしてはいけないのと同列で、肉食してはいけならないと記されている.
当然、死や病と同じく、不浄であるがために禁止されていると考えるべきであろう.
神祇令とあるように、神道の観点からの肉食禁止令であるため、余計である.
しかし、この条の最後に「不預穢悪事(穢悪(えお)の事に預からず)」、穢悪、つまり、不浄なものに関係しないこととある.
これが「喪を弔い、病を問い、宍を食うを得ず」から先の全ての条文にかかるとは考えにくい.
その間に「亦不判刑殺不決罰罪人不作音楽(亦刑殺判(ことわ)らず、罪人を決罰せず、音楽を作(な)さず)」とあり、亦以下が並列に続いているからである.
つまり、肉食は、「穢悪の事に預からず」にかからず、不浄ではないと考えられていたことになる.
さらに、死刑を実施せず、刑罰を言い渡さずはともかくとして、音楽をなさずが、穢悪にあたるとは思えない.
というのは、新嘗祭には雅楽が演奏されるからである.
特に、五節舞として知られるものは、「続日本紀」天平15(743)年5月癸卯(5日)の条に「皇太子親舞五節(皇太子(後の孝謙天皇)親しく五節を舞う)」とあり、
この記事の中で橘諸兄が元正上皇に、天武天皇が始めた舞であると伝えている.
これが事実であるのなら、天武の在位は「大宝律令」以前であり、記事中に礼と楽とあるので、演奏されていたことになる.
もっとも、「大宝律令」は、中国の律令の丸写しである.
当時の中国の律令も失われているので、「唐律疏議」という書に引用されているものを示すと、「諸大祀在散斎而弔喪問疾判署刑殺文書及決罰者」とはあるが、肉食も、音楽もない.
穢悪に関係するなという規定もない.
条文が欠落している可能性もあるが、それよりは、日本で追加したと考えるべきである.
したがって、祭祀にあたって肉食してはいけないというのは、日本独自のものとなり、しかも、不浄だからではないということになる.
その上、この禁令も大祭がすめば関係はないし、大祭に関係する人々だけに限定されるものである.
2022.2/3
Up Down
#377
不浄ではないのに、忌避すべきというのは不思議な話ではある.
ただ、肉食や音楽が禁止となっているのは、これが楽しみになるからと考えれば分からないでもない.
つまり、肉食も、音楽も、贅沢な暮らしである.
そうではなく、散斎の間は、身を慎んで、質素に暮らせと命令しているのである.
ただ、「大宝律令」の肉食禁止令は、「喪を弔い、病を問う」ことと同列に並んでおり、これらは「穢悪の事に預からず」にかからない.
しかし、「刑殺判(ことわ)らず、罪人を決罰せず」はともかくとして、死や病は最大の不浄ではないだろうか.
実際、中国の条文に「弔喪問疾判署刑殺文書及決罰者」と、これらが入っている.
別に、不浄のものに関係しないという文面がないので、祭に不浄のものを入れてはいけないという理由だろうと考えられる.
ところが、「大宝律令」の文面から考えるとこ、死や病は不浄ではないということになるので、おかしいのではないかと思われる方も多いと思う.
ただ、#311で紹介した「始死停喪十余日当時不食肉(始め死するや停喪十余日、時に当りて肉を食はず)」という「魏志倭人伝」の文の後に、
「喪主哭泣他人就歌舞飲酒(喪主は哭泣(こっきゅう)し、他人は歌舞、飲酒に就く)」とある.
人が死ぬと10日間あまり服喪し、その間、肉を食べない.
そして、喪主は泣き叫ぶが、他は歌い踊り、酒を飲むというのである.
つまり、宴会であるが、実は、私の田舎では、数十年前まで同様のことを行っていた.
葬式となると、供養と称して顔も知らない親戚や近所の人が集まり、酒を飲んで宴会を開いていたのである.
いわゆる御斎(おとき)であるが、中には博打を打つ者さえいたので、酒を嗜まない私達は、眉を顰めていた.
つまり、今は知らないが、つい最近まで倭人の風習が残っていたわけである.
もっとも、民俗学の方では、大騒ぎをすることにより、死者の魂を呼び戻そうとした名残と考えられている.
靖国神社の前身は東京招魂社というが、この招魂は、祭神の魂を招いて慰霊するという意味でついている.
人が死ぬと、死者の霊魂は付近を彷徨っていると考えられていたわけである.
また、「百人一首」にも収められた式子内親王の「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする」の「玉の緒」は、
魂の緒(紐)で、身体と魂を繋げているものの意味である.
これが切れると命が絶えるというのである.
逆に、緒が切れないうちは、身体の外に出て行っても呼び戻せると考えたのであろう.
古代中国でも招魂というものはあったが、葬式は、盛大に泣くのがよいというので泣き女が雇われたものの、招魂自体は静かに行う.
「魏志倭人伝」にわざわざ書かれたのは、中国式でない、つまり、正しくない蛮習と考えられたからである.
2022.2/5
Up
Down
#377
不浄ではないのに、忌避すべきというのは不思議な話ではある.
ただ、肉食や音楽が禁止となっているのは、これが楽しみになるからと考えれば分からないでもない.
つまり、肉食も、音楽も、贅沢な暮らしである.
そうではなく、散斎の間は、身を慎んで、質素に暮らせと命令しているのである.
ただ、「大宝律令」の肉食禁止令は、「喪を弔い、病を問う」ことと同列に並んでおり、これらは「穢悪の事に預からず」にかからない.
しかし、「刑殺判(ことわ)らず、罪人を決罰せず」はともかくとして、死や病は最大の不浄ではないだろうか.
実際、中国の条文に「弔喪問疾判署刑殺文書及決罰者」と、これらが入っている.
別に、不浄のものに関係しないという文面がないので、祭に不浄のものを入れてはいけないという理由だろうと考えられる.
ところが、「大宝律令」の文面から考えるとこ、死や病は不浄ではないということになるので、おかしいのではないかと思われる方も多いと思う.
ただ、#311で紹介した「始死停喪十余日当時不食肉(始め死するや停喪十余日、時に当りて肉を食はず)」という「魏志倭人伝」の文の後に、
「喪主哭泣他人就歌舞飲酒(喪主は哭泣(こっきゅう)し、他人は歌舞、飲酒に就く)」とある.
人が死ぬと10日間あまり服喪し、その間、肉を食べない.
そして、喪主は泣き叫ぶが、他は歌い踊り、酒を飲むというのである.
つまり、宴会であるが、実は、私の田舎では、数十年前まで同様のことを行っていた.
葬式となると、供養と称して顔も知らない親戚や近所の人が集まり、酒を飲んで宴会を開いていたのである.
いわゆる御斎(おとき)であるが、中には博打を打つ者さえいたので、酒を嗜まない私達は、眉を顰めていた.
つまり、今は知らないが、つい最近まで倭人の風習が残っていたわけである.
もっとも、民俗学の方では、大騒ぎをすることにより、死者の魂を呼び戻そうとした名残と考えられている.
靖国神社の前身は東京招魂社というが、この招魂は、祭神の魂を招いて慰霊するという意味でついている.
人が死ぬと、死者の霊魂は付近を彷徨っていると考えられていたわけである.
また、「百人一首」にも収められた式子内親王の「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする」の「玉の緒」は、
魂の緒(紐)で、身体と魂を繋げているものの意味である.
これが切れると命が絶えるというのである.
逆に、緒が切れないうちは、身体の外に出て行っても呼び戻せると考えたのであろう.
古代中国でも招魂というものはあったが、葬式は、盛大に泣くのがよいというので泣き女が雇われたものの、招魂自体は静かに行う.
「魏志倭人伝」にわざわざ書かれたのは、中国式でない、つまり、正しくない蛮習と考えられたからである.
2022.2/5
Up Down
#378
鈴本という人がおり、鈴本演芸場という存在があるにも関わらず、よく鈴木と間違えられていた.
これは、鈴木という苗字が一番多いとされた時代があり、今でも日本第2位とか3位の大姓だからである.
その上、鈴という漢字を使う苗字は、他にはあまりなく、苗字で鈴という字を見ると鈴木だと思ってしまうからである.
しかし、そのように珍しい鈴の字を使う鈴木姓がなぜ天下の大姓なのかというと、熊野信仰が絡んでくる.
熊野の神官穂積氏の本家と目され、南方熊楠の名の由来になった藤白神社の鈴木氏があり、熊野信仰を各地に広めた際に、信者に自分の苗字を与えたからである.
そして、この鈴木というのは、異説もあるが、棒に鈴をつけた神具である.
神楽舞の際に巫女が手に持って鳴らす神楽鈴というのがあるが、あの棒を槍のように長くしたものである.
人が死ぬと、地面を撞いて鈴を鳴らし、魂を呼ぼうとしたのである.
神を呼ぶというのだから、目的は異なるが、神殿の賽銭箱の上にある緒のついた巨大な鈴(本坪鈴)もそうである.
お守りについている鈴も、神を呼ぶためのものであろう.
もっとも、縄文時代の遺跡から出るものは、焼き物の土鈴であるが、やがて、金属製のものが出てくる.
銅鐸もこの一種である.
鐸は、木鐸、風鐸等の言葉で分かるように鈴の一種だからである.
実際、中に砂が詰まった状態の銅鐸をコンピューター断層撮影(CT)スキャンをしたところ、
内部に舌(ぜつ)と呼ばれる金属製の棒が見られ、打ち鳴らしたことによる摩耗部も確認されている.
銅鐸の使用法や、正確な目的は不明だが、弥生時代に巨大化すると舌のないものも増えてくるものの、
本来は鈴であり、神を呼ぶため、あるいは招魂のために作られたのではないかと思う.
また、死者ではないが、アマテラスが天岩戸に隠れた際、外で大騒ぎをして連れ戻すという神話がある.
アマノウズメなどはストリップまで披露しているわけだが、この神話を太陽の死と再生と考えれば、この範疇に入れてもよいである.
死ぬ時でそうであるのなら、病の時はどうなのだろう.
私の記憶では、死んでから葬式の間、つまり、通夜から埋葬の間だけだったが、臨終の際にも行われていたのかもしれない.
家族にとって、通夜で大騒ぎされるのは迷惑だが、他の人にとっては、酒を飲んで騒げる貴重なハレの場である.
だとすれば、「喪を弔い、病を問う」ことは、身を慎んで質素にする場ではないと、当時の日本人は考えていたのかもしれない.
2022.2/7
Up
Down
#378
鈴本という人がおり、鈴本演芸場という存在があるにも関わらず、よく鈴木と間違えられていた.
これは、鈴木という苗字が一番多いとされた時代があり、今でも日本第2位とか3位の大姓だからである.
その上、鈴という漢字を使う苗字は、他にはあまりなく、苗字で鈴という字を見ると鈴木だと思ってしまうからである.
しかし、そのように珍しい鈴の字を使う鈴木姓がなぜ天下の大姓なのかというと、熊野信仰が絡んでくる.
熊野の神官穂積氏の本家と目され、南方熊楠の名の由来になった藤白神社の鈴木氏があり、熊野信仰を各地に広めた際に、信者に自分の苗字を与えたからである.
そして、この鈴木というのは、異説もあるが、棒に鈴をつけた神具である.
神楽舞の際に巫女が手に持って鳴らす神楽鈴というのがあるが、あの棒を槍のように長くしたものである.
人が死ぬと、地面を撞いて鈴を鳴らし、魂を呼ぼうとしたのである.
神を呼ぶというのだから、目的は異なるが、神殿の賽銭箱の上にある緒のついた巨大な鈴(本坪鈴)もそうである.
お守りについている鈴も、神を呼ぶためのものであろう.
もっとも、縄文時代の遺跡から出るものは、焼き物の土鈴であるが、やがて、金属製のものが出てくる.
銅鐸もこの一種である.
鐸は、木鐸、風鐸等の言葉で分かるように鈴の一種だからである.
実際、中に砂が詰まった状態の銅鐸をコンピューター断層撮影(CT)スキャンをしたところ、
内部に舌(ぜつ)と呼ばれる金属製の棒が見られ、打ち鳴らしたことによる摩耗部も確認されている.
銅鐸の使用法や、正確な目的は不明だが、弥生時代に巨大化すると舌のないものも増えてくるものの、
本来は鈴であり、神を呼ぶため、あるいは招魂のために作られたのではないかと思う.
また、死者ではないが、アマテラスが天岩戸に隠れた際、外で大騒ぎをして連れ戻すという神話がある.
アマノウズメなどはストリップまで披露しているわけだが、この神話を太陽の死と再生と考えれば、この範疇に入れてもよいである.
死ぬ時でそうであるのなら、病の時はどうなのだろう.
私の記憶では、死んでから葬式の間、つまり、通夜から埋葬の間だけだったが、臨終の際にも行われていたのかもしれない.
家族にとって、通夜で大騒ぎされるのは迷惑だが、他の人にとっては、酒を飲んで騒げる貴重なハレの場である.
だとすれば、「喪を弔い、病を問う」ことは、身を慎んで質素にする場ではないと、当時の日本人は考えていたのかもしれない.
2022.2/7
Up Down
#379
中世の日本に来た西洋人が驚いたことは数多いが、簡単に人が殺されるというのもその一つである.
たとえば、フロイスは「日本人は、動物を殺すのを見ると仰天するが、人殺しは普通である」と書いている.
この時代のヨーロッパの人達の命が安くなかったという意味ではない.
かの悪名高い異端審査の時代だからである.
したがって、その彼等が驚くのだからということにはなる.
ただ、9歳でポルトガルの宮廷に、16歳でイエズス会に入り、インドのゴアに渡ったフロイスが、母国の実情をどれだけ知っていたかは不明である.
また、戦国時代と奈良時代以前とを一緒にするのもどうかと思うが、
「刑殺判(ことわ)らず、罪人決罰せず」というのが不浄でないとすれば、このあたりに根拠があるのかもしれない.
「養老律令」の刑法である「賊盗律」等には死罪の規定があったからである.
方法として絞と斬の2つがあり、絞は絞首刑だが、2本の綱で罪人の首を挟んで、左右逆方向に絞るという、時間のかかる残酷なものであった.
しかし、首を切り落とす斬首刑のほうが重いとされた.
これは、時間がかかるほうが、恩赦が出る可能性が少しでも高まるからという理由であった.
他に、首を切り落とされたら、肉体の復活の可能性が絶たれるからというものがあった.
招魂である.
そして、この両方とも市で行われた.
高位の者や女性の場合はこの限りではなかったようであるが、公開処刑である.
異端審査もそうだが、フランスでギヨチンが猛威を振るっていた恐怖政治の時代等、公開処刑は多くの観客を集めていた.
日本でもそうであったと思われる.
一応、刑部省が初審を行った後、太政官による確認がなされ、執行にあたっては天皇に3回覆奏することとなっていた.
ただ、平安時代に嵯峨天皇が盗犯に対する死刑を停止したというように、窃盗でも死刑になる場合があった.
もちろん、殺人罪の場合、相手が死ななくても絞、死んだ場合は斬である.
したがって、死刑に対するハードルは低く、冬季に実施が限定されていたため、毎日のように行われていた場合もあると思われる.
そのような状況の中で、不浄のこととは考えられなかった可能性はある.
それどころか、当たり前のこと、あるいは、正義を行っているとして楽しく思う可能性もあるのである.
2022.2/11
Up
Down
#379
中世の日本に来た西洋人が驚いたことは数多いが、簡単に人が殺されるというのもその一つである.
たとえば、フロイスは「日本人は、動物を殺すのを見ると仰天するが、人殺しは普通である」と書いている.
この時代のヨーロッパの人達の命が安くなかったという意味ではない.
かの悪名高い異端審査の時代だからである.
したがって、その彼等が驚くのだからということにはなる.
ただ、9歳でポルトガルの宮廷に、16歳でイエズス会に入り、インドのゴアに渡ったフロイスが、母国の実情をどれだけ知っていたかは不明である.
また、戦国時代と奈良時代以前とを一緒にするのもどうかと思うが、
「刑殺判(ことわ)らず、罪人決罰せず」というのが不浄でないとすれば、このあたりに根拠があるのかもしれない.
「養老律令」の刑法である「賊盗律」等には死罪の規定があったからである.
方法として絞と斬の2つがあり、絞は絞首刑だが、2本の綱で罪人の首を挟んで、左右逆方向に絞るという、時間のかかる残酷なものであった.
しかし、首を切り落とす斬首刑のほうが重いとされた.
これは、時間がかかるほうが、恩赦が出る可能性が少しでも高まるからという理由であった.
他に、首を切り落とされたら、肉体の復活の可能性が絶たれるからというものがあった.
招魂である.
そして、この両方とも市で行われた.
高位の者や女性の場合はこの限りではなかったようであるが、公開処刑である.
異端審査もそうだが、フランスでギヨチンが猛威を振るっていた恐怖政治の時代等、公開処刑は多くの観客を集めていた.
日本でもそうであったと思われる.
一応、刑部省が初審を行った後、太政官による確認がなされ、執行にあたっては天皇に3回覆奏することとなっていた.
ただ、平安時代に嵯峨天皇が盗犯に対する死刑を停止したというように、窃盗でも死刑になる場合があった.
もちろん、殺人罪の場合、相手が死ななくても絞、死んだ場合は斬である.
したがって、死刑に対するハードルは低く、冬季に実施が限定されていたため、毎日のように行われていた場合もあると思われる.
そのような状況の中で、不浄のこととは考えられなかった可能性はある.
それどころか、当たり前のこと、あるいは、正義を行っているとして楽しく思う可能性もあるのである.
2022.2/11
Up Down
#380
もっとも、不殺生戒というのはそれなりに重視されたようである.
#374に述べた天武の放生会は、本邦における最初ではあるが、これより前、578年に、敏達天皇は毎月六斎日に殺生禁断をせよと、畿内に命令している.
この六斎日というのは毎月8、14、15、23、29、30の6日間は殺さず、盗まず、婬せず等の八斎戒を守るという仏教行事である.
611年には、聖徳太子が推古天皇の遊猟を諫めたという記録もあるが、これも仏教の不殺生戒に由来するものであろう.
天武以降では、689年に持統天皇が、近畿を中心とする数か所に殺生禁断の地が設けさせ、定期的に放生会を開いている.
また、722年に元正天皇が、730年と732年に聖武天皇が、755年、756年と758年に孝謙天皇が、770年には称徳天皇が殺生や肉食の禁止令を出している.
ただし、これらは、六斎日の殺生禁止を除くと、すべて、日照りや旱魃、天皇、その親の健康状態の悪化や服喪のためである.
したがって、これらは、期日指定があるものであり、肉食というより、美食を慎むという意味で行われていると考えたほうがよい.
そして、その起源は、「魏志倭人伝」に登場する持衰(じさい)であると考えられる.
持衰は、#377の倭人の葬儀の記事の直後に、倭人が中国に渡る際には「恒使一人不梳頭不去*幾蝨衣服垢汚不食肉不近婦人
(恒に一人をして、頭を梳(くしけず)らず、*幾蝨(きしつ)を去らず、衣服は垢汚(こうお)し、肉を食らわず、婦人を近づけず)」とあるものである.
いつも一人の髪を梳(と)かさせず、シラミを取らせず、衣服を垢で汚れたままで、肉を食べさせず、女性を近づけない」としたのである.
不潔にし、肉食や性交をさせない者を1人出すことによって、航海の安全を願ったわけである.
つまり、昔から日本には、誰かが、何らかの我慢をすることにより、災禍をやり過ごせるという考えがあったということになる.
上記の肉食禁止令も我慢であり、身を慎むことである.
それによって、災禍をやり過ごせると信じられていたのである.
そして、時には命がけで臨んだようである.
「後漢書」に「若在塗吉利、則雇以財物、如病疾遭害、以爲持衰不謹、便共殺之
(若し、塗(みち)に在りて吉利なれば、則ち財物を以て雇ひ、病疾の如き害に遭へば以て持衰が謹しまずと為し、便ち共に之を殺す)」
道中、問題がなければ財貨を支払い、病人が出たら、持衰が慎まなかったからだとして皆で殺してしまうとあるからである.
*幾は虫偏がある.
2022.2/14
Up
Down
#380
もっとも、不殺生戒というのはそれなりに重視されたようである.
#374に述べた天武の放生会は、本邦における最初ではあるが、これより前、578年に、敏達天皇は毎月六斎日に殺生禁断をせよと、畿内に命令している.
この六斎日というのは毎月8、14、15、23、29、30の6日間は殺さず、盗まず、婬せず等の八斎戒を守るという仏教行事である.
611年には、聖徳太子が推古天皇の遊猟を諫めたという記録もあるが、これも仏教の不殺生戒に由来するものであろう.
天武以降では、689年に持統天皇が、近畿を中心とする数か所に殺生禁断の地が設けさせ、定期的に放生会を開いている.
また、722年に元正天皇が、730年と732年に聖武天皇が、755年、756年と758年に孝謙天皇が、770年には称徳天皇が殺生や肉食の禁止令を出している.
ただし、これらは、六斎日の殺生禁止を除くと、すべて、日照りや旱魃、天皇、その親の健康状態の悪化や服喪のためである.
したがって、これらは、期日指定があるものであり、肉食というより、美食を慎むという意味で行われていると考えたほうがよい.
そして、その起源は、「魏志倭人伝」に登場する持衰(じさい)であると考えられる.
持衰は、#377の倭人の葬儀の記事の直後に、倭人が中国に渡る際には「恒使一人不梳頭不去*幾蝨衣服垢汚不食肉不近婦人
(恒に一人をして、頭を梳(くしけず)らず、*幾蝨(きしつ)を去らず、衣服は垢汚(こうお)し、肉を食らわず、婦人を近づけず)」とあるものである.
いつも一人の髪を梳(と)かさせず、シラミを取らせず、衣服を垢で汚れたままで、肉を食べさせず、女性を近づけない」としたのである.
不潔にし、肉食や性交をさせない者を1人出すことによって、航海の安全を願ったわけである.
つまり、昔から日本には、誰かが、何らかの我慢をすることにより、災禍をやり過ごせるという考えがあったということになる.
上記の肉食禁止令も我慢であり、身を慎むことである.
それによって、災禍をやり過ごせると信じられていたのである.
そして、時には命がけで臨んだようである.
「後漢書」に「若在塗吉利、則雇以財物、如病疾遭害、以爲持衰不謹、便共殺之
(若し、塗(みち)に在りて吉利なれば、則ち財物を以て雇ひ、病疾の如き害に遭へば以て持衰が謹しまずと為し、便ち共に之を殺す)」
道中、問題がなければ財貨を支払い、病人が出たら、持衰が慎まなかったからだとして皆で殺してしまうとあるからである.
*幾は虫偏がある.
2022.2/14
Up Down
#381
民俗学者の大林太良によると、インドネシアのセラム島では、長期航海中、持衰のような人物、通常は同じ村の少女が1人、陸上に残されるそうである.
航海の間、少女は何もすることは許されず、家から出ることも許されない.
もし、彼女が病気になると、それは船に不幸があったということであり、死ぬようなことがあれば、沈んだと考えられる.
また、船に不幸があった場合、少女は殺されるという.
日本人は、黒潮に乗って南方から来たという説があり、語彙も似た点が多い.
もし、そうであるのならば、持衰のルーツもこの辺りにあるのかもしれないが、だとすれば、倭人の船に乗っていなくてもよいとなる.
実際、「万葉集」には「梳毛見自屋中毛波可自久左麻久良多婢由久伎美乎伊波布等毛比*氏
(櫛も見じ、屋内(やぬち)も掃かじ、草枕、旅行く君をいはふと思ひて」という作者未詳の歌がある.
天平勝宝4(752)年、遣唐使出立の際に歌われたものである.
櫛も使わず、家の中も掃かず、旅に出る君の無事を祈っていますというのであるから、まさしく持衰である.
そして、これが持衰であるのならば、「婦人を近づけず」とあるため、男性であると思われてがちであるが、女性の可能性もあるということになる.
実際、歴史学者の義江明子の研究によると、倭国の社会は、男女間の性差がきわめて少なかったそうである.
このため、男性優先の中国の視点から誤解されることも多く、たとえば、倭人は多くの妻を持つという記述が「魏志倭人伝」にあるが、誤断だそうである.
というのは、少なくとも平安時代まで、日本は妻問(つまどい)婚であったからである.
妻問婚は、招婿婚ともいうが、男性が女性のもとに通うというものである.
このため、男性に何人の妻がいると聞けば、過去も、現在進行形も含めて数人の妻がいると答える.
しかし、女性に何人の夫がいるかと聞いても、同様の答えが戻ってくるのである.
つまり、一夫多妻ではなく、多夫多妻であったのである.
しかし、このことは、当時の中国人には理解の外であった.
このため、「後漢書」においては、整合性を求めるあまり、「国多女子(国女子多し)」と書き加えている.
もちろん、日本国内から出土する人骨の男女比は、これを否定している.
したがって、少数の例だけを見ての判断である可能性もあるし、女性にそのようなことをさせるわけがないという予断に基づくものかもしれないのである.
また、上記の「万葉集」の歌も、女性に限定できないという考え方もできる.
ただ、女性の遣唐使はいないので、この歌を作ったのは女性であろうと判断しているだけである.
*氏は下に一がある.
2022.2/17
Up
Down
#381
民俗学者の大林太良によると、インドネシアのセラム島では、長期航海中、持衰のような人物、通常は同じ村の少女が1人、陸上に残されるそうである.
航海の間、少女は何もすることは許されず、家から出ることも許されない.
もし、彼女が病気になると、それは船に不幸があったということであり、死ぬようなことがあれば、沈んだと考えられる.
また、船に不幸があった場合、少女は殺されるという.
日本人は、黒潮に乗って南方から来たという説があり、語彙も似た点が多い.
もし、そうであるのならば、持衰のルーツもこの辺りにあるのかもしれないが、だとすれば、倭人の船に乗っていなくてもよいとなる.
実際、「万葉集」には「梳毛見自屋中毛波可自久左麻久良多婢由久伎美乎伊波布等毛比*氏
(櫛も見じ、屋内(やぬち)も掃かじ、草枕、旅行く君をいはふと思ひて」という作者未詳の歌がある.
天平勝宝4(752)年、遣唐使出立の際に歌われたものである.
櫛も使わず、家の中も掃かず、旅に出る君の無事を祈っていますというのであるから、まさしく持衰である.
そして、これが持衰であるのならば、「婦人を近づけず」とあるため、男性であると思われてがちであるが、女性の可能性もあるということになる.
実際、歴史学者の義江明子の研究によると、倭国の社会は、男女間の性差がきわめて少なかったそうである.
このため、男性優先の中国の視点から誤解されることも多く、たとえば、倭人は多くの妻を持つという記述が「魏志倭人伝」にあるが、誤断だそうである.
というのは、少なくとも平安時代まで、日本は妻問(つまどい)婚であったからである.
妻問婚は、招婿婚ともいうが、男性が女性のもとに通うというものである.
このため、男性に何人の妻がいると聞けば、過去も、現在進行形も含めて数人の妻がいると答える.
しかし、女性に何人の夫がいるかと聞いても、同様の答えが戻ってくるのである.
つまり、一夫多妻ではなく、多夫多妻であったのである.
しかし、このことは、当時の中国人には理解の外であった.
このため、「後漢書」においては、整合性を求めるあまり、「国多女子(国女子多し)」と書き加えている.
もちろん、日本国内から出土する人骨の男女比は、これを否定している.
したがって、少数の例だけを見ての判断である可能性もあるし、女性にそのようなことをさせるわけがないという予断に基づくものかもしれないのである.
また、上記の「万葉集」の歌も、女性に限定できないという考え方もできる.
ただ、女性の遣唐使はいないので、この歌を作ったのは女性であろうと判断しているだけである.
*氏は下に一がある.
2022.2/17
Up Down
#382
持衰の衰は、衣の中に毛状のものが垂れる形を入れたもので、蓑(みの)の原型とされるが、蓑に似た喪服の意味でも使われる.
ここから、衰えるという意味も発生しているが、持衰は喪服をまとっているの意味である.
そして、中国の葬儀は、現代のものの中には派手なものも多いが、古代は身を慎んで哀悼することが多いようである.
したがって、「喪主は哭泣し、他人は歌舞、飲酒に就く」というのは、中国流と異なるために記されたものである.
この持衰の話は、この葬儀の話の後にあるが、葬儀の関連で置かれたものであろう.
ところで、持衰は自斎であるという考えがある.
自斎という言葉は辞書にないが、自ら物忌するということであろう.
斎には清めるという意味があるからである.
しかし、持衰は、穢れや汚物を引き受ける行為ではあっても、清める行為とはいいがたい.
「じさい」という音が共通するだけである.
実際、「魏志倭人伝」には、この葬儀の記事の直後、持衰の記事との間に「已葬挙家詣水中澡浴以如練沐
(已(すで)に葬れば、挙家(きょか)水中に詣(いた)りて澡浴し、以て練沐(れんもく)の如くす)」とある.
練沐は、よく分からないが、中国では葬儀の1年後から喪服を脱いで練絹(ねりぎぬ)を着るとあるので、それを着て沐浴するという意味であろう.
ここでは、挙家とあるので、葬儀が済むと、一家を挙げて沐浴するというのである.
自斎というものがあるとすれば、むしろ、こちらであろう.
一般に、禊(みそぎ)と呼ばれるものである.
禊は、身清(みすす)ぎからだという説もあるが、身削(みそ)ぎの意味であろう.
穢れや汚れを身体から削ぐのである.
しかし、死が不浄でないとすれば、そのようなことをする必要もない.
にもかかわらず、一家を挙げて沐浴するのは、何らかの穢れがついたからである.
その穢れが死でないとしたら、何だろう.
2022.2/20
Down
#382
持衰の衰は、衣の中に毛状のものが垂れる形を入れたもので、蓑(みの)の原型とされるが、蓑に似た喪服の意味でも使われる.
ここから、衰えるという意味も発生しているが、持衰は喪服をまとっているの意味である.
そして、中国の葬儀は、現代のものの中には派手なものも多いが、古代は身を慎んで哀悼することが多いようである.
したがって、「喪主は哭泣し、他人は歌舞、飲酒に就く」というのは、中国流と異なるために記されたものである.
この持衰の話は、この葬儀の話の後にあるが、葬儀の関連で置かれたものであろう.
ところで、持衰は自斎であるという考えがある.
自斎という言葉は辞書にないが、自ら物忌するということであろう.
斎には清めるという意味があるからである.
しかし、持衰は、穢れや汚物を引き受ける行為ではあっても、清める行為とはいいがたい.
「じさい」という音が共通するだけである.
実際、「魏志倭人伝」には、この葬儀の記事の直後、持衰の記事との間に「已葬挙家詣水中澡浴以如練沐
(已(すで)に葬れば、挙家(きょか)水中に詣(いた)りて澡浴し、以て練沐(れんもく)の如くす)」とある.
練沐は、よく分からないが、中国では葬儀の1年後から喪服を脱いで練絹(ねりぎぬ)を着るとあるので、それを着て沐浴するという意味であろう.
ここでは、挙家とあるので、葬儀が済むと、一家を挙げて沐浴するというのである.
自斎というものがあるとすれば、むしろ、こちらであろう.
一般に、禊(みそぎ)と呼ばれるものである.
禊は、身清(みすす)ぎからだという説もあるが、身削(みそ)ぎの意味であろう.
穢れや汚れを身体から削ぐのである.
しかし、死が不浄でないとすれば、そのようなことをする必要もない.
にもかかわらず、一家を挙げて沐浴するのは、何らかの穢れがついたからである.
その穢れが死でないとしたら、何だろう.
2022.2/20
PREVIOUS ☆ NEXT
Since 1 Jan.
2022.
Last up-dated,
26 Feb. 2022.


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
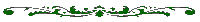 Sasayaki011.
Sasayaki011.
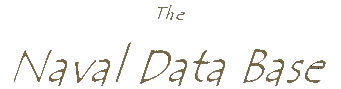 Ver.1.22a.
Ver.1.22a.
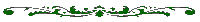 Copyright
(c)
hush ,2001-22. Allrights Reserved.
Copyright
(c)
hush ,2001-22. Allrights Reserved.
Up
動画