Down
無用の記録
1-
51- 101-
150- 191-
229- 255-
293- 311-
333- 361-
383- 402-
412- 422-
trivia's
trivia
Up
Down
#422
「かちかち山」には狸汁が登場する.
この昔話は、室町時代には成立していたといわれるが、現存する最古のものは、「むぢなの敵討」と呼ばれるものである.
これは、赤本と呼ばれる江戸初期に刊行されていた草双紙の一種で、子供向けの絵入りの本である.
つまり、少なくとも江戸時代の初めには、狸汁と聞いて驚くような食生活はしていなかったということになる.
そうでなければ、子供用の本に狸を殺して食べてしまおうなどという話は登場しない.
むしろ、現代の私達のほうが、狸の知略に負けた婆が殺され、汁になって爺に食われるというほうが衝撃度は強いと思う
(もっとも、現在の童話では随分と変化しているので、本来の話を知らない人のほうが多いかもしれない).
当時の人々が同様の感覚を持つかどうかは分からないが、もしも肉食をしていないのなら、婆の狸を捕まえて食べようというほうに衝撃を受けると思う.
しかし、この話は江戸時代を通じて生き残り、現在に伝わっているということは、そのことに、ことさらの忌避感を持たなかったということになる.
つまり、江戸時代の人々は、肉食を普通のものと捉えていたことになる.
2023.1/10
Up Down
#423
実際、#316に記した江戸時代初期の1636年の手書きの版が残る「料理物語」には、第五
獣(けだもの)ノ部に、「鹿、狸、猪、兎、川うそ、熊、いぬ」と並んでおり、
狸のところには「汁 でんがく 山椒みそ」とある.
汁の他、田楽、山椒味噌で食べたらしい.
狸汁については「野はしりは皮をはぐ也みたぬきはやきはぎよし
味噌汁にて仕立候 妻は大こんごばう其外色色 すい口にんにくだし酒塩」とかなり詳しい.
文中にある「みたぬき」は、「文明本節用集https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286982(454コマ)」にある猯(みたぬき)であろう.
猯は「まみ」とも読む.
東京に狸穴と書いて「まみあな」と読むところがあるが、その「まみ」である.
では、狸と断定してよいかというと、これがそう簡単ではない.
この語は、穴熊を含むからである.
分類学上、狸は犬科であり、穴熊は鼬(イタチ)科である.
そのようなものを混同するとはと言われそうだが、昨今では麝香猫科の白鼻芯(ハクビシン)や
浣熊(アライグマ)科の浣熊までが狸と間違えられるという現実を考えると仕方ないことかもしれない.
だいたい、狸という漢字にしたって、本来は山猫なので、狸の話を調べていると混乱してくる.
2023.1/11
Up
Down
#423
実際、#316に記した江戸時代初期の1636年の手書きの版が残る「料理物語」には、第五
獣(けだもの)ノ部に、「鹿、狸、猪、兎、川うそ、熊、いぬ」と並んでおり、
狸のところには「汁 でんがく 山椒みそ」とある.
汁の他、田楽、山椒味噌で食べたらしい.
狸汁については「野はしりは皮をはぐ也みたぬきはやきはぎよし
味噌汁にて仕立候 妻は大こんごばう其外色色 すい口にんにくだし酒塩」とかなり詳しい.
文中にある「みたぬき」は、「文明本節用集https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286982(454コマ)」にある猯(みたぬき)であろう.
猯は「まみ」とも読む.
東京に狸穴と書いて「まみあな」と読むところがあるが、その「まみ」である.
では、狸と断定してよいかというと、これがそう簡単ではない.
この語は、穴熊を含むからである.
分類学上、狸は犬科であり、穴熊は鼬(イタチ)科である.
そのようなものを混同するとはと言われそうだが、昨今では麝香猫科の白鼻芯(ハクビシン)や
浣熊(アライグマ)科の浣熊までが狸と間違えられるという現実を考えると仕方ないことかもしれない.
だいたい、狸という漢字にしたって、本来は山猫なので、狸の話を調べていると混乱してくる.
2023.1/11
Up Down
#424
「野はしり」はここにしか登場しないらしく、「日本国語大辞典(第1版)」にも収録されていない.
したがって、簡単には特定できないのだが、「みたぬきはやきはぎよし」とある.
焼き剥ぎ、つまり、丸焼きにして皮を剥ぐのがよいというのである.
つまり、「みたぬき」は、焼いて毛を取ってしまうのが楽だというのである.
その理由を考えると、毛皮に有用性がないからということになる.
逆に、「野はしりは皮をはぐ也」とあるのだから、「野はしり」の毛皮は有用性があるということになる.
このため、「野はしり」とあるのが狸、「みたぬき」が穴熊であると考えられている.
狸の毛皮は珍重されるが、穴熊はそうでないからである.
穴熊の毛は剛く、皮下脂肪が多い.
これに対し、狸の毛は毛筆の穂先に使われるぐらい柔らかく、「取らぬ狸の皮算用」という諺があるように、毛皮は高価で取引される.
このため、狸は1920年代後半から約30年間にわたって当時のソ連に導入されたぐらいである.
これは赤軍の衣料のためであったが、戦後、その必要がなくなって放たれた狸は東ヨーロッパ中に広まり、現在ではさらに広がっている.
このため、本来、北東アジアにしかいなかった狸の分布領域はユーラシア大陸の東西に分かれて広まることになったが、狂犬病を伝播させるものとして問題視されている.
2023.1/12
Up
Down
#424
「野はしり」はここにしか登場しないらしく、「日本国語大辞典(第1版)」にも収録されていない.
したがって、簡単には特定できないのだが、「みたぬきはやきはぎよし」とある.
焼き剥ぎ、つまり、丸焼きにして皮を剥ぐのがよいというのである.
つまり、「みたぬき」は、焼いて毛を取ってしまうのが楽だというのである.
その理由を考えると、毛皮に有用性がないからということになる.
逆に、「野はしりは皮をはぐ也」とあるのだから、「野はしり」の毛皮は有用性があるということになる.
このため、「野はしり」とあるのが狸、「みたぬき」が穴熊であると考えられている.
狸の毛皮は珍重されるが、穴熊はそうでないからである.
穴熊の毛は剛く、皮下脂肪が多い.
これに対し、狸の毛は毛筆の穂先に使われるぐらい柔らかく、「取らぬ狸の皮算用」という諺があるように、毛皮は高価で取引される.
このため、狸は1920年代後半から約30年間にわたって当時のソ連に導入されたぐらいである.
これは赤軍の衣料のためであったが、戦後、その必要がなくなって放たれた狸は東ヨーロッパ中に広まり、現在ではさらに広がっている.
このため、本来、北東アジアにしかいなかった狸の分布領域はユーラシア大陸の東西に分かれて広まることになったが、狂犬病を伝播させるものとして問題視されている.
2023.1/12
Up Down
#425
一方、肉の評価は逆転する.
したがって、この「かちかち山」のもとが「むぢなの敵討」だというのは興味深い.
むじな(狢)は、地域によって異なるが、狸ではなく、穴熊を指すことが多く、穴熊は狸より美味しいとされるからである.
というより、狸はあまり美味しいといわれないし、獣臭がきつく、人によっては食べられたものではないとさえいう.
たとえば、1709年に刊行された貝原益軒の「大和本草(10コマ)」では、猯(貉偏を獣偏で代用した)をミタヌキとし「脂多ク味ヨクして野猪ノ如シ肉ヤハラカ也」と評している.
脂肪分が多くて味がよく猪のようだが、肉は柔らかいとかなりの褒めようである.
これが穴熊であることは「其ノ四足ノ指各五恰如人ノ手指ノ(その四足の指それぞれ五つ、あたかも人の手指のごとし)」とあることからも確かである.
狸は4本指だがらである.
また、狸汁と言いながら、狸を使うとおいしくないので、穴熊を使うことも多いそうである.
したがって、「むぢなの敵討」の狢が穴熊であるのなら、どちらがより美味しいかを知っていたことになる.
もっとも、本作に描かれている「むぢな」の絵は、顔の中央に黒い部分があり、狸でも、穴熊でもない.
江戸時代にもいたかもしれないとされる白鼻芯でもない.
もちろん、浣熊でも、山猫でもない.
耳や尾の形状は狸に似るが、狸の特徴である脚部の黒さもない.
したがって、正解は藪の中である.
2023.1/13
参考:白鼻芯、狸、穴熊、浣熊の見分け方.
Up
Down
#425
一方、肉の評価は逆転する.
したがって、この「かちかち山」のもとが「むぢなの敵討」だというのは興味深い.
むじな(狢)は、地域によって異なるが、狸ではなく、穴熊を指すことが多く、穴熊は狸より美味しいとされるからである.
というより、狸はあまり美味しいといわれないし、獣臭がきつく、人によっては食べられたものではないとさえいう.
たとえば、1709年に刊行された貝原益軒の「大和本草(10コマ)」では、猯(貉偏を獣偏で代用した)をミタヌキとし「脂多ク味ヨクして野猪ノ如シ肉ヤハラカ也」と評している.
脂肪分が多くて味がよく猪のようだが、肉は柔らかいとかなりの褒めようである.
これが穴熊であることは「其ノ四足ノ指各五恰如人ノ手指ノ(その四足の指それぞれ五つ、あたかも人の手指のごとし)」とあることからも確かである.
狸は4本指だがらである.
また、狸汁と言いながら、狸を使うとおいしくないので、穴熊を使うことも多いそうである.
したがって、「むぢなの敵討」の狢が穴熊であるのなら、どちらがより美味しいかを知っていたことになる.
もっとも、本作に描かれている「むぢな」の絵は、顔の中央に黒い部分があり、狸でも、穴熊でもない.
江戸時代にもいたかもしれないとされる白鼻芯でもない.
もちろん、浣熊でも、山猫でもない.
耳や尾の形状は狸に似るが、狸の特徴である脚部の黒さもない.
したがって、正解は藪の中である.
2023.1/13
参考:白鼻芯、狸、穴熊、浣熊の見分け方.
Up Down
#426
現在の狸汁には、獣肉が使用されていないものも多い.
レシピを探しても、蒟蒻(こんにゃく)を油で炒め、牛蒡(ごぼう)、大根と一緒に煮たものと出てくることが多い.
これは、羊羹が、本来、羊の羹(あつもの=スープ)で、羊肉を小豆で代用したように、狸の肉を触感の似た油で炒めた蒟蒻にしたからである.
川路聖謨(としあきら)というと、幕末、日露和親条約を調印し外国奉行になった幕臣だが1849-51年に奈良奉行を勤めている.
その時の日記「寧府紀事」の嘉永元年正月25日(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920537、22-3コマ)に、「宝蔵院は昨日稽古はしめなるに古格にて狸汁を食する也」とある.
宝蔵院は興福寺の塔頭であったが、宝蔵院流槍術で知られる.
その稽古に家人を行かせたところ、稽古始めだったので昔からの風習で狸汁が出たというのである.
「いにしへは真の狸にて稽古場に精進なかりしか今はこんにやく汁を狸汁とてくはするよし也」と続くので、以前は本物の狸を使っていたことになる.
ところが、3代目の頃に精進料理に変えたそうである.
3代目、宝蔵院胤清は1634年に生まれ99年に死んでいるので、江戸時代初期のことということになる.
これは、寺院であったこともあるだろうが、綱吉の生類憐みの令の影響も強いと思われる.
その後、1778年の「屠龍工随筆」という本にも「蒟蒻などを油で炒めて牛蒡、大根を混へて煮るを名付けて狸汁といふなり」とある.
作者の小栗百万は、旨原(しげん)という号で知られた俳人で、江戸の人であるので、この頃には、狸汁は江戸においても精進料理に転じていたのであろう.
しかしながら、「かちかち山」の狸汁は、明らかに獣肉を使用するものを指している.
実際、「屠龍工随筆」の前掲記事の直前には「肉を入れぬ先、鍋に油を別けて炒りて後、牛蒡、蘿蔔(らふ=大根)など入れて煮たるがよしと人のいへり」とあって、
以前は獣肉を使用していたようである.
2023.1/14
Up
Down
#426
現在の狸汁には、獣肉が使用されていないものも多い.
レシピを探しても、蒟蒻(こんにゃく)を油で炒め、牛蒡(ごぼう)、大根と一緒に煮たものと出てくることが多い.
これは、羊羹が、本来、羊の羹(あつもの=スープ)で、羊肉を小豆で代用したように、狸の肉を触感の似た油で炒めた蒟蒻にしたからである.
川路聖謨(としあきら)というと、幕末、日露和親条約を調印し外国奉行になった幕臣だが1849-51年に奈良奉行を勤めている.
その時の日記「寧府紀事」の嘉永元年正月25日(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920537、22-3コマ)に、「宝蔵院は昨日稽古はしめなるに古格にて狸汁を食する也」とある.
宝蔵院は興福寺の塔頭であったが、宝蔵院流槍術で知られる.
その稽古に家人を行かせたところ、稽古始めだったので昔からの風習で狸汁が出たというのである.
「いにしへは真の狸にて稽古場に精進なかりしか今はこんにやく汁を狸汁とてくはするよし也」と続くので、以前は本物の狸を使っていたことになる.
ところが、3代目の頃に精進料理に変えたそうである.
3代目、宝蔵院胤清は1634年に生まれ99年に死んでいるので、江戸時代初期のことということになる.
これは、寺院であったこともあるだろうが、綱吉の生類憐みの令の影響も強いと思われる.
その後、1778年の「屠龍工随筆」という本にも「蒟蒻などを油で炒めて牛蒡、大根を混へて煮るを名付けて狸汁といふなり」とある.
作者の小栗百万は、旨原(しげん)という号で知られた俳人で、江戸の人であるので、この頃には、狸汁は江戸においても精進料理に転じていたのであろう.
しかしながら、「かちかち山」の狸汁は、明らかに獣肉を使用するものを指している.
実際、「屠龍工随筆」の前掲記事の直前には「肉を入れぬ先、鍋に油を別けて炒りて後、牛蒡、蘿蔔(らふ=大根)など入れて煮たるがよしと人のいへり」とあって、
以前は獣肉を使用していたようである.
2023.1/14
Up Down
#427
また、江戸時代、街道筋に狸汁を提供する店が多くあったという.
これが、精進料理のそれであるか、本物の狸を使ったものかは不分明であるが、おそらくは後者であろう.
ただし、これを実証するのは難しい.
というのは、江戸時代の書で獣肉を扱ったものは少なく、狸汁の中身に狸の肉を使ったという記述は、管見の限りでは見当たらないからである.
ただ、仮名垣魯文の「安愚楽鍋」の冒頭、「開場」に「盲文爺のたぬき汁」とある.
盲文爺というのは、ももんじ(屋)のいささか趣味の悪い言い換えである.
そして、ももんじ屋は、百獣屋とも書くように、江戸近辺で獣肉を売ったり、食べさせたりしていた店のことである.
ももんじは、百獣(ももじゅう)の変化したものとも、モモンガの名との類似性を書く人もいるし、妖怪を意味する幼児語ももんじい(百々爺)に由来するともいう.
うち、江戸の両国や麹町にあったものが有名だが、江戸近郊には多くあったようである.
そのような店で食べさせている狸汁が、獣肉を使っていないわけはない.
したがって、この本の出た1872(明治4)年の段階、つまり、幕末前後において、獣肉を使った狸汁は普通にあったということになる.
2023.1/15
Up
Down
#427
また、江戸時代、街道筋に狸汁を提供する店が多くあったという.
これが、精進料理のそれであるか、本物の狸を使ったものかは不分明であるが、おそらくは後者であろう.
ただし、これを実証するのは難しい.
というのは、江戸時代の書で獣肉を扱ったものは少なく、狸汁の中身に狸の肉を使ったという記述は、管見の限りでは見当たらないからである.
ただ、仮名垣魯文の「安愚楽鍋」の冒頭、「開場」に「盲文爺のたぬき汁」とある.
盲文爺というのは、ももんじ(屋)のいささか趣味の悪い言い換えである.
そして、ももんじ屋は、百獣屋とも書くように、江戸近辺で獣肉を売ったり、食べさせたりしていた店のことである.
ももんじは、百獣(ももじゅう)の変化したものとも、モモンガの名との類似性を書く人もいるし、妖怪を意味する幼児語ももんじい(百々爺)に由来するともいう.
うち、江戸の両国や麹町にあったものが有名だが、江戸近郊には多くあったようである.
そのような店で食べさせている狸汁が、獣肉を使っていないわけはない.
したがって、この本の出た1872(明治4)年の段階、つまり、幕末前後において、獣肉を使った狸汁は普通にあったということになる.
2023.1/15
Up Down
#428
しかし、それは庶民の話であって、貴人は違うのではないかと考える人もいるかもしれない.
ただ、彦根の井伊家は、譜代大名の筆頭として、幕府に陣太鼓に使う牛皮を献上する役目を持っていた.
しかも、死んだものよりも生きた牛のほうが質がよいというので、禁止されていたはずの屠殺が公認されていた.
そして、その課程で出てくる牛肉を3代直澄の時代から将軍家に献上している.
もっとも、食用としてではない.
薬用としてである.
元禄年間(1688-1704)、江戸在勤中の同家の花木伝右衛門が「本草綱目」という中国の薬学書を読んでいて、一つの項目に着目した.
「黄牛肉佳良甘味無毒安中益気養脾胃補益腰脚(黄牛の肉は佳良にして甘味無毒、中を安んじ気を増し、脾胃を養い腰脚を補益す)」.
黄牛の肉は体によいと書かれていたのである.
この記述をもとに作られたのが反本丸(へんぽんがん)と呼ばれる丸薬である.
しかし、元禄年間というと、徳川綱吉が将軍の時代、生類憐みの令の真っ最中である.
また、花木伝右衛門という人は井伊直澄の家来であるとされるが、この頃には直澄は死んでいる.
次の直興の時には出仕しなかったということなのだろうかとも思うが、伝記が伝わっていないので不明である.
また、「本草綱目」は中国の書であるので、当然、肉の効能はたくさん出てくる.
その中で、この記述だけを重視したのはなぜかということになる.
しかも、単なる牛ではなく、黄牛である.
2023.1/16
Up
Down
#428
しかし、それは庶民の話であって、貴人は違うのではないかと考える人もいるかもしれない.
ただ、彦根の井伊家は、譜代大名の筆頭として、幕府に陣太鼓に使う牛皮を献上する役目を持っていた.
しかも、死んだものよりも生きた牛のほうが質がよいというので、禁止されていたはずの屠殺が公認されていた.
そして、その課程で出てくる牛肉を3代直澄の時代から将軍家に献上している.
もっとも、食用としてではない.
薬用としてである.
元禄年間(1688-1704)、江戸在勤中の同家の花木伝右衛門が「本草綱目」という中国の薬学書を読んでいて、一つの項目に着目した.
「黄牛肉佳良甘味無毒安中益気養脾胃補益腰脚(黄牛の肉は佳良にして甘味無毒、中を安んじ気を増し、脾胃を養い腰脚を補益す)」.
黄牛の肉は体によいと書かれていたのである.
この記述をもとに作られたのが反本丸(へんぽんがん)と呼ばれる丸薬である.
しかし、元禄年間というと、徳川綱吉が将軍の時代、生類憐みの令の真っ最中である.
また、花木伝右衛門という人は井伊直澄の家来であるとされるが、この頃には直澄は死んでいる.
次の直興の時には出仕しなかったということなのだろうかとも思うが、伝記が伝わっていないので不明である.
また、「本草綱目」は中国の書であるので、当然、肉の効能はたくさん出てくる.
その中で、この記述だけを重視したのはなぜかということになる.
しかも、単なる牛ではなく、黄牛である.
2023.1/16
Up Down
#429
黄牛と書いて「きうし」とも「あめうし」と読む.
「あめうし」は飴色をした牛の意である.
飴色の飴は水飴で、今のものは無色透明だが、かつては麦芽の影響でやや褐色を帯びていた.
したがって、褐色を帯びた色の牛となるが、和牛というと黒毛という印象が強い.
褐毛和牛というものもあるが、これは和牛にスイスのシンメンタール種を掛け合わせたものである.
当然、江戸時代にはいない.
ただし、鎌倉末期に描かれた「国牛十図」というものがあり、そこには当時の日本にいた9種の牛の図が描かれている.
9種ならば、十図ではなく九図ではないかとなるわけだが、冒頭に「一図逸スルカ」と安永7(1778)年につけられた序文にあるので、本来は十図だったのかもしれない.
それはともかくとして、その中にある筑紫牛と御厨牛はその系統の色である.
特に御厨牛は褐色と称してよい毛色で描かれている.
もっとも、御厨牛は肥前国の産とあるので、彦根のある近江国から遠く離れている.
ただ、鎌倉末期から江戸時代までの間にはかなりの期間があるので、伝わっていても不思議はない.
しかし、黄牛を「おうぎゅう、こうぎゅう」と読むと、意味が異なってくる.
コブウシまたはゼビューZebuと呼ばれるインドウシと従来の牛との交雑種を指すからである.
コブウシは、背中の肩の辺りに瘤があるためそう呼ばれるが、この瘤は、駱駝のそれとは違って筋肉ではあるものの、同様に暑さに強い.
そして、この系統の牛は日本に入ってきていなかったといわれるが、「本草綱目」にある黄牛は本種である.
2023.1/17
Up
Down
#429
黄牛と書いて「きうし」とも「あめうし」と読む.
「あめうし」は飴色をした牛の意である.
飴色の飴は水飴で、今のものは無色透明だが、かつては麦芽の影響でやや褐色を帯びていた.
したがって、褐色を帯びた色の牛となるが、和牛というと黒毛という印象が強い.
褐毛和牛というものもあるが、これは和牛にスイスのシンメンタール種を掛け合わせたものである.
当然、江戸時代にはいない.
ただし、鎌倉末期に描かれた「国牛十図」というものがあり、そこには当時の日本にいた9種の牛の図が描かれている.
9種ならば、十図ではなく九図ではないかとなるわけだが、冒頭に「一図逸スルカ」と安永7(1778)年につけられた序文にあるので、本来は十図だったのかもしれない.
それはともかくとして、その中にある筑紫牛と御厨牛はその系統の色である.
特に御厨牛は褐色と称してよい毛色で描かれている.
もっとも、御厨牛は肥前国の産とあるので、彦根のある近江国から遠く離れている.
ただ、鎌倉末期から江戸時代までの間にはかなりの期間があるので、伝わっていても不思議はない.
しかし、黄牛を「おうぎゅう、こうぎゅう」と読むと、意味が異なってくる.
コブウシまたはゼビューZebuと呼ばれるインドウシと従来の牛との交雑種を指すからである.
コブウシは、背中の肩の辺りに瘤があるためそう呼ばれるが、この瘤は、駱駝のそれとは違って筋肉ではあるものの、同様に暑さに強い.
そして、この系統の牛は日本に入ってきていなかったといわれるが、「本草綱目」にある黄牛は本種である.
2023.1/17
Up Down
#430
したがって、「本草綱目」云々は権威付けかもしれない.
ただし、薬用であったとしても牛肉が将軍家に献上されていたのは事実である.
もっとも、反本丸がどのようなものであったか、よく分かっていない.
丸薬のように思える記述もあれば、味噌漬けの牛肉だったとするものもあるからである.
ただ、毎年、井伊家から将軍や諸大名に牛肉の味噌漬けを贈るのが吉例になっていた.
干し肉が献上された記録もある.
実際、大石内蔵助から彦根産黄牛の味噌漬をおすそ分けするとした堀部弥兵衛金丸に宛てた書状が残っている.
堀部は、いわゆる赤穂47士の最高齢で、討ち入りの際には77歳であった.
このため、「養老品故其許ニハ重畳ニ存候倅主税なとにまえらせ候」とある.
老齢のそちらにはよいが、息子の主税(大石良金)には渡せられないのでと冗談を書いているので、滋養強壮薬であったのだろう.
12日としか同書には記載がないのでいつのものかは不明であるが、この書状が本物であったとすれば、討ち入りのあった1701年より前のことになる.
したがって、この時代、浅野家の家老であった内蔵助が手に入れられる程度には彦根の味噌漬け牛肉は普及していたことになる.
もしかすると、大石家のルーツは近江なので、そちら経由かもしれないが、さらにおすそ分けできるということは、もとはそれなりの量があったということである.
彦根で反本丸と印された版木が見つかっているので、広範囲に売られてもいたのであろう.
2023.1/19
Up
Down
#430
したがって、「本草綱目」云々は権威付けかもしれない.
ただし、薬用であったとしても牛肉が将軍家に献上されていたのは事実である.
もっとも、反本丸がどのようなものであったか、よく分かっていない.
丸薬のように思える記述もあれば、味噌漬けの牛肉だったとするものもあるからである.
ただ、毎年、井伊家から将軍や諸大名に牛肉の味噌漬けを贈るのが吉例になっていた.
干し肉が献上された記録もある.
実際、大石内蔵助から彦根産黄牛の味噌漬をおすそ分けするとした堀部弥兵衛金丸に宛てた書状が残っている.
堀部は、いわゆる赤穂47士の最高齢で、討ち入りの際には77歳であった.
このため、「養老品故其許ニハ重畳ニ存候倅主税なとにまえらせ候」とある.
老齢のそちらにはよいが、息子の主税(大石良金)には渡せられないのでと冗談を書いているので、滋養強壮薬であったのだろう.
12日としか同書には記載がないのでいつのものかは不明であるが、この書状が本物であったとすれば、討ち入りのあった1701年より前のことになる.
したがって、この時代、浅野家の家老であった内蔵助が手に入れられる程度には彦根の味噌漬け牛肉は普及していたことになる.
もしかすると、大石家のルーツは近江なので、そちら経由かもしれないが、さらにおすそ分けできるということは、もとはそれなりの量があったということである.
彦根で反本丸と印された版木が見つかっているので、広範囲に売られてもいたのであろう.
2023.1/19
Up Down
#431
もっとも、貴人の中には牛肉を忌避する人もいた.
たとえば、井伊直弼である.
安政の大獄で知られる直弼は、13代井伊直中の14男である.
しかも、庶子である.
このため、父の死後は部屋住みの生活であった.
ただ、当主の息子であるため、好きように生活したようで、さまざまなことに足を踏み入れ、特に茶道で有名であった.
しかしながら、兄で直中の11男直元の死により運命が変わる.
直元が、直中の3男直亮(なおあき)の養嗣子で、彼の死によって直弼に当主の番が回ってきたのである.
直弼35歳の時のことである.
その4年後の1850年、直亮の死により家督を相続した直弼は、さらにその8年後には大老となる.
彼は、多くの命令を出したが、その中に彦根での屠殺禁止令があった.
このため、牛肉の味噌漬けは作られなくなり、将軍家、諸大名への献上も停止した.
これに音を上げたのが水戸徳川家の当主斉昭(なりあき)、最後の将軍徳川慶喜の実父である.
どうも、二度にわたり斉昭が直弼に牛肉を贈ってほしいと頼んだが断られたと「水戸藩党争始末」にあるらしい.
これが、二人の争いの発端となり、斉昭が直弼により蟄居を命じられ、失意のうちに亡くなった.
これが桜田門外の変で直弼が水戸藩士に襲われて命を失くすことに繋がるというのである.
2023.1/20
Up
Down
#431
もっとも、貴人の中には牛肉を忌避する人もいた.
たとえば、井伊直弼である.
安政の大獄で知られる直弼は、13代井伊直中の14男である.
しかも、庶子である.
このため、父の死後は部屋住みの生活であった.
ただ、当主の息子であるため、好きように生活したようで、さまざまなことに足を踏み入れ、特に茶道で有名であった.
しかしながら、兄で直中の11男直元の死により運命が変わる.
直元が、直中の3男直亮(なおあき)の養嗣子で、彼の死によって直弼に当主の番が回ってきたのである.
直弼35歳の時のことである.
その4年後の1850年、直亮の死により家督を相続した直弼は、さらにその8年後には大老となる.
彼は、多くの命令を出したが、その中に彦根での屠殺禁止令があった.
このため、牛肉の味噌漬けは作られなくなり、将軍家、諸大名への献上も停止した.
これに音を上げたのが水戸徳川家の当主斉昭(なりあき)、最後の将軍徳川慶喜の実父である.
どうも、二度にわたり斉昭が直弼に牛肉を贈ってほしいと頼んだが断られたと「水戸藩党争始末」にあるらしい.
これが、二人の争いの発端となり、斉昭が直弼により蟄居を命じられ、失意のうちに亡くなった.
これが桜田門外の変で直弼が水戸藩士に襲われて命を失くすことに繋がるというのである.
2023.1/20
Up Down
#432
げに食べ物の恨みは怖ろしいとなるわけだが、「水戸藩党争始末」を読んでいないので本当かどうかは分からない.
ただ、井伊直弼が屠殺を禁止し、牛肉を贈るのを辞めたというのは同書にしかない記述である.
しかも、この本は1893(明治26)にもなって無名氏という匿名の人物が書いたものである.
せめて、他の文献等で直弼が屠殺を禁止したというのがあればよいが、現時点では全面的に受け入れるのは難しい.
というのは、大老といえども、徳川御三家の当主に楯突くかという疑問があるからである.
もちろん、斉昭を謹慎や永蟄居を命じたのは井伊直弼である.
しかし、それは乾坤一擲の大勝負であり、斉昭にも攻め入れられる失点があった.
味噌漬けを贈る、贈らないという瑣事ではない.
しかも、その瑣事は将軍に連なる人物を軽視するというものである.
大老とはいえ、そこまでの高い地位であったのだろうか.
しかも、相手は二度にわたって申し込んできているとされる.
問題になるのではないかと思う.
ただ、玉虫左太夫が記した「桜田騒動記」には、「大老が牛の代わりに首切られ」等の落首が見られるそうである.
この本も未見であるが、この人は日米修好通商条約の調印のためアメリカに渡った使節団の記録係である.
少なくとも、そういうふうにとられるものがあったのであろう.
2023.1/22
Up
Down
#432
げに食べ物の恨みは怖ろしいとなるわけだが、「水戸藩党争始末」を読んでいないので本当かどうかは分からない.
ただ、井伊直弼が屠殺を禁止し、牛肉を贈るのを辞めたというのは同書にしかない記述である.
しかも、この本は1893(明治26)にもなって無名氏という匿名の人物が書いたものである.
せめて、他の文献等で直弼が屠殺を禁止したというのがあればよいが、現時点では全面的に受け入れるのは難しい.
というのは、大老といえども、徳川御三家の当主に楯突くかという疑問があるからである.
もちろん、斉昭を謹慎や永蟄居を命じたのは井伊直弼である.
しかし、それは乾坤一擲の大勝負であり、斉昭にも攻め入れられる失点があった.
味噌漬けを贈る、贈らないという瑣事ではない.
しかも、その瑣事は将軍に連なる人物を軽視するというものである.
大老とはいえ、そこまでの高い地位であったのだろうか.
しかも、相手は二度にわたって申し込んできているとされる.
問題になるのではないかと思う.
ただ、玉虫左太夫が記した「桜田騒動記」には、「大老が牛の代わりに首切られ」等の落首が見られるそうである.
この本も未見であるが、この人は日米修好通商条約の調印のためアメリカに渡った使節団の記録係である.
少なくとも、そういうふうにとられるものがあったのであろう.
2023.1/22
Up Down
#433
徳川斉昭は水戸学の牽引者であり、廃仏毀釈論者であった.
このため、寺院の梵鐘や仏像までを集めて大砲を鋳造し、水戸東照宮から僧侶を駆逐した.
しかし、水戸徳川家の祖頼房が東照宮に寄付した灯籠まで鋳つぶしたことが問題となり、斉昭は謹慎を命じられる.
その後、海防参与として復帰した斉昭は井伊直弼と争い、次の将軍に子の慶喜を送り込もうとして失敗、再度、失脚する.
結局、これが解けぬままに死去したのが桜田門外の変に繋がるわけである.
これに対し、直弼が屠畜を禁止したのは、仏教の敬虔な信者だったからということになっている.
たしかに、やはり敬虔な信者であった父直中の影響から13歳頃から参禅を含む修業を行っている.
しかし、父親のように寺を建立したわけではない.
もちろん、暗殺されたからそのような時間がなかったのだと言われたらそうかもしれないとは思う.
ただ、前回述べたように、水戸家と争うのは危険なことである.
失敗すれば大変なことになる.
譜代大名の筆頭であるから、改易まではいかなくても、閉門、蟄居、場合によれば切腹になりかねない.
督促されたのに、味噌漬けを贈らないというのは、子供じみた行動である.
そのようなことすら分からぬ愚者であったということになる.
さらにいうと、直弼は開国の方向へ行ったわけだが、これは肉食と直結する行いである.
2023.2/2
Up
Down
#433
徳川斉昭は水戸学の牽引者であり、廃仏毀釈論者であった.
このため、寺院の梵鐘や仏像までを集めて大砲を鋳造し、水戸東照宮から僧侶を駆逐した.
しかし、水戸徳川家の祖頼房が東照宮に寄付した灯籠まで鋳つぶしたことが問題となり、斉昭は謹慎を命じられる.
その後、海防参与として復帰した斉昭は井伊直弼と争い、次の将軍に子の慶喜を送り込もうとして失敗、再度、失脚する.
結局、これが解けぬままに死去したのが桜田門外の変に繋がるわけである.
これに対し、直弼が屠畜を禁止したのは、仏教の敬虔な信者だったからということになっている.
たしかに、やはり敬虔な信者であった父直中の影響から13歳頃から参禅を含む修業を行っている.
しかし、父親のように寺を建立したわけではない.
もちろん、暗殺されたからそのような時間がなかったのだと言われたらそうかもしれないとは思う.
ただ、前回述べたように、水戸家と争うのは危険なことである.
失敗すれば大変なことになる.
譜代大名の筆頭であるから、改易まではいかなくても、閉門、蟄居、場合によれば切腹になりかねない.
督促されたのに、味噌漬けを贈らないというのは、子供じみた行動である.
そのようなことすら分からぬ愚者であったということになる.
さらにいうと、直弼は開国の方向へ行ったわけだが、これは肉食と直結する行いである.
2023.2/2
Up Down
#434
1612(慶長17)年8月6日、幕府は「牛を殺す事御制禁也、自然殺すものにハ、一切不可売事」という禁令を出している.
牛を殺すことは禁止である、殺して売ってもいけないというのだが、これはキリシタン禁教令5ヶ条の1条である.
この年、幕府は禁教令を出しているが、その一環として出されたもので、キリスト教の信者が牛を屠って食べることに由来するものである.
そして、アメリカはキリスト教の国である.
したがって、井伊直弼が日米修好通商条約を締結しようとしていることは、肉食を認めることになる.
もっとも、オランダもキリスト教国であるが、プロテスタントの国であるため、ポルトガルとは違う信仰の国、すなわち、非キリスト教国家であるとしていた.
このため、ヨーロッパの国ではただ一人日本との通商が認められていたわけであるが、アメリカもプロテスタントを中心とする国である.
したがって、井伊直弼は勘違いしていたという考えもできようが、ペリーは日本人の役人に艦上で晩餐会を開いている.
当然、牛肉を含む料理が出ており、そのことは直弼も承知しているはずである.
また、初代駐日大使となるハリスはアメリカ領事館が置かれた玉泉寺で牛を屠ったようで、牛を括りつけたとされる木が残っている.
味噌漬けを贈らないなどという児戯にも類したことをするような人物が認めることではない.
2023.2/7
Up
Down
#434
1612(慶長17)年8月6日、幕府は「牛を殺す事御制禁也、自然殺すものにハ、一切不可売事」という禁令を出している.
牛を殺すことは禁止である、殺して売ってもいけないというのだが、これはキリシタン禁教令5ヶ条の1条である.
この年、幕府は禁教令を出しているが、その一環として出されたもので、キリスト教の信者が牛を屠って食べることに由来するものである.
そして、アメリカはキリスト教の国である.
したがって、井伊直弼が日米修好通商条約を締結しようとしていることは、肉食を認めることになる.
もっとも、オランダもキリスト教国であるが、プロテスタントの国であるため、ポルトガルとは違う信仰の国、すなわち、非キリスト教国家であるとしていた.
このため、ヨーロッパの国ではただ一人日本との通商が認められていたわけであるが、アメリカもプロテスタントを中心とする国である.
したがって、井伊直弼は勘違いしていたという考えもできようが、ペリーは日本人の役人に艦上で晩餐会を開いている.
当然、牛肉を含む料理が出ており、そのことは直弼も承知しているはずである.
また、初代駐日大使となるハリスはアメリカ領事館が置かれた玉泉寺で牛を屠ったようで、牛を括りつけたとされる木が残っている.
味噌漬けを贈らないなどという児戯にも類したことをするような人物が認めることではない.
2023.2/7
Up Down
#435
江戸時代前期の俳人松永貞徳の「徒然慰(なぐさみ)草」巻4第119段に、「吉利支丹の日本へいりたりし時は、京衆牛肉をわかとがうしてもてはやせり」とある.
戦国末期、キリシタンであるポルトガル人が来航した際、京都で「わか」と号(称)する牛肉料理が流行したというのである.
この「わか」は、ポルトガル語のvaca、牝牛である.
ラテン語ではvaccaであり、そこから、牛痘は英語でvaccine、ドイツ語でVakzinとなる.
ワクチンである.
ポルトガル語ではヴァカ、ラテン語の発音もヴァーカと聞こえるが、当時の日本人にはヴァはワと聞こえたのであろう.
今ならバカであろう.
そして、ポルトガル語ではvacaは牝牛の意味と牛肉の意味で使う.
一応、carne de vaca(牛の肉)という言い方もあるが、vacaだけで充分に通じる.
たとえば、Alho e sal na vacaアホ・エ・サル・ナ・バカはニンニクと塩をかけた牛肉である.
それはともかくとして、ノルマンディー公ウィリアムに敗れたイギリスでは、上流階級がフランス語、庶民が英語と言葉が二分された.
ために、スコットの小説「アイヴァンホー」の冒頭に、豚は生きている間はサクソン語でswineであるが、肉になった途端、上流階級が食べるのでporkとなると書いてある.
このporkは現在ではporcと綴られるがフランス語で、豚を意味する(イタリア語でポルコ・ロッソPorco
Rossoは赤い豚である).
また、フランス語の牛Boeufは英語の牛肉ビーフbeefであり、羊moutonは羊肉マトンmuttonなのである.
このような変化はヨーロッパの言語では珍しいケースであり、植物の間は稲、種は米と呼ばれ、食べられるようになると飯と名を変えるようなことはない
(もっとも、日本語でも米以外はあまり変化しない).
2023.2/8
Up
Down
#435
江戸時代前期の俳人松永貞徳の「徒然慰(なぐさみ)草」巻4第119段に、「吉利支丹の日本へいりたりし時は、京衆牛肉をわかとがうしてもてはやせり」とある.
戦国末期、キリシタンであるポルトガル人が来航した際、京都で「わか」と号(称)する牛肉料理が流行したというのである.
この「わか」は、ポルトガル語のvaca、牝牛である.
ラテン語ではvaccaであり、そこから、牛痘は英語でvaccine、ドイツ語でVakzinとなる.
ワクチンである.
ポルトガル語ではヴァカ、ラテン語の発音もヴァーカと聞こえるが、当時の日本人にはヴァはワと聞こえたのであろう.
今ならバカであろう.
そして、ポルトガル語ではvacaは牝牛の意味と牛肉の意味で使う.
一応、carne de vaca(牛の肉)という言い方もあるが、vacaだけで充分に通じる.
たとえば、Alho e sal na vacaアホ・エ・サル・ナ・バカはニンニクと塩をかけた牛肉である.
それはともかくとして、ノルマンディー公ウィリアムに敗れたイギリスでは、上流階級がフランス語、庶民が英語と言葉が二分された.
ために、スコットの小説「アイヴァンホー」の冒頭に、豚は生きている間はサクソン語でswineであるが、肉になった途端、上流階級が食べるのでporkとなると書いてある.
このporkは現在ではporcと綴られるがフランス語で、豚を意味する(イタリア語でポルコ・ロッソPorco
Rossoは赤い豚である).
また、フランス語の牛Boeufは英語の牛肉ビーフbeefであり、羊moutonは羊肉マトンmuttonなのである.
このような変化はヨーロッパの言語では珍しいケースであり、植物の間は稲、種は米と呼ばれ、食べられるようになると飯と名を変えるようなことはない
(もっとも、日本語でも米以外はあまり変化しない).
2023.2/8
Up Down
#436
もっとも、ブラジル人に聞くと、雌牛は仔を産むし、乳も出すので、肉牛には使わない.
したがって、去勢牛を意味するboiを使うと教えられた.
ただ、松阪牛は仔牛を産んでいない雌牛に限定しており、筋肉質な雄牛よりも好まれる場合もあるので、肉牛=雄牛とは限らない.
また、以前、別のブラジル人に聞いたところでは、boiを使う州とvacaを使う州があるとのことである.
そのせいか、ポルトガル語版Wikipediaでは、牛肉はCarne
bovinaの項に収められている.
このbovinaは牛を意味する普通名詞bovinoの女性形であるが、女性形になったのは肉を意味するcarneが女性名詞だからであり、雌牛という意味ではない.
したがって、16世紀のポルトガル人がvacaを使っていたかどうかはこれだけでは不明である.
ただし、同時代の宣教師の書いた「日葡辞書(パリ本)https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852354j/f242.highres」には
"Guiunicu.Vxino nicu.carne
de boy, ou vaca"とある.
「牛肉(ぎゅうにく):うしにく」と、当時のポルトガル式ローマ字で書かれた後に続く部分は「去勢牛または雌牛の肉」という意味である.
なお、牛をVxiと表記していることから、Vはウであり、Vacaはウァカと読まれたので「わか」と呼ばれたと考える人がいるかもしれない.
しかし、UがVから分かれたのは17世紀から18世紀である.
この時代にはUという文字がなかったので、VをUとして使用しているだけである.
また、boiがboyと表記されているが、これはスペルが固定されていなかったからである.
2023.2/10
Up
Down
#436
もっとも、ブラジル人に聞くと、雌牛は仔を産むし、乳も出すので、肉牛には使わない.
したがって、去勢牛を意味するboiを使うと教えられた.
ただ、松阪牛は仔牛を産んでいない雌牛に限定しており、筋肉質な雄牛よりも好まれる場合もあるので、肉牛=雄牛とは限らない.
また、以前、別のブラジル人に聞いたところでは、boiを使う州とvacaを使う州があるとのことである.
そのせいか、ポルトガル語版Wikipediaでは、牛肉はCarne
bovinaの項に収められている.
このbovinaは牛を意味する普通名詞bovinoの女性形であるが、女性形になったのは肉を意味するcarneが女性名詞だからであり、雌牛という意味ではない.
したがって、16世紀のポルトガル人がvacaを使っていたかどうかはこれだけでは不明である.
ただし、同時代の宣教師の書いた「日葡辞書(パリ本)https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852354j/f242.highres」には
"Guiunicu.Vxino nicu.carne
de boy, ou vaca"とある.
「牛肉(ぎゅうにく):うしにく」と、当時のポルトガル式ローマ字で書かれた後に続く部分は「去勢牛または雌牛の肉」という意味である.
なお、牛をVxiと表記していることから、Vはウであり、Vacaはウァカと読まれたので「わか」と呼ばれたと考える人がいるかもしれない.
しかし、UがVから分かれたのは17世紀から18世紀である.
この時代にはUという文字がなかったので、VをUとして使用しているだけである.
また、boiがboyと表記されているが、これはスペルが固定されていなかったからである.
2023.2/10
Up Down
#437
「日葡辞書」は中世日本語の根本資料として有名だが、当時のポルトガル語の資料としても使える.
したがって、ここにVacaとある以上、「わか」はこの語に由来すると考えてよい.
そして、わざわざポルトガル語由来の言葉で呼ばれたということは、それまでの日本人は牛肉を食べなかったということになる.
実際、九州を征服した豊臣秀吉は、1587(天正15)年6月19日、
「牛馬ヲ売買ころし食事、是又可為曲事事(牛馬を売り買いころし、食う事、是れ又曲事たるべき事)」という禁令を出している.
牛馬を売買したり、殺したり、食べることは道義に反するというのである.
そして、その翌日、イエズス会副管区長クエリヨ(コエーリョ)とフロイスに対して
「牛馬は人間に仕え有益なる動物であるに、何故に之を食ふ如き道理に背いたことをなすか」と詰問している(村上直次郎訳「イエズス会日本年報」).
牛馬は有益な動物なぜ、道理に背いて、なぜ食べてしまうのかというのである.
したがって、秀吉の時代、牛馬を食用にすることはなかったということになる.
これに対して、フロイスはその「日本史」の中で、馬肉を食べることを否定し、牛はそれように飼っているので大丈夫であると答えたと記述している.
そして、その数年後、日本人の間で卵や牛肉料理が好まれるようになり、秀吉も好んでいたと記している.
つまり、秀吉は片方で非難しながら、道義に反する牛肉を食べていたわけである.
2023.2/14
Up
Down
#437
「日葡辞書」は中世日本語の根本資料として有名だが、当時のポルトガル語の資料としても使える.
したがって、ここにVacaとある以上、「わか」はこの語に由来すると考えてよい.
そして、わざわざポルトガル語由来の言葉で呼ばれたということは、それまでの日本人は牛肉を食べなかったということになる.
実際、九州を征服した豊臣秀吉は、1587(天正15)年6月19日、
「牛馬ヲ売買ころし食事、是又可為曲事事(牛馬を売り買いころし、食う事、是れ又曲事たるべき事)」という禁令を出している.
牛馬を売買したり、殺したり、食べることは道義に反するというのである.
そして、その翌日、イエズス会副管区長クエリヨ(コエーリョ)とフロイスに対して
「牛馬は人間に仕え有益なる動物であるに、何故に之を食ふ如き道理に背いたことをなすか」と詰問している(村上直次郎訳「イエズス会日本年報」).
牛馬は有益な動物なぜ、道理に背いて、なぜ食べてしまうのかというのである.
したがって、秀吉の時代、牛馬を食用にすることはなかったということになる.
これに対して、フロイスはその「日本史」の中で、馬肉を食べることを否定し、牛はそれように飼っているので大丈夫であると答えたと記述している.
そして、その数年後、日本人の間で卵や牛肉料理が好まれるようになり、秀吉も好んでいたと記している.
つまり、秀吉は片方で非難しながら、道義に反する牛肉を食べていたわけである.
2023.2/14
Up Down
#438
他の宣教師の記録にも、長崎、特に平戸では、牛肉はかなり食べられていた.
このことは、スペイン人商人ヒロンGironの「日本王国記」にも記されている.
ヒロンは、延べ20年間にわたって長崎で活動した人物であるが1607年に10年ぶりに来日した際、長崎での牛肉の値段が8倍に上がっていたと記している.
人口が増え、牛肉を食べる人も増え、価格が高騰したからである.
では、「牛馬ヲ売買云々」、#434に述べた「牛を殺す事云々」という秀吉や家康(発令時の将軍は秀忠)の禁令は何だったのかとなる.
しかも、#428に述べたように、井伊家の牛肉の味噌漬けは将軍家をはじめとする各家に贈られている.
秀吉はもちろん、家康の禁令すらも無視されているわけである.
したがって、これはキリシタン対策であったというのが研究者の一致したところである.
「牛を殺す事云々」という禁令はキリシタン禁教令の一環だからである.
秀吉の禁令も同様である.
したがって、キリシタンでない人々にとって、牛を殺し、その肉を食べるのは禁止されていないということになる.
さらに1637年の島原の乱とその後の取締りでキリシタンというものが表面上は存在しなくった後は、意味を失うものであったのである.
その後、肉食は綱吉の生類憐れみの令により下火になったと思われるが、8代吉宗が1720年に漢訳洋書輸入の禁令を緩めたことにより再燃する.
長崎では殺生禁止令が2度にわたって出されているが、同地の唐人とオランダ人は禁止令の対象外であり、他所より肉の入手が簡単だったからである.
このため、長崎で蘭学を学んだ者を中心に肉食が流行したのである.
2023.2/23
Up
Down
#438
他の宣教師の記録にも、長崎、特に平戸では、牛肉はかなり食べられていた.
このことは、スペイン人商人ヒロンGironの「日本王国記」にも記されている.
ヒロンは、延べ20年間にわたって長崎で活動した人物であるが1607年に10年ぶりに来日した際、長崎での牛肉の値段が8倍に上がっていたと記している.
人口が増え、牛肉を食べる人も増え、価格が高騰したからである.
では、「牛馬ヲ売買云々」、#434に述べた「牛を殺す事云々」という秀吉や家康(発令時の将軍は秀忠)の禁令は何だったのかとなる.
しかも、#428に述べたように、井伊家の牛肉の味噌漬けは将軍家をはじめとする各家に贈られている.
秀吉はもちろん、家康の禁令すらも無視されているわけである.
したがって、これはキリシタン対策であったというのが研究者の一致したところである.
「牛を殺す事云々」という禁令はキリシタン禁教令の一環だからである.
秀吉の禁令も同様である.
したがって、キリシタンでない人々にとって、牛を殺し、その肉を食べるのは禁止されていないということになる.
さらに1637年の島原の乱とその後の取締りでキリシタンというものが表面上は存在しなくった後は、意味を失うものであったのである.
その後、肉食は綱吉の生類憐れみの令により下火になったと思われるが、8代吉宗が1720年に漢訳洋書輸入の禁令を緩めたことにより再燃する.
長崎では殺生禁止令が2度にわたって出されているが、同地の唐人とオランダ人は禁止令の対象外であり、他所より肉の入手が簡単だったからである.
このため、長崎で蘭学を学んだ者を中心に肉食が流行したのである.
2023.2/23
Up Down
#439
「談林十百韻(だんりんとっぴゃくいん)」という連歌集がある.
談林の名が示すように西山宗因の談林派俳諧の名の由来になったもので、宗因の発句を巻頭に載せた九吟百韻からなる.
その459番に「肉食に牛も命やおしからん」という句がある.
牛も命が惜しいのだろうと言っているのだから、牛肉が食用になっていたということになるが、この本は1675年に刊行されている.
4代将軍家綱の時代である.
つまり、先の禁令の出された時代から50年ほどしか経っていない.
談林派は京都、大坂、江戸の三都に急速に広がり#435に記した松永貞徳の貞門派を超えて主流となった俳諧の一派である.
つまり、京都で流行した牛肉料理は、この時代までに江戸まで広がっていたのである.
また、作者の一朝の出自は不明であるが、同集に名を残す小沢卜尺は江戸の名主であり、松尾芭蕉に住まいを貸した人物である.
つまり、武士ではない.
宗因は熊本の加藤家出身の武士であるが、宗因を囲んで談林派と呼ばれた人達はパトロンであり、江戸の富裕な町民であろう.
つまり、江戸時代の初期、武士だけではなく、庶民も牛肉を食べていたことになる.
2023.3/3
Up
Down
#439
「談林十百韻(だんりんとっぴゃくいん)」という連歌集がある.
談林の名が示すように西山宗因の談林派俳諧の名の由来になったもので、宗因の発句を巻頭に載せた九吟百韻からなる.
その459番に「肉食に牛も命やおしからん」という句がある.
牛も命が惜しいのだろうと言っているのだから、牛肉が食用になっていたということになるが、この本は1675年に刊行されている.
4代将軍家綱の時代である.
つまり、先の禁令の出された時代から50年ほどしか経っていない.
談林派は京都、大坂、江戸の三都に急速に広がり#435に記した松永貞徳の貞門派を超えて主流となった俳諧の一派である.
つまり、京都で流行した牛肉料理は、この時代までに江戸まで広がっていたのである.
また、作者の一朝の出自は不明であるが、同集に名を残す小沢卜尺は江戸の名主であり、松尾芭蕉に住まいを貸した人物である.
つまり、武士ではない.
宗因は熊本の加藤家出身の武士であるが、宗因を囲んで談林派と呼ばれた人達はパトロンであり、江戸の富裕な町民であろう.
つまり、江戸時代の初期、武士だけではなく、庶民も牛肉を食べていたことになる.
2023.3/3
Up Down
#440
江戸幕府が贅沢禁止令を出しても、なかなか守られなかったというのは有名な話である.
もっとも、公然と禁令を犯すのではない.
二階建てが禁止されると、外観だけは平屋に見える家が流行り、絹が駄目だというと服の裏地や襦袢に使うようになる.
これが、表ではなく裏に凝るのが粋であるという、日本の不思議な文化の由来であるが、禁令を意識したものであることは確かである.
しかし、肉食禁止令も同様であったかというと、それは疑問である.
前回示したように、そういう句が載った本が公然と刊行されているからである.
また、「牛喰ふておのおの白き鼻の先」という句もあるらしい.
これは「俳諧○(はいかいけい)」という本に載っているものであるが、実物を見ていない.
この本は、点者(てんじゃ)と呼ばれる俳諧等の優劣を決めるのを職業にしていた者の選んだ句を集めたものである.
○という見慣れぬ文字は「くじり」と読み、結び目を解くために先端を尖らせた角製の道具である.
したがって、様々な句集を「紐解いて」集めたという意味であろうが、点者の好みを伝える手引書であった.
こういう書は、俳諧を嗜む者の参考になるものであったからではないかと思うが、初代、二代雪成によって、同じ題名のものが何種類か出ている.
しかし、そのすべてを確認できなかったので伝聞である.
ただ、そのような句があったのならば5代将軍綱吉の生類憐れみの令によっても牛肉料理は残ったということになる.
同書の刊行は1768年から1831年頃にかけてであり、綱吉の死後のことだからである.
2023.3/6
Up
Down
#440
江戸幕府が贅沢禁止令を出しても、なかなか守られなかったというのは有名な話である.
もっとも、公然と禁令を犯すのではない.
二階建てが禁止されると、外観だけは平屋に見える家が流行り、絹が駄目だというと服の裏地や襦袢に使うようになる.
これが、表ではなく裏に凝るのが粋であるという、日本の不思議な文化の由来であるが、禁令を意識したものであることは確かである.
しかし、肉食禁止令も同様であったかというと、それは疑問である.
前回示したように、そういう句が載った本が公然と刊行されているからである.
また、「牛喰ふておのおの白き鼻の先」という句もあるらしい.
これは「俳諧○(はいかいけい)」という本に載っているものであるが、実物を見ていない.
この本は、点者(てんじゃ)と呼ばれる俳諧等の優劣を決めるのを職業にしていた者の選んだ句を集めたものである.
○という見慣れぬ文字は「くじり」と読み、結び目を解くために先端を尖らせた角製の道具である.
したがって、様々な句集を「紐解いて」集めたという意味であろうが、点者の好みを伝える手引書であった.
こういう書は、俳諧を嗜む者の参考になるものであったからではないかと思うが、初代、二代雪成によって、同じ題名のものが何種類か出ている.
しかし、そのすべてを確認できなかったので伝聞である.
ただ、そのような句があったのならば5代将軍綱吉の生類憐れみの令によっても牛肉料理は残ったということになる.
同書の刊行は1768年から1831年頃にかけてであり、綱吉の死後のことだからである.
2023.3/6
Up Down
#441
では、牛肉がおおっぴらに食べられていたかというと、それは疑問である.
もし、そうであるならば、牛肉を詠んだ句がもっとあってよい.
また、牛肉食に対する禁忌が俗信には多い.
いわく、妊婦は食べてはいけない、竈で煮てはいけない、牛を飼っている家は食べてはいけない、山に持っていってはいけない、祭の当屋は食べてはいけないという類いである.
これらが明治以前に遡れるかどうかで意味合いが異なってくるが、仮に江戸時代まで遡るものであれば、その条件に当てはまらなければ食べてよいということになる.
しかし、これらの禁忌は、牛肉を食べることが公然と行う物ではないということも示唆している.
実際、西日本を中心に、牛を意味する「たじし」という言葉が広がっているが、この語は#319で述べたように田+宍(肉)で、牛肉が元来の意味である.
新井白石の「東雅(4コマ)」に「東国の俗には牛をタシといふなり.タシとは田鹿なり」とあり、この「タシ」も「たじし」であろう.
鹿も宍だからである.
ところが、「日葡辞書」にはxixi(宍)はnicu(肉)とあり、Guiunicu(牛肉)も#436に述べたように立項されているが、taxixiもtaxiもない.
したがって、この「たじ(し)」は、「東雅」の成立した1719年頃までに広まったものであろうが、そういう言い換えが必要だったのはなぜだろうか.
2023.3/25
Up
Down
#441
では、牛肉がおおっぴらに食べられていたかというと、それは疑問である.
もし、そうであるならば、牛肉を詠んだ句がもっとあってよい.
また、牛肉食に対する禁忌が俗信には多い.
いわく、妊婦は食べてはいけない、竈で煮てはいけない、牛を飼っている家は食べてはいけない、山に持っていってはいけない、祭の当屋は食べてはいけないという類いである.
これらが明治以前に遡れるかどうかで意味合いが異なってくるが、仮に江戸時代まで遡るものであれば、その条件に当てはまらなければ食べてよいということになる.
しかし、これらの禁忌は、牛肉を食べることが公然と行う物ではないということも示唆している.
実際、西日本を中心に、牛を意味する「たじし」という言葉が広がっているが、この語は#319で述べたように田+宍(肉)で、牛肉が元来の意味である.
新井白石の「東雅(4コマ)」に「東国の俗には牛をタシといふなり.タシとは田鹿なり」とあり、この「タシ」も「たじし」であろう.
鹿も宍だからである.
ところが、「日葡辞書」にはxixi(宍)はnicu(肉)とあり、Guiunicu(牛肉)も#436に述べたように立項されているが、taxixiもtaxiもない.
したがって、この「たじ(し)」は、「東雅」の成立した1719年頃までに広まったものであろうが、そういう言い換えが必要だったのはなぜだろうか.
2023.3/25
Up Down
#442
牛の別名としては赤べこで有名な「べこ」がある.
これはモーと記されることの多い牛の鳴き声をベーとしたからとされる.
聞き慣れない鳴き声のように思うが、「日本方言地図」の記載には、牛の鳴き声としてモー、メー、ベー等が記されており、ベーは東北地方と鹿児島に偏在している.
方言周圏論にしたがえば、ベーが古い牛の鳴き声だったのであろう.
もっとも、「べこ」という呼び名は東北地方のみであり(鹿児島には「べぶ」という言い方が記載されているが)、文献上の初出も菅江真澄の「迦須牟巨麻賀多(かすむ駒形)」である.
これは1786(天明6)年に東北地方を旅した記録で、岩手県胆沢(いさわ)郡胆沢町徳岡(現、奥州市胆沢区)の民家に滞在していた真澄は、正月9日、囲炉裏端で子供達の争う声を書き残している.
「また草子に牛の画あるを、こは某(なに)なるぞ、牛子(べこ)といへば、いな牛(うし)なりとあらがひ」とあるのがそれである.
草紙に牛の絵が描いてあるのを「べこ」だと答えた子に対し、別の子が「うし」だと反論しているのである.
何気ない一齣を書き残したのは、この辺りでは牛の仔を「べこ」と呼ぶのかという興味があったからであろう.
そして、このことは、この当時、「べこ」は「うし」を駆逐していた訳ではないということを示している.
真澄は牛子(べこ)と牛(うし)を区別しており、この時代では、まだ、牛そのものを意味する語ではなかったのである.
つまり、入ってきてから日の浅い言葉であったということになる.
この語の始まりが幼児語であった可能性もあるが、牛の愛称のようなものであったのであろう.
2023.5/25
Up
Down
#442
牛の別名としては赤べこで有名な「べこ」がある.
これはモーと記されることの多い牛の鳴き声をベーとしたからとされる.
聞き慣れない鳴き声のように思うが、「日本方言地図」の記載には、牛の鳴き声としてモー、メー、ベー等が記されており、ベーは東北地方と鹿児島に偏在している.
方言周圏論にしたがえば、ベーが古い牛の鳴き声だったのであろう.
もっとも、「べこ」という呼び名は東北地方のみであり(鹿児島には「べぶ」という言い方が記載されているが)、文献上の初出も菅江真澄の「迦須牟巨麻賀多(かすむ駒形)」である.
これは1786(天明6)年に東北地方を旅した記録で、岩手県胆沢(いさわ)郡胆沢町徳岡(現、奥州市胆沢区)の民家に滞在していた真澄は、正月9日、囲炉裏端で子供達の争う声を書き残している.
「また草子に牛の画あるを、こは某(なに)なるぞ、牛子(べこ)といへば、いな牛(うし)なりとあらがひ」とあるのがそれである.
草紙に牛の絵が描いてあるのを「べこ」だと答えた子に対し、別の子が「うし」だと反論しているのである.
何気ない一齣を書き残したのは、この辺りでは牛の仔を「べこ」と呼ぶのかという興味があったからであろう.
そして、このことは、この当時、「べこ」は「うし」を駆逐していた訳ではないということを示している.
真澄は牛子(べこ)と牛(うし)を区別しており、この時代では、まだ、牛そのものを意味する語ではなかったのである.
つまり、入ってきてから日の浅い言葉であったということになる.
この語の始まりが幼児語であった可能性もあるが、牛の愛称のようなものであったのであろう.
2023.5/25
Up Down
#443
「べこ」に対して、「たじし」というのは判じ物である.
田の宍というのは、何かと考えないと答えが出ないからである.
しかし、田にいる肉という意味だと、イナゴ類を肉とみなすかどうか不明だが、タニシやザリガニ、カエルのことかも知れない.
それを狙って飛来する鷺等のことかも知れない.
場合によっては、猪や鹿であっても、田を荒らしに来る動物だと言い張れば該当する.
つまり、牛を食べるのかとか聞かれたとしても、猪や鹿は薬と称して食用になっているのだから、問題はないでしょうとなる.
その上、「しし」に宍と漢字を当てれば肉の意味であるが、獣と書いても「しし」と読むことができるので、田の獣の意味であるという申し開きも可能なのである.
つまり、肉という意味ではないので、牛を食べるという意味の名ではないということになる.
そう考えていくと、「たじし」という語の始まりは隠語であったのかもしれない.
隠語というのは他人に知られたくないようにするための一種の暗号だから、牛肉を食する行為は人目をはばかるものだったということになる.
そして、そう考えると、なぜ、すき焼きなのかという理由も解けてくる.
つまり、「カチカチ山」では狸鍋となっているように、大抵の肉料理は鍋なのに、なぜ牛肉だけは焼くのかということである.
#333に書いたように、日本の焼肉の歴史は浅い.
油が貴重品であったからであろうが、文明開化で牛肉を食べるようになっても、牛鍋が主流で、焼いたりはしない.
2023.6/18
Up
Down
#443
「べこ」に対して、「たじし」というのは判じ物である.
田の宍というのは、何かと考えないと答えが出ないからである.
しかし、田にいる肉という意味だと、イナゴ類を肉とみなすかどうか不明だが、タニシやザリガニ、カエルのことかも知れない.
それを狙って飛来する鷺等のことかも知れない.
場合によっては、猪や鹿であっても、田を荒らしに来る動物だと言い張れば該当する.
つまり、牛を食べるのかとか聞かれたとしても、猪や鹿は薬と称して食用になっているのだから、問題はないでしょうとなる.
その上、「しし」に宍と漢字を当てれば肉の意味であるが、獣と書いても「しし」と読むことができるので、田の獣の意味であるという申し開きも可能なのである.
つまり、肉という意味ではないので、牛を食べるという意味の名ではないということになる.
そう考えていくと、「たじし」という語の始まりは隠語であったのかもしれない.
隠語というのは他人に知られたくないようにするための一種の暗号だから、牛肉を食する行為は人目をはばかるものだったということになる.
そして、そう考えると、なぜ、すき焼きなのかという理由も解けてくる.
つまり、「カチカチ山」では狸鍋となっているように、大抵の肉料理は鍋なのに、なぜ牛肉だけは焼くのかということである.
#333に書いたように、日本の焼肉の歴史は浅い.
油が貴重品であったからであろうが、文明開化で牛肉を食べるようになっても、牛鍋が主流で、焼いたりはしない.
2023.6/18
Up Down
#444
ちょっと待ってくれ、すき焼きは焼きと書くが、実質的に煮物だと言われる方がおられると思う.
そして、そのような方は、おそらく、関東、もしくは、東日本にルーツを持つ人だと思う.
というのは、関東のすき焼きは割り下というもので煮るのが基本だからである.
つまり、醤油は濃口か薄口か、鰹出汁か昆布出汁か、カレーに入れる肉の種類は牛か豚か、桜餅の形状等、
関東と関西の食文化には大きな違いがあるが、すき焼きもその一つなのである.
他にも、旧日本陸軍で牛缶と呼ばれたものは、牛肉の大和煮である.
したがって、牛肉は焼くものではなく、日本では煮るものではないかという意見も出てくるであろう.
しかし、それは間違いである.
関東のすき焼きは、明治の文明開化によって発生した牛鍋の後裔だからである.
そして、そうなったのは1923年9月1日の関東大震災の影響である.
この震災は死亡者が10万5千人以上と、阪神淡路、東北の両震災を合わせたよりも多く、その9割が焼死であったことから、建築基準法の耐震基準だけでなく、耐火基準も見直された.
また、多くの韓国・朝鮮人が虐殺され、甘粕事件も起きている.
震災の影響としては、谷崎潤一郎の関西移住が知られるが、文化面ではホテル・ウェディングがそうである.
実は、この日、帝国ホテルでは2代目本館の完成のお披露目が行われる予定であったが、建物は無事に震災を乗り切った.
設計に当たったアメリカの設計家ライトの許には、その耐震設計の御陰だと支配人から電報が届いたとあるが、これはライトの捏造である.
実際には、彼は耐震構造など考えてもいなかったし、予算の使いすぎで馘首されていたのである.
ただ、世間では、その堅牢さが喧伝され、多くの神社が倒壊したため、できなくなった結婚式を多賀大社の分霊を招いた帝国ホテルで行ったのである.
これが、一般に広がったのである.
他にも、料理の面で多くの変化があった.
2023.6/20
Up
Down
#444
ちょっと待ってくれ、すき焼きは焼きと書くが、実質的に煮物だと言われる方がおられると思う.
そして、そのような方は、おそらく、関東、もしくは、東日本にルーツを持つ人だと思う.
というのは、関東のすき焼きは割り下というもので煮るのが基本だからである.
つまり、醤油は濃口か薄口か、鰹出汁か昆布出汁か、カレーに入れる肉の種類は牛か豚か、桜餅の形状等、
関東と関西の食文化には大きな違いがあるが、すき焼きもその一つなのである.
他にも、旧日本陸軍で牛缶と呼ばれたものは、牛肉の大和煮である.
したがって、牛肉は焼くものではなく、日本では煮るものではないかという意見も出てくるであろう.
しかし、それは間違いである.
関東のすき焼きは、明治の文明開化によって発生した牛鍋の後裔だからである.
そして、そうなったのは1923年9月1日の関東大震災の影響である.
この震災は死亡者が10万5千人以上と、阪神淡路、東北の両震災を合わせたよりも多く、その9割が焼死であったことから、建築基準法の耐震基準だけでなく、耐火基準も見直された.
また、多くの韓国・朝鮮人が虐殺され、甘粕事件も起きている.
震災の影響としては、谷崎潤一郎の関西移住が知られるが、文化面ではホテル・ウェディングがそうである.
実は、この日、帝国ホテルでは2代目本館の完成のお披露目が行われる予定であったが、建物は無事に震災を乗り切った.
設計に当たったアメリカの設計家ライトの許には、その耐震設計の御陰だと支配人から電報が届いたとあるが、これはライトの捏造である.
実際には、彼は耐震構造など考えてもいなかったし、予算の使いすぎで馘首されていたのである.
ただ、世間では、その堅牢さが喧伝され、多くの神社が倒壊したため、できなくなった結婚式を多賀大社の分霊を招いた帝国ホテルで行ったのである.
これが、一般に広がったのである.
他にも、料理の面で多くの変化があった.
2023.6/20
Up Down
#445
江戸前と称する寿司屋が全国各地にある.
これは江戸という冠称が示すように、東京湾で獲れた新鮮な魚介類を使ったという意味である.
つまり、東京の地元料理なのであるが、関東大震災で職場を失った職人が、故郷に帰って握ったことから全国に広がった.
それまで、関西で寿司というと、なれ寿司や押し寿司であり、酢飯に寿司種を載せただけの早寿司は一般的ではなかったのである.
また、東京で使われていた鮨という文字が使われるようになったのも震災の影響である.
それまで、大阪では鮓が多く、京都では朝廷に献上されることから寿司という佳字を使っていたのである.
今でも西日本では寿司のほうが多いので、こちらを使っているが、東日本の人には馴染みが薄いかもしれない.
天麩羅が全国に広がったのも、江戸前寿司と同じ理由である.
それまで、関西でも天麩羅と呼ばれていたものはあったが、それは今日でいう薩摩揚げであったからである.
また、青島で捕虜となり、前年、横浜に店を開いたドイツ人カール・ユーハイムが神戸に移住したのも同様の理由である.
したがって、震災がなければ、バウムクーヘンは横浜の銘菓となったかもしれない.
また、炊き出しにヒントを得て東京の浅草の女性が創作した料理が釜飯である.
その一方で、おでんは関西から進出したとされるが、震災前からあったようなので、これは怪しい.
ただ、すき焼きは、関西から伝わったようである.
戦前のコメディアン古川緑波(ロッパ)の「牛鍋からすき焼へ」という文章にこうある.
「ザラメを入れる、味噌を入れる.
ザクの数が又、やたらに多い、青い菜っぱ、青い葱、ゆばから麩まで入れる.
そこへ又、牛肉そのものの、薄い大きい片を、まぜこぜにして、ぶち込んで、かき廻す」.
初めて関西風のすき焼きに出くわしたときの感想であるが、関西圏の者としてはどこがおかしいのかと思う.
それはともかくとして、「大体に於て、大正十二年の関東大震災の後ぐらいからではあるまいか、東京にも、関西風すき焼が進出して来たのは.
そして、大いにこれが勢力を得て、それから段々と、東京の店でも、牛鍋とは言わなくなり、専ら、すき焼と称するようになった.
看板も、牛鍋という文字は、見られなくなって、すべて、すき焼となってしまった」とある.
2023.6/25
Up
Down
#445
江戸前と称する寿司屋が全国各地にある.
これは江戸という冠称が示すように、東京湾で獲れた新鮮な魚介類を使ったという意味である.
つまり、東京の地元料理なのであるが、関東大震災で職場を失った職人が、故郷に帰って握ったことから全国に広がった.
それまで、関西で寿司というと、なれ寿司や押し寿司であり、酢飯に寿司種を載せただけの早寿司は一般的ではなかったのである.
また、東京で使われていた鮨という文字が使われるようになったのも震災の影響である.
それまで、大阪では鮓が多く、京都では朝廷に献上されることから寿司という佳字を使っていたのである.
今でも西日本では寿司のほうが多いので、こちらを使っているが、東日本の人には馴染みが薄いかもしれない.
天麩羅が全国に広がったのも、江戸前寿司と同じ理由である.
それまで、関西でも天麩羅と呼ばれていたものはあったが、それは今日でいう薩摩揚げであったからである.
また、青島で捕虜となり、前年、横浜に店を開いたドイツ人カール・ユーハイムが神戸に移住したのも同様の理由である.
したがって、震災がなければ、バウムクーヘンは横浜の銘菓となったかもしれない.
また、炊き出しにヒントを得て東京の浅草の女性が創作した料理が釜飯である.
その一方で、おでんは関西から進出したとされるが、震災前からあったようなので、これは怪しい.
ただ、すき焼きは、関西から伝わったようである.
戦前のコメディアン古川緑波(ロッパ)の「牛鍋からすき焼へ」という文章にこうある.
「ザラメを入れる、味噌を入れる.
ザクの数が又、やたらに多い、青い菜っぱ、青い葱、ゆばから麩まで入れる.
そこへ又、牛肉そのものの、薄い大きい片を、まぜこぜにして、ぶち込んで、かき廻す」.
初めて関西風のすき焼きに出くわしたときの感想であるが、関西圏の者としてはどこがおかしいのかと思う.
それはともかくとして、「大体に於て、大正十二年の関東大震災の後ぐらいからではあるまいか、東京にも、関西風すき焼が進出して来たのは.
そして、大いにこれが勢力を得て、それから段々と、東京の店でも、牛鍋とは言わなくなり、専ら、すき焼と称するようになった.
看板も、牛鍋という文字は、見られなくなって、すべて、すき焼となってしまった」とある.
2023.6/25
Up Down
#446
もっとも、東京浅草で1880年から料理店を始めた、ちんやの閉店を伝える新聞記事には1903年にすき焼き専門店になったとある.
震災前である.
ただ、この店名を継承した店のHPにある、すき焼き
ものがたりというページにはそのようなことは書いてない.
前出の古川緑波(ロッパ)の「牛鍋からすき焼へ」にもこの店名は出ているが、こちらにも書いてない.
したがって、料理店から牛鍋専門店になったという意味で、すき焼き専門店と記者が記したのではないかと思う.
この予測が正しいのなら、すき焼きという言葉が東京で一般的になったのは、緑波の述べているように震災後であろう.
もっとも、それは名前だけであり、実際には関東風に趣を変えた煮込み料理である.
そして、この名称が牛鍋の代わりに使われるようになったのであるから、牛鍋という名称がすき焼きになっただけとも考えられる.
もっとも、牛鍋に使われた肉は角切りの場合もあり、味噌味のものもあったので、すき焼き風になった牛鍋というほうが正しいであろう.
また、大和煮はもともとが缶詰であり、当然、明治以降の発明である.
つまり、関東のすき焼きは煮るものであるが、本来は焼くものであったということになる.
これは#443に書いたように、日本の肉食の基本が鍋であったということを考えると、この時代の、この国においては、特異な料理法である.
しかも、すき焼きの「すき」は、好きに焼くからだとこじつける人もいるが、農具である鋤の上で焼いたことに由来する.
他には杉焼きから来たとか、「すきみ」に由来すると書いてあるものがある.
杉焼きというのは#316で示した「料理物語」の中に登場する.
ただし、杉箱の中に鯛だとか野菜だとかを入れて味噌で煮るもので、ここで書いているすき焼きとは似ても似つかぬものである.
また、「すきみ」、つまり、薄く削いだ肉に由来するというのは、薄切りの牛肉を用いるものだから、妥当なように見えるが、この語は魚肉に用いるのが本来である.
したがって、鋤焼きのほうが語源説としては正しい.
2023.6/28
Up
Down
#446
もっとも、東京浅草で1880年から料理店を始めた、ちんやの閉店を伝える新聞記事には1903年にすき焼き専門店になったとある.
震災前である.
ただ、この店名を継承した店のHPにある、すき焼き
ものがたりというページにはそのようなことは書いてない.
前出の古川緑波(ロッパ)の「牛鍋からすき焼へ」にもこの店名は出ているが、こちらにも書いてない.
したがって、料理店から牛鍋専門店になったという意味で、すき焼き専門店と記者が記したのではないかと思う.
この予測が正しいのなら、すき焼きという言葉が東京で一般的になったのは、緑波の述べているように震災後であろう.
もっとも、それは名前だけであり、実際には関東風に趣を変えた煮込み料理である.
そして、この名称が牛鍋の代わりに使われるようになったのであるから、牛鍋という名称がすき焼きになっただけとも考えられる.
もっとも、牛鍋に使われた肉は角切りの場合もあり、味噌味のものもあったので、すき焼き風になった牛鍋というほうが正しいであろう.
また、大和煮はもともとが缶詰であり、当然、明治以降の発明である.
つまり、関東のすき焼きは煮るものであるが、本来は焼くものであったということになる.
これは#443に書いたように、日本の肉食の基本が鍋であったということを考えると、この時代の、この国においては、特異な料理法である.
しかも、すき焼きの「すき」は、好きに焼くからだとこじつける人もいるが、農具である鋤の上で焼いたことに由来する.
他には杉焼きから来たとか、「すきみ」に由来すると書いてあるものがある.
杉焼きというのは#316で示した「料理物語」の中に登場する.
ただし、杉箱の中に鯛だとか野菜だとかを入れて味噌で煮るもので、ここで書いているすき焼きとは似ても似つかぬものである.
また、「すきみ」、つまり、薄く削いだ肉に由来するというのは、薄切りの牛肉を用いるものだから、妥当なように見えるが、この語は魚肉に用いるのが本来である.
したがって、鋤焼きのほうが語源説としては正しい.
2023.6/28
Up Down
#447
実際、「料理早指南」という1801年刊行の料理書によると、鋤やきは「雁鴨かもしかのるい(中略)鋤のうへに右の鳥類をやく也」とある.
この鋤というのは、地面を掘ったり、草の根を切るのに使用される農機具である.
鍬と似ているが、鉾のように、金属部分が柄の先にまっすぐ、もしくは、やや傾いてついている.
中国では鍬という文字を使い、鋤は日本でいう鍬(くわ)に相当する.
「日本書紀」ではスキを鍬と書いているが、「古事記」では鋤(字体は金偏に且)を使っているので、かなり古い時期に間違ったようである.
ただ、弥生時代の遺跡から木鋤が見つかっているので、日本でも使われていたことになる.
掘棒の類を除けば、最古の農具となるが、形状の近いスコップ類の普及により駆逐された農具である.
文献上の初出は「雄略記」で、「乙女のい隠る丘を金鋤も五百箇もがも鋤き撥ぬるもの」という歌がそうである.
乙女が隠れた岡を金鋤の五百もあれば岡をならして(見つけられる)ものなのにという意味で、金鋤は「加那須岐(かなすき)」と万葉仮名で書かれている.
そして、この歌が詠まれたために「号其岡謂金鋤岡也(その岡を金鋤岡と号(なづ)くと謂う)」とあるのだから、この時代には金属製の物が広まっていたことになる.
実際、弥生時代の遺跡からも青銅製や鉄製のものが出ている.
また、「料理早指南」の記述によれば、鳥肉を焼く料理であるが、他の料理書では、鯨肉や魚類を焼くものも紹介されている.
この当時の鯨は巨大な魚という扱いであるが、かもしかも含めて、すき焼きとは、鋤の上で肉を焼く料理の総称ということになる.
むしろ、牛肉を使用するとは限らないとなるのだが、確実に牛肉を鋤の上で焼いているのが分かるのは、蘭学者箕作阮甫の日記「西征紀行」である.
阮甫は、ペリーの持ってきたアメリカ大統領の国書を翻訳したことで知られる人物であるが、長崎での日露和親条約締結に向けての交渉にも参加した.
この時の正使が#426に取り上げた川路聖謨であるが、彼は年賀としてロシアから牛肉を貰い、反訳清書を届けた阮甫が用人部屋でこれを食べさせて貰っている.
1854年正月5日のことである.
2023.7/1
Up
Down
#447
実際、「料理早指南」という1801年刊行の料理書によると、鋤やきは「雁鴨かもしかのるい(中略)鋤のうへに右の鳥類をやく也」とある.
この鋤というのは、地面を掘ったり、草の根を切るのに使用される農機具である.
鍬と似ているが、鉾のように、金属部分が柄の先にまっすぐ、もしくは、やや傾いてついている.
中国では鍬という文字を使い、鋤は日本でいう鍬(くわ)に相当する.
「日本書紀」ではスキを鍬と書いているが、「古事記」では鋤(字体は金偏に且)を使っているので、かなり古い時期に間違ったようである.
ただ、弥生時代の遺跡から木鋤が見つかっているので、日本でも使われていたことになる.
掘棒の類を除けば、最古の農具となるが、形状の近いスコップ類の普及により駆逐された農具である.
文献上の初出は「雄略記」で、「乙女のい隠る丘を金鋤も五百箇もがも鋤き撥ぬるもの」という歌がそうである.
乙女が隠れた岡を金鋤の五百もあれば岡をならして(見つけられる)ものなのにという意味で、金鋤は「加那須岐(かなすき)」と万葉仮名で書かれている.
そして、この歌が詠まれたために「号其岡謂金鋤岡也(その岡を金鋤岡と号(なづ)くと謂う)」とあるのだから、この時代には金属製の物が広まっていたことになる.
実際、弥生時代の遺跡からも青銅製や鉄製のものが出ている.
また、「料理早指南」の記述によれば、鳥肉を焼く料理であるが、他の料理書では、鯨肉や魚類を焼くものも紹介されている.
この当時の鯨は巨大な魚という扱いであるが、かもしかも含めて、すき焼きとは、鋤の上で肉を焼く料理の総称ということになる.
むしろ、牛肉を使用するとは限らないとなるのだが、確実に牛肉を鋤の上で焼いているのが分かるのは、蘭学者箕作阮甫の日記「西征紀行」である.
阮甫は、ペリーの持ってきたアメリカ大統領の国書を翻訳したことで知られる人物であるが、長崎での日露和親条約締結に向けての交渉にも参加した.
この時の正使が#426に取り上げた川路聖謨であるが、彼は年賀としてロシアから牛肉を貰い、反訳清書を届けた阮甫が用人部屋でこれを食べさせて貰っている.
1854年正月5日のことである.
2023.7/1
Up Down
#448
牛は1/4頭分を白布に包んだものだそうである.
「西征紀行」には「牛肉を余輩のために松前の犂にて烹(に)て一盃を進む」とある.
犂は、牛馬に牽かせる大型の鋤である.
松前は、「まさき」と読むと愛媛県にあるが、通常は北海道のことである.
当時の言い方なら、蝦夷地である.
松浦武四郎が同地を北加伊道(北海道)と命名したのは、この日記の書かれた15年後の1869年で、松前家の領地であることからこう呼ばれていた.
もっとも、長崎に「松前の犂」があるのも奇妙な話であるが、日記は、この後、「江戸より来りて俄羅斯牛肉を松前の犂にて烹るとハ、人生の一奇事なるべし」と続く.
江戸から長崎に来て、ロシアの牛肉を松前の犂で烹るとは奇妙な話であるというのである.
つまり、松前は、ロシアとともに、江戸や長崎の対蹠点として挙げられていることになる.
したがって、この松前は北海道を意味すると考えるしかないので、誰かが収集したアイヌ式の犂が置いてあったのかもしれない.
もっとも、松前家は彼等に鉄が渡るのを制限していたので、形式はアイヌ式でも、材料は違っていた可能性はあるが、アイヌと本土の犂の違いはよく分からなかった.
しかし、木製の犂で烹るのは難しい.
紙鍋でも水分が蒸発しない限りは煮炊きできるが、木製の鍋では無理だからである.
第一、鉄鍋ぐらいあるだろうから、そのようなことをする理由がない.
したがって、刃先だけでも金属のものでないとおかしいわけだが、それだと平たい金属板である.
「烹て」とはあるが、煮るのに使うのには適しない形状である.
ただし、この字は割烹のように料理するという意味で使われるので、牛肉を犂の上で料理したという意味であろう.
だとすれば、牛肉を手に入れた阮甫等は、当時の獣肉の通常の料理法である鍋ではなく、すき焼きを選んだということになる.
松前の犂があったからであろうが、牛肉を調理するのならすき焼きであるという常識があったということである.
2023.7/26
Down
#448
牛は1/4頭分を白布に包んだものだそうである.
「西征紀行」には「牛肉を余輩のために松前の犂にて烹(に)て一盃を進む」とある.
犂は、牛馬に牽かせる大型の鋤である.
松前は、「まさき」と読むと愛媛県にあるが、通常は北海道のことである.
当時の言い方なら、蝦夷地である.
松浦武四郎が同地を北加伊道(北海道)と命名したのは、この日記の書かれた15年後の1869年で、松前家の領地であることからこう呼ばれていた.
もっとも、長崎に「松前の犂」があるのも奇妙な話であるが、日記は、この後、「江戸より来りて俄羅斯牛肉を松前の犂にて烹るとハ、人生の一奇事なるべし」と続く.
江戸から長崎に来て、ロシアの牛肉を松前の犂で烹るとは奇妙な話であるというのである.
つまり、松前は、ロシアとともに、江戸や長崎の対蹠点として挙げられていることになる.
したがって、この松前は北海道を意味すると考えるしかないので、誰かが収集したアイヌ式の犂が置いてあったのかもしれない.
もっとも、松前家は彼等に鉄が渡るのを制限していたので、形式はアイヌ式でも、材料は違っていた可能性はあるが、アイヌと本土の犂の違いはよく分からなかった.
しかし、木製の犂で烹るのは難しい.
紙鍋でも水分が蒸発しない限りは煮炊きできるが、木製の鍋では無理だからである.
第一、鉄鍋ぐらいあるだろうから、そのようなことをする理由がない.
したがって、刃先だけでも金属のものでないとおかしいわけだが、それだと平たい金属板である.
「烹て」とはあるが、煮るのに使うのには適しない形状である.
ただし、この字は割烹のように料理するという意味で使われるので、牛肉を犂の上で料理したという意味であろう.
だとすれば、牛肉を手に入れた阮甫等は、当時の獣肉の通常の料理法である鍋ではなく、すき焼きを選んだということになる.
松前の犂があったからであろうが、牛肉を調理するのならすき焼きであるという常識があったということである.
2023.7/26
PREVIOUS ☆ NEXT
Since 7 Jan.
2023.
Last up-dated,
26 July 2023.


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
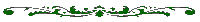 Sasayaki015.
Sasayaki015.
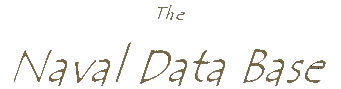 Ver.1.23a.
Ver.1.23a.
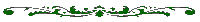 Copyright (c) hush ,2001-23. Allrights
Reserved.
Copyright (c) hush ,2001-23. Allrights
Reserved.
Up
動画