Down
無用の記録
1-
51- 101-
150- 191-
乱丸:#10 トヨタ:#19 ナマズ:#28 レストラン:#37 桜の開花情報:#43 ツバキ:#49 自閉症:#53 太陽は赤い:#58 日出処天子:#89 ミイラ取り:#96
国:#109 リンゴ:#114 米:#137 50音:#150 タヌキ:#163 象:#193 鵲:#212 虎:#222
銀杏について:229-
一寸法師:255-
春暁:293-
日本人と肉食について
前編:311-
333- 361-
383- 402-
後編:422-
猫年412-
カチカチ山422-
trivia's
trivia
Up Down
#1
1923ハワイ准州上下両院の連合決議案第1号が決議された.
これはハイビスカスをハワイの花とするものであった.
2015.2/2
Up
Down
#1
1923ハワイ准州上下両院の連合決議案第1号が決議された.
これはハイビスカスをハワイの花とするものであった.
2015.2/2
Up Down
#2
節分というのは立春の前日で、この日、鰯の頭に柊の枝を刺すのは春迎えの行事で、五行で水気に配当される魚、弱、冬を木気(春)で殺すことを意味し、平安時代の「土左日記」にも登場する.
2015.2/3
Up
Down
#2
節分というのは立春の前日で、この日、鰯の頭に柊の枝を刺すのは春迎えの行事で、五行で水気に配当される魚、弱、冬を木気(春)で殺すことを意味し、平安時代の「土左日記」にも登場する.
2015.2/3
Up Down
#3
人参のヘタの部分を水に浸けておくと芽が出て、葉が出るが、同様のことは大根ではできない.
これは、人参のヘタは根の一部であるが、大根の根のように見える部分の上部は茎だからである.
このため、上部を土の上に出しておくと緑色になる.
いわゆる青首大根である.
2015.2/4
Up
Down
#3
人参のヘタの部分を水に浸けておくと芽が出て、葉が出るが、同様のことは大根ではできない.
これは、人参のヘタは根の一部であるが、大根の根のように見える部分の上部は茎だからである.
このため、上部を土の上に出しておくと緑色になる.
いわゆる青首大根である.
2015.2/4
Up Down
#4
大根は、英語では、日本語のままdaikonとかdaikon radishと言うが、これはドイツ語でも一緒である.
また、大根という漢字を中国人に見せても、理解されない.
これは、中国にないからではなく、中国語で大根は羅葡と言うからだが、大根の繊切りを千六本と言うのは、中国語の繊羅葡(シエンルオポ)に由来する.
ペルー人に言わすと、大根は売っているが、日本のように大きなものはないそうである.
ただし、ブラジルでは日本のと同じものを売っているそうだが、日系人が作っているのかもしれないとのことである.
2015.2/5
Up
Down
#4
大根は、英語では、日本語のままdaikonとかdaikon radishと言うが、これはドイツ語でも一緒である.
また、大根という漢字を中国人に見せても、理解されない.
これは、中国にないからではなく、中国語で大根は羅葡と言うからだが、大根の繊切りを千六本と言うのは、中国語の繊羅葡(シエンルオポ)に由来する.
ペルー人に言わすと、大根は売っているが、日本のように大きなものはないそうである.
ただし、ブラジルでは日本のと同じものを売っているそうだが、日系人が作っているのかもしれないとのことである.
2015.2/5
Up Down
#5
ブラジル人に聞いた話.
この料理はどうやって作るのですか?
バカをアホとサルで味付けして….
ポルトガル語で、Vacaは牛肉、Alhoはニンニク、Salは塩を意味する.
バカをアホで炒めてというのは思いついたことはあるが、それにサルを加えるのは思いつかなかった.
残念である.
2015.2/6
Up
Down
#5
ブラジル人に聞いた話.
この料理はどうやって作るのですか?
バカをアホとサルで味付けして….
ポルトガル語で、Vacaは牛肉、Alhoはニンニク、Salは塩を意味する.
バカをアホで炒めてというのは思いついたことはあるが、それにサルを加えるのは思いつかなかった.
残念である.
2015.2/6
Up Down
#6
揚子江と言っても、今の若い方には通じない.
昨今は長江と言うからである.
これは、揚子江が一部地域名だったからで、中国本土の呼び方に統一したということらしい.
また、メキシコ湾流は北大西洋海流と言うらしいし、新羅、百済は、「しらぎ、くだら」ではなく、新羅は「しんら、しるら」、百済は「ひゃくさい、ぺくちぇ」、と呼ぶらしい.
ふーん.
2015.2/7
Up
Down
#6
揚子江と言っても、今の若い方には通じない.
昨今は長江と言うからである.
これは、揚子江が一部地域名だったからで、中国本土の呼び方に統一したということらしい.
また、メキシコ湾流は北大西洋海流と言うらしいし、新羅、百済は、「しらぎ、くだら」ではなく、新羅は「しんら、しるら」、百済は「ひゃくさい、ぺくちぇ」、と呼ぶらしい.
ふーん.
2015.2/7
Up Down
#7
豊臣秀吉を祭る京都の豊国神社は1615年に徳川家康の命令により破却された豊国廟を1868再興したものである.
再興時、まだ戊辰戦争の真っ最中であったが、新政府は反徳川の象徴となるものを探しており、そこで選ばれたのが秀吉だったからである.
秀吉の墓所である阿弥陀ヶ峰へ向かう道を塞ぐ格好で、幕府が移設させた新日吉(いまひえ)神社神殿を仮社殿としたこの神社は
1881年、現在地である方広寺大仏殿跡に遷座している.
ところで、その7年後の1898年は秀吉の没後300年であった.
この時、盛大な式典が開かれ、大衆芸能を中心に秀吉の人気が高まったが、これは、その前年にあった日清戦争の勝利が大きい.
戦争の主戦場は朝鮮半島であったが、これより先に同地に侵攻したのが秀吉であったからである.
2015.2/8
Up
Down
#7
豊臣秀吉を祭る京都の豊国神社は1615年に徳川家康の命令により破却された豊国廟を1868再興したものである.
再興時、まだ戊辰戦争の真っ最中であったが、新政府は反徳川の象徴となるものを探しており、そこで選ばれたのが秀吉だったからである.
秀吉の墓所である阿弥陀ヶ峰へ向かう道を塞ぐ格好で、幕府が移設させた新日吉(いまひえ)神社神殿を仮社殿としたこの神社は
1881年、現在地である方広寺大仏殿跡に遷座している.
ところで、その7年後の1898年は秀吉の没後300年であった.
この時、盛大な式典が開かれ、大衆芸能を中心に秀吉の人気が高まったが、これは、その前年にあった日清戦争の勝利が大きい.
戦争の主戦場は朝鮮半島であったが、これより先に同地に侵攻したのが秀吉であったからである.
2015.2/8
Up Down
#8
豊国神社のある方広寺は秀吉が東大寺の大仏より大きな盧舎那仏を本尊にして建てられたものである.
その後、子の秀頼が大仏を完成させたが、家康が梵鐘の銘文に「国家安康」、「君臣豊楽」の文字があるのは、
家康の家と康を分断し豊臣を君主とする意味だとして開眼供養を延期させたのは、有名な話である.
この大仏は1662年に地震により壊れ、熔かされた銅は寛永通宝となったといわれるが、
梵鐘のほうは、不思議なことに、今に残る.
2015.2/9
Up
Down
#8
豊国神社のある方広寺は秀吉が東大寺の大仏より大きな盧舎那仏を本尊にして建てられたものである.
その後、子の秀頼が大仏を完成させたが、家康が梵鐘の銘文に「国家安康」、「君臣豊楽」の文字があるのは、
家康の家と康を分断し豊臣を君主とする意味だとして開眼供養を延期させたのは、有名な話である.
この大仏は1662年に地震により壊れ、熔かされた銅は寛永通宝となったといわれるが、
梵鐘のほうは、不思議なことに、今に残る.
2015.2/9
Up Down
#9
方広寺の鐘どころか、寺そのものも遺っている.
もちろん、規模は随分と縮小されているのだが、豊国廟が破棄されたのと大きな違いを見せている.
これは銘文を考えた南禅寺の文英清韓を藤堂高虎が庇護したからだとか、
秀吉の正室ねねが存続を願ったからだとか、寺ゆえに、家康も手を出さなかったのだとか、諸説が出ている.
また、「国家安康」、「君臣豊楽」等という文言を家康は気にしておらず、開戦の道具に使っただけだからという人もいる.
しかし、1780年に刊行された「都名所図会」に掲載されている同寺大仏殿は非常に巨大なものである.
この大仏殿はその18年後に落雷により木造の大仏とともに焼失したが、
その後、大仏のみは肩より上だけを、以前より縮小した形で再建されている.
この大仏の様子は「東海道中膝栗毛」の中に描写されているが、
掌に畳が8枚敷けるというように、その巨大さを伝えている.
そのようなものの存在を許したのは、目立つからであろう.
つまり、この近在を通った者は、東大寺の大仏を超えるその巨大さに驚き、豊臣家の巨富に思いを馳せるであろう.
そして、その次に、その豊臣家を滅ぼしたのは誰かということになる.
幕府に逆らった者はどうなるのか、この寺や大仏、また、梵鐘を見る者に考えさせることになるのである.
2015.2/10
Up
Down
#9
方広寺の鐘どころか、寺そのものも遺っている.
もちろん、規模は随分と縮小されているのだが、豊国廟が破棄されたのと大きな違いを見せている.
これは銘文を考えた南禅寺の文英清韓を藤堂高虎が庇護したからだとか、
秀吉の正室ねねが存続を願ったからだとか、寺ゆえに、家康も手を出さなかったのだとか、諸説が出ている.
また、「国家安康」、「君臣豊楽」等という文言を家康は気にしておらず、開戦の道具に使っただけだからという人もいる.
しかし、1780年に刊行された「都名所図会」に掲載されている同寺大仏殿は非常に巨大なものである.
この大仏殿はその18年後に落雷により木造の大仏とともに焼失したが、
その後、大仏のみは肩より上だけを、以前より縮小した形で再建されている.
この大仏の様子は「東海道中膝栗毛」の中に描写されているが、
掌に畳が8枚敷けるというように、その巨大さを伝えている.
そのようなものの存在を許したのは、目立つからであろう.
つまり、この近在を通った者は、東大寺の大仏を超えるその巨大さに驚き、豊臣家の巨富に思いを馳せるであろう.
そして、その次に、その豊臣家を滅ぼしたのは誰かということになる.
幕府に逆らった者はどうなるのか、この寺や大仏、また、梵鐘を見る者に考えさせることになるのである.
2015.2/10
Up Down
#10
織田信長の小姓として有名な森蘭丸は、本来、乱丸だったのかもしれない.
信長の添状に森乱成利と書かれており、「信長公記」にも森乱としか書かれていないからである.
蘭丸となったのは、江戸時代中期の儒学者貝原益軒が「朝野雑載」に「お蘭」と書いてからである.
この中で、彼が台に橘を満載したのを持とうとしたのを
信長が「おらん、其方が力にてはあぶなし.倒るるな」と制したという話を載せている.
そして、座敷中に橘が転がったのを、後に気の毒にと言われた際に、信長がそう言われたので、わざと倒れたと答えたという.
他にも、彼が信長に忠誠を尽くしたという話が載っているが、ある意味、度を越したものが多い.
しかし、このような挿話は、先行書には登場しない.
信長在世中に記録されなかった挿話が、江戸時代中期にもなって「発見」されたわけである.
男性の名に「お」を冠し、蘭の字を使用したのは、信長が好色であり、男色にも通じていたと言いたかったのであろう.
2015.2/11
Up
Down
#10
織田信長の小姓として有名な森蘭丸は、本来、乱丸だったのかもしれない.
信長の添状に森乱成利と書かれており、「信長公記」にも森乱としか書かれていないからである.
蘭丸となったのは、江戸時代中期の儒学者貝原益軒が「朝野雑載」に「お蘭」と書いてからである.
この中で、彼が台に橘を満載したのを持とうとしたのを
信長が「おらん、其方が力にてはあぶなし.倒るるな」と制したという話を載せている.
そして、座敷中に橘が転がったのを、後に気の毒にと言われた際に、信長がそう言われたので、わざと倒れたと答えたという.
他にも、彼が信長に忠誠を尽くしたという話が載っているが、ある意味、度を越したものが多い.
しかし、このような挿話は、先行書には登場しない.
信長在世中に記録されなかった挿話が、江戸時代中期にもなって「発見」されたわけである.
男性の名に「お」を冠し、蘭の字を使用したのは、信長が好色であり、男色にも通じていたと言いたかったのであろう.
2015.2/11
Up Down
#11
もっとも、この当時、人名等に適当な字を当てるのは、よくあることである.
たとえば、坂本龍馬の名を、勝海舟は「氷川清話」の中で坂下良馬と書いており、木戸孝允の手紙には坂本良馬として登場する.
このため、龍は「りゅう」ではなく「りょう」が正しいとなる.
良に、「りゅう」という読み方はないからである.
ただ、明治時代に坂崎紫瀾という人が小説の中で登場させた際には、
龍馬に「りゅうま」と振り仮名をしていたそうで、「りょうま」という読み方は知られていなかった.
本人が姪への手紙で「りよふ」と記していることもあって、「りょうま」でよいのだが、
司馬遼太郎が小説の主人公に取り上げるまで、この読み方は知られていなかったのである.
もっとも、坂崎紫瀾が小説に取り上げたなどということは、よほどの好事家でなければ知らんことであるので、
坂本龍馬は、司馬遼太郎が発掘したといっても過言ではない.
2015.2/12
Up
Down
#11
もっとも、この当時、人名等に適当な字を当てるのは、よくあることである.
たとえば、坂本龍馬の名を、勝海舟は「氷川清話」の中で坂下良馬と書いており、木戸孝允の手紙には坂本良馬として登場する.
このため、龍は「りゅう」ではなく「りょう」が正しいとなる.
良に、「りゅう」という読み方はないからである.
ただ、明治時代に坂崎紫瀾という人が小説の中で登場させた際には、
龍馬に「りゅうま」と振り仮名をしていたそうで、「りょうま」という読み方は知られていなかった.
本人が姪への手紙で「りよふ」と記していることもあって、「りょうま」でよいのだが、
司馬遼太郎が小説の主人公に取り上げるまで、この読み方は知られていなかったのである.
もっとも、坂崎紫瀾が小説に取り上げたなどということは、よほどの好事家でなければ知らんことであるので、
坂本龍馬は、司馬遼太郎が発掘したといっても過言ではない.
2015.2/12
Up Down
#12
「朝野雑載」でも、「森お蘭是を披露す」とある以外は「おらん」であり、ことさらに蘭を使用したわけではない.
また、「石山本願寺日記」だけだが、同時代の文書としては珍しく、本能寺で信長とともに討死にした人物として「森お蘭」と記載されている.
したがって、蘭の字は、単なる当て字と考えてもよいのだが、問題は「お」である.
あまり、男性の名に「お」を冠することはないと思うのだが、これはこの当時の風習だったのか、織田家だけのものだったのか知りたいものだと思う.
2015.2/13
Up
Down
#12
「朝野雑載」でも、「森お蘭是を披露す」とある以外は「おらん」であり、ことさらに蘭を使用したわけではない.
また、「石山本願寺日記」だけだが、同時代の文書としては珍しく、本能寺で信長とともに討死にした人物として「森お蘭」と記載されている.
したがって、蘭の字は、単なる当て字と考えてもよいのだが、問題は「お」である.
あまり、男性の名に「お」を冠することはないと思うのだが、これはこの当時の風習だったのか、織田家だけのものだったのか知りたいものだと思う.
2015.2/13
Up Down
#13
岐阜県各務原市には織田町、信長町がある.
2015.2/15
Up
Down
#13
岐阜県各務原市には織田町、信長町がある.
2015.2/15
Up Down
Down
 奈良市南都銀行本店(1926六十八銀行奈良支店として竣工)にて、2011年2月19日撮影.
Up
奈良市南都銀行本店(1926六十八銀行奈良支店として竣工)にて、2011年2月19日撮影.
Up Down
#14
上の写真はキャプションにもあるように大正末年に竣工した六十八銀行奈良支店、現在の奈良市南都銀行本店玄関の列柱であるが、羊のレリーフがあるのは、家畜が財産という意味を持つからである.
設計した長野宇平治の作品の一つに1920年竣工した三井銀行下関支店、現在は山口銀行旧本店として一般開放されている建物の正面窓の上に牛が浮彫りされており、南都銀行本店と同じように花綱で飾られているからである.
長野宇平治は東京駅の設計者として知られる辰野金吾の弟子だが、ギリシャ、ローマの建築様式に興味があったのだろうと思う.
イオニア様式の柱もそうだが、家畜が財産の象徴になるというのも、このあたりの考えだからである.
2015.1/16
Up
Down
#14
上の写真はキャプションにもあるように大正末年に竣工した六十八銀行奈良支店、現在の奈良市南都銀行本店玄関の列柱であるが、羊のレリーフがあるのは、家畜が財産という意味を持つからである.
設計した長野宇平治の作品の一つに1920年竣工した三井銀行下関支店、現在は山口銀行旧本店として一般開放されている建物の正面窓の上に牛が浮彫りされており、南都銀行本店と同じように花綱で飾られているからである.
長野宇平治は東京駅の設計者として知られる辰野金吾の弟子だが、ギリシャ、ローマの建築様式に興味があったのだろうと思う.
イオニア様式の柱もそうだが、家畜が財産の象徴になるというのも、このあたりの考えだからである.
2015.1/16
Up Down
#15
イトーヨーカドーは1920年に東京浅草に開店した羊華堂洋品店が前身である.
この羊華は銀座で繁盛していた日華堂にちなんだもので、日を羊に変えたのは、創業者が未年の生まれだったからである.
2015.2/17
Up
Down
#15
イトーヨーカドーは1920年に東京浅草に開店した羊華堂洋品店が前身である.
この羊華は銀座で繁盛していた日華堂にちなんだもので、日を羊に変えたのは、創業者が未年の生まれだったからである.
2015.2/17
Up Down
#16
三重県四日市市にできたサークルKが、私が県内で出会った最初のコンヴィニエンス・ストアーである.
今から30年くらい昔のことである.
ここは、当の昔になくなったが、今でも覚えているのは、夜9時までの営業だったということである.
現在の感覚から行くと、それはコンヴィニエンス・ストアーと呼べないとなりそうだが、
深夜の国道で開いていたのはこの店だけだったのである.
しかし、この種の店が、最初から24時間営業だったわけではない.
1927年、テキサス州のサウスランド・アイスという氷屋が週7日16時間営業を始めた.
家庭用冷蔵庫が普及していなかった時代、氷というのは、各家庭にとって重要な代物だったからである.
このため、夏季限定であったが、日曜日も営業、朝から深夜までというこのスタイルは、
周辺家庭に好評を持って迎えられた.
そして、日用品も扱ってはという意見に従った同店は、本社の同意の上に、これを実施、さらなる喜びで迎えられた.
戦後、1946年にこの会社は7-Elevenと改名したが、これは朝7時から夜11時までという営業時間によるものである.
都市部は知らないが、地方都市の場合、深夜に営業するのは、人件費だけでも大変である.
夜9時は少し早いだろうが、12時くらいまでにして、4-5時間閉店しても、あまり困る人はいないように思う.
2015.2/18
Up
Down
#16
三重県四日市市にできたサークルKが、私が県内で出会った最初のコンヴィニエンス・ストアーである.
今から30年くらい昔のことである.
ここは、当の昔になくなったが、今でも覚えているのは、夜9時までの営業だったということである.
現在の感覚から行くと、それはコンヴィニエンス・ストアーと呼べないとなりそうだが、
深夜の国道で開いていたのはこの店だけだったのである.
しかし、この種の店が、最初から24時間営業だったわけではない.
1927年、テキサス州のサウスランド・アイスという氷屋が週7日16時間営業を始めた.
家庭用冷蔵庫が普及していなかった時代、氷というのは、各家庭にとって重要な代物だったからである.
このため、夏季限定であったが、日曜日も営業、朝から深夜までというこのスタイルは、
周辺家庭に好評を持って迎えられた.
そして、日用品も扱ってはという意見に従った同店は、本社の同意の上に、これを実施、さらなる喜びで迎えられた.
戦後、1946年にこの会社は7-Elevenと改名したが、これは朝7時から夜11時までという営業時間によるものである.
都市部は知らないが、地方都市の場合、深夜に営業するのは、人件費だけでも大変である.
夜9時は少し早いだろうが、12時くらいまでにして、4-5時間閉店しても、あまり困る人はいないように思う.
2015.2/18
Up Down
#17
もっとも、同じ頃に東京に住んでいた相方に言わせると、アパートの近くに7-Elevenがあって、
11時までやっているだって、凄いねよ言いながら出かけて行ったそうである.
つまり、その当時の東京でもそうであったのだから、地方都市の場合、夜9時まででも充分に画期的だったのである.
それでも、これより先、東京で2部の大学に通っていたかつての同僚は、24時間営業のガソリン・スタンドで働いていたそうだから、
おそらくは長距離トラック対応だったのだろうが、一部では、すでに不夜城だったようである.
これに対し、うちの田舎は、昨年、ようやくコンヴィニエンス・ストアーができた.
それでも家から20km以上離れているのだが、ようやく限界集落にも都市化の波が押し寄せたのかもしれない.
もっとも、夜、通ったことがないので、何時まで営業しているかは知らない.
2015.2/19
Up
Down
#17
もっとも、同じ頃に東京に住んでいた相方に言わせると、アパートの近くに7-Elevenがあって、
11時までやっているだって、凄いねよ言いながら出かけて行ったそうである.
つまり、その当時の東京でもそうであったのだから、地方都市の場合、夜9時まででも充分に画期的だったのである.
それでも、これより先、東京で2部の大学に通っていたかつての同僚は、24時間営業のガソリン・スタンドで働いていたそうだから、
おそらくは長距離トラック対応だったのだろうが、一部では、すでに不夜城だったようである.
これに対し、うちの田舎は、昨年、ようやくコンヴィニエンス・ストアーができた.
それでも家から20km以上離れているのだが、ようやく限界集落にも都市化の波が押し寄せたのかもしれない.
もっとも、夜、通ったことがないので、何時まで営業しているかは知らない.
2015.2/19
Up Down
#18
7-Elevenのマークの7の部分は橙と赤に塗り分けられているが、橙は夜明けの色、赤は夕刻の空の色を表しているという説がある.
もっとも、随分昔からアメリカで使用されていたデザインを踏襲しているので、真相は分からないそうである.
同様に、ロゴがELEVEnと末尾だけ小文字になっているのも、真相は不明であるが、
711では一般名詞なので、商標登録ができなかったからであるとか、デザイン上の問題であるといわれている.
一方、この商標の使用権を持っているイトーヨーカ堂(店舗名はイトーヨーカドー)は、
本業であるスーパー・マーケット業のほうが7-Elevenよりも売上げが小さくなったので、主として敵対的買収の自衛策として、
ファミリー・レストランのデニーズとともに2005年に持株会社に移行した.
これが、セブン&アイ・ホールディングスであるが、そのロゴはSEVEN
& i HOLDINGSとなっており、iだけが小さい.
これは、イトーヨーカ堂のほうが小さくなったという自嘲的な意味でそうなったわけでなく、これもデザイン上の問題であろう.
2015.2/21
Up
Down
#18
7-Elevenのマークの7の部分は橙と赤に塗り分けられているが、橙は夜明けの色、赤は夕刻の空の色を表しているという説がある.
もっとも、随分昔からアメリカで使用されていたデザインを踏襲しているので、真相は分からないそうである.
同様に、ロゴがELEVEnと末尾だけ小文字になっているのも、真相は不明であるが、
711では一般名詞なので、商標登録ができなかったからであるとか、デザイン上の問題であるといわれている.
一方、この商標の使用権を持っているイトーヨーカ堂(店舗名はイトーヨーカドー)は、
本業であるスーパー・マーケット業のほうが7-Elevenよりも売上げが小さくなったので、主として敵対的買収の自衛策として、
ファミリー・レストランのデニーズとともに2005年に持株会社に移行した.
これが、セブン&アイ・ホールディングスであるが、そのロゴはSEVEN
& i HOLDINGSとなっており、iだけが小さい.
これは、イトーヨーカ堂のほうが小さくなったという自嘲的な意味でそうなったわけでなく、これもデザイン上の問題であろう.
2015.2/21
Up Down
#19
豊田佐吉というと豊田自動織機の創業者であり、トヨタ・グループの創業者とされる.
このため、トヨタが1967年に発売された車にセンチュリー(世紀)という名をつけている.
この年が明治100年だったからであるが、同時に豊田佐吉の生誕100年でもあったからである.
しかし、豊田佐吉の苗字は「とよだ」であり、「とよた」ではない.
もちろん、トヨタの現在の社長で、創業家の出である豊田章男の苗字も「とよだ」である.
実際、豊田自動織機自動車部として現在のトヨタが1935年に創業した際の商標はTOYODAとなっている.
しかし、その翌年、最初の乗用車は国産トヨタ号と命名され、翌年にはトヨタ自動車工業と社名も変更する.
というのは、この乗用車の販売に際して公募したトヨダ・マークで一等になったのが、
トヨタという文字を円で囲んだものであったからである.
つまり、社名を間違えているわけだが、これは応募総数2万7千通の中で、これしかないと思わせるものであった.
以後、1989年に現在のマークに変更されるまで使用されていた事実が、このことを雄弁に語っている.
しかし、困ったことにあまりに完璧なデザインであったので、トヨタをトヨダとするわけにはいかなかったのである.
濁点だけで、バランスが崩れるのである.
これが、国産トヨダ号だった乗用車を改名し、社名を変えた理由である.
もっとも、同社の公式HPにある公式見解には、そのようなことは書いてないし、もっと違う理由が書かれている.
ただ、トヨペットをトョペットと表記していた会社だから、デザイン第一だったのだと思うばかりである.
2015.2/22
Up
Down
#19
豊田佐吉というと豊田自動織機の創業者であり、トヨタ・グループの創業者とされる.
このため、トヨタが1967年に発売された車にセンチュリー(世紀)という名をつけている.
この年が明治100年だったからであるが、同時に豊田佐吉の生誕100年でもあったからである.
しかし、豊田佐吉の苗字は「とよだ」であり、「とよた」ではない.
もちろん、トヨタの現在の社長で、創業家の出である豊田章男の苗字も「とよだ」である.
実際、豊田自動織機自動車部として現在のトヨタが1935年に創業した際の商標はTOYODAとなっている.
しかし、その翌年、最初の乗用車は国産トヨタ号と命名され、翌年にはトヨタ自動車工業と社名も変更する.
というのは、この乗用車の販売に際して公募したトヨダ・マークで一等になったのが、
トヨタという文字を円で囲んだものであったからである.
つまり、社名を間違えているわけだが、これは応募総数2万7千通の中で、これしかないと思わせるものであった.
以後、1989年に現在のマークに変更されるまで使用されていた事実が、このことを雄弁に語っている.
しかし、困ったことにあまりに完璧なデザインであったので、トヨタをトヨダとするわけにはいかなかったのである.
濁点だけで、バランスが崩れるのである.
これが、国産トヨダ号だった乗用車を改名し、社名を変えた理由である.
もっとも、同社の公式HPにある公式見解には、そのようなことは書いてないし、もっと違う理由が書かれている.
ただ、トヨペットをトョペットと表記していた会社だから、デザイン第一だったのだと思うばかりである.
2015.2/22
Up Down
#20
豊田市は町村合併により豊橋市を抜いて、愛知県第2の大都市となったが、
もとは加茂郡挙母(ころも)町という田舎町であった.
ここに豊田自動織機自動車部が工場を建てたのは、地縁でもなんでもない.
もともと豊田家は静岡県湖西市の出である.
創業者の豊田喜一郎もそちらで生まれているが、名古屋市で育った.
そして、工場用地としてここを選んだのだが、それは、交通の要衝である割には土地が安かったからである.
また、田畑を潰したくないという意向もあり、示されたのが論地ヶ原という荒蕪地だったのも都合がよかったのである.
そして、挙母町は1951年に挙母市になったが、58年、商工会議所が豊田市と改名したいと申し出てきた.
挙母の名に馴染みを残す人も多く、改名には市を二分する論議が沸き起こったが、結局、翌年には豊田市になった.
もっとも、「とよだ」ではなく、「とよた」としたのは、個人を顕彰するためではないという意味なのだろうと思う.
2015.2/23
Up
Down
#20
豊田市は町村合併により豊橋市を抜いて、愛知県第2の大都市となったが、
もとは加茂郡挙母(ころも)町という田舎町であった.
ここに豊田自動織機自動車部が工場を建てたのは、地縁でもなんでもない.
もともと豊田家は静岡県湖西市の出である.
創業者の豊田喜一郎もそちらで生まれているが、名古屋市で育った.
そして、工場用地としてここを選んだのだが、それは、交通の要衝である割には土地が安かったからである.
また、田畑を潰したくないという意向もあり、示されたのが論地ヶ原という荒蕪地だったのも都合がよかったのである.
そして、挙母町は1951年に挙母市になったが、58年、商工会議所が豊田市と改名したいと申し出てきた.
挙母の名に馴染みを残す人も多く、改名には市を二分する論議が沸き起こったが、結局、翌年には豊田市になった.
もっとも、「とよだ」ではなく、「とよた」としたのは、個人を顕彰するためではないという意味なのだろうと思う.
2015.2/23
Up Down
#21
奈良県天理市の名は、天理教に由来する.
旧名は丹波市町であるが、1954年の合併時にこの市名になったが、
天理教側は丹波市町のあった山辺郡の名を採って、山辺市を推していたようである.
実際、信者の一人が市長を相手取って、山辺市に改名するように裁判を起こしたことがあるが、
この人物が市民どころか、奈良県民でもなかったので、門前払いになっている.
同様に、岡山県浅口郡金光町は、金光教に由来していたが、2006年、、合併により浅口市となって消滅した.
先の豊田市も含めて、私的な団体名を自治体名にしたのは、この3つだけであるという.
ただし、市町村内の町名としては、随分とたくさんある.
たとえば、津市三重町は、後に合併して東洋紡となった三重紡績の宿舎があったところで、
雲出鋼管町には、日本鋼管(現在はJFEスチール)津製作所がある.
また、四日市市の石原町、大協町、東邦町、富士町は、
石原産業、大協石油(現在はコスモ石油)、東邦重工業(現在は三菱化学)、富士電機(現在は富士電機システムズ)に由来する.
これらは、埋立て地にあり、新町名を考える際に、そこに進出する社名をつけたのだろうが、行政側のサーヴィスでもあったと思う.
そして、鋼管町、鋼管通というような地名は、上記の津市以外にも神奈川県川崎市、岡山県笠岡市、広島県福山市にもある.
もっとも、やはりJFEスチールになった川崎製鉄の場合は、
岩手県久慈市、千葉市中央区、愛知県半田市、岡山県倉敷市にその名を冠した町があり、
川崎重工業のほうも岐阜県各務原市、兵庫県明石市、香川県坂出市に同様のものがある.
しかし、自治体名となるとハードルが高い.
先の天理市にしても、宗教団体側が嫌がったように、
そちらからの圧力で命名されたと考えられがちになり、印象が芳しくないからである.
したがって、大阪府門真市が、守口市と合併しようとした際に、新市名として松下市というのが候補に上ったらしいが、
松下電器産業(現在はパナソニック)のほうで断ったというのも、ありえる話なのである.
もっとも、守口市には松下町があり、ここには松下電池工業(現在はパナソニックのエナジー社)があるのだから、
それを徹底したわけではないらしいが.
2015.2/24
Up
Down
#21
奈良県天理市の名は、天理教に由来する.
旧名は丹波市町であるが、1954年の合併時にこの市名になったが、
天理教側は丹波市町のあった山辺郡の名を採って、山辺市を推していたようである.
実際、信者の一人が市長を相手取って、山辺市に改名するように裁判を起こしたことがあるが、
この人物が市民どころか、奈良県民でもなかったので、門前払いになっている.
同様に、岡山県浅口郡金光町は、金光教に由来していたが、2006年、、合併により浅口市となって消滅した.
先の豊田市も含めて、私的な団体名を自治体名にしたのは、この3つだけであるという.
ただし、市町村内の町名としては、随分とたくさんある.
たとえば、津市三重町は、後に合併して東洋紡となった三重紡績の宿舎があったところで、
雲出鋼管町には、日本鋼管(現在はJFEスチール)津製作所がある.
また、四日市市の石原町、大協町、東邦町、富士町は、
石原産業、大協石油(現在はコスモ石油)、東邦重工業(現在は三菱化学)、富士電機(現在は富士電機システムズ)に由来する.
これらは、埋立て地にあり、新町名を考える際に、そこに進出する社名をつけたのだろうが、行政側のサーヴィスでもあったと思う.
そして、鋼管町、鋼管通というような地名は、上記の津市以外にも神奈川県川崎市、岡山県笠岡市、広島県福山市にもある.
もっとも、やはりJFEスチールになった川崎製鉄の場合は、
岩手県久慈市、千葉市中央区、愛知県半田市、岡山県倉敷市にその名を冠した町があり、
川崎重工業のほうも岐阜県各務原市、兵庫県明石市、香川県坂出市に同様のものがある.
しかし、自治体名となるとハードルが高い.
先の天理市にしても、宗教団体側が嫌がったように、
そちらからの圧力で命名されたと考えられがちになり、印象が芳しくないからである.
したがって、大阪府門真市が、守口市と合併しようとした際に、新市名として松下市というのが候補に上ったらしいが、
松下電器産業(現在はパナソニック)のほうで断ったというのも、ありえる話なのである.
もっとも、守口市には松下町があり、ここには松下電池工業(現在はパナソニックのエナジー社)があるのだから、
それを徹底したわけではないらしいが.
2015.2/24
Up Down
#22
三重県鈴鹿市も本田市に改名しようとしたという話がある.
この時、本田宗一郎は歴史ある地名を変えるのはと言って固辞したという.
彼自身は、自分の子をホンダに入れなかったし、
社名をホンダにしたのは最大の失敗であると言っているのだから、当然であろう.
ただ、伝説の多い人物なので、これもその一つかもしれないが.
なお、トヨタ自動車高岡工場の所在地は、豊田市本田町である.
2015.2/25
Up
Down
#22
三重県鈴鹿市も本田市に改名しようとしたという話がある.
この時、本田宗一郎は歴史ある地名を変えるのはと言って固辞したという.
彼自身は、自分の子をホンダに入れなかったし、
社名をホンダにしたのは最大の失敗であると言っているのだから、当然であろう.
ただ、伝説の多い人物なので、これもその一つかもしれないが.
なお、トヨタ自動車高岡工場の所在地は、豊田市本田町である.
2015.2/25
Up Down
#23
豊田市本田町のトヨタ自動車高岡工場は、市内高岡地区にあるので、この名がある.
この高岡地区は、1965年に碧海郡高岡町を合併したことにより成立したものである.
そして、高岡町は1906年に駒場、若園、竹、堤の4村合併により成立した高岡村を前身としている.
うち、駒場、竹、堤の名は、現在も町名として残されているが、若園の名は残されていない.
ただ、同地域の町名は30ほどあるので、旧若園村だけが、いくつもの町に分散されたとは考えにくい.
ということは、各旧村の中心部のみに旧村名を継承し、その他の部分には新たに町名をつけたのであろう.
本田町は、その中の一つであろうが、問題はその時期である.
この工場は、高岡町の豊田市合併の翌年、1966年に操業を開始している.
したがって、合併前に名称変更がなされたのであろうとは思う.
もし、合併時になされたのであれば、トヨタ市にホンダの名の町が新たに作られ、
しかも、そこに工場を誘致させようということになるからである.
そして、住居表示に関する法律というものが作られ、各地の地名が大幅に変更されたのは、1962年以降だからである.
なお、この工場のかなりの部分が豊田市ではなく、刈谷市になっている.
Up
Down
#23
豊田市本田町のトヨタ自動車高岡工場は、市内高岡地区にあるので、この名がある.
この高岡地区は、1965年に碧海郡高岡町を合併したことにより成立したものである.
そして、高岡町は1906年に駒場、若園、竹、堤の4村合併により成立した高岡村を前身としている.
うち、駒場、竹、堤の名は、現在も町名として残されているが、若園の名は残されていない.
ただ、同地域の町名は30ほどあるので、旧若園村だけが、いくつもの町に分散されたとは考えにくい.
ということは、各旧村の中心部のみに旧村名を継承し、その他の部分には新たに町名をつけたのであろう.
本田町は、その中の一つであろうが、問題はその時期である.
この工場は、高岡町の豊田市合併の翌年、1966年に操業を開始している.
したがって、合併前に名称変更がなされたのであろうとは思う.
もし、合併時になされたのであれば、トヨタ市にホンダの名の町が新たに作られ、
しかも、そこに工場を誘致させようということになるからである.
そして、住居表示に関する法律というものが作られ、各地の地名が大幅に変更されたのは、1962年以降だからである.
なお、この工場のかなりの部分が豊田市ではなく、刈谷市になっている.
Up Down
#24
タイでは、バイクのことをホンダと呼ぶ.
このため、スズキのホンダという言い方もある.
2015.2/27
Up
Down
#24
タイでは、バイクのことをホンダと呼ぶ.
このため、スズキのホンダという言い方もある.
2015.2/27
Up Down
#25
50ccのバイク50台を連ねて四日市から伊勢まで行ったという話を、昔、聞いた.
50ccだから50台でも2500ccにしかならない.
普通乗用車1台分である.
それでも50人移動できるのだから、凄いなと思ったのだが、燃料代を考えると、ちょっと待てよとなる.
50km/lぐらい走ることができるバイクもあるそうだが、この当時のバイクなら30km/lぐらいではないかと思う.
四日市=伊勢間を60kmとすると、1台あたり片道で2l、往復で4lの燃料が必要である.
これが50台だから、往復では200l必要である.
これが乗用車だとどうだろう.
電気自動車が走っていなかった時代なので、普通乗用車の燃費が10km/lぐらいだと仮定する.
50人運ぶには10台、これで往復すると、120lですむ.
ついでにバスの燃費を調べてみると、だいたい2-3km/lという数値が出た.
もちろん、大型バスのそれであるから、一度に50人以上運べる.
それが、3km/lなら40l、2km/lでも60lで往復できるのである.
バイク50台が道路を走るのだから、運転次第では、渋滞を引起こす恐れもある.
楽しそうだなと思ったのだが、案外、贅沢なことなのだなと思った次第である.
2015.2/28
Up
Down
#25
50ccのバイク50台を連ねて四日市から伊勢まで行ったという話を、昔、聞いた.
50ccだから50台でも2500ccにしかならない.
普通乗用車1台分である.
それでも50人移動できるのだから、凄いなと思ったのだが、燃料代を考えると、ちょっと待てよとなる.
50km/lぐらい走ることができるバイクもあるそうだが、この当時のバイクなら30km/lぐらいではないかと思う.
四日市=伊勢間を60kmとすると、1台あたり片道で2l、往復で4lの燃料が必要である.
これが50台だから、往復では200l必要である.
これが乗用車だとどうだろう.
電気自動車が走っていなかった時代なので、普通乗用車の燃費が10km/lぐらいだと仮定する.
50人運ぶには10台、これで往復すると、120lですむ.
ついでにバスの燃費を調べてみると、だいたい2-3km/lという数値が出た.
もちろん、大型バスのそれであるから、一度に50人以上運べる.
それが、3km/lなら40l、2km/lでも60lで往復できるのである.
バイク50台が道路を走るのだから、運転次第では、渋滞を引起こす恐れもある.
楽しそうだなと思ったのだが、案外、贅沢なことなのだなと思った次第である.
2015.2/28
Up Down
#26
ユウウツのウツという漢字を正確に書ける人は珍しいと思う.
しかし、中国人はたいていの人が書ける.
簡体字では郁だからである.
しかし、それは馥郁の郁であって、鬱ではないと言われそうである.
ただ、日本語と中国語では漢字が異なる場合がある.
有名なところでは、機が机になる.
飛行机(飛は簡体字)のように使うが、中国では机の意味の漢字は卓の下の十が木になった字である.
したがって、机という字は馴染みが少なく、同じ音である機の意味に使うのである.
他には、谷は穀の意味で使う.
中国語では谷は渓を使うからである.
また、微妙に字体が違う場合もある.
先ほどの卓もそうだが、骨とか、過とかいう文字の上の┌の部分が、┐になる.
どっちがもともとの字に近いのかは知らないが.
2015.3/1
Up
Down
#26
ユウウツのウツという漢字を正確に書ける人は珍しいと思う.
しかし、中国人はたいていの人が書ける.
簡体字では郁だからである.
しかし、それは馥郁の郁であって、鬱ではないと言われそうである.
ただ、日本語と中国語では漢字が異なる場合がある.
有名なところでは、機が机になる.
飛行机(飛は簡体字)のように使うが、中国では机の意味の漢字は卓の下の十が木になった字である.
したがって、机という字は馴染みが少なく、同じ音である機の意味に使うのである.
他には、谷は穀の意味で使う.
中国語では谷は渓を使うからである.
また、微妙に字体が違う場合もある.
先ほどの卓もそうだが、骨とか、過とかいう文字の上の┌の部分が、┐になる.
どっちがもともとの字に近いのかは知らないが.
2015.3/1
Up Down
#27
戦前だと思うが、漢文の先生が揚子江(長江)にマグロが泳いでいるのかと聞かれて、往生したという話があった.
これは、鮪という漢字が、昔の中国ではヘラチョウザメを指していたからである.
昔の中国人は、大海に住むマグロなど見たことがなかったのである.
したがって、杜甫あたりの詩に登場する鮪は、このヘラチョウザメのことである.
当然、マグロを食するなどということもなく、字もなかったが、日本の場合は違った.
縄文時代の遺跡からも骨が出ているからである.
また、「古事記」にも志毘(しび)の名で登場する.
ただし、それほど大切にされた魚ではない.
腐敗しやすく、保存のために干しても、食べられないほど堅くなる.
その上、生簀で飼うにも大きすぎる.
塩漬けにするしかないのだが、これだと味が落ちる.
したがって、古名の「しび」が死日に通じるなどと書いた人もいるぐらいだが、
醤油の登場により食べられるようになる.
醤油の中に身を漬けておくことによって、保存ができるようになったのである.
このため、鮨種にも使われるようにもなったが、大衆魚であった.
特に、トロと呼ばれる脂身の多い部分は腐敗しやすく、食べる人がいなかったという.
これが一変するのは、冷凍技術が発達したからであるが、馴染みはあるので漢字が必要であった.
このため、日本で作られたのが鮪という漢字である.
こういう漢字を国字というが、その頃は、中国にこの字があるのは知られていなかったのであろう.
もっとも、現代中国では、鮪は、マグロである.
おそらく、日本人を通じて伝わったのだろうが、昨今の乱獲報道を聞くと、
冷凍技術の発達をマグロたちは恨んでいるだろうなと思う.
2015.3/2
Up
Down
#27
戦前だと思うが、漢文の先生が揚子江(長江)にマグロが泳いでいるのかと聞かれて、往生したという話があった.
これは、鮪という漢字が、昔の中国ではヘラチョウザメを指していたからである.
昔の中国人は、大海に住むマグロなど見たことがなかったのである.
したがって、杜甫あたりの詩に登場する鮪は、このヘラチョウザメのことである.
当然、マグロを食するなどということもなく、字もなかったが、日本の場合は違った.
縄文時代の遺跡からも骨が出ているからである.
また、「古事記」にも志毘(しび)の名で登場する.
ただし、それほど大切にされた魚ではない.
腐敗しやすく、保存のために干しても、食べられないほど堅くなる.
その上、生簀で飼うにも大きすぎる.
塩漬けにするしかないのだが、これだと味が落ちる.
したがって、古名の「しび」が死日に通じるなどと書いた人もいるぐらいだが、
醤油の登場により食べられるようになる.
醤油の中に身を漬けておくことによって、保存ができるようになったのである.
このため、鮨種にも使われるようにもなったが、大衆魚であった.
特に、トロと呼ばれる脂身の多い部分は腐敗しやすく、食べる人がいなかったという.
これが一変するのは、冷凍技術が発達したからであるが、馴染みはあるので漢字が必要であった.
このため、日本で作られたのが鮪という漢字である.
こういう漢字を国字というが、その頃は、中国にこの字があるのは知られていなかったのであろう.
もっとも、現代中国では、鮪は、マグロである.
おそらく、日本人を通じて伝わったのだろうが、昨今の乱獲報道を聞くと、
冷凍技術の発達をマグロたちは恨んでいるだろうなと思う.
2015.3/2
Up Down
#28
鮎は、日本ではアユだが、中国語ではナマズを意味する.
ただ、日本で鮎という漢字を使用し始めたのは奈良時代で、「古事記」では年魚、「日本書紀」では細鱗魚と書かれている.
そして、記紀ともに女性が川でアユを釣れるかどうかで占いをしたという話である.
うち、「日本書紀」では、女性が神宮皇后になっているのだが、
古典に占いに使う魚だとなっているので、鮎という字を当てたのであろう.
しかし、後にナマズにこの字が使われているのを知って、鯰という字を当てたのだろう.
占は、もちろん、「セン」と読むが、粘土のように「ネン」と読む場合もあり、念と同じだからである.
そう思って、中国語のナマズを調べてみたら、鮎も使うが、鯰も使っていた.
どうやら、鯰は中国でできた字らしい.
せっかく考えたのに残念である.
2015.3/3
Up
Down
#28
鮎は、日本ではアユだが、中国語ではナマズを意味する.
ただ、日本で鮎という漢字を使用し始めたのは奈良時代で、「古事記」では年魚、「日本書紀」では細鱗魚と書かれている.
そして、記紀ともに女性が川でアユを釣れるかどうかで占いをしたという話である.
うち、「日本書紀」では、女性が神宮皇后になっているのだが、
古典に占いに使う魚だとなっているので、鮎という字を当てたのであろう.
しかし、後にナマズにこの字が使われているのを知って、鯰という字を当てたのだろう.
占は、もちろん、「セン」と読むが、粘土のように「ネン」と読む場合もあり、念と同じだからである.
そう思って、中国語のナマズを調べてみたら、鮎も使うが、鯰も使っていた.
どうやら、鯰は中国でできた字らしい.
せっかく考えたのに残念である.
2015.3/3
Up Down
#29
日本で、ナマズに鯰という文字が当てはめられた結果、この魚は地震を起こすことになった.
念という文字は、思念という言葉が示すように思うであり、五事の中の思に配当される.
五事というのは聴きなれないが、五行の中にある分類である.
貌、視、思、言、聴、つまり、表情、見ること、思うこと、言うこと、聴くことであるが、思は土気に配当される.
そして、ナマズの特徴は、泥中に棲み、鱗がなく、頭も、口も四角いということである.
泥が土であることは、説明を要しない.
鱗がないということは、五虫の中の裸虫に分類される.
裸虫とは、鱗も、羽も、毛も、甲もない動物という意味で、この場合の虫は、動物という意味である.
そして、裸虫は、土気に配当される.
また、四角は大地の象徴である.
中国では、地は方形で、空は円形だったからである.
つまり、ナマズは解字によっても、外観によっても、生息環境によっても、土気の生物ということになる.
その土気の生物が動くということは、大地が振動するということである.
これが、ナマズが騒ぐと、地震が起きるとなった理由である.
2015.3/4
Up
Down
#29
日本で、ナマズに鯰という文字が当てはめられた結果、この魚は地震を起こすことになった.
念という文字は、思念という言葉が示すように思うであり、五事の中の思に配当される.
五事というのは聴きなれないが、五行の中にある分類である.
貌、視、思、言、聴、つまり、表情、見ること、思うこと、言うこと、聴くことであるが、思は土気に配当される.
そして、ナマズの特徴は、泥中に棲み、鱗がなく、頭も、口も四角いということである.
泥が土であることは、説明を要しない.
鱗がないということは、五虫の中の裸虫に分類される.
裸虫とは、鱗も、羽も、毛も、甲もない動物という意味で、この場合の虫は、動物という意味である.
そして、裸虫は、土気に配当される.
また、四角は大地の象徴である.
中国では、地は方形で、空は円形だったからである.
つまり、ナマズは解字によっても、外観によっても、生息環境によっても、土気の生物ということになる.
その土気の生物が動くということは、大地が振動するということである.
これが、ナマズが騒ぐと、地震が起きるとなった理由である.
2015.3/4
Up Down
#30
中国で、ナマズを鮎と書くのは、体の表面が粘液で覆われているからであろう.
非常に狭いところに棲んでいるので、鱗よりも有利だったからだと思う.
というのは、同じような生育環境にあるウナギが、やはり、粘液で覆われているからである.
もっとも、ウナギの場合は鱗はある.
ただし、顕微鏡で見ないと分からないほど細かなものが皮下にあるので、分からない.
したがって、鮎はウナギでもよかったのだが、ウナギを意味する漢字は、中国でも鰻である.
曼は、蔓の文字が示すように、長いであるので、その細長い形状に注目したということになる.
このため、鮎はナマズとなるのだが、鯰という漢字は、中国では、あまり使われないので、念から五事の思という発想はない.
また、土気の生物という考えも少ないと思う.
黒いからである.
五行で、黒は水気の色である.
これに対し、土気の色は黄色である.
このあたり、日中間で見方が異なるのだが、中国の大地は黄色い.
黄砂の堆積でできているからである.
したがって、土気色という言葉も、本来は黄色のはずである.
黄疸の症状が出ている顔色を表す言葉だったのかもしれない.
したがって、ナマズは、中国では土気の生物ではなく、もちろん、地震を起こすこともない.
2015.3/5
Up
Down
#30
中国で、ナマズを鮎と書くのは、体の表面が粘液で覆われているからであろう.
非常に狭いところに棲んでいるので、鱗よりも有利だったからだと思う.
というのは、同じような生育環境にあるウナギが、やはり、粘液で覆われているからである.
もっとも、ウナギの場合は鱗はある.
ただし、顕微鏡で見ないと分からないほど細かなものが皮下にあるので、分からない.
したがって、鮎はウナギでもよかったのだが、ウナギを意味する漢字は、中国でも鰻である.
曼は、蔓の文字が示すように、長いであるので、その細長い形状に注目したということになる.
このため、鮎はナマズとなるのだが、鯰という漢字は、中国では、あまり使われないので、念から五事の思という発想はない.
また、土気の生物という考えも少ないと思う.
黒いからである.
五行で、黒は水気の色である.
これに対し、土気の色は黄色である.
このあたり、日中間で見方が異なるのだが、中国の大地は黄色い.
黄砂の堆積でできているからである.
したがって、土気色という言葉も、本来は黄色のはずである.
黄疸の症状が出ている顔色を表す言葉だったのかもしれない.
したがって、ナマズは、中国では土気の生物ではなく、もちろん、地震を起こすこともない.
2015.3/5
Up Down
#31
震は八卦の一つで、東の正位に位置する.
そして、東は木気である.
したがって、地震も木気である.
雷は天空の振動であり、地震は大地の震動であると考えられ、雷は細長いからである.
そして、木のように細長く伸びるものは、木気とされる.
ところで、中国は、存外に地震が多い.
もっとも、その地域は西部と北東部に偏っているが、関中でもないわけではない.
そして、地震は地中の陽気が地上に出る際に生じるからだと考えられていた.
木気は季節でいえば春であり、植物の芽が地中から出てくる季節である.
このあたりから思いついたものかもしれない.
2015.3/8
Up
Down
#31
震は八卦の一つで、東の正位に位置する.
そして、東は木気である.
したがって、地震も木気である.
雷は天空の振動であり、地震は大地の震動であると考えられ、雷は細長いからである.
そして、木のように細長く伸びるものは、木気とされる.
ところで、中国は、存外に地震が多い.
もっとも、その地域は西部と北東部に偏っているが、関中でもないわけではない.
そして、地震は地中の陽気が地上に出る際に生じるからだと考えられていた.
木気は季節でいえば春であり、植物の芽が地中から出てくる季節である.
このあたりから思いついたものかもしれない.
2015.3/8
Up Down
#32
もっとも、日本でも、地震が木気とされた時代はあった.
その証拠が、要石である.
御存知のように、この石は、鹿島神宮の境内の一隅に上端部だけを見せている.
香取神宮にも同じ名の石があるが、一般に知られているのは鹿島神宮のほうである.
そして、この神社に祭られているのは武甕槌(たけみかづち)である.
この神は、建御雷神とも書かれるように、雷神である.
また、鹿島神宮は、大和朝廷の時代、日本の東端に位置していた.
そして、雷も、東も木気である.
その木気を制するのは、金気であるが、石は、この金気なのである.
石は、土気のように思うが、金気の性質として、硬い、丸いというものがある.
そして、要石のほとんどは地中にあって全容は分からないが、球形であるといわれる.
また、地中に埋まっているというのは、金が土中から生じるという五行の考えの表象である.
したがって、要石は金気の塊となるのだが、なぜ、そのようなものが、木気の神社にあるのだろうか.
武甕槌を押さえるためである.
武甕槌は雷神であり、それゆえに地震を起こすと考えられていたからであろう.
日本の場合、中国よりも、地震に対する恐怖は強かったからである.
2015.3/9
Up
Down
#32
もっとも、日本でも、地震が木気とされた時代はあった.
その証拠が、要石である.
御存知のように、この石は、鹿島神宮の境内の一隅に上端部だけを見せている.
香取神宮にも同じ名の石があるが、一般に知られているのは鹿島神宮のほうである.
そして、この神社に祭られているのは武甕槌(たけみかづち)である.
この神は、建御雷神とも書かれるように、雷神である.
また、鹿島神宮は、大和朝廷の時代、日本の東端に位置していた.
そして、雷も、東も木気である.
その木気を制するのは、金気であるが、石は、この金気なのである.
石は、土気のように思うが、金気の性質として、硬い、丸いというものがある.
そして、要石のほとんどは地中にあって全容は分からないが、球形であるといわれる.
また、地中に埋まっているというのは、金が土中から生じるという五行の考えの表象である.
したがって、要石は金気の塊となるのだが、なぜ、そのようなものが、木気の神社にあるのだろうか.
武甕槌を押さえるためである.
武甕槌は雷神であり、それゆえに地震を起こすと考えられていたからであろう.
日本の場合、中国よりも、地震に対する恐怖は強かったからである.
2015.3/9
Up Down
#33
しかし、地震が木気であるというのは、理解しにくい.
地震は大地の震動である以上、土気となるのが自然であるからである.
したがって、土気のナマズが原因であるとなると、広く一般に受け入れられた.
特に、1697年初演の歌舞伎「暫(しばらく)」では、ナマズを思わせる隈取をした
鯰入道とか鹿島入道震斎とか呼ばれる人物が登場する.
ここで鹿島とあるのは、鹿島神宮のことである.
これは、武甕槌が地震を司るということから選ばれたものであろうが、
神を災厄の元凶とするのに抵抗があったために、そこに棲むナマズとなったのであろう.
と同時に、土気を制するのは木気であるということで、鹿島神宮が地震封じの神となった.
地震の発生源とされたのが、逆に、地震封じの神になったのだから、武甕槌も驚いただろうが、
1855年の安政の大地震により、この説は急速に広まった.
地震の発生が10月2日であり、旧暦10月は神無月であったからである.
神無月であるので、武甕槌は出雲に出かけており、その留守を狙ってナマズが暴れたのだという風評が広まったのである.
そして、この風評を広めたのは鯰絵と呼ばれた浮世絵であった.
これはナマズを描いており、この絵を持っていると地震を免れるとされたので、約2ヶ月の200種以上も登場した.
その中に、鹿島明神を描いたものが多かったのである.
一大転換はもう一つあった.
要石が、鳴動しようとするナマズを押さえるものとなったのである.
しかし、金気は土気から生まれるとされるが、土気を防ぐとはされない.
土気を防ぐのは、前回も述べたように木気である.
したがって、この石が単なる重石に転じてしまったのは、当然のことだが、不憫なことである.
2015.3/10
Up
Down
#33
しかし、地震が木気であるというのは、理解しにくい.
地震は大地の震動である以上、土気となるのが自然であるからである.
したがって、土気のナマズが原因であるとなると、広く一般に受け入れられた.
特に、1697年初演の歌舞伎「暫(しばらく)」では、ナマズを思わせる隈取をした
鯰入道とか鹿島入道震斎とか呼ばれる人物が登場する.
ここで鹿島とあるのは、鹿島神宮のことである.
これは、武甕槌が地震を司るということから選ばれたものであろうが、
神を災厄の元凶とするのに抵抗があったために、そこに棲むナマズとなったのであろう.
と同時に、土気を制するのは木気であるということで、鹿島神宮が地震封じの神となった.
地震の発生源とされたのが、逆に、地震封じの神になったのだから、武甕槌も驚いただろうが、
1855年の安政の大地震により、この説は急速に広まった.
地震の発生が10月2日であり、旧暦10月は神無月であったからである.
神無月であるので、武甕槌は出雲に出かけており、その留守を狙ってナマズが暴れたのだという風評が広まったのである.
そして、この風評を広めたのは鯰絵と呼ばれた浮世絵であった.
これはナマズを描いており、この絵を持っていると地震を免れるとされたので、約2ヶ月の200種以上も登場した.
その中に、鹿島明神を描いたものが多かったのである.
一大転換はもう一つあった.
要石が、鳴動しようとするナマズを押さえるものとなったのである.
しかし、金気は土気から生まれるとされるが、土気を防ぐとはされない.
土気を防ぐのは、前回も述べたように木気である.
したがって、この石が単なる重石に転じてしまったのは、当然のことだが、不憫なことである.
2015.3/10
Up Down
#34
彼女は、母親の住む福島県いわき市に向かう途中だった.
地震が襲ったのは茨城県内を電車が通過中のことだった.
被害はなかったが、列車の運行が中止になったので、名も知らぬ町の体育館で一夜を明かした.
一人暮らしの母親と食べるために、奮発して横浜のデパートで買った弁当が手許にあったが、
取り出せる雰囲気ではなかった.
福島市に住む彼女の兄は、自宅マンションの玄関のドアが変形して開かなくなっていたが、
窓から出ると、車を走らせた.
あらゆる所で道路が損壊しているのを迂回しながら、土地勘だけで母親の元に走った.
その間、車のラジオは壊滅的な状況を報せてばかりいた.
電話は通じない.
結局、いわき市にたどり着いたのは夜になってからだった.
家に駆け込むと、母親はぽつんと炬燵に座っていたそうである.
どういう状況で地震を迎えたかは分からない.
記憶が残っていないからである.
ただ、石垣が崩れてはいたが、津波の被害はなかったということだけしか分からない.
あれから4年が経つ.
幸い、親戚の中に甚大な被災を被った者はいない.
しかし、多分、それは運がよかっただけなのだろうと思う.
2015.3/11
#35
Up
Down
#34
彼女は、母親の住む福島県いわき市に向かう途中だった.
地震が襲ったのは茨城県内を電車が通過中のことだった.
被害はなかったが、列車の運行が中止になったので、名も知らぬ町の体育館で一夜を明かした.
一人暮らしの母親と食べるために、奮発して横浜のデパートで買った弁当が手許にあったが、
取り出せる雰囲気ではなかった.
福島市に住む彼女の兄は、自宅マンションの玄関のドアが変形して開かなくなっていたが、
窓から出ると、車を走らせた.
あらゆる所で道路が損壊しているのを迂回しながら、土地勘だけで母親の元に走った.
その間、車のラジオは壊滅的な状況を報せてばかりいた.
電話は通じない.
結局、いわき市にたどり着いたのは夜になってからだった.
家に駆け込むと、母親はぽつんと炬燵に座っていたそうである.
どういう状況で地震を迎えたかは分からない.
記憶が残っていないからである.
ただ、石垣が崩れてはいたが、津波の被害はなかったということだけしか分からない.
あれから4年が経つ.
幸い、親戚の中に甚大な被災を被った者はいない.
しかし、多分、それは運がよかっただけなのだろうと思う.
2015.3/11
#35
Up Down
1+1x2は4ではない.
2015.3/12
Up
Down
1+1x2は4ではない.
2015.3/12
Up Down
#36
過日、将棋の八段が二歩で敗れた.
もちろん、二歩は反則であるが、相手が気づかずに投了した場合は、指した方が反則負けにならずに、勝ってしまう.
逆に、二歩をしたのに気づかず、そのまま対局をしていて、負けてしまうということもある.
あくまでも対局であり、審判がいないからである.
実際、二歩をしたのに、相手が気づかなかったので、三歩も打って勝ったという話を読んだことがある.
もちろん、プロの対局ではない…と思う.
2015.3/13
Up
Down
#36
過日、将棋の八段が二歩で敗れた.
もちろん、二歩は反則であるが、相手が気づかずに投了した場合は、指した方が反則負けにならずに、勝ってしまう.
逆に、二歩をしたのに気づかず、そのまま対局をしていて、負けてしまうということもある.
あくまでも対局であり、審判がいないからである.
実際、二歩をしたのに、相手が気づかなかったので、三歩も打って勝ったという話を読んだことがある.
もちろん、プロの対局ではない…と思う.
2015.3/13
Up Down
#37
1765年にブーランジェという人が、パリに居酒屋を開いたが、すぐに訴えられた.
ブーランジェが売っていたのは、肉や野菜を煮込んだスープであったが、彼はギルドに入っていなかったからである.
しかも、当時のフランスでは、肉を焼く者、豚肉を売る者、鶏肉を売る者、ソースを作る者、内臓肉を売る者というふうに、
細かく分類されたギルドがあった.
そして、これらの誰かが他のギルドに分類されるものを扱おうと思うと、そちらから取り寄せるしかなかった.
しかし、ブーランジェのスープには、羊のも、鶏肉のもあったし、牛肉や鶏から取ったブイヨンも扱っていたのである.
これに対し、彼は、これはレストランという新しい料理であると主張して、裁判に勝ってしまうのである.
これが、レストランの語源である.
2015.3/15
Up
Down
#37
1765年にブーランジェという人が、パリに居酒屋を開いたが、すぐに訴えられた.
ブーランジェが売っていたのは、肉や野菜を煮込んだスープであったが、彼はギルドに入っていなかったからである.
しかも、当時のフランスでは、肉を焼く者、豚肉を売る者、鶏肉を売る者、ソースを作る者、内臓肉を売る者というふうに、
細かく分類されたギルドがあった.
そして、これらの誰かが他のギルドに分類されるものを扱おうと思うと、そちらから取り寄せるしかなかった.
しかし、ブーランジェのスープには、羊のも、鶏肉のもあったし、牛肉や鶏から取ったブイヨンも扱っていたのである.
これに対し、彼は、これはレストランという新しい料理であると主張して、裁判に勝ってしまうのである.
これが、レストランの語源である.
2015.3/15
Up Down
#38
レストランとは、回復させる場所という意味である.
これは、ブーランジェが店頭に書いた
Venite ad me, vos qui
stomaco laboratis, et ego restaurabo vos.
来たれ、胃に不満を持つ人、私はあなたを完全に回復させます.
つまり、
私の店に来れば、あなたの空腹を完全に癒して差し上げます
というラテン語の看板に由来する.
このうち、restaurabo、回復させるという意味のフランス語訳restaurer、
ちなみに、この語の英訳restoreは、リストアという語で、データーや機械の復元の意味で日本語でも使用されるが、
この語の現在分詞restaurantがレストランである.
レストランとは、空腹や疲れを回復させる場所とか、食事という意味であったのである.
2015.3/16
Up
Down
#38
レストランとは、回復させる場所という意味である.
これは、ブーランジェが店頭に書いた
Venite ad me, vos qui
stomaco laboratis, et ego restaurabo vos.
来たれ、胃に不満を持つ人、私はあなたを完全に回復させます.
つまり、
私の店に来れば、あなたの空腹を完全に癒して差し上げます
というラテン語の看板に由来する.
このうち、restaurabo、回復させるという意味のフランス語訳restaurer、
ちなみに、この語の英訳restoreは、リストアという語で、データーや機械の復元の意味で日本語でも使用されるが、
この語の現在分詞restaurantがレストランである.
レストランとは、空腹や疲れを回復させる場所とか、食事という意味であったのである.
2015.3/16
Up Down
#39
それまでの料理店は、各種ギルドがそれぞれの専門料理をこしらえ、提供していたのだが、注文によるものではなかった.
しかも、料理は大皿で提供され、各人が切り取って食べていたので、料理がなくなったら営業は終了であった.
その上、常連以外は入れなかった.
したがって、一般人は自宅で食べる以外は、晩餐会にでも招かれる以外に方法はなかった.
これに対し、ブーランジェのレストランは、一人でも自由に入れたし、小皿で提供されていた.
メニューも、最初はスープだけだったが、徐々に増えていったようである.
そして、メニューには代金が書かれていた.
何を当たり前のことを言われそうだが、当時のメニューというのは、晩餐会等で出される料理の一覧である.
金額など書いてあるわけがなかったのである.
その後、フランス革命までに100軒ものレストランがパリに誕生したのも当然であった.
2015.3/17
Up
Down
#39
それまでの料理店は、各種ギルドがそれぞれの専門料理をこしらえ、提供していたのだが、注文によるものではなかった.
しかも、料理は大皿で提供され、各人が切り取って食べていたので、料理がなくなったら営業は終了であった.
その上、常連以外は入れなかった.
したがって、一般人は自宅で食べる以外は、晩餐会にでも招かれる以外に方法はなかった.
これに対し、ブーランジェのレストランは、一人でも自由に入れたし、小皿で提供されていた.
メニューも、最初はスープだけだったが、徐々に増えていったようである.
そして、メニューには代金が書かれていた.
何を当たり前のことを言われそうだが、当時のメニューというのは、晩餐会等で出される料理の一覧である.
金額など書いてあるわけがなかったのである.
その後、フランス革命までに100軒ものレストランがパリに誕生したのも当然であった.
2015.3/17
Up Down
#40
革命後レストランが急速に増えたのは、ギルドが廃止されたということもあるが、失業する料理人が増えたからである.
失業する料理人が増えたのに、なぜ、レストランが増えたかというと、王侯貴族が廃されたからである.
彼等は、自らの食事のためと晩餐会のために、料理人を雇っていた.
もちろん、彼等はギルドに加入する必要はなかったから、どのような料理でも作れた.
前回、晩餐会にでも招かれる以外に方法はなかったと書いたのは、この意味である.
しかし、革命は王侯貴族を廃し、結果としてパトロンを失った彼等は、自分で料理店を開くしかなかったのである.
そして、革命政府は、民衆に娯楽を与える必要性があった.
政府は民衆の支持の上に成り立っていたからである.
もっと正確にいうと、民衆が暴徒化し政府を打毀しにかかるということを恐れたのである.
そのために、政府が考えた最大の娯楽がギロチンであったのだが、食事も、また、その一つであったのである.
2015.3/19
Up
Down
#40
革命後レストランが急速に増えたのは、ギルドが廃止されたということもあるが、失業する料理人が増えたからである.
失業する料理人が増えたのに、なぜ、レストランが増えたかというと、王侯貴族が廃されたからである.
彼等は、自らの食事のためと晩餐会のために、料理人を雇っていた.
もちろん、彼等はギルドに加入する必要はなかったから、どのような料理でも作れた.
前回、晩餐会にでも招かれる以外に方法はなかったと書いたのは、この意味である.
しかし、革命は王侯貴族を廃し、結果としてパトロンを失った彼等は、自分で料理店を開くしかなかったのである.
そして、革命政府は、民衆に娯楽を与える必要性があった.
政府は民衆の支持の上に成り立っていたからである.
もっと正確にいうと、民衆が暴徒化し政府を打毀しにかかるということを恐れたのである.
そのために、政府が考えた最大の娯楽がギロチンであったのだが、食事も、また、その一つであったのである.
2015.3/19
Up Down
#41
レストランを「発明」したブーランジェは、正体不明の人物である.
正しい名前からして分からない.
いろいろと調べてみたが、ほとんどがBoulangerとあるだけだが、たまにA.Boulangerと書いてあるものがある.
また、M.Boulangerとかいてあるものもあるし、boulangerとするものもある.
もし、boulangerと小文字で始まる表記が正しいのなら、これは普通名詞だから、パン屋という意味になる.
ただ、この表記はほとんどないので、Boulangerは固有名詞と考えたほうがよい.
パン屋という意味の英語のベーカーBakerがありふれた苗字であるように、
フランスでも、ブーランジェはよくある苗字だからである.
また、生年も没年も出自も分からない.
ただ、ブーランジェなのである.
しかし、ロンドン大学のスパングRebecca L.Spangという歴史家が、
2000年に「レストランの誕生:パリと現代グルメ文化The Invention
of the Restaurant」という本を出版しており、
同書で、ブーランジェはシャントワゾーMathurin Roze
de Chantoiseauという人物の別名であることが明らかにしている.
この人物は、フランスでは貴族を表すドを苗字の前につけているが、貴族ではなかったようである.
ただ、実業家で、ギルドが力を持っていたとしても、彼らより上位にあったようである.
だからこそ、彼はギルドとの裁判に打ち勝つことができたのであろう.
2015.3/20
Up
Down
#41
レストランを「発明」したブーランジェは、正体不明の人物である.
正しい名前からして分からない.
いろいろと調べてみたが、ほとんどがBoulangerとあるだけだが、たまにA.Boulangerと書いてあるものがある.
また、M.Boulangerとかいてあるものもあるし、boulangerとするものもある.
もし、boulangerと小文字で始まる表記が正しいのなら、これは普通名詞だから、パン屋という意味になる.
ただ、この表記はほとんどないので、Boulangerは固有名詞と考えたほうがよい.
パン屋という意味の英語のベーカーBakerがありふれた苗字であるように、
フランスでも、ブーランジェはよくある苗字だからである.
また、生年も没年も出自も分からない.
ただ、ブーランジェなのである.
しかし、ロンドン大学のスパングRebecca L.Spangという歴史家が、
2000年に「レストランの誕生:パリと現代グルメ文化The Invention
of the Restaurant」という本を出版しており、
同書で、ブーランジェはシャントワゾーMathurin Roze
de Chantoiseauという人物の別名であることが明らかにしている.
この人物は、フランスでは貴族を表すドを苗字の前につけているが、貴族ではなかったようである.
ただ、実業家で、ギルドが力を持っていたとしても、彼らより上位にあったようである.
だからこそ、彼はギルドとの裁判に打ち勝つことができたのであろう.
2015.3/20
Up Down
#42
また、ブーランジェは、自分の店先にラテン語で看板を書いている.
しかし、当時のフランスの庶民がラテン語を読み書きできたのだろうかというと、疑問が残る.
「三銃士」の中で、ダルタニャンが銃士隊長のトレヴィユと最初に出会った際に、
相互にラテン語がよく分からないと言っているが、ともに貴族の出である.
教育を受けたはずの貴族でそうであるのなら、庶民が書けるとは思えない.
もっとも、ポルトスは、新教徒について、我々がラテン語で歌う賛美歌をフランス語で歌うだけの違いだと言っている.
したがって、当時のフランス人がラテン語に馴染みがなかったわけではない.
ただ、馴染みがあるのとラテン語を読み書きできるのとは別である.
仏式の葬式に出る.
お経が流れる.
唱和する人もいる.
しかし、その経典の意味を分かっている人はどれだけいるのだろうか.
サンスクリットを中国で翻訳したものを、我々は昔の中国の音で読んでいるからである.
経文を見れば、意味はある程度分かるし、川端康成のように読み物として面白いと人も出てくる.
しかし、耳で聞いている限り、和讃のようなものは別として、理解不能であるが、
これを日本語訳してという動きは出ていない.
つまり、日本人は、意味も分からぬままに、お経をありがたがっているということになる.
当時のフランス人もそうだったのだろうと思う.
Venite ad me, vos qui
stomaco laboratis, et ego restaurabo vos.
来たれ、胃に不満を持つ人、私はあなたを完全に回復させます.
このラテン語は、聖書の一説をもじったものだそうだが、この意味が分かる人はラテン語の知識を持つ人である.
当然、これを読んで来店しようとする人は、ラテン語の知識をもつ人である.
そして、これを書いた人も同様である.
一般大衆ではない.
ブーランジェが、シャントワゾーという実業家の別名であると聞いて、
それでラテン語で書けたのかと、ようやく、得心したのは、そういうわけである.
2015.3/21
Up
Down
#42
また、ブーランジェは、自分の店先にラテン語で看板を書いている.
しかし、当時のフランスの庶民がラテン語を読み書きできたのだろうかというと、疑問が残る.
「三銃士」の中で、ダルタニャンが銃士隊長のトレヴィユと最初に出会った際に、
相互にラテン語がよく分からないと言っているが、ともに貴族の出である.
教育を受けたはずの貴族でそうであるのなら、庶民が書けるとは思えない.
もっとも、ポルトスは、新教徒について、我々がラテン語で歌う賛美歌をフランス語で歌うだけの違いだと言っている.
したがって、当時のフランス人がラテン語に馴染みがなかったわけではない.
ただ、馴染みがあるのとラテン語を読み書きできるのとは別である.
仏式の葬式に出る.
お経が流れる.
唱和する人もいる.
しかし、その経典の意味を分かっている人はどれだけいるのだろうか.
サンスクリットを中国で翻訳したものを、我々は昔の中国の音で読んでいるからである.
経文を見れば、意味はある程度分かるし、川端康成のように読み物として面白いと人も出てくる.
しかし、耳で聞いている限り、和讃のようなものは別として、理解不能であるが、
これを日本語訳してという動きは出ていない.
つまり、日本人は、意味も分からぬままに、お経をありがたがっているということになる.
当時のフランス人もそうだったのだろうと思う.
Venite ad me, vos qui
stomaco laboratis, et ego restaurabo vos.
来たれ、胃に不満を持つ人、私はあなたを完全に回復させます.
このラテン語は、聖書の一説をもじったものだそうだが、この意味が分かる人はラテン語の知識を持つ人である.
当然、これを読んで来店しようとする人は、ラテン語の知識をもつ人である.
そして、これを書いた人も同様である.
一般大衆ではない.
ブーランジェが、シャントワゾーという実業家の別名であると聞いて、
それでラテン語で書けたのかと、ようやく、得心したのは、そういうわけである.
2015.3/21
Up Down
#43
桜の開花情報が出始めたが、こういう情報がニュース、それもトップ・ニュースになる国は、日本だけであろう.
したがって、他の国から見ると何とのどかなということになるのだが、実は、これは切実な問題から始まったことである.
1902、05、13年と、明治から大正にかけて、東北地方は冷害に襲われた.
冷害になるとどうなるかというと、イネが稔りにくくなり、米ができない.
だいたい、本来、イネは、熱帯の植物である.
このため、田に水を入れたり、抜いたりして、
人工的に熱帯の気候である雨季と乾季を作り出すわけだが、当然、寒さに弱い.
特に、夏季、18゚C以下の気温が続くと、花粉を作れなくなり、収量が落ちる.
それでも、東北地方の太平洋側、岩手県南部から福島県にかけては、黒潮の影響で比較的暖かい.
福島県南東部のいわき市などは、雪が降ってもすぐに融けてしまうぐらいである.
それが、やませ(山背)と呼ばれる、オホーツク海から吹き寄せる東風が長く続くと、冷風だけに気温が下がる.
これが、イネの花粉のできる時期と重なると、米ができないということになる.
2015.3/22
Up
Down
#43
桜の開花情報が出始めたが、こういう情報がニュース、それもトップ・ニュースになる国は、日本だけであろう.
したがって、他の国から見ると何とのどかなということになるのだが、実は、これは切実な問題から始まったことである.
1902、05、13年と、明治から大正にかけて、東北地方は冷害に襲われた.
冷害になるとどうなるかというと、イネが稔りにくくなり、米ができない.
だいたい、本来、イネは、熱帯の植物である.
このため、田に水を入れたり、抜いたりして、
人工的に熱帯の気候である雨季と乾季を作り出すわけだが、当然、寒さに弱い.
特に、夏季、18゚C以下の気温が続くと、花粉を作れなくなり、収量が落ちる.
それでも、東北地方の太平洋側、岩手県南部から福島県にかけては、黒潮の影響で比較的暖かい.
福島県南東部のいわき市などは、雪が降ってもすぐに融けてしまうぐらいである.
それが、やませ(山背)と呼ばれる、オホーツク海から吹き寄せる東風が長く続くと、冷風だけに気温が下がる.
これが、イネの花粉のできる時期と重なると、米ができないということになる.
2015.3/22
Up Down
#44
もっとも、やませは日本海側では恵みの風である.
山脈にぶつかった冷風は、水蒸気が凝縮され、熱を放出するとともに、雲となり、雨となる.
そして、山頂を越えると、湿気を放出した乾いた空気となって駆け下りる.
しかし、湿った空気は温度の変動幅が小さいのに対して、乾いた空気は変動幅が大きい.
このため、山頂を越えた空気は、熱風となって駆け下りる.
アルプス山脈を越えた熱風は、ドイツ語でフェーンと呼ばれ、これが一般化しているが、
アメリカのロッキー山脈を越えて東側に吹き下りる風はチヌークと呼ばれ、ヘリコプターの名になっている.
気象用語では、風炎とも呼ばれるようだが、
アメリカ、サウス・ダコタ州では、-20゚Cからわずか2分間で7゚Cまで27゚C上昇し、
カナダ、アルバータ州では、1時間で-19゚Cから22゚Cまで41゚C上昇したという記録がある.
実際、日本の最高気温記録は2007年に埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市が40.9゚Cを記録するまで、
山形県山形市が1933年に記録した40.8゚Cであった.
これは、奥羽山脈の西側ではフェーン現象が生じやすいからであるが、このため、東北地方の日本海側の夏は暑い.
その上、豪雪地帯であるため、雪融け水が豊富にある.
この付近が有名な稲作地帯であるのは、このせいである.
しかし、フェーン現象の影響が少なかった場合、簡単に冷害になる.
2015.3/23
Up
Down
#44
もっとも、やませは日本海側では恵みの風である.
山脈にぶつかった冷風は、水蒸気が凝縮され、熱を放出するとともに、雲となり、雨となる.
そして、山頂を越えると、湿気を放出した乾いた空気となって駆け下りる.
しかし、湿った空気は温度の変動幅が小さいのに対して、乾いた空気は変動幅が大きい.
このため、山頂を越えた空気は、熱風となって駆け下りる.
アルプス山脈を越えた熱風は、ドイツ語でフェーンと呼ばれ、これが一般化しているが、
アメリカのロッキー山脈を越えて東側に吹き下りる風はチヌークと呼ばれ、ヘリコプターの名になっている.
気象用語では、風炎とも呼ばれるようだが、
アメリカ、サウス・ダコタ州では、-20゚Cからわずか2分間で7゚Cまで27゚C上昇し、
カナダ、アルバータ州では、1時間で-19゚Cから22゚Cまで41゚C上昇したという記録がある.
実際、日本の最高気温記録は2007年に埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市が40.9゚Cを記録するまで、
山形県山形市が1933年に記録した40.8゚Cであった.
これは、奥羽山脈の西側ではフェーン現象が生じやすいからであるが、このため、東北地方の日本海側の夏は暑い.
その上、豪雪地帯であるため、雪融け水が豊富にある.
この付近が有名な稲作地帯であるのは、このせいである.
しかし、フェーン現象の影響が少なかった場合、簡単に冷害になる.
2015.3/23
Up Down
#45
桜の開花予報は、この冷害の予想ができないかということから始まったものである.
もし、冷害が予測できるのなら、植付時期を調整して、花粉のできるころに温度を確保することも可能だからである.
そして、この予想は1926年に東京付近の観測で始まり、3年後には開花予想も試みられた.
しかし、その後も冷害は発生し、特に1930年代前半には集中したことから、経済恐慌も重なったこともあって、多くの子女が売られた.
これに対し、桜の開花予想が冷害の予想に役立ったかどうかは分からない.
しかし、観測は続けられたようで、戦後、1951年に、関東地方で本格的な予報が始まる.
その後、1965年に奄美、沖縄を除く全国で始められたが、2010年以降は気象庁の手を離れて、民間に移行している.
2015.3/26
Up
Down
#45
桜の開花予報は、この冷害の予想ができないかということから始まったものである.
もし、冷害が予測できるのなら、植付時期を調整して、花粉のできるころに温度を確保することも可能だからである.
そして、この予想は1926年に東京付近の観測で始まり、3年後には開花予想も試みられた.
しかし、その後も冷害は発生し、特に1930年代前半には集中したことから、経済恐慌も重なったこともあって、多くの子女が売られた.
これに対し、桜の開花予想が冷害の予想に役立ったかどうかは分からない.
しかし、観測は続けられたようで、戦後、1951年に、関東地方で本格的な予報が始まる.
その後、1965年に奄美、沖縄を除く全国で始められたが、2010年以降は気象庁の手を離れて、民間に移行している.
2015.3/26
Up Down
#46
以前にも書いたが、ソメイヨシノには実がならない.
たまに、マッチ棒のようなサクランボがつくことはあるが、
これは、他の品種の花粉を受粉したもので、地面に落ちても、芽は出ない.
したがって、挿し木で増やすしかない.
つまり、日本中のソメイヨシノは、たった1本の原木の子孫ということになる.
その原木は、多分、東京の駒込染井村にあったと思われるが、当然、同じ遺伝子情報を持っている.
同一地域のソメイヨシノが、ほぼ同時に咲き、散るのはそのせいである.
また、北海道北部、東部はエゾヤマザクラかチシマザクラが、沖縄、奄美はカンヒザクラが使われるが、
それ以外の地域の開花情報に使われるのがソメイヨシノであるのも、このせいである.
全国一律に開花情報を提供するためには、一斉に開花するこの特質が便利だったからである.
2015.3/28
Up
Down
#46
以前にも書いたが、ソメイヨシノには実がならない.
たまに、マッチ棒のようなサクランボがつくことはあるが、
これは、他の品種の花粉を受粉したもので、地面に落ちても、芽は出ない.
したがって、挿し木で増やすしかない.
つまり、日本中のソメイヨシノは、たった1本の原木の子孫ということになる.
その原木は、多分、東京の駒込染井村にあったと思われるが、当然、同じ遺伝子情報を持っている.
同一地域のソメイヨシノが、ほぼ同時に咲き、散るのはそのせいである.
また、北海道北部、東部はエゾヤマザクラかチシマザクラが、沖縄、奄美はカンヒザクラが使われるが、
それ以外の地域の開花情報に使われるのがソメイヨシノであるのも、このせいである.
全国一律に開花情報を提供するためには、一斉に開花するこの特質が便利だったからである.
2015.3/28
Up Down
#47
繰り返しになるが、イネは熱帯の植物である.
したがって、寒冷地で栽培しても、うまくは栽培できない.
それでも、東北や北陸で栽培が続けられたのは、米の栄養価が比較的高いからである.
飯と味噌汁だけでも、一日の糧としては何とかなるのである.
もちろん、寒冷地であるので、収量も低いし、優良なものはできない.
実際、戦前の評価は他の地域より一等下るものであった.
その常識が覆されたのは1931年のことである.
この年に導入された水稲農林1号がすばらしい性質を持っていたからである.
まず、耐冷性が強かった.
その3年後に東北地方を冷害が襲った際、その被害が局限されたのは、明らかにこの品種の御蔭であった.
また、多収性である上に、味がよかったのである.
そして、早稲であった.
このため、戦後すぐの食料不足の際、端境期に全国に供給され、多くの国民の命を救ったのである.
2015.4/1
Up
Down
#47
繰り返しになるが、イネは熱帯の植物である.
したがって、寒冷地で栽培しても、うまくは栽培できない.
それでも、東北や北陸で栽培が続けられたのは、米の栄養価が比較的高いからである.
飯と味噌汁だけでも、一日の糧としては何とかなるのである.
もちろん、寒冷地であるので、収量も低いし、優良なものはできない.
実際、戦前の評価は他の地域より一等下るものであった.
その常識が覆されたのは1931年のことである.
この年に導入された水稲農林1号がすばらしい性質を持っていたからである.
まず、耐冷性が強かった.
その3年後に東北地方を冷害が襲った際、その被害が局限されたのは、明らかにこの品種の御蔭であった.
また、多収性である上に、味がよかったのである.
そして、早稲であった.
このため、戦後すぐの食料不足の際、端境期に全国に供給され、多くの国民の命を救ったのである.
2015.4/1
Up Down
#48
この水稲農林1号から生まれたのが、農林100号である.
コシヒカリの名で親しまれているこの品種は、寒冷地用である.
というのは、熱帯夜が続くと実入りが悪くなるからである.
したがって、熱帯夜が続く地方には向いていないが、東北地方の日本海側は、栽培適地である.
フェーン現象により昼間は高温になるが、夜間は気温が下がるからである.
このため、コシヒカリを栽培する農家が増えたのだが、その足元をすくったのが、1993年の冷害である.
作況指数が94以下だと不良、90以下だと著しい不良となるのが、全国平均で74となり、東北地方はさらに下回ったのである.
この結果、日本中で1000万tの需要が見込まれたのに対して、この年の収穫量は800万tに達しなかった.
そして、米の買占めと売惜しみから、店頭から米が消えるという騒動まで発生した.
しかし、もし、コシヒカリ一辺倒でなかったら、もう少し、収穫は増えたかもしれないといわれる.
2015.4/2
Up
Down
#48
この水稲農林1号から生まれたのが、農林100号である.
コシヒカリの名で親しまれているこの品種は、寒冷地用である.
というのは、熱帯夜が続くと実入りが悪くなるからである.
したがって、熱帯夜が続く地方には向いていないが、東北地方の日本海側は、栽培適地である.
フェーン現象により昼間は高温になるが、夜間は気温が下がるからである.
このため、コシヒカリを栽培する農家が増えたのだが、その足元をすくったのが、1993年の冷害である.
作況指数が94以下だと不良、90以下だと著しい不良となるのが、全国平均で74となり、東北地方はさらに下回ったのである.
この結果、日本中で1000万tの需要が見込まれたのに対して、この年の収穫量は800万tに達しなかった.
そして、米の買占めと売惜しみから、店頭から米が消えるという騒動まで発生した.
しかし、もし、コシヒカリ一辺倒でなかったら、もう少し、収穫は増えたかもしれないといわれる.
2015.4/2
Up Down
#49
Down
#49
 タマツバキは、日本の競争馬である.
この馬は、サラブレッドではなくアングロアラブであるが、タマツバキ記念という重賞レースがあったように、
戦後初期の日本競馬界を代表する名馬であった.
しかし、その後、ツバキを馬名につけた例は少ない.
これといった産駒が出なかったということもあるだろうが、ツバキは縁起が悪いとされたからであろう.
ツバキの花は、花ごと落ちるからである.
特に、1969年、当時は東京優駿と呼ばれた日本ダービーで、
本命とされたタカツバキから騎手が落馬してからは、ほとんど使われていない.
つまり、ツバキの名は、落馬を連想するということで、使われなくなったのである.
Up
タマツバキは、日本の競争馬である.
この馬は、サラブレッドではなくアングロアラブであるが、タマツバキ記念という重賞レースがあったように、
戦後初期の日本競馬界を代表する名馬であった.
しかし、その後、ツバキを馬名につけた例は少ない.
これといった産駒が出なかったということもあるだろうが、ツバキは縁起が悪いとされたからであろう.
ツバキの花は、花ごと落ちるからである.
特に、1969年、当時は東京優駿と呼ばれた日本ダービーで、
本命とされたタカツバキから騎手が落馬してからは、ほとんど使われていない.
つまり、ツバキの名は、落馬を連想するということで、使われなくなったのである.
Up Down
#50
入院見舞いにツバキの花を持っていくのは禁忌とされているらしい.
これは、首が落ちるに繋がるとされ、ツバキが武士に嫌がられたという話に由来するものであろう.
血を思わせる赤い花が、重なって落ちるのは、確かに印象深いものがある.
したがって、ツバキは死に繋がる花として忌み嫌われたとしても不思議はない.
それが、待てよと思ったのは、徳川2代将軍秀忠はツバキの愛好家だと知ってからである.
そして、江戸時代は園芸が非常に発展した時代で、ツバキの品種改良が進んだ時代であった.
これは、次の家光も樹木を好み、大名からの献上品が相次いだことに由来するが、
ツバキが忌み嫌われたのならば、そのようなことはありえないはずである.
調べてみると、武士がツバキを忌み花としたという記述が出てくるのは、明治以降らしい.
どうやら、これは、幕末から明治にかけてに作られた流言らしい.
2015.4/6
Down
#50
入院見舞いにツバキの花を持っていくのは禁忌とされているらしい.
これは、首が落ちるに繋がるとされ、ツバキが武士に嫌がられたという話に由来するものであろう.
血を思わせる赤い花が、重なって落ちるのは、確かに印象深いものがある.
したがって、ツバキは死に繋がる花として忌み嫌われたとしても不思議はない.
それが、待てよと思ったのは、徳川2代将軍秀忠はツバキの愛好家だと知ってからである.
そして、江戸時代は園芸が非常に発展した時代で、ツバキの品種改良が進んだ時代であった.
これは、次の家光も樹木を好み、大名からの献上品が相次いだことに由来するが、
ツバキが忌み嫌われたのならば、そのようなことはありえないはずである.
調べてみると、武士がツバキを忌み花としたという記述が出てくるのは、明治以降らしい.
どうやら、これは、幕末から明治にかけてに作られた流言らしい.
2015.4/6
NEXT
Last up-dated,
7 Jan. 2023.


 The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
Sasayaki01.
The
Encyclopedia of World ,Modern Warships.
Sasayaki01.
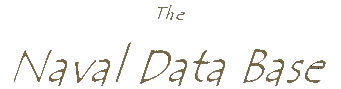 Ver.1.22a.
Ver.1.22a.
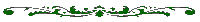 Copyright
(c)
hush ,2001-22. Allrights Reserved.
Copyright
(c)
hush ,2001-22. Allrights Reserved.
Up
動画

